2022年3月の人気記事ランキング
2022年3月1日〜3月30日までの間に、JobPicksで閲覧数の多かった記事トップ5はこちら。
今月は、多くのビジネスシーンで求められるようになった統計・分析の基礎が学べる書籍まとめや、メンズスキンケアブランド「BULK HOMME(バルクオム)」創業者の野口卓也さんが薦めるビジネス書紹介が上位に入った。

1位:統計学・データ分析の初心者でも「数字に強くなる」プロ推薦の必読本(2022/3/11)

2位:仕事の悩みが「軽くなる読書」バルクオム野口卓也の苦境を救った5冊(2022/3/18)

3位:起業に役立つ「20代の経験」どう積むか?10X・矢本真丈の答え(2022/3/16)

4位:【ランキング】グーグルほか有名企業で学んだ「生産性向上」のヒント(2022/3/2)
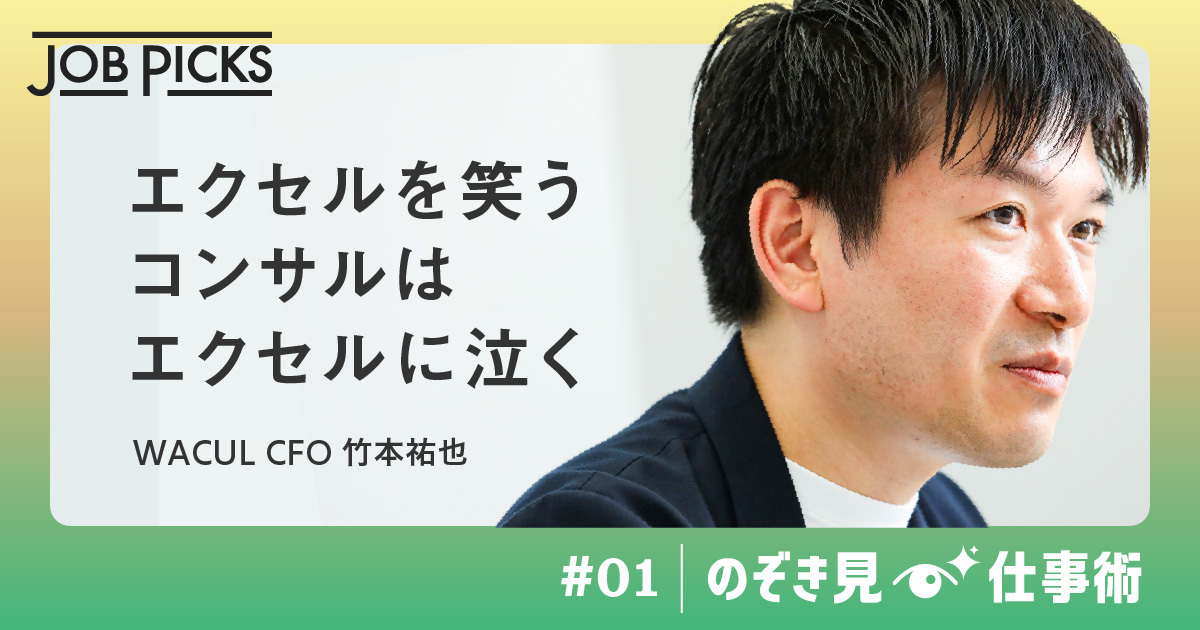
5位:【超実践】コンサルが知っておくべきエクセル関数5選(2021/6/25)
1位の記事は、NewsPicksでのPick数が1000を超えており、データ分析業務を生業とするユーザーが自身の学習法を披露するようなコメントもあった。
2位の記事では、年間100冊以上は本を読むという“本の虫”の野口さんが、19歳から始まった起業家人生を支えた「苦境に陥った時に救ってくれる5冊」をピックアップ。
「ピンチの時には、心の余裕も時間の余裕もない。そこから慌てて本を読んでインプットするのは、なかなか難しい」と、読書習慣の大切さも絡めながら自身の推し本を解説している。
2つとも、読書によって仕事やキャリア形成の糧となる知識・スキルを身に付けたいと考えるユーザーに支持された格好だ。
そこで本稿では、これまでJobPicksが掲載してきた不定期連載「私を変えた座右の書」や「ロールモデルの本棚」シリーズを紹介しながら、仕事人生に役立つ本との向き合い方を読み解いていこう。
【職種別】仕事の基礎力が身に付く本との付き合い方
社会人になってから手に取ることが増えるのは、自身の仕事の基本を学びたい、業界トレンドを知りたいという動機で読むビジネス書だろう。
以下で紹介するのは、人気職種で活躍するロールモデルや、新たに生まれたフューチャーワークに従事する開拓者たちの読書術。それぞれどんなこだわりを持って読書をしているのか、参考にしてみよう。
■メルカリの「法人営業の匠」が営業嫌いを克服した方法
下の記事でインタビューしたメルカリの法人営業担当・杉本浩一さんは、新卒で入った大手通信キャリアや、その後に転職したLINEで数々の事業提携をリードしてきた。
だが、もともと吃音(きつおん)持ちだったこともあり、社会人のスタートでは「営業だけはやりたくない」と考えていたそう。そこから苦手意識を克服し、「ノウハウ以上にスタンスが大事」という独自の営業スタイルを確立してきたという。

LINEで大型提携を連発、「法人営業の匠」を育てた5冊
そんな杉本さんは、読書を通じて営業という仕事の本質を学んだそうだ。「人を見て、人を動かす仕事」と定義し、古典的名著の『影響力の武器』(誠信書房)やシェークスピアの人間劇『マクベス』(新潮社)なども推薦している。
読書は人間の心理を学ぶため、というわけだ。
■マーケターコミュニティの主宰者が学んだ5冊
下の記事は、総計1万人以上のマーケターが集まる学習コミュニティ「マーケティングトレース」を主宰する黒澤友貴さんが推薦する、マーケターの基礎が学べる本紹介だ。
例えば、高名なビジネスデザイナー濱口秀司さんの著書『SHIFT:イノベーションの作法』(ダイヤモンド社)から、あらゆる仕事はコンセプトから議論することで成功確率が上がるという基本を学んだという。

【黒澤友貴】明日から“マーケター脳”になる5つの書籍
黒澤さんは、マーケティングでも「コンセプトや戦略から議論する思考力が求められる」と語る。
だからこそ、太平洋戦争で日本軍がアメリカ軍に敗れた理由を分析した名著『失敗の本質』(ダイヤモンド社)や、イノベーター企業が行ってきた“創造的な模倣の方法”を分析した『模倣の経営学』(日本経済新聞出版)なども参考にしているという。
過去の事例から戦略立案の本質を学ぶ。これは、経営関連のビジネス書を読むことで得られるメリットの一つと言える。
■カスタマーエクスペリエンスの実践者が学んだ5冊
続いて紹介するのは、オフライン・オンラインの双方で良質な「顧客接点」を設計することでビジネスを推進するカスタマーエクスペリエンス(CX)を実践するマザーハウスの神村将志さんに聞いた推薦書だ。

マザーハウスの「すごい顧客体験づくり」試行錯誤を支えた良書5選
神村さんは、今ほどCXが注目されていなかった2010年代前半から、組織全体で良質なユーザーコミュニケーションを行うための方法論を模索してきた。
そのため、『ITビジネスの原理』(NHK出版)や『考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則』(ダイヤモンド社)など、一見CXとは関係のなさそうな書籍からもエッセンスを学びながら「これまでにないブランドコミュニケーションのスタイル」をつくってきたそうだ。
新しい仕事を始める時こそ、他の業務分野で名著と呼ばれる本から仕事の本質を学ぶ。その積み重ねが、挑戦を支えるのだろう。
キャリアの転機を生む本との付き合い方
次は、各界で活躍するビジネスパーソンが、自身のキャリア形成に影響を与えた本を紹介している記事を3つ取り上げよう。
下の記事に登場するAIベンチャーWACULのCFO・竹本祐也さんは、読書を通じて「迷ったら危険な道をゆく」「自分が興味があることを抽象化して考える」習慣を身に付けたそうだ。
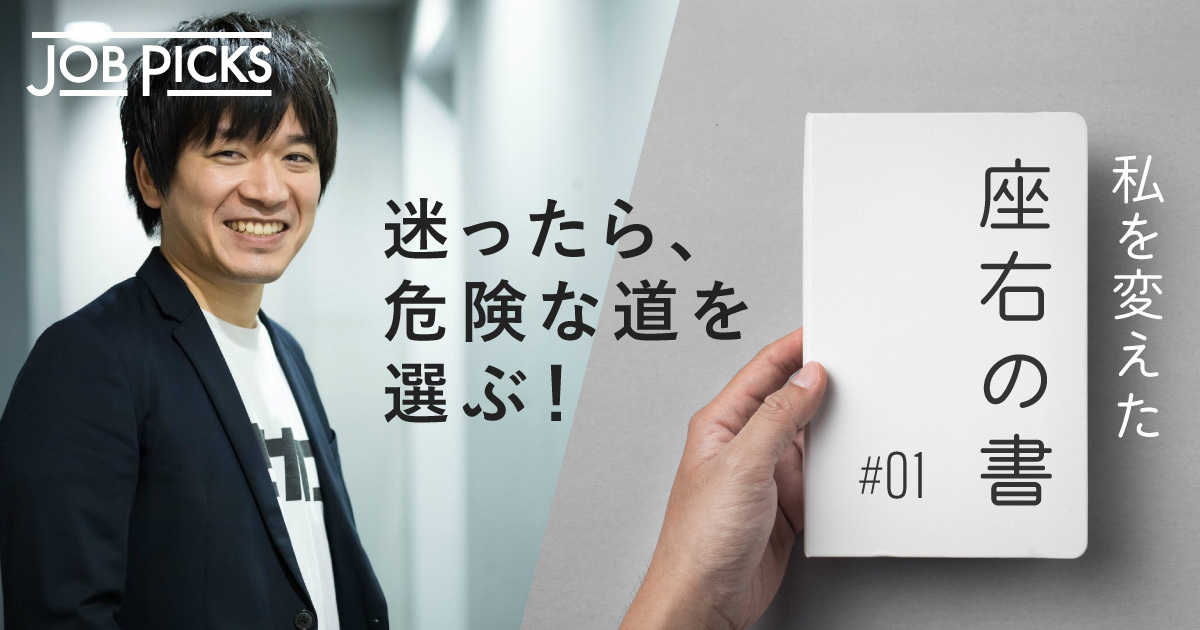
【CFO】私をゴールドマン、コンサル、スタートアップに導いた5冊
それを支えた書籍は、『イシューからはじめよ──知的生産の「シンプルな本質」』(英治出版)のような思考術の名著から、芸術家・岡本太郎の『自分の中に毒を持て―あなたは“常識人間"を捨てられるか』(青春出版社)まで、幅広いジャンルになっている。
この「幅広いジャンルの本に影響を受けた」という点で竹本さんと共通しているのは、国家公務員でありながらキャリア教育研究家として官民の枠を超えて教育関連プロジェクトに取り組む橋本賢二さん。
独ナチスが運営していた強制収容所(ホロコースト)を生き抜いた著者の体験記『夜と霧』(みすず書房)には生きる意味を学び、司馬遼太郎が坂本龍馬の生き様を描いた『坂の上の雲』(文藝春秋)では使命感と危機感を持って仕事に取り組む姿勢を学んだという。
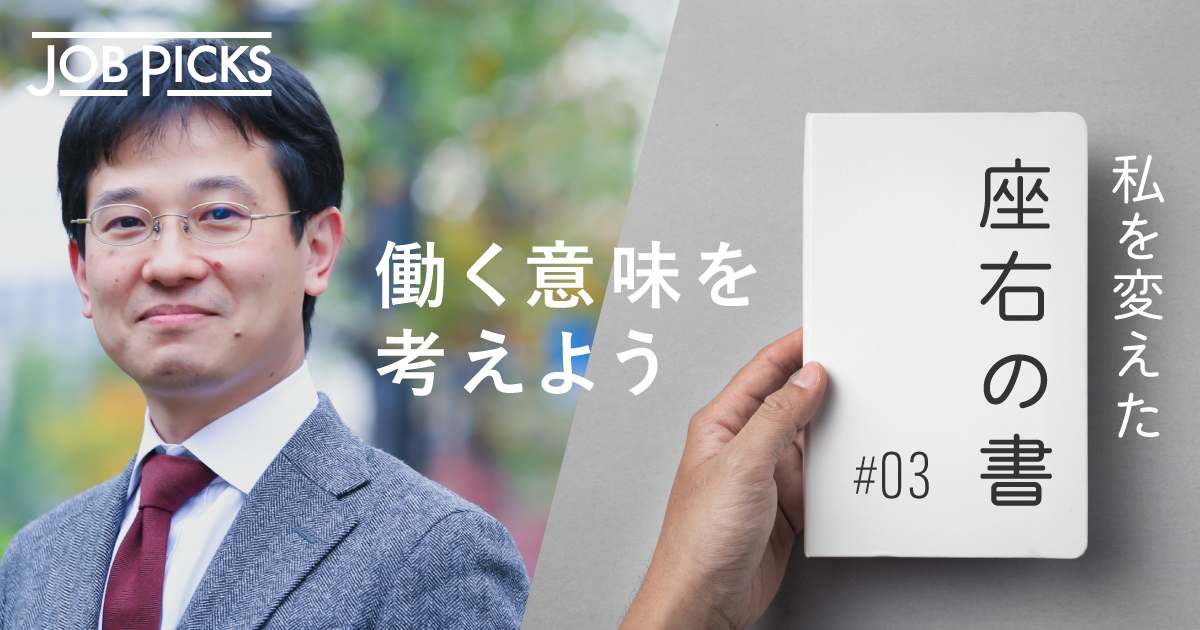
【読書術】“越境公務員”が薦める、働く意味に出会う珠玉の5冊
「何のために働くのか?」という根本的な問いを模索する際、読書は最高の“相談相手”になるということだ。
ZOZOテクノロジーズのAIプロデューサーで『文系AI人材になる―統計・プログラム知識は不要』(東洋経済新報社)の著者・野口竜司さんも、この“相談相手”を読書に求めた1人。
新卒で入社したマーケティングエージェンシーで10以上の新規事業を立ち上げ、現在はAIという新たなビジネス領域で活躍する野口さんは、読書を「働き方を拡張するきっかけ」にしてきたそうだ。
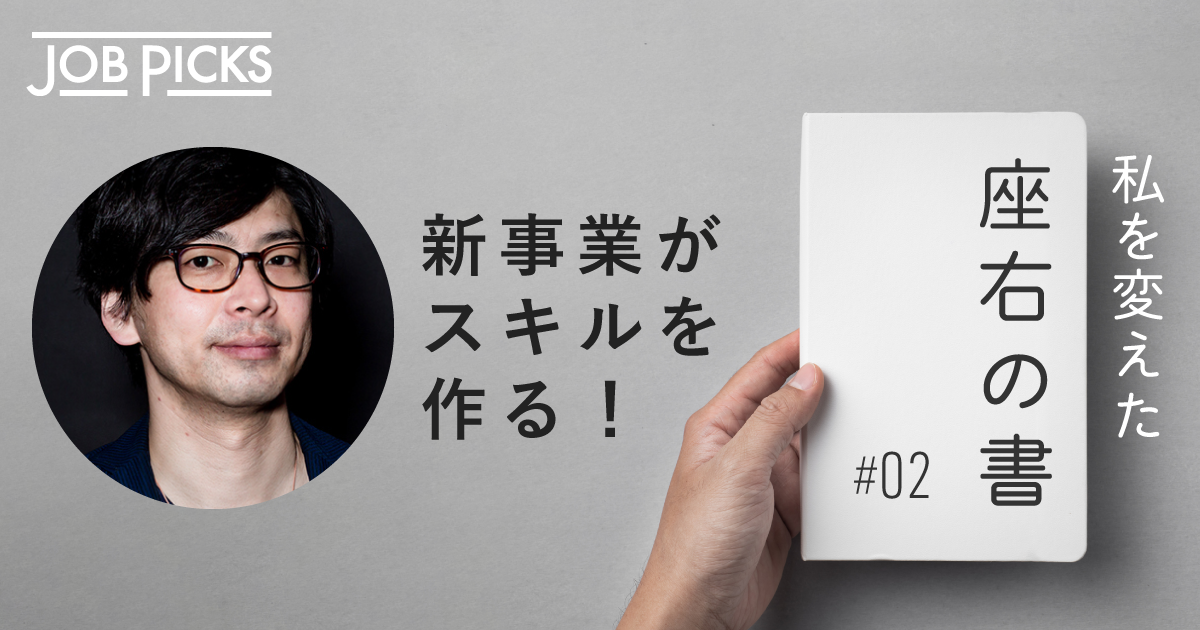
【AIプロデューサー】文系でも技術系のプロになる働き方
例えば、堀江貴文さんの著書『多動力』(幻冬舎)からは、今でこそ一般化しているパラレルワークを始めるためのヒントを得た。
「この本を読んで『もっと同時並行でいろいろやっていいんだ!』と背中を押された」と語り、未知の課題を解決するには過去とは違うアプローチで行動するべきという考え方に確信が持てたという。
読書習慣には、次の挑戦を後押ししてくれる効果もあるのだ。
仕事の悩みを解消する本との付き合い方
最後は、この「後押し」の力を違う観点から得る読書術を紹介しよう。さまざまな課題に直面した際に役立つ本の読み方だ。
下で紹介する2つの記事では、仕事やキャリアの悩みに直面したロールモデルが、自身を変えた本を紹介している。

元DeNAプロマネの20代を救った「チーム運営の悩み」解消する5冊
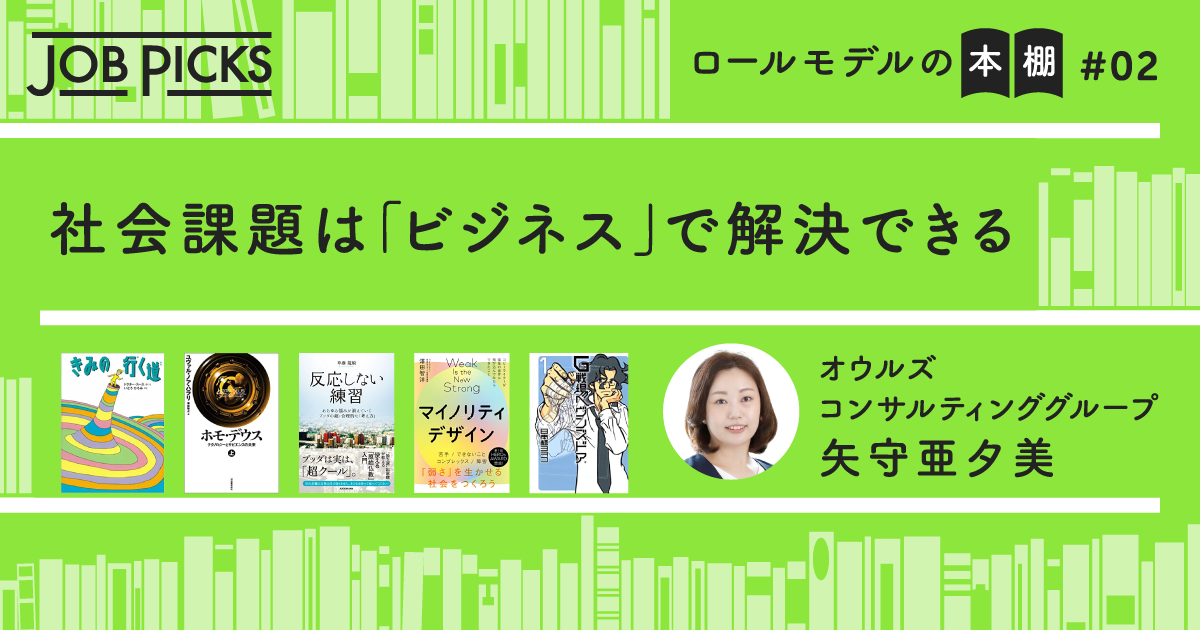
【座右の書】脱・競争社会をつくりたい。負けず嫌いの東大卒コンサルを変えた5冊
新卒でDeNAに入社してプロダクトマネジメントを中心にキャリアを築き、現在はオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」を展開するオトバンク取締役を務める飯泉早希さんは、本を通じて「新しい世界に連れて行ってくれる扉」を得たと語っている。
若手プロダクトマネージャーとして、「経験が少ない身でどうチームを引っ張っていけばいいのか?」と悩んだ時は、学生時代に読んだ『君に友だちはいらない』(講談社)を再読。
本書で紹介されている「偉業は1人の天才ではなく、チームによって成し遂げられる」というエピソードを思い出し、突破口を開いたそうだ。
『君に友だちはいらない』の中ではこれを、黒澤明監督の代表作『七人の侍』の例をひいて説明しています。
『七人の侍』は、登場する侍が他にはない個性と才能を持ちながら、互いの欠点を補って村を守るというチームの持つ力が分かるストーリーです。そしてこのシナリオも、3人のシナリオライターが同時に脚本を書き始め、それぞれの良い部分を抜き出して完成したという、チームによって成し遂げられたことでした。
この本を学生時代に読んでいたことで、心のどこかでずっとチームの持つ可能性を信じ、異なる才能と経験を持った他者とチームを組んで事に向かう機会を探していたんだと思います(飯泉さん)。
この話から、読書を通じて得た知見は「思わぬタイミングで役立つ」という教訓も得られる。
今すぐ仕事に役立つハウツー本だけでなく、心の琴線に触れた本をカジュアルに読み続ける習慣が大切——。そんなふうに考えて、改めて本を開いてみるのもいいだろう。

合わせて読む:【最新版】ゲイツ、ザッカーバーグ…起業家10人の愛読書136冊
文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / uniquepixel