事業責任を負ってこそ見える景色
—— 飯泉さんはDeNA、メルペイとITベンチャー2社でプロダクトマネージャーを経験した後、オトバンクで取締役をしています。転職の理由は何だったのですか?
前職のメルペイでは同僚にも恵まれ、素晴らしい環境でした。
一方で、DeNA時代の上司に「事業責任を背負って初めて見える景色がある」と言われたことが、長い間心に引っかかっていました。事業のPL(損益計算)責任がない状態であれこれ思うことは、楽な立場から考える安易な理想に過ぎないのではないか、という後ろめたさがあったのです。
あらゆるトレードオフを勘案して意思決定をし、決めたことを正解にすることにコミットしないと、怠け者の自分は考え抜く深さも精度も上がらないと焦ってもいました。
そんな折に、もともと知り合いだったオトバンク代表の久保田(裕也さん)から声をかけてもらい、オーディオブックの配信プラットフォーム「audiobook.jp」の事業責任者として働くことになったのです。
—— オーディオブック事業に携わっていますが、飯泉さん自身はよく本を読みますか?
小学生の時から、図書館で週に10冊くらい本を借りて夢中で貪り読んでいたほど、自分にとって本は大きな存在です。

社会人となった今は、年に30〜50冊ほどに減ってはいるものの、本がキャリアの支えとなったことも何度かあります。
特にDeNA時代はキャリアに迷走していた時期で、手に取った本からヒントをもらうこともしばしばありました。
そもそもDeNAをファーストキャリアに選んだのは、規模は小さくてもいいので、若手のうちから裁量権を持って物事を動かす経験を積みたかったから。
特にIT業界は市場の変化もプロダクトの開発スピードも速く、年齢に関係なく意思決定と実行が期待されているので、ITベンチャーのDeNAは自分の性に合っていると考えたのです。
しかし、入社したものの、チームを率いる難しさに頭を抱えたり、自分のキャリアに自信が持てなくなったりと、何度も壁にぶつかりました。
受け止め方までがフィードバック
——「チームを率いる難しさ」とは具体的にどのようなものですか?
壁にぶつかったのは、食のメディアのキュレーションチームに在籍していた時です。
新卒1年目ながらリーダーを任されたことで、メンバーへフィードバックをする機会が出てきました。
しかし経験の浅い私にとって、年齢や社会経験の異なる相手に自分の考えを伝えるのは思っていた以上に難しく、メンバーとの関係をこじらせてしまったこともあります。
自己流では行き詰まりを覚えたため、フィードバックに関する入門書をザッピングすることにしました。
そのなかで最も参考になったのが、『ハーバード あなたを成長させるフィードバックの授業』(東洋経済新報社)でした。
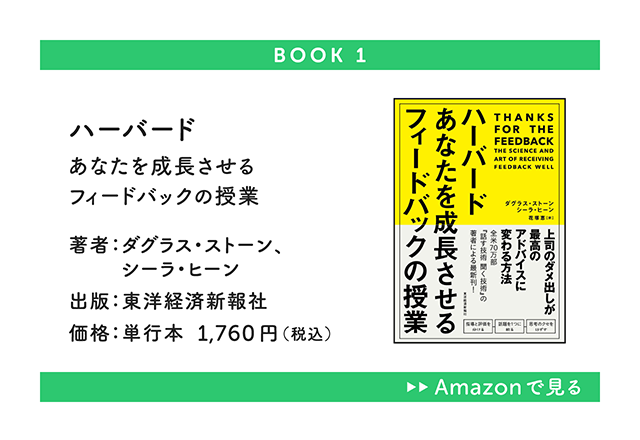
この本は、単なるフィードバックのノウハウにとどまらず、そもそもフィードバックとは何で、どんな役割を果たすのかなど、フィードバックという行為を体系的に解説しています。
フィードバックと聞くと、「他人から一方的に評価を通告されるもの」「他人に点数をつけてダメ出しをするもの」といった連想をする人も少なくないでしょう。
私もそんなイメージを抱いていた1人です。
しかし、この本に出会い、フィードバックとは与える側にとっても受け取る側にとっても「物事を一緒に進めていくためのツール」になるんだ、という理解に変わったのです。
—— 具体的に、どんな「ツール」になるのですか?
この本で最も特徴的なのが、「与え方のみならず、受け止め方まで含めてフィードバックのスキームだ」と解説している点です。

フィードバックによって人間関係が窮屈になってしまうのは、与える側と受け取る側の間に生じる「ニーズのズレ」が主な原因なんですね。
与える側が良いフィードバックを行ったつもりでも、受け止める側がその時の状況や感情などにより、歪んだ捉え方をしてしまうことは大いにあり得る。
「どうフィードバックするか」という形にばかりこだわっていた私にとって、この話は目からうろこでした。
本の内容を参考に、相手がフィードバックを受け取りやすい環境の整備にまで気を配るようにすると、以前に比べて一回一回のフィードバックが有効なものになりました。また自分自身も、周りからのフィードバックを受け止めて自分を変えていくことにポジティブになれました。
この本には夫婦や親子など身近な事例も多く載っているため、ビジネスの場のみならず、日常生活でも応用できるはずです。
「専門性を持たない」という専門性
——「自分のキャリアに自信が持てない」と悩んだ背景についても教えてください。
入社3年目で協業案件のプロダクトマネージャーに就任し、しばらく経った頃でした。
DeNAに入社後、人事、マーケティング、プロダクトマネージャーとキャリアの初期で幅広い業務を経験できた一方、何か特定の専門性が身についたわけではなく、「私のキャリアはこれでいいのか」と不安になったのです。
そんな時に、私にヒントを与えてくれたのが、偶然見たNHKの番組「100分de名著」で紹介されていた司馬遼太郎の『花神』(新潮社)でした。
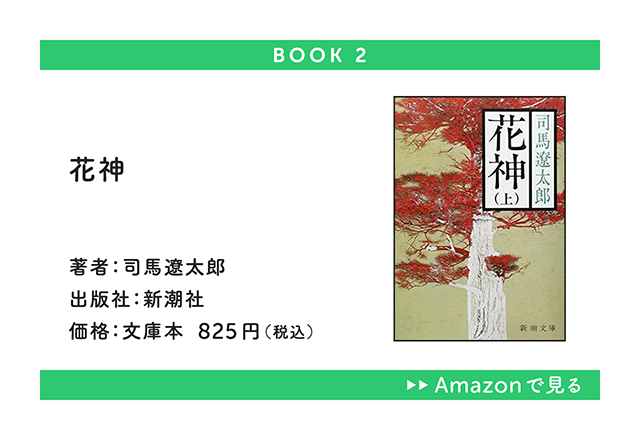
幕末明治の日本を舞台に、技術オタクの蘭学医・大村益次郎が、長州藩の政治家・桂小五郎によって才能を見いだされ、革命を成し遂げていく話です。
この小説で最も印象的だったのが、桂の立ち回り。
空気の読めない合理主義者である大村は、由緒や慣習など、当時の武家社会ならではのルールになじめませんでした。次第に大村に反感を覚える者も出てくるのですが、彼の合理性が維新に不可欠と信じる桂は、最後まで大村を守り抜きます。
すると、一介の医者に過ぎなかった大村が軍人としての才能を開花させ、戊辰戦争を勝利に導き、明治の時代を切り開くのです。
最初はこの小説をエンタメとして楽しんでいたのですが、読み進めているうちに、ふと、桂の姿に自分のキャリアのヒントがあるように思えてきました。
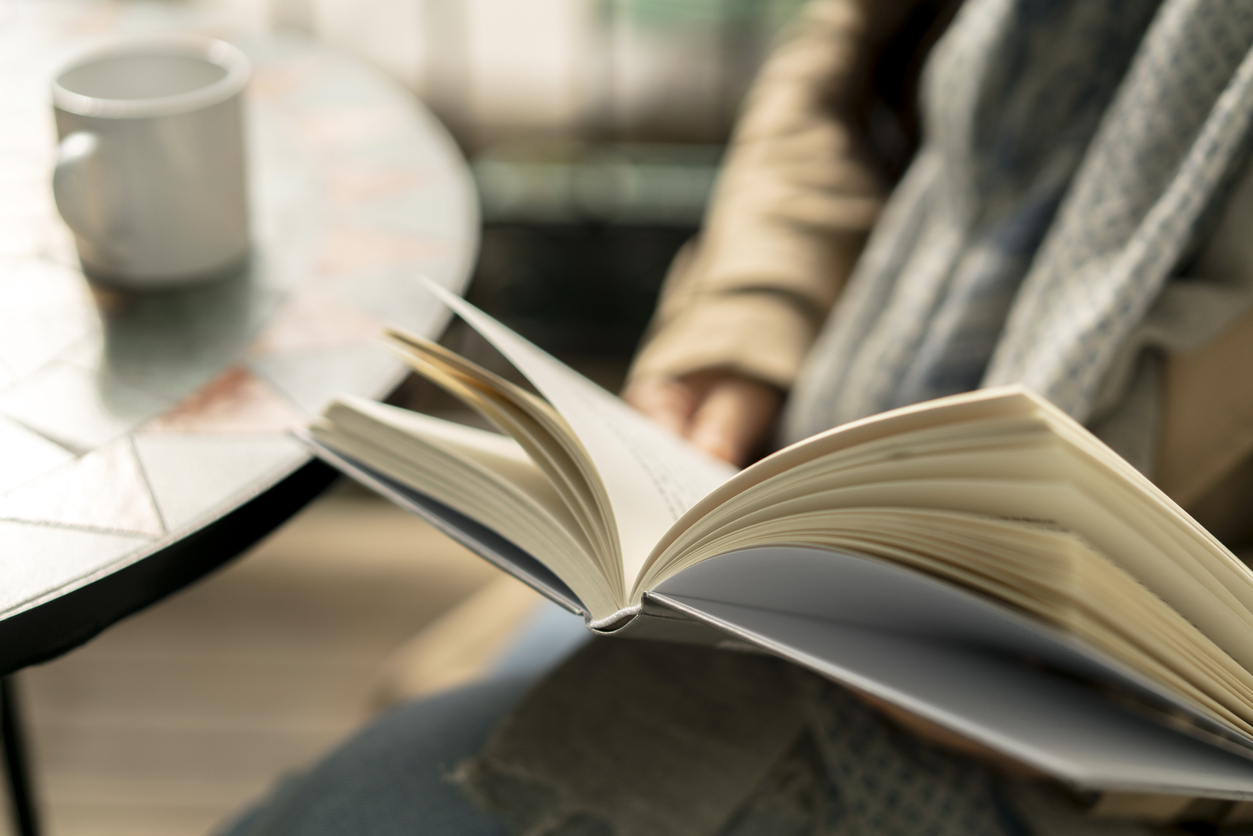
確かに、大村は技術者としては秀でていました。しかし、バランス感覚の優れた桂がいなければ、ただただ厄介者扱いされて、その才能を生かすことはなかったかもしれません。
翻って私は、エンジニアやデザイナーのように、高い専門的なスキルは身につけていません。けれども「スペシャリストの強みが最大限発揮されるように、目指す旗を立てたり環境を整えたりすことはできるかもしれない」と気づいたのです。
そして、その役割はチームで物事を進める際に重要になるのではないかとも思いました。
—— スペシャリストが専門性を発揮するための環境づくりができることも、一つの専門性だと。
そのために、自分が相手の何を信頼して何を託しているのかを明確にし、周囲にも共有する。このマインドセットを桂から学びましたね。
「物事を為すために、スペシャリスト以外でも生きる道がある」と腹落ちしたことで、キャリアへの不安と専門性に対する一種のコンプレックスから脱却できました。
そして、高い専門性を持つ人たちにリスペクトを持ちながら楽しんでプロダクトを作れるようになりました。
偉業はチームで成し遂げられる
—— 飯泉さんは、そもそもなぜプロダクトマネージャーに興味を持ったのでしょうか?
1人ではなく異なる才能と経験を持った人が集まったチームで、共通の目標に向かってモノを作っていけるからです。
エンジニアやデザイナーと初めて働いた時に、バックグラウンドや背負っているアイデンティティが違うと、同じゴールに向かっていてもこんなにも視点や考え方が違うのかと驚きました。
そして、だからこそより良いモノができると気づき、プロダクトづくりの醍醐味を実感しました。
この考え方は、『君に友だちはいらない』(講談社)でも紹介されています。「偉業は1人の天才ではなく、チームによって成し遂げられる」のです。
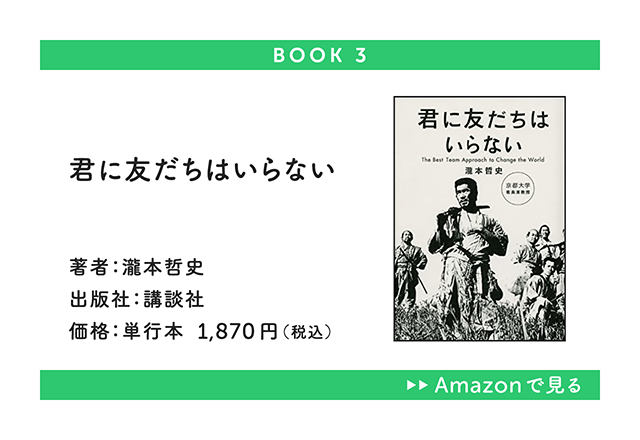
さきほどの『花神』の話にも通じますが、1人でできる仕事には限りがある。1人の天才が築き上げたように見える偉業も、背景を紐解けば必ず多様なメンバーによって構成されています。
『君に友だちはいらない』の中ではこれを、黒澤明監督の代表作『七人の侍』の例をひいて説明しています。
『七人の侍』は、登場する侍が他にはない個性と才能を持ちながら、互いの欠点を補って村を守るというチームの持つ力が分かるストーリーです。そしてこのシナリオも、3人のシナリオライターが同時に脚本を書き始め、それぞれの良い部分を抜き出して完成したという、チームによって成し遂げられたことでした。
この本を学生時代に読んでいたことで、心のどこかでずっとチームの持つ可能性を信じ、異なる才能と経験を持った他者とチームを組んで事に向かう機会を探していたんだと思います。
マネージャーは「てこの原理」を使え
—— ほかに、キャリアを考える上で参考になった本はありますか?
DeNAに入社して4年目頃、ゲーム事業部の編成部長となった時に読んだ、『HIGH OUTPUT MANAGEMENT』(日経BP)です。
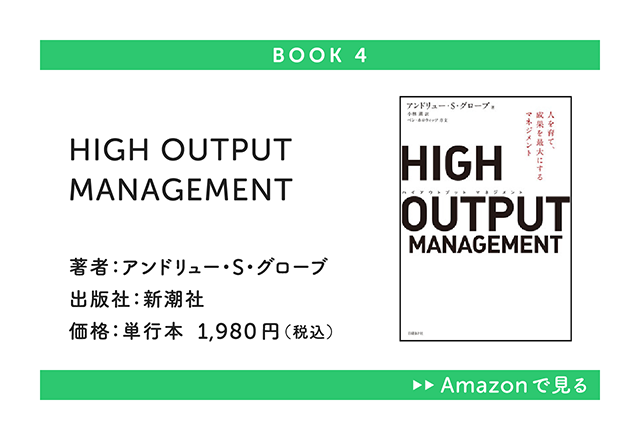
それまでも小規模のグループでリーダーはやったことがありましたが、マネージャー職として20人強を束ねるのは初めての経験でした。
この本では、マネジメントの機能の説明に終始せず、「マネジメントとは自分の組織、隣接する組織両方のアウトプットを大きくしていく活動であり、そのアウトプット量で評価が決まる」と、その本質が明瞭に記されていました。
本を読む以前は、メンバーの評価やアサイン調整、モチベーションマネジメントなど、他人の評価や考え方によってすべきことが変化して気苦労の多いイメージを抱いており、自分はマネジメントに向いていないと考えていました。
ですが、むしろそれらをやることで、組織に「てこの原理」を効かせ、インパクトを最大化できるポジションなんだ、という認識に変わり、マネジメントの面白さに気づきました。
現在も、メンバーの背中をちょっと押すことでワッと転がるように勢いづき、物事が自律的にどんどんと動いていく時は、マネジメントする立場としてとても嬉しく感じます。

—— オトバンクの事業責任者になってみて、これまでとは違う苦労はありますか?
オーディオブックという事業特有の経営の難しさを痛感する日々です。
オーディオブックは市場がまだ発展途上の産業であり、かつコンテンツ産業は「ヒットするのは千三つ」と言われるほど、他のビジネスに比べても合理的な事業戦略が描きづらいのです。
そんな自分が、最近とても心動かされたのが、『PIXAR<ピクサー> 世界一のアニメーション企業の今まで語られなかったお金の話』(文響社)というビジネス・ノンフィクションです。
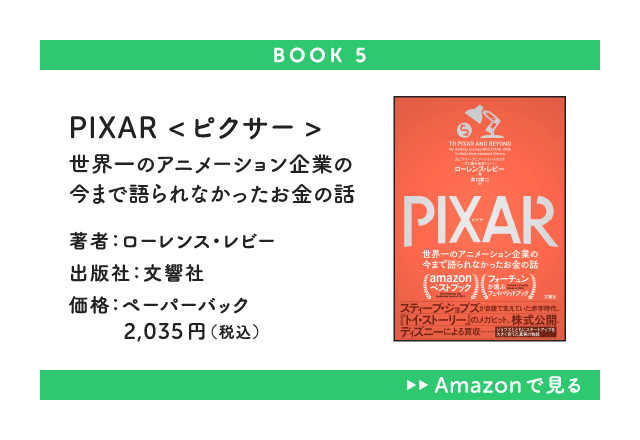
著者のローレンス・レビーが、事業戦略もままならない赤字のグラフィックス会社だったピクサーに立て直し屋として入り、オーナーのスティーブ・ジョブズやクリエイターのジョン・ラセターらとともに数十億ドル規模のエンターテインメントスタジオに変身させるまでを綴っています。
クリエイティブを追求したいという理想と、会社としてビジネスの厳しい世界を生き残らなければいけないという現実。いかに両者の折り合いをつけようかと頭を悩ませ続けるレビーの姿に、同じコンテンツ産業の経営に携わる者として共感せざるを得ませんでした。
また、雲泥の実力差があるディズニーとの交渉で「ここを譲れば妥結できる」という場面で、レビーが安易でまあまあな結論には飛びつかない点にもしびれました。
「妥協するなら、ピクサーという会社の可能性を信じて自分が入った意味がない」とクリエイターと彼らが生み出す映画の可能性を信じ続けることは、並大抵の合理的なビジネスパーソンにはできません。
ジョブズとあらゆる角度で事業戦略を議論するレビーの明晰さと、一癖も二癖もあるジョブズを諌めながら議論の着地点を見つける彼の見事な手腕と温かな人間性にも感銘を受けました。

奇跡のような連続ヒットが実現したのは、天才クリエイターだけでも稀代の経営者だけでもなく、著者のような技術とストーリーの力を信じてビジネスに仕立てるスキルと情熱を持った人がいたから。
これもまさしく、チームアプローチで成し遂げた偉業なのです。
ピクサーが幾多の困難を乗り越えて人々に素晴らしい作品を届けたように、私も同じ志を持つ仲間とともに、音声の力と可能性を信じ、より多くの人に新たな世界や価値観と出会えるようにしていきたいと思いました。
—— 最後に、オーディオブックを展開し、自らも読書家である飯泉さんにとって、本とはどのような存在ですか?
いつだって「新しい世界に連れて行ってくれる扉」のような存在です。
今自分が本の事業に携わっているのも、新たな読書の形をより多くの人に届け、いつでも・どこでも新しい世界や価値観に触れて人生を豊かにするきっかけが作れたら、という思いからです。
私がチームの大切さやマネジメントの醍醐味を本から受け取り価値観が変わったように、立ち止まった時には本の中に次の世界への扉を探してみるのもいいかもしれません。
数ある本の中から自分を変える扉に出会えた感動は、キャリアを前に進める原動力となるはずです。

合わせて読む:【LINE・24歳】若手プロダクトマネージャーの仕事の中身
取材・文:小原由子、編集:高橋智香、デザイン:國弘朋佳、撮影:飯泉早希(本人提供)