「営業だけはやりたくなかった」
—— 杉本さんは、法人営業のやりがいや極意をツイッターなどで日々発信していますが、最初は営業をやりたくなかったそうですね。
むしろ営業「だけ」はやりたくない、と考えていたクチです。
小さい頃に吃音(きつおん)持ちだったこともあり、コミュニケーションそのものに苦手意識を持っていました。
新卒で大手通信会社に入社したのですが、そのときもエンジニアやコンサルを志望していました。とにもかくにも、営業だけは嫌だったんです。
ただ、なんのいたずらなのか、配属先は法人営業の部門でした。キャリアのスタート時点が、仕事に対するモチベーションが最も低い時期だったと思います。
——「営業嫌い」だった杉本さんが、なぜ今も営業を?
実際に働いてみて、仕事のイメージが覆されたんです。
営業と聞くと、ノルマがあるとか、頭をペコペコ下げるとか、泥くさいイメージを持つ人が少なくないと思います。
もちろんそうしたシチュエーションはありますが、あくまで一部であり、むしろ楽しくて仕方がない仕事でした。
例えば、顧客から信頼を得て大きな発注をいただけたり、モノを売るだけでなく事業を推進したり、営業はイメージしている以上にやりがいのある仕事です。
自分が携わった仕事が新聞に取り上げられたときは、社会に良い影響を与えられたんだと実感できて、本当にうれしかったですね。
結局10年以上にわたり、法人営業一筋のキャリアを歩んでいます。
—— これまでの経験を振り返り、印象的だった仕事を教えてください。
例を挙げればキリがありませんが、前職のLINEにいたとき、ヤマト運輸と提携した事業が強く印象に残っています。

私たちは日常的に運送サービスを使っています。おそらく、多くの人が再配達の依頼をしたことがあるでしょう。急用が発生しても、時間を改めて荷物の受け取りができる便利なサービスです。
しかし、ドライバーさんにかかる負担が問題視されていますし、CO2の排出量が増えるので、環境にもよくありません。
特に近年はEC市場が拡大していることもあり、「不必要だったはずの再配達」が社会的な問題になりつつあります。
そうした背景から、荷物のお届け予定や不在連絡を「LINE」で通知でき、日時や受け取り場所の変更ができる仕組みをヤマト運輸と共同で開発しました。
ただ、当時のLINEは上場前で、社会的な信用が今ほど高いわけではありませんでした。一方、ヤマト運輸は歴史のある会社です。
門前払いとはいいませんが、取り組みが実施されるまでには、少なからず困難がありました。
それでも、課題を解決したい、絶対に成功させたいという思いで取り組み続けた結果、アイデアが形になったんです。
両社がプレスリリースを発表したあとは、瞬く間に利用者が増えていきました。
ユーザーは配達時間をリアルタイムでコントロールでき、ヤマト運輸はコストの削減はもちろん、サービスが向上して、ドライバーさんは負担が減る。
このような三方よしのサービスをリリースでき、「便利なサービスだよね」という声も聞こえてきて、営業として働く意義を強く感じました。
本① : 「営業嫌い」を変えたバイブル本
—— 営業に対する苦手意識があったにもかかわらず、成果を上げられるようになったのはなぜですか?
現場で教わったこともありますが、書籍にも助けられてきました。
私にとっての“バイブル”は、デール・カーネギーによる『セールス・アドバンテージ』(創元社)です。
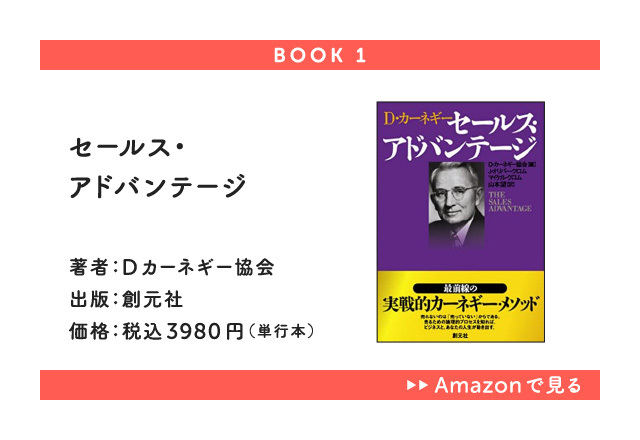
本①:『セールス・アドバンテージ』(創元社)
社会人1年目のときに、「営業は嫌だ、でもなんとかしないといけない」と、わらにもすがる思いで手に取った書籍でした。
同書では、ビジネスチャンスの創出から受注後のフォローアップまで、営業職がかかわる仕事のフローを13のステップに分けて解説しています。私はこの本に、営業に求められるマインドを全て教わりました。
中でも印象だったのが、「面会」のフェーズです。
営業の成果は、販売する商品やサービスの質にある程度依存します。しかし、カーネギーは、「この人に任せれば安心だな」という信頼がなければ、そもそも受注するのは困難だといいます。
例えば、「電話への迅速な対応」といった基本の積み重ねが信頼をつくっていくことなど、同書から得た学びは今でも私の営業活動を支えています。
—— 迅速な対応が難しいときはどうするのでしょうか?
連絡が来る想定ができているなら事前に伝えておきますし、すぐに対応が難しい際は「のちほどお返事します」と一報を入れることくらいはできます。
ささいなことに感じるかもしれませんが、それらの積み重ねが信頼の構築につながるんです。
—— たしかに、それだけで随分と印象が良くなる気がします。
今だからこそわかることですが、『セールス・アドバンテージ』の13ステップは結局、社会人が実践すべき根本のスキルなんです。
営業職以外の方にも同書を紹介しますが、みなさん喜んでくれます。「後輩や部下にも読ませます」といってくれる人がいるくらいです。
私にとってのバイブルは他にもありますが、お薦めの書籍を問われたら、まず『セールス・アドバンテージ』を紹介しています。
本②・③「脱・売るだけの営業」を実現する二冊
—— 営業職として成果を上げるうえで、参考になった書籍を他にも教えてください。
世界的な名著ですが、『影響力の武器』(誠信書房)も参考にしています。
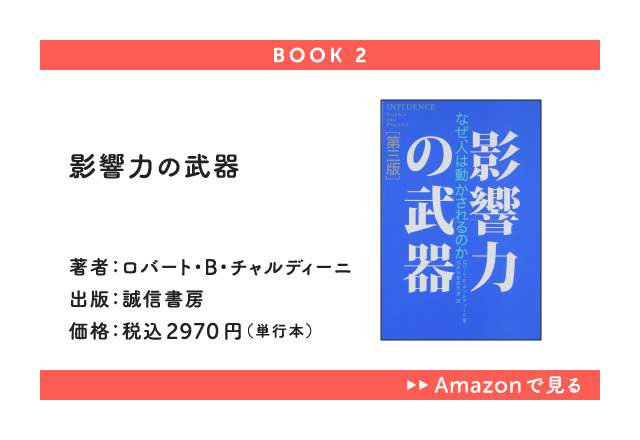
本②:『影響力の武器』(誠信書房)
同書は、人がどのような心理的メカニズムで動かされるのかを、社会心理学の観点から解説しています。
例えば、「これはお客様だけに話しますが......」といって特別感を持たせる「希少性の原則」など、営業に生かせるテクニックが網羅されています。
また、本書で紹介されているテクニックを身につければ、相手をだまそうとする悪徳営業から身を守ることもできます。いうなれば「護身の書」です。
営業パーソンに限らず、全ての社会人に読んでいただきたい一冊として推薦します。
商品を販売するのではなく、事業を推進する営業パーソンを目指すなら、マッキンゼー出身のトム・ピーターズが上梓した『セクシープロジェクトで差をつけろ!』(CCCメディアハウス)がお薦めです。
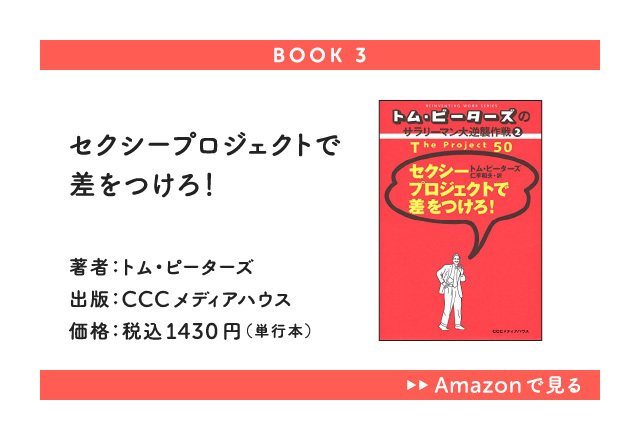
本③:『セクシープロジェクトで差をつけろ!』(CCCメディアハウス)
この本のメッセージの一つが「共謀者を探せ」です。
これまでの仕事を振り返ると、“共謀者”を見つけたことでうまくいった経験がたくさんあります。
先述したヤマト運輸さんの事例もですが、前職時代に、キリンと取り組んだ次世代自販機「Tappines(タピネス)」という事業もその一つです。
自動販売機とLINEをBluetoothで接続し、ドリンクを購入するとポイントがたまって、ポイントでドリンクチケットがもらえるサービスなのですが、当時はスマホと自動販売機をコネクト(接続)する段階で技術面のハードルがありました。
どうやって壁を突破しようかと頭をひねりましたが、1人ではどうしても妙案が浮かびません。
そこで、技術に明るいエンジニアを、社内、先方を問わず探しました。
すると、事業とは関係のないところでシステム開発をしていたメンバーたちに出会えました。
彼らを共謀者としてプロジェクトに招き入れたところ、その技術力をもって、壁を乗り越えることができました。
自分の力でなんとかしようとすることも大切ですが、やはり1人では限界があります。ただ、仲間の力を借りれば、難題を解くことも可能です。
同書からは、単なるテクニックではなく、事業を成長させるための方法論を学ぶことができました。
本④・⑤:営業テクニックよりも大切なことを学ぶ二冊
—— 営業テクニックを学ぶことだけが、営業パーソンのすべきことではないのですね。
私はそう思います。
そうした意味で、シェークスピアの『マクベス』(新潮社)も私のバイブルです。
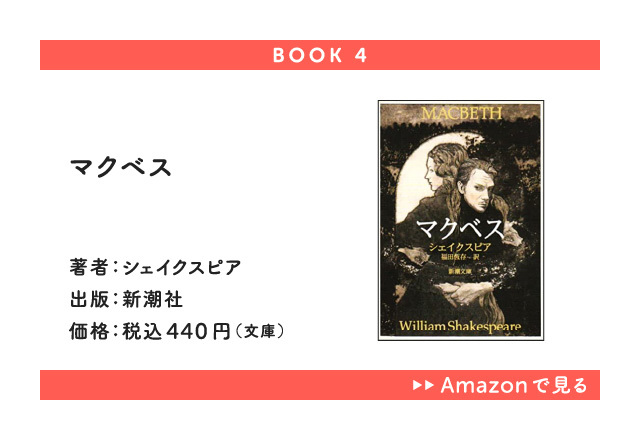
本④:『マクベス』(新潮社)
私は、営業は「人を見て、人を動かす仕事」だと考えています。
人を動かすには、相手のことを理解する想像力が必要で、シェークスピアの人間劇には人の心を理解するためのヒントが詰まっているんです。
以前、会社が主催するインターン生向けのビジネスコンテストで、興味深いシーンに出会いました。
コンテストの概要は、学生がチームに分かれて、アイデアをアパレル業界のお客さんに提案するというものです。
あるチームは、市場のニーズをくみ取った、非常に優れたアイデアを提案しました。唯一欠点があるとすれば、価格設定の詰めが甘かったくらいです。
他のチームは、アパレルへの愛が詰まったアイデアを提案しました。ただ、アイデアの磨き込みが不十分で、ビジネス視点では前者の方が優位に見えます。
しかし、選ばれた提案は後者でした。
コンテストが終了したあと、審査員に「前者のアイデアが、価格設定まで秀逸だったらどうしたか?」と聞いてみたんです。
すると彼は「それでも後者に票を入れる。私は一緒に仕事をしたいと思える人を選ぶ」といいました。
実際のビジネスシーンではないものの、お客様が営業を選ぶときの本質を見た気がしたんです。「営業パーソンは、こうでなくっちゃ」と。
カーネギーの『セールス・アドバンテージ』にも通じますが、人はサービスの品質だけに動かされるわけではありません。「一緒に仕事がしたい」と思われるビジネスパーソンを目指すなら、テクニックだけに目を向けているようでは不十分です。
もし一流の営業パーソンを目指すのであれば、ノウハウ本だけでなく、『マクベス』のような文学も手に取ってみてほしいです。
リッツ・カールトンの日本支社長を務めた高野登さんの『リッツ・カールトンが大切にする サービスを超える瞬間』(かんき出版)も、生き方を教わった書籍です。
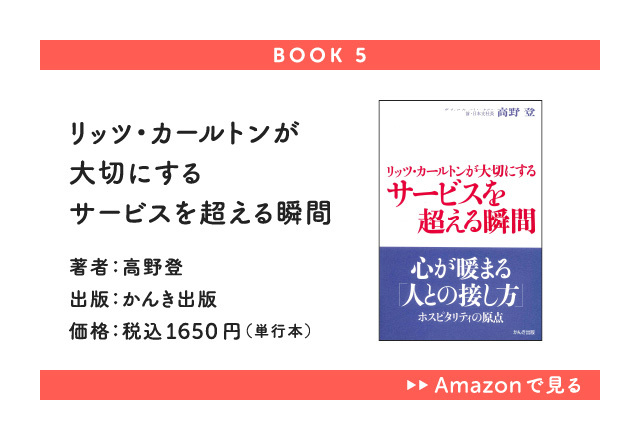
本⑤:『リッツ・カールトンが大切にする サービスを超える瞬間』(かんき出版)
同書で紹介されているリッツ・カールトンのスタッフの振る舞いには、営業パーソンとしてではなく、1人のビジネスパーソンとして学ぶことがたくさんありました。
例えば、「浜辺でプロポーズをしたいから、彼女が座るための椅子を残しておいてくれ」という要望への対応です。
スタッフの方は、椅子だけでなくシャンパンやお花を用意し、足に砂がつかないよう砂浜にタオルを敷いたそうです。
「ドリルを欲しがっているお客さんが本当に欲しいのは、ドリルではなく穴である」という話を思い出しましたね。
書籍は“人生の羅針盤”になる
—— 書籍から学んだことが、仕事に生かされた経験はありますか?
リッツ・カールトンのスタッフに学んだ、「お客様に感動を与える仕事」を実践した結果、億単位の受注をいただいた経験があります。
先方が事業を海外展開するにあたり、出張に同行して、一緒に現地を視察したときのことです。
先方は、現地で利用する通信サービスを比較検討しなければなりませんでした。その際に、私は出張報告書の代筆をしたんです。
会社では、サービスを選ぶための出張が終わると、担当者が社内に報告書を提出する必要があります。
出張は、終わったあとも大変なんです。
そこで、当たり前ではありますが、よりサービスに詳しかった私が、その役割を一手に引き受けることにしました。
要するに、お客様が体一つで出張に行けるよう手はずを整えました。
そして、仕事には直接関係ありませんが、「旅のしおり」も作成し、短い期間でも出張を存分に満喫できるよう、観光地や飲食店をリサーチしておいたんです。
出張先で、先方は大変に喜んでくれました。事業がうまくいきそうだと信頼してくれたことはもちろん、ちょっとした工夫があったからこそ、大型受注をいただけたのだと思います。
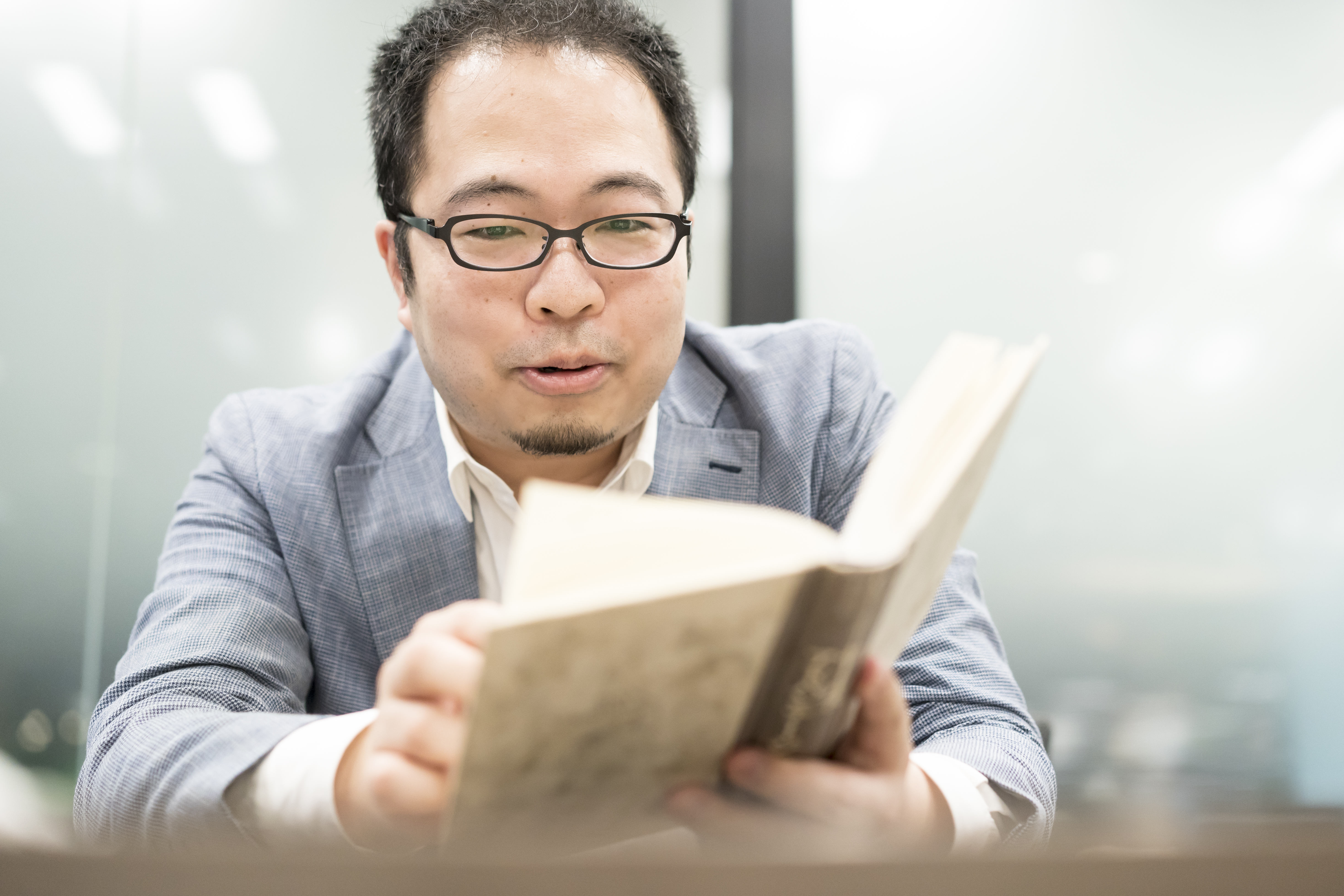
—— 杉本さんのように、書籍の学びを仕事に生かすには、どのようなアプローチが求められますか? 若手ビジネスパーソンにアドバイスをお願いします。
まずは、たくさんの本に触れることだと思います。
今回は5冊の書籍を紹介しましたが、影響を受ける本は人によって違います。
ですから、本屋さんに足を運び、さまざまなテーマの書籍を手に取ってみてください。
そのうちいくつかの書籍が、人生の羅針盤になっていくはずです。
生涯の友といえる書籍に出会ったら、今度は何度も読み返してみてください。すると、気が付いた頃には日々の行動が変わり、成果もついてくるのではないかと思います。
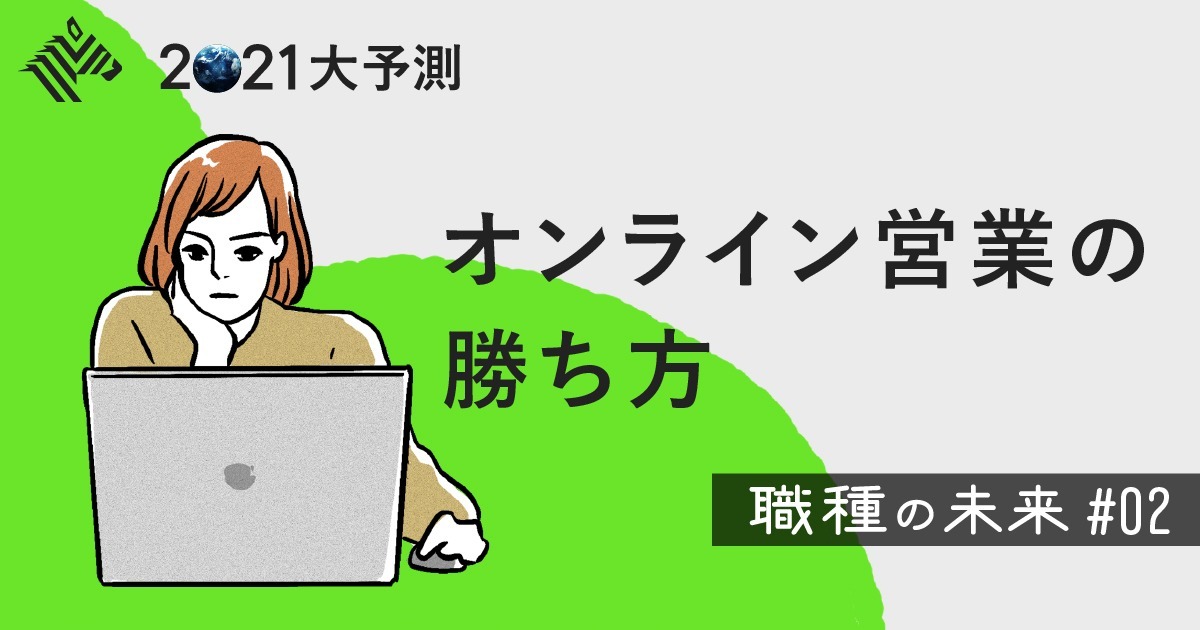
合わせて読む:【仕事の未来】2021年、営業に求められる「3つの力」
取材・文:齋藤知治、編集:佐藤留美、オバラ ミツフミ、デザイン:岩城ユリエ、撮影:大隅智洋