2022年9月の人気記事ランキング
2022年9月1日〜9月27日までの間に、JobPicksで閲覧数の多かった記事トップ5はこちら。
今月の1位は、本業とは異なる「企業分析」のノウハウを独学・発信し続けたことで、Twitterでフォロワー5万のインフルエンサーになった奥村さんのキャリアインタビューとなった。
.png)
1位:【奥村美里】企業分析でフォロワー5万人「箔より自信」のキャリア術(2022/9/9)

2位:経営コンサルも実践「短期間で顧客の心をつかむ」ワザ9選(2022/9/14)
.png)
3位:三井物産「異例の新卒5年目社長」を育てた、結果を出す人の行動学(2022/8/5)
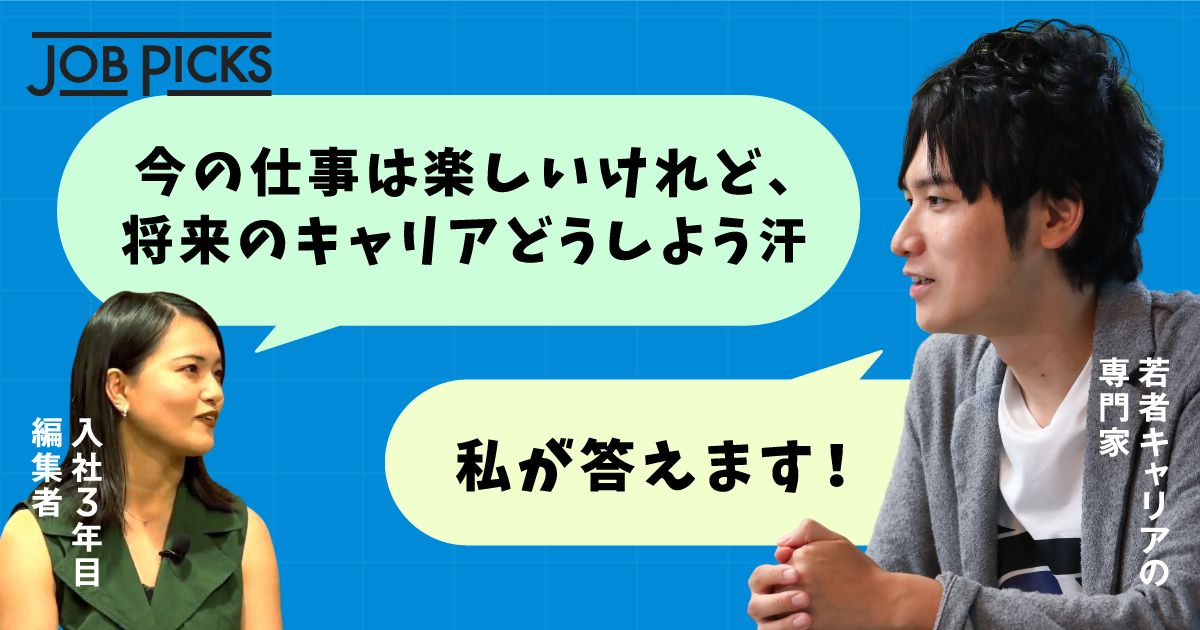
4位:【なぜ】残業も叱責もない「働きやすい職場」を去る若者の本音(2022/9/22)
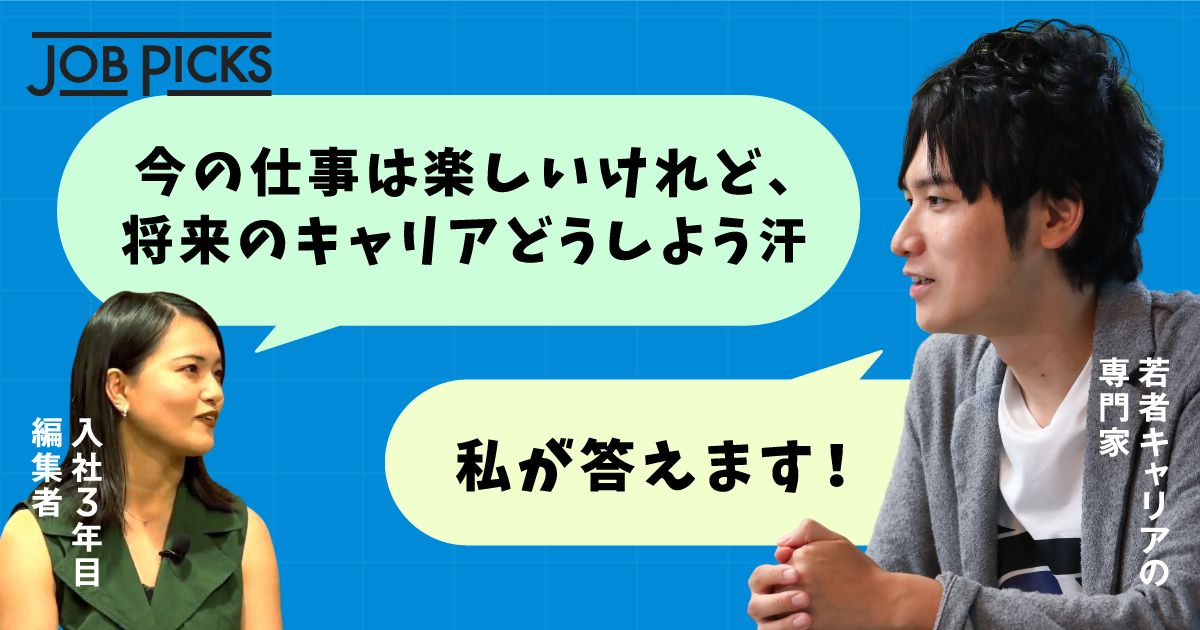
5位:「目標から逆算」は無意味。新卒3年、キャリアの悩みはこう解消せよ(2022/9/16)
奥村さんが企業分析ツイートを始めたきっかけは、学生時代に参加した長期インターンで周囲の仲間との能力差を痛感したからだそう。
「このままではまずい」という焦燥感から、偶然見つけた企業分析セミナーに参加し、以降、独学した成果をツイートするのを習慣化したという。
その結果、ベンチャー企業のタイミーへの就職後は希望していた財務・IRの部門に配属されるなど、キャリアに好影響をもたらすようになったのだ。
こうした小さなアクションが転機を生むことは、5位に入った記事でキャリア研究家の古屋星斗さん(リクルートワークス研究所)がアドバイスする「キャリアのモヤモヤ解消法」とも合致する。
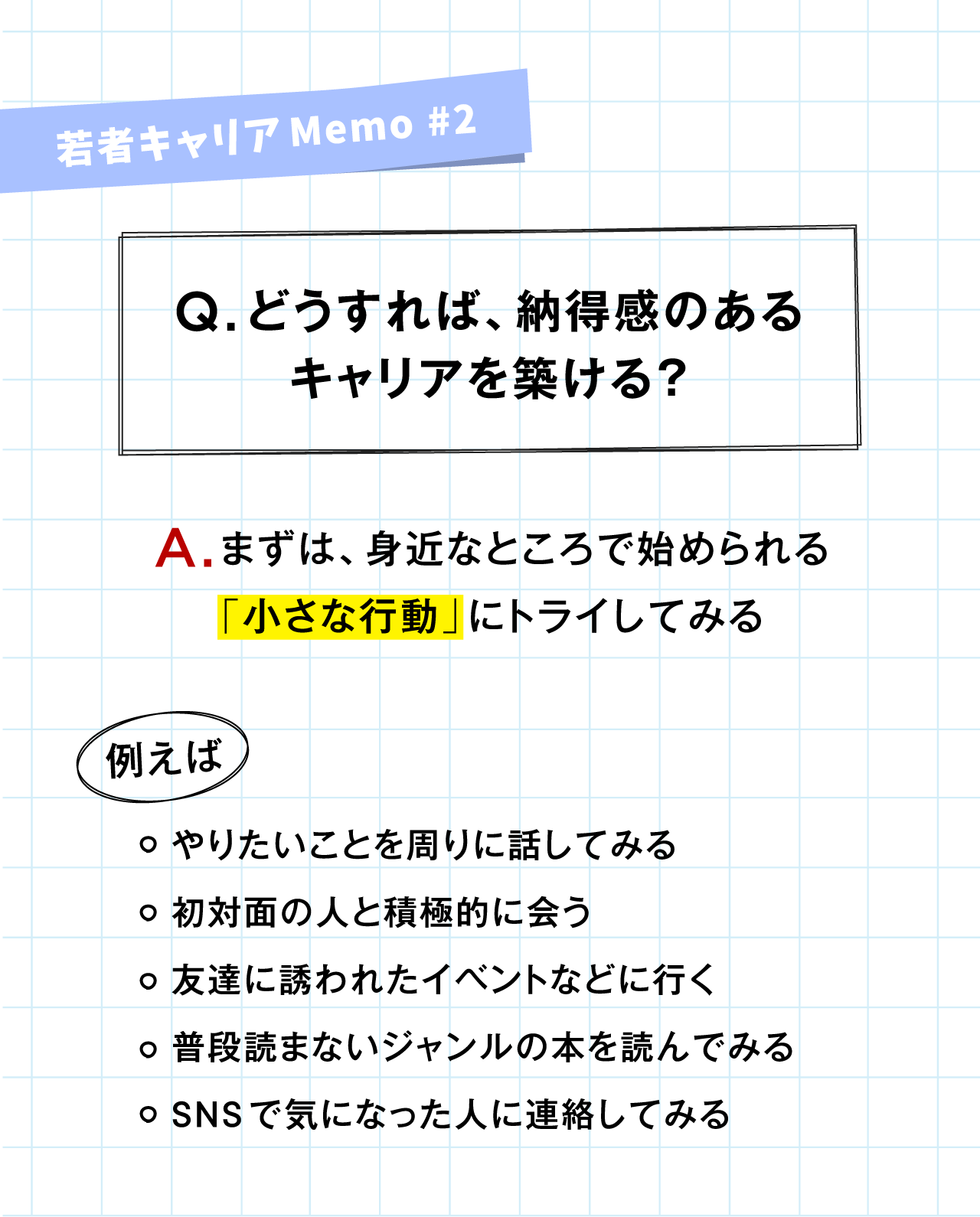
そこで今回は、奥村さんのように「小さく始めた行動」がその後のキャリア形成に大きな影響を与えるようになったというロールモデルの経験談をいくつか紹介しよう。
好きで続けられる事柄を極める
独学の結果をSNSでアウトプットし続けたらキャリアが大きく変わったというもう1人のロールモデルが、Twitterで「パワポ芸人」として知られる豊間根青地さんだ。
今はフォロワー10万を超えるアカウント「トヨマネ(@toyomane)」の名前で知られる彼が、パワポでの情報整理術を発信し始めたのは、本業とは関係ない出来事だったという。
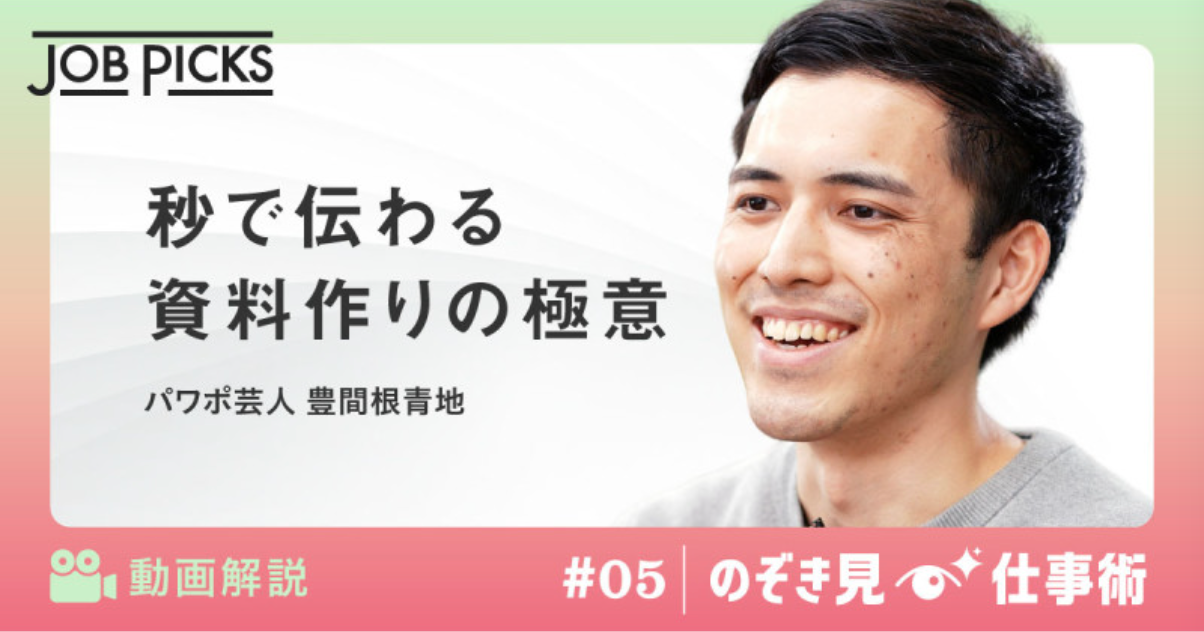
【トヨマネ】フォロワー7万のパワポ芸人が伝授「スライド作成8つの鉄則」
下の記事によると、新卒でサントリーに就職して通販事業の販促に携わる中で、上司に「相手の気持ちを考えて情報を整理する」という基礎をたたき込んでもらったのがパワポに開眼するきっかけだったという。

【山下良輔×トヨマネ】28歳までにどうなりたい?から考えるキャリア論
どうすれば、言いたいことが伝わるかを考えた結果、ロジカルかつストーリーのある資料づくりを意識する習慣が身についたんです。
(中略)僕は、一度自分の中の「これが好きだ」という感覚を言語化するのがいいと思います。
具体的には、今までの人生で自分が楽しいと感じた瞬間を列挙して、共通点を見つけていくんです。
たとえば、「新歓イベントの時みたいに、いろんな人と会って話をしている瞬間が好きだな」とか「部活のように、目標を立ててそこに向かってチームで頑張っているのが好きだな」といった具合です。
僕自身も、パワーポイントが大好きなのは間違いないんですが、ツールそのものが好きでパワポ芸人になったわけではありません。
それ以上に、「物事をかみ砕いて、分かりやすく、面白く、人に伝える」ことが好きで、たまたまその手法として、最も適していたのがパワポだった、という感覚に近いです。
自分のなかで、この「好き」という感覚が言語化できていると、就職する時だけではなく、社会人になって転職したり、将来のキャリアを考える時にも有効な「判断軸」ができ上がると思います。
トヨマネさんの場合、この「好きでやり続けられる事柄」を見つけた結果、2022年には企業・個人のビジュアルコミュニケ―ションを支援する会社Cataca inc.を創業することになった。
本業で身に付けた知識やスキルだけがキャリア形成につながるわけではないという好例だ。
「推し活」すらキャリアの転機に
趣味的に始めた事柄が、本業になったという別の事例も紹介しよう。
専門商社で働くかたわら、グッズ企画・制作を手掛けるデザインスタジオ・R11R(アールイレブンアール)を起業した片口陸さんだ。
起業の詳しい経緯は下の記事に譲るが、片口さんが年商数千万円の“副業”を始めたきっかけは、アイドルの「推し活」にあったという。
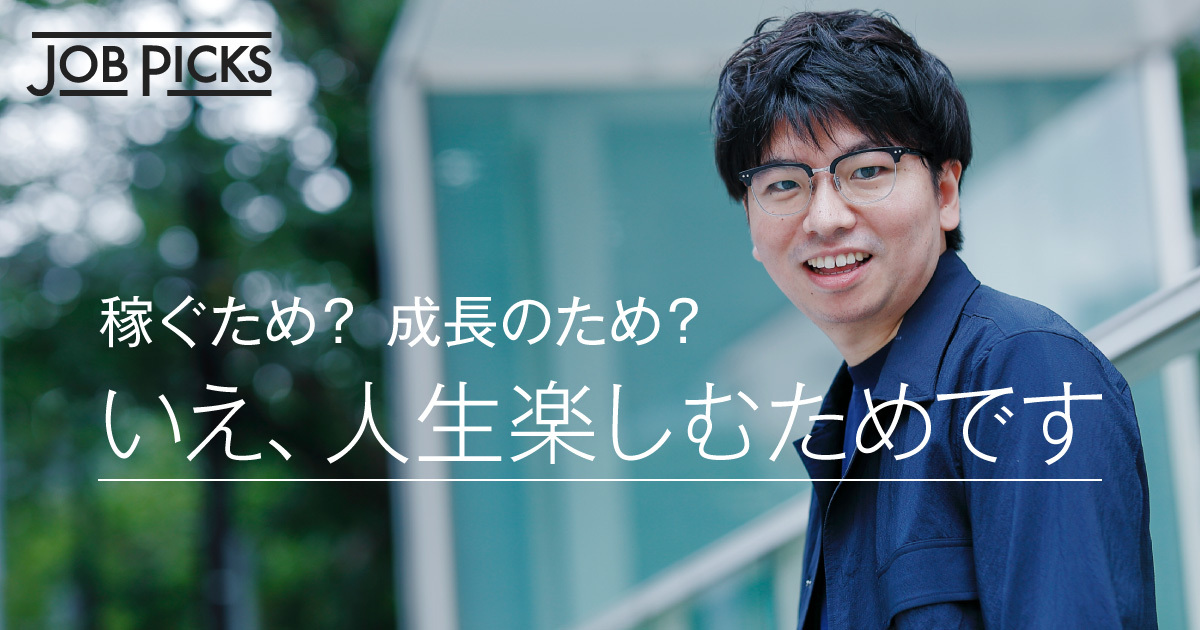
【CEO】起業は「好きを仕事にする手段」元銀行員の新しい副業スタイル
(追っかけをしていたアイドルグループの)開催されているほとんど全てのライブに足を運んでいましたし、同じCDを何枚も購入していたので、ちょっとした有名人になっていました。
その結果、推しのメンバーの誕生日を祝うライブで企画の責任者をさせてもらえることになったのです。
そこで私は、オリジナルTシャツの制作を提案しました。ビジネスではないので原価でお配りしましたが、それが飛ぶように売れて……。この経験が、起業のきっかけになっています。
この推し活を始める前は、地元・富山県の地方銀行に勤めていた片口さん。そこで融資営業をしている中で、働く意義を見失ってしまったことから、「もっと人生を楽しみたい」と一念発起して上京したのだ。
これが、会社勤めをしながら自らの会社を経営するというダブルワークの“エピソード・ゼロ”になっている。
ストレスなく過ごすための行動が、自身のキャリアに思わぬ転機をもたらした形だ。
身近な人を喜ばせるのが学ぶ力に
次は、「身近な人を助ける」ために始めた行動が、天職を見つけるきっかけになったという川俣涼さんのキャリアを紹介しよう。
下のインタビュー記事にもあるように、川俣さんは消防士からエンジニアに転身するという稀有な経験をしている。
未経験転職に挑もうとしたきっかけは、妻が開業した鍼灸院の公式サイトを作ることだったという。

消防士からエンジニアへ、究極の「未経験転職」3つのポイント
学生時代に部活のホームページを作った経験があったため、妻から依頼されました。
写真を自分で撮って、予約フォームも実装して。独学で学びながら作りました。
次第に「茨城県 鍼灸」で検索するとトップに表示されるようになり、ホームページ経由でたくさんのお客さんが訪れ、1カ月先まで予約が埋まるようになったんです。
自分の創意工夫が、妻の反応やお客さんの予約数など、目に見える結果として表れるのが楽しくて仕方なくて。
夢中になるうちに、患者管理のWebアプリや、確定申告用の売り上げ仕分けの自動化など、裏側の業務改善の仕組みまで作り込んでいました。
消防士として24時間勤務したあとの休日は、自分の好奇心のおもむくまま、勉強し続けていました。
消防士は心身ともに大変な仕事だ。それでも「休日を使ってでも勉強したい」と思えたのは、自らの書くコードで喜ぶ人の姿があったからだろう。
将来性や収入の良さを考えてプログラミングを学ぶより、学習意欲が持続しやすいのも容易に想像できる。
身近な人を助ける、喜ばせるという動機のパワーがここに隠されている。
頼まれ仕事で意外な強みを発見
人が喜ぶことをするという行動は、何も能動的である必要すらない。
他人に求められたことを「まずやってみる」ことが、自身の強みを再認識させるきっかけになることもあるからだ。
社員の7割が女性という営業アウトソーシング企業「Surpass」の取締役を務める青木想さんは、リクルート→ジブラルタ生命保険を経て起業している。
30代のシングルマザーとして起業した時、“事業の種”を見つけた瞬間は、知り合いに頼まれてやるようになった経営企画セミナーにあった。

【決断】31歳で外資生保に転身。元リク経営企画の戦略的キャリア
きっかけは本当にたまたまで、起業家コミュニティの代表と知り合いになったことです。
当初は法人保険の開拓をしたくてコミュニティに通っていたのですが、ある日その方から「青木さんはリクルートで経営企画をしていたそうなので、起業家向けに経営管理に関するセミナーをやってくれませんか」とお声がけいただきました。
リクルート時代は、毎日「総勘定元帳」という、6000〜7000行におよぶエクセルのシートとにらめっこをしていました。だから、帳簿を見せてもらえば、その会社が何で収益を上げていて、どこに経営上の課題があって、何が問題なのか見当がついたのです。
起業家や経営者の方なら、きっとご自身で経営管理をしていたり、経営企画の方が会社にいたりするのだと思っていました。でも、実際にはそうではなかった。
このときに初めて、自分の経営企画での経験が「武器」になるのだと知ったんです。
私の経験が役に立つなら、とセミナーを開くうちに、保険の相談に加えて、経営の相談をいただくようになりました。
上のコメントにもあるように、自分の強みは案外「自分では分かっていない」もの。
この強みを見いだすのに、最も手っ取り早い手段が、頼まれ仕事をやってみるというアクションだ。
近年は「会社に頼って生きていてはダメ」「自ら戦略的にキャリア形成を考えなければならない」という言説をよく耳にするが、青木さんはこの風潮に違和感を持っているという。
よくある勘違いは、戦略における「HOW=手段」に重きを置き過ぎることです。
今は環境に恵まれていて、Twitterや書籍、Web記事などを通して多くの人のHOWを知れますし、どうやったら成功できるのかを簡単に学ぶことができます。
だから、「HOWをギチギチに組み立てること」が戦略だと考えている人が多いように思えるんです。
「外資系コンサルでとりあえず3年は働こう」「次は、実務経験を積むためにスタートアップに転職しなければ」といった具合に、です。
でも、外資コンサルで働くことも、スタートアップに行くことも、あくまで「手段」でしかないですよね。
大事なのはその先に、何を得たいのか、自分はどうなりたいのか、なのです。
(中略)一番大事なのは、「WHAT=ありたい姿」を決めることです。将来こうなりたいとか、半年後にこういう状態になっていたいという、到達したい「点」ともいえます。
この「点」を探すためには、求められたことをやってみるという「小さな行動」も意味があるという話だ。
最初は「意識低い系」でいい
最後は、まだ社会に出ていない学生にも役立ちそうなエピソードを紹介しよう。
現在はデザインファームのグッドパッチでUXデザイナーをしている藤原彩さんは、北九州市立大学の出身だ。いわゆる地方大学生で、首都圏の学生が「意識高く」就活に臨んでいるという情報を、斜に構えて受け止めていたという。
そんな彼女を変えたのは、身近な友人の留学話。意思を持って未来を切り開こうとする友だちの姿を見て、焦りを感じたのだ。
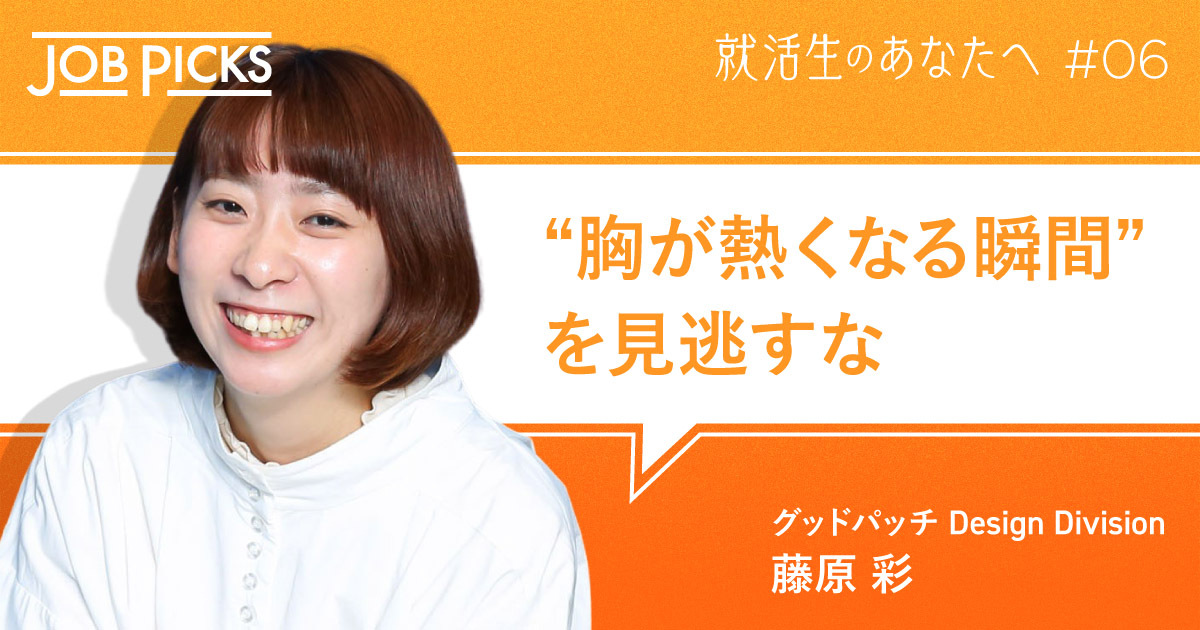
【Goodpatch・26歳】自分の人生は、ドラマチックにデザインしよう
私とその親友は、どちらかといえばキャリア意識の低いタイプでした。
“自分を持っている同級生たち”を尊敬していましたが、同じように夢を追う勇気はなく、「なかなか“あっち側”には行けないね」という会話をしていたことを鮮明に覚えています。
でも、ある日突然、友人が「留学することにした」と言い出したのです。
昨日まで“こっち側”にいたはずの彼女が、いきなり“あっち側”に行ってしまう。
「そうなんだ」と気丈に振る舞いましたが、内心は「自分だけが、自分の人生について真剣に考えていない」という焦りでいっぱいでした。
とはいえ、焦っているだけでは、なにも始まりません。
親友につられるように、私も将来について真剣に考えはじめました。
その後、藤原さんは「将来について考えられるだけの経験を積もう」と休学を決意。上京して長期インターンに挑戦しようと行動を起こした。
上京前に内定を得ていた会社で突然不採用になるなど、いくつかの不運もあったそうだが、人づてに現在の勤め先であるグッドパッチを紹介されてインターン入社。
そこから、「学生時代はUXデザイナーという仕事があることすら知らなかった」藤原さんのキャリアが始まった。
キャリア形成に関する有名な理論に、「計画的偶発性理論」がある。
個人のキャリア形成の8割は、偶然の出来事に影響を受けている。とはいえ次の5つを大事に行動すれば、「後で振り返ると計画していたかのように」キャリアを築くことができるという内容だ。
好奇心(Curiosity)新しいことに興味を持ち続ける
持続性(Persistence)失敗してもあきらめず努力する
楽観性(Optimism)何事もポジティブに考える
柔軟性(Flexibility)一つの事柄にこだわり過ぎない
冒険心(Risk Taking)結果が分からなくても挑戦する
今回紹介したロールモデルたちも、このうち、いずれかに則って行動していたことが分かるだろう。
将来が不安だと嘆くより、まず行動を。人に言われたら「ど正論」と感じることを、実際の行動に移せるか否か。これが明るい将来を呼び込むのだ。
【参加型】安宅和人氏らと描く「3年後の自分を変える」シナリオ文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー写真:iStock / Alexey Yaremenko