いま、私が「22歳だったら」
—— 工業高校を卒業後、地元の企業に就職し、2度のコンサルファームへの転職を経て独立した山下さん。いま、キャリアのスタートラインに立ったとしたら、どんな企業に就職したいですか?
山下良輔(以下、山下) いま新卒なら、大企業などある程度大きな組織で働いた経験がある人や、過去に起業経験がある人がつくった「大人ベンチャー」を選びます。
.png)
これまでの転職経験を踏まえて痛感するのは、どんな仕事でもまずは論理的思考や仕事の段取り、社内外の人との調整といった「ベーシックなスキル」が求められるということです。
そして、これらを身につけるには、ある程度組織体制が整っていて、かつ若手にも挑戦の機会が回ってくる会社で働くのが近道。
社会人経験が浅い人が起業したベンチャーも勢いがあっていいかもしれませんが、目の前の利益を追うことが優先され、組織としてはあまり成熟していないケースもしばしばです。
一方、大企業は教育体制などはしっかりしていますが、人数が多いため、打席に立てる回数が限られています。
なので、大企業とベンチャーのいいとこ取りができる「大人ベンチャー」が、僕にとってはベストなファーストキャリアだな、と。
—— 山下さんが最初に就職した企業も、いわゆる「大人ベンチャー」だったのですか?
山下 いえ、創業60年ぐらいの地方の中小企業です。ただ、新規事業が多く展開されていたので、ベンチャーのような気風がありました。
自分も「もっといろいろな経験を積みたいです」と上司に頼みこんだ結果、入社5年目の22歳で海外で工場を立ち上げるプロジェクトのリーダーに選んでもらえました。
そこで、ゼロから仕事をつくる経験をしたことが、その後のキャリアにもプラスになっています。
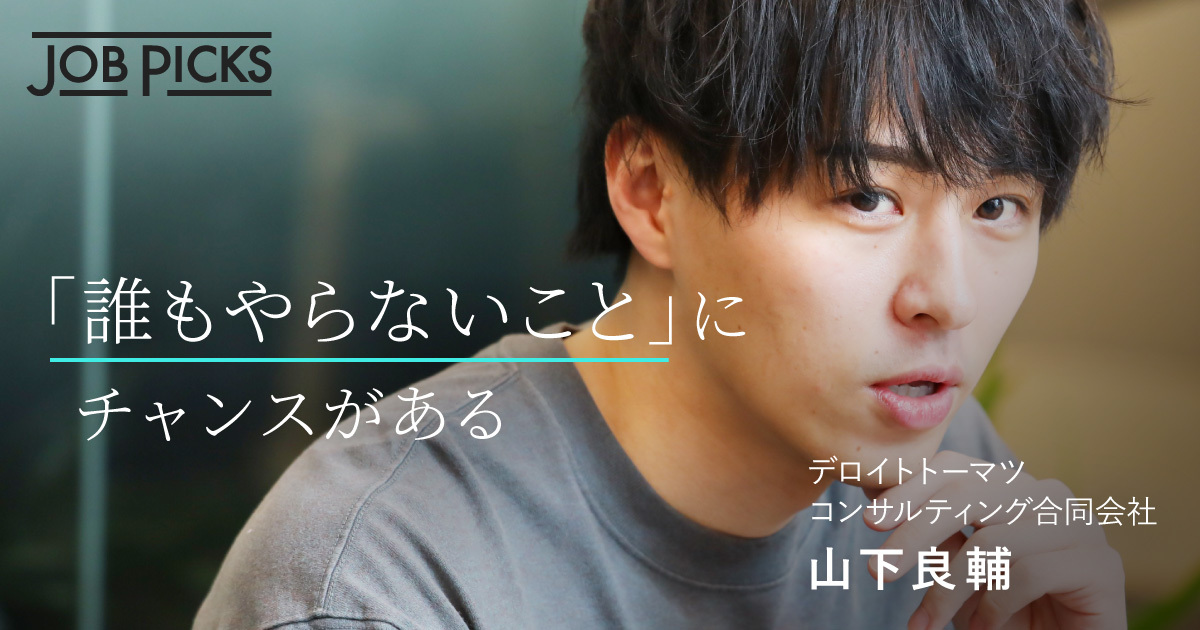
【山下良輔】工業高校から、有名コンサルに転職した31歳の逆転人生
なので、仮にベンチャーでなかったとしても、僕だったら「若手でも大きな仕事を任せてもらえるか」とか「新規事業部門に配属される可能性があるか」という観点で企業選びをすると思います。
—— 新卒でサントリーに入社し、趣味として発信していた「パワーポイント術」を武器に独立された豊間根さんはどうですか?
豊間根青地(以下、トヨマネ) そうですね……。あまり答えになってないかもしれませんが、22歳の自分が心から「ときめく」企業に行くと思います。
「ときめく」というと抽象的に聞こえるかもしれませんが、働いた経験がほとんどない就活期こそ、特に「直感」を大切するといいんじゃないかな、と考えていて。

会社説明会に行ったり、実際にその企業の社員と話をしたりして抱く企業のイメージって、やっぱりその会社の風土やカルチャーに紐付いているものが多いんですよ。
それこそ、サントリーは就活生だった僕が「いい人多そうだな」「さわやかそうだな」と入社を決めたのですが、実際に入ってみたら、本当にいい人たちばかりで(笑)。
なので、キャリアのスタートラインに立ったとしたら、まずは企業のことを調べたり、社員と話をしてみたりする。そして、「ここで働きたい!」と食指が動いた企業に就職すると思います。
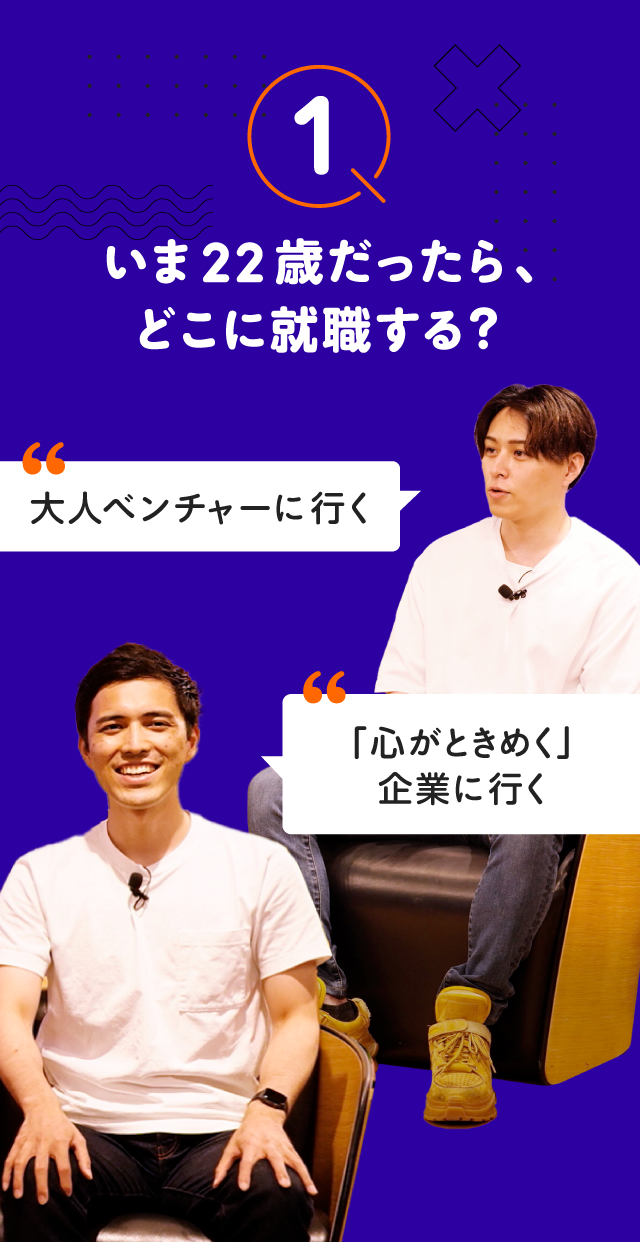
「石の上にも3年」は本当か
—— いまお話しいただいたような企業に入社したとして、お2人は、はじめの1〜3年目を具体的にどう過ごしたいですか?
山下 正直、1年目は仕事を覚えることで精いっぱいだと思います。だからこそ、大切なのは、「1年目の経験で学んだポイントを、2〜3年目の仕事に生かしていけるかどうか」。
仕事を続けていると、1年経ったくらいのタイミングで「このケース、前にもあったな」と、いろいろな反省や改善点が見えてくるものです。
なので、1年目は基礎固め、2年目は実戦経験を積んで、3年目の終わりまでには専門スキルを確立し、プロジェクトでちゃんと結果を出す。僕ならそんな風に過ごしますね。
トヨマネ 僕も、まずは「目の前に与えられた仕事に一生懸命取り組む」と思います。
「そんなの当たり前だ」と思われる方もいるかもしれませんが、こういうベーシックな部分を突き詰められるかが、後々の仕事に影響してくるんですよね。
.jpg)
特に、社会人になりたての頃は、どうしても派手なプロジェクトに目が行ってしまうものですよね。
ですが、むやみにキラキラしたものを追い求めるより、まずは、ちゃんと与えられた仕事をきっちりやって、結果を出す。
「半径5m以内の人の期待に真摯に応える」と言うか、人から信頼してもらえて初めて、大きな仕事ができるのではないか、と。
僕はいまでこそ「パワポ芸人」として独立していますが、そもそもパワーポイントに力を入れるようになったきっかけは、上司に「相手の気持ちを考えて情報を整理する」という基礎をたたき込んでもらったからなんですね。
どうすれば、言いたいことが伝わるかを考えた結果、ロジカルかつストーリーのある資料づくりを意識する習慣が身についたんです。
—— 入社しても3年はつらくても耐えるべきだ、という「石の上にも三年」についてはどうお考えですか?
トヨマネ 僕は一理あると思います。「最初はつらかったけど、続けてみると意外と自分にその仕事が向いていた」というケースもありますから。
やっぱり仕事が大変な時こそ、「会社のせいでうまくいかないんだ」と思うより、その経験をどう自分のものにできるかが、その後の成長にかかっている気がしていて。
これは持論ですが、基本「自責思考」と言いますか、人生は良い意味で「自分のせい」にしたほうが、楽しいし、生きがいにあふれたものになると思います。
ただし、いわゆるブラック企業など、理不尽を強いられる環境もあると思うので、そういう場合は早めに会社を変えるなどの選択をしたほうがいいかもしれません。
山下 そうですね。僕も、3年という数字で区切るというよりは、自分が持っているスキルと経験から、いまの会社に残るのがベストなのか、他の選択肢を取ったほうがいいのかを判断するのがいいと思います。
たとえば、3年目までは責任ある仕事を任されない会社でも、4〜5年目にはプロジェクトに参加できるとか、7年目以降に大きなチャレンジの公募がある、という話もある。
こうした「会社に残ることで得られるチャンス」を考慮しないで、「『石の上にも三年』が過ぎたので転職します!」というのは、ちょっとおかしな話ですよね。
そういう意味では、自分よりも2〜3年上の先輩が参加しているプロジェクトをリサーチして、まずは自社でキャリアを積むメリットを押さえておく。
その上で他社の仕事内容を調べて、都度比較検討をしていくのがいいかと。

「やりたいことがわからない」問題
——「やりたいことがわからない」と悩む就活生や若手社会人は少なくありません。お2人は、どうすれば「やりたいこと」が見つかると思いますか?
山下 難しいですね。まず「やりたいこと」と「やってみたいこと」は明確に違います。
ですが、おそらく、就職活動の時って多くの人が「やってみたいこと」で選んでいると思っていて。
たとえば、「マーケターになりたい」という就活生は少なくないですが、それは「やりたいこと」じゃなくて「やってみたいこと」ですよね?
多くの学生は、インターンなどでマーケティングの実務に携わった経験があるわけではないと思います。
なので僕からアドバイスがあるとすれば、「やってみたいこと」は全部やってみて、それからいいと思ったことを突き詰めていけばいい、ということです。
それこそいまの時代、リモートでできるインターンも増えていますし、たとえばSNSを使って自分で疑似的にマーケティングを体験することもあるでしょう。
で、実際にやってみて、それが本当に「やりたいこと」なのかを検証してみる。
はじめから「私がやりたいことはこれだと思う」と決め打ちするのではなく、少しずつチャレンジして絞っていく、というスタンスでいいと思います。
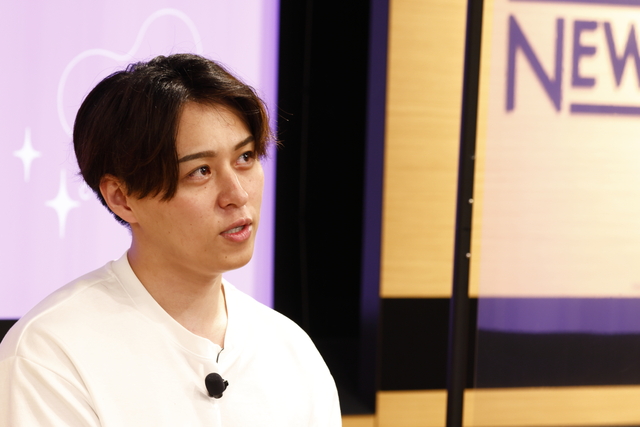
トヨマネ 僕は、一度自分の中の「これが好きだ」という感覚を言語化するのがいいと思います。
具体的には、今までの人生で自分が楽しいと感じた瞬間を列挙して、共通点を見つけていくんです。
たとえば、「新歓イベントの時みたいに、いろんな人と会って話をしている瞬間が好きだな」とか「部活のように、目標を立ててそこに向かってチームで頑張っているのが好きだな」といった具合です。
僕自身も、パワーポイントが大好きなのは間違いないんですが、ツールそのものが好きでパワポ芸人になったわけではありません。
それ以上に、「物事をかみ砕いて、分かりやすく、面白く、人に伝える」ことが好きで、たまたまその手法として、最も適していたのがパワポだった、という感覚に近いです。
自分のなかで、この「好き」という感覚が言語化できていると、就職する時だけではなく、社会人になって転職したり、将来のキャリアを考える時にも有効な「判断軸」ができ上がると思います。

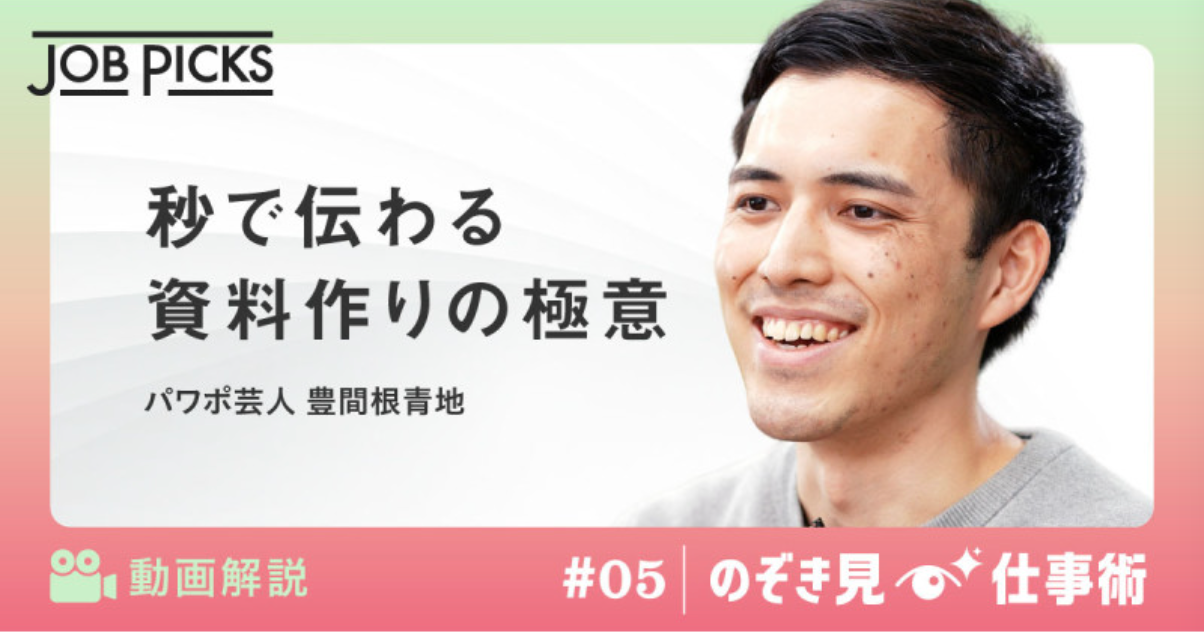
【トヨマネ】フォロワー7万のパワポ芸人が伝授「スライド作成8つの鉄則」
文:藤原環生、編集:高橋智香、デザイン:石丸恵理、撮影:竹井俊晴
編集部注(2022年11月14日):記事中で「デロイト トーマツ コンサルティング」を外資系と表記していましたが、正確には外資系ではないため、記載を変更いたしました。掲載後の修正をお詫びいたします。