「ありのまま」と「何者」のジレンマ
—— 長時間労働や上司による厳しいマネジメントがない、いわゆる「働きやすい」職場を去る若者が増えていると聞きます。一体なぜでしょうか?
古屋 結論から申し上げると、働きやすいがゆえに、「本当にこの職場にいて大丈夫なのか」と不安を感じているからです。
残業も休日出勤もないし、上司からの厳しい叱責もない。
それ自体は望ましいことですが、一方で若者たちは「きちんとスキルが身についているのか」「社会にとって有用な人間になれているのか」と、自身のキャリアの「サステナビリティ」を、非常にシビアに考えています。
私が入社1〜3年目の若手社員を対象に実施したインタビューでも、「業務量はほどほどで、会社の人間関係も良好。居心地はよいが、このままでは成長できないと感じて焦る」と答える方が一定いました。

こうした不安の背景には、若者たちの持つ、とある複雑な感情があると考察しています。
それは、「ありのままでいたい」と「何者かになりたい」という、時に矛盾するキャリア観を、同時に抱いていることです。
「好きな場所で、好きな時間に働きたい」「自分の強みを生かして、後悔なく仕事をしたい」と、世間など関係なく、“ありのまま”の自然体で過ごしたいと思っている。
一方で、「この職種で一人前になりたい」「30歳までに自分だけの成功体験を得たい」といった、“何者”かになり、社会で認められたいという気持ちもある。
SNSなどで、「ありのままに生きる人」と「若くして何者かになった人」のストーリーが繰り返しシェアされるなかで、こうした2つのキャリア観の間で揺れ動く若者が増えているのです。

現在の職場環境は、“ありのまま”への欲求には応えられていますが、“何者かになりたい”という欲求には、あまり応えられていません。
過剰な労働がなく、自分の行動に対して否定的なリアクションが来ない、「心理的安全性」が高い職場は増えました。
ですが、働きやすさを追い求めるあまり、他の職場でも通用するスキルが身につく、その後のキャリアの選択肢が増えるといった「キャリア安全性」の低い職場も、同時に増えてしまった。
この「キャリア安全性」の低い職場のことを、私は「ゆるい職場」と呼んでいます。
部下に「気を使う」上司たち
一方、今の若者たちの多くが求めるのは、「心理的安全性」と「キャリア安全性」の双方を満たす、働きやすいけれど「ゆるくない」環境です。
実際にデータを取っても、「職場が『きつい』と感じ、辞めたいと思う」方と同じくらい、「仕事に成長実感がなく、『ゆるくて』辞めたいと思う」方がいるとわかっています。
「入れば一生安泰」と言われた大企業を辞めて独立したり、スタートアップ企業に転職したりする事例が増えてきているのも、こうした背景からです。
—— 単純に、労働時間や待遇といった「働きやすさ」を改善するのでは、不十分だ、と。
ええ。そして、さらなる懸念は、こうした若者の不安に対して、直属の上司などマネジメント層がアプローチできていない、という点です。
というのも、自分たちが育てられてきた環境とはあまりに違いすぎて、どうマネジメントするのが正解なのかわからず、戸惑っている方が多いんです。

特に、コンプライアンスやハラスメントに関する研修も増えていますから、「どう仕事を振ればいいのか」「どこまで厳しく言ってよいのか」と気にするうちに、腫れ物に触るような扱いになる。
若者側もそうした上司たちの葛藤にうすうす気づいているけれど、なんと声がけしていいかわからず、その扱いを受け入れてしまう。
こうした不思議な「気の使い合い」によって、若者が成長実感を得られない環境が、どんどん増えていってしまっているのです。
フィードバック、もらえていますか
—— 具体的にどうすれば、若者の「キャリアの不安」を解消できるのでしょうか?
当事者である若者本人と、上長などマネジメント層、それぞれへのアプローチがあると考えています。
まず、若者本人の場合は、小さくてもいいから「何らかのアクションを取れるか」に懸かっています。
言葉にするとごく当たり前のことですが、やはりいくら悩んでいても、不安は解消されません。
それよりも、本当に「一歩踏み出せるかどうか」くらいの、小さな行動を取れるかどうかが、実は後々のキャリアに大きな影響を及ぼすことが、研究で明らかになっています。
たとえば、「興味を持った社外のイベントがあったら行く」「SNSで気になっていた人に、リプライを送ってみる」といった小さなアクションが、非常に大切なんですね。
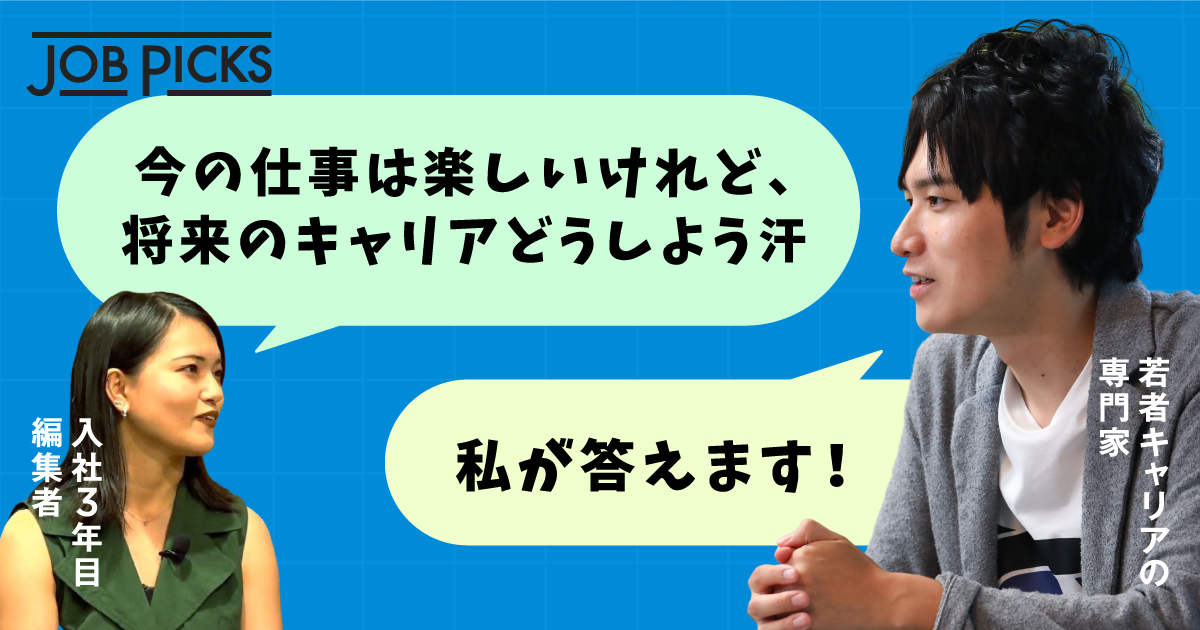
「目標から逆算」は無意味。新卒3年、キャリアの悩みはこう解消せよ
特に、私が今すぐアクションとしておすすめしたいのが、職場の人に日常的にフィードバックをもらったり、直接キャリア相談をしたりすることです。
「え?そんなに単純なこと?」と思われるかもしれませんが、期末の査定や1on1のタイミング以外で、業務のフィードバックをもらったり、キャリアについて話したりする機会って、案外少ないんですよね。
それでも直属の上長であれば、話す機会があるかもしれませんが、業務で週に2〜3回関わる先輩から、仕事についてコメントをもらうタイミングって、あるようで実は少ない。
ですが、一歩踏み出してフィードバックが欲しいと自ら話をすれば、自分の思いもよらなかった長所が知れたり、自分の伸びしろがわかったりする可能性があるわけです。
ちなみに、私がインタビューをした若者のなかには、「自分がセレクトした先輩30人から、徹底的にフィードバックをもらえるSlack(業務コミュニケーションツール)のチャンネルを作り、成長機会につなげている」という猛者もいました。
もちろん、いきなりそこまでやるのはハードルが高いと思いますが、一言話しかけてみる、少しメッセージを送ってみる、くらいのアクションであれば、取れる方も多いと思います。

とはいえ、「改めてフィードバックをもらうのはなんだか緊張する」という方もいるかもしれません。
ですが、先ほども申し上げたとおり、マネジメント側もどこまで部下に対してフィードバックをしていいか、戸惑っているケースが多いです。
つまり、若手側がフィードバックをほしいと思わなければ、何も起こらない。
直接それを伝えたほうが、その後の良好なコミュニケーションにつながったり、自分の希望する仕事が回ってきたりする可能性が高くなるわけです。
このように、フィードバック一つとっても、主導権が若者側に移りつつあるということを、まずはお伝えしたいです。
「仕事の巻き取り」はご法度
——マネジメント側は、どんなことを意識したらいいのでしょうか?
今お話ししたことの裏返しになりますが、「若者がアクションを起こしやすい環境を整えてあげる」ことが大切だと思います。
その足がかりとして、まずは本人がどういう志向を持っていて、何をモチベーションの源泉としているか、どういうサポートをしてほしいと思っているのか。
こうした点について、きちんとヒアリングする機会を設けるのも、マネージャーの重要な仕事の一つです。
一番望ましくないのは、「仕事を巻き取ってしまう」こと。
若手が仕上げきれなかった仕事に対して、「あとはやっておくから大丈夫だよ」と言って、フィードバックもあまりせずに、そのまま仕事を引き受けるパターンです。

若手に負荷をかけないという親切心や、労働時間などへの配慮があっての行動だとは思うのですが、これでは本人の成長につながりません。
むしろ、少々時間はかかるかもしれませんが、きちんとフィードバックをして仕事を差し戻し、若手ができるようになるまでサポートをする。
それこそが、結果的に「配慮あるマネジメント」だと言えると思います。
いろいろとお話ししてきましたが、 ここ数年での職場の環境変化を経て、自分で能動的に考えなくてはいけないけれど、行動次第でキャリアをいくらでも変えられる時代になりました。
長時間労働もハラスメントも減って、どんどん自由にキャリアを描けるようになってきています。
そんな時代だからこそ、若者本人にとっては小さなアクションが、そしてマネジメント側は、それを促し、サポートできるかが重要になる。
こうした両者のちょっとした行動の積み重ねが、若者が生き生き働ける環境をつくっていくのだと思います。
【参加型】安宅和人氏らと描く「3年後の自分を変える」シナリオ取材・文:高橋智香、編集:伊藤健吾、デザイン:石丸恵理、撮影:遠藤素子