プロジェクトマネジメントを学ぶメリットとは
働き方改革、IT化が進むビジネスプロセス、コロナ禍によるリモートワークの普及etc.。2022年代は、これまで以上にプロジェクトマネジメントの能力が求められる時代だ。
年功序列を前提とした従来型の組織マネジメントが崩壊したと指摘されて、はや20年近くたったが、近年はより多くの業務がプロジェクト化している。
社内だけでなく、社外の専門家たちとコラボレートするプロジェクトも一般化しており、チームをリードするプロジェクトマネージャー(PM)の仕事はもう「経験豊富なベテランの仕事」ではなくなっている。
コンサルタント・著述家として知られる山口周さんは、著書『外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント』(大和書房)で、プロジェクトマネジメントのスキルを活用することで多くのビジネスパーソンの仕事が「楽しくなる」とも述べている。
タスクをこなすのが中心となる「手続き処理型」の仕事から、「プロジェクトマネジメント型」のワークスタイルに変わると、仕事の成果物=自分の作品になるからだ。
そのためにも、自分だけでなく、プロジェクトに参加するメンバー各々に裁量を委ね、実力を発揮してもらうマネジメントの方法論を皆が学ぶ必要があると述べている。
【読書】「勝てる」プロジェクトは、何が違うのか?また、下の記事では、業種や職種に関係なく「転職で年収アップ」を実現する人の傾向としても「組織をマネジメントし、プロジェクトの運用もできる」ことが挙げられている。
プロジェクトマネジメントのスキルは、キャリア形成でも大きな糧となるわけだ。
【衝撃データ】年収800万円以上の人の「スキルと経験」BEST 20では、肩書、役割としてのプロジェクトマネージャーを目指す人以外にも有益なこの能力を、効果的に身に付けるにはどうすればいいのか。
PMBOK(Project Management Body of Knowledge)やPMI(プロジェクトマネジメント協会)が定める手法を体系的に学ぶのも大切だが、ここでは日々プロジェクトマネジメントを行う人たちの経験談を紹介したい。
中でも、JobPicksに経験談を投稿するロールモデルが、実務を遂行する過程で学んだというおすすめ本を紹介していこう(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。
マネジメントの基本を学ぶ3冊
最初に紹介するのは、あらゆるプロジェクトを担当する際に求められる基本的な考え方が学べる本3冊だ。
基本とはつまり、プロジェクトが本来何のために計画され、かかわる「人」の参加目的は何かを理解する作業だ。
この基本がなければ、プロジェクトマネジメントは単なる業務の管理作業に成り下がってしまう。戦略、計画だけではチームは動かないということを肝に命じておこう。
【1】『非営利組織の経営―原理と実践』(ダイヤモンド社)
突然「非営利組織」の話になるのはなぜ?と思う方もいるかもしれないが、本書を薦める理由は著者にある。
この本を書いたのは、偉大な経営学者として知られるピーター・F・ドラッカー。プロジェクトマネジメントの専門家でドラッカーの理論に学んだと語る人は多く、いわばマネジメントの大家とも言えるだろう。
フジテレビジョンの経営企画・辻貴之さんは、この本を通じて「組織で活動する本質的な意味が分かった」と述べている。
非営利組織の経営
組織に求められることは成果をあげること、そのためにそこに集う個人に求められることは成果をあげることに貢献するために何がやりたい・やれる存在と記憶されたいかを考え、示し続けること…などなど、営利・非営利問わずに、複数の人と事を成す際には必読であると考えているから。 リーダーシップ・ビジョン・マネジメント・成果・人事など、経営に必要なことを学び、考えるきっかけがたくさん含まれています。 ドラッカーというとよく出てくる「何によって記憶されたいか」という一説も、この本に書かれています。最初に読んだ19歳の大学2年の夏から気づけば27年。常に側に置いています。
座学の研修などでは学べない、プロジェクトを動かす本質的な力を身に付けるためにも、営利目的ではない組織をリードするための(ある意味で究極的な)マネジメント手法を学んでみよう。
【2】『人を動かす』(創元社)
1937年に初版が出て以来、世界中でロングセラーとなっている名著『人を動かす』は、プロジェクト運営で最重要となる対人コミュニケーションのイロハが学べる1冊だ。
巨大なプロジェクトを推進する商社パーソンの丸紅・中村裕之さんも、まさにタイトル通り「人を動かす」ためのエッセンスが学べたと本書を薦めている。
人を動かす
入社してから10年間は資源系(石炭)の部署にいました。最初の3年間は
不朽の名作ということで、マネジメント系の仕事に携わる人は本書の骨子となる「三原則」に学んだと語るケースが非常に多い。それらの声は、下の記事でもまとめているので、ぜひ目を通してほしい。
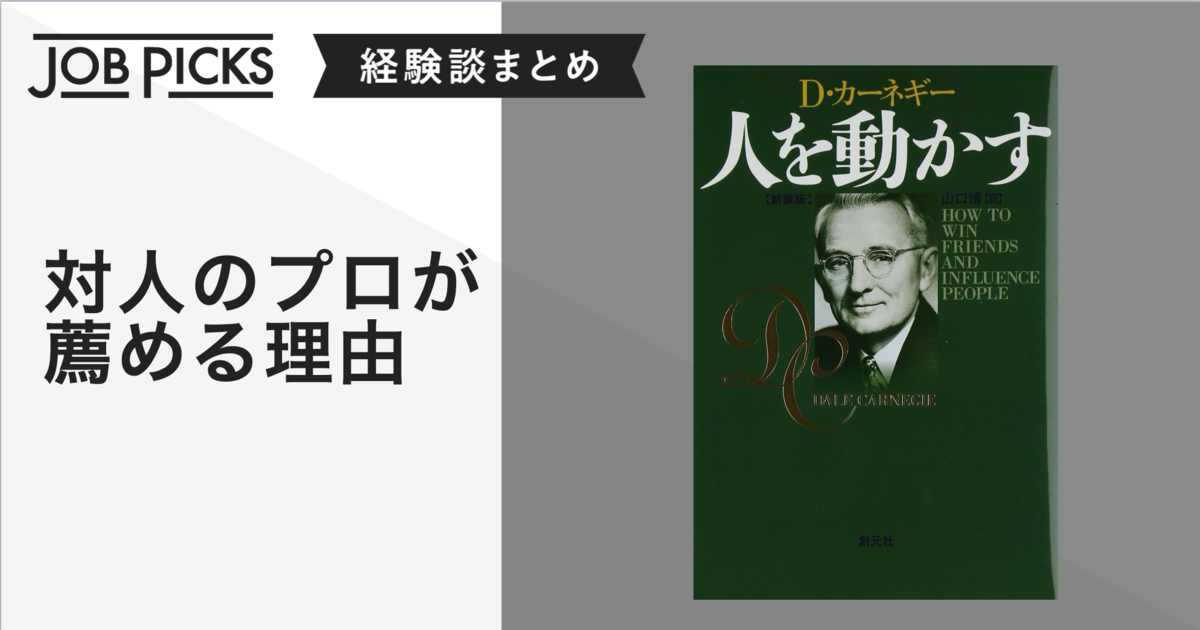
【カーネギー】不朽の名著『人を動かす』で、交渉力やマネジメント力を鍛える
【3】『イシューからはじめよ——知的生産の「シンプルな本質」』(英治出版)
プロジェクトとは「特定の課題を解決するための取り組み」であり、その大前提として必要な「何のイシューを解決するべきか?」を見極める際に本書が役立つ。
論理的に課題解決のストーリーラインを構成するには、イシュードリブンで動くのが最重要のポイントだからだ。
いわゆる仮説思考の基本としても愛読される本書は、プロジェクト型のワークスタイルで働くコンサルタントが推薦するケースが非常に多い。
例えばPwCコンサルティングの大塚泰子さんは、「答えるべき問いを正確に定義できたら、そのプロジェクトは8割終わったようなもの」と述べている。
イシューからはじめよ
コンサルタントの基本の基という感じです。 issue shaper
また、A.T. カーニー(グローバル・ブランド名:カーニー)を経て、AIベンチャーのWACULでCFO(最高財務責任者)を務める竹本祐也さんは、コンサル時代の苦労に炎上案件での経験を挙げている。その原因となる「仮説の間違い」をただす意味でも、『イシューからはじめよ』が参考になると話す。
炎上という名の地獄
「炎上案件」 そう呼ばれるものが、不定期にですがやってきます。
イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプルな本質」
コンサルティングの業務は、顧客の経営課題に対して、あらかじめ決められ
本書についても、読みどころをまとめた過去記事があるので、合わせて読んでほしい。
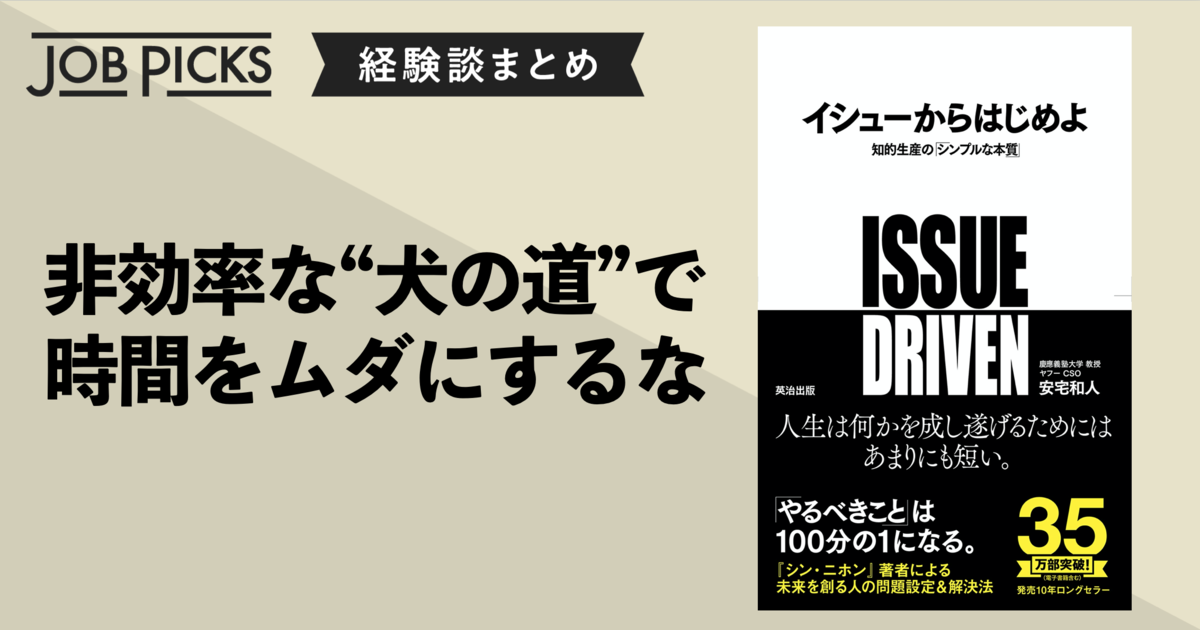
【証言6選】『イシューからはじめよ』で生産性が劇的に上がるワケ
プロジェクト推進を各論で学べる2冊
続いて紹介するのは、より具体的なプロジェクトマネジメントの要諦が分かる書籍だ。
ここでは、「プロジェクトマネジメント」でググっても出てこないような良書2冊をとりあげよう。
【4】『君に友だちはいらない』(講談社)
本書はマッキンゼー出身でエンジェル投資家、イノベーション研究の大家としても知られる故・瀧本哲史さんが遺した名著として知られている。
グローバル資本主義を生き抜くための「武器としてのチーム」論をまとめており、国境・企業・部門などの枠組みを超えて仲間を集め、チームとして機能させるためのノウハウが満載だ。
フラワーギフト通販の日比谷花壇で事業企画を担当する小野高海船さんも、本書を通じて「プロジェクトメンバーの個々の能力を引き出し、最高のパフォーマンスを出す」手法を学んだと述べている。
君に友達はいらない
この本で書かれているのは「チーム作り」の大切さについてです。プロジェ
DeNAを経てオーディオブック配信のオトバンク取締役になった飯泉早希さんも、本書に出てくる『七人の侍』の事例を通じて、「異なる才能と経験を持った他者とチームを組んで事に向かう」やり方を学んだという。

元DeNAプロマネの20代を救った「チーム運営の悩み」解消する5冊
【5】『最高の結果を出すKPIマネジメント』(フォレスト出版)
2019年の「ビジネス書グランプリ」マネジメント部門の1冊にノミネートされた本書は、KPIドリブンの事業運営で知られるリクルートで“KPI講師”を務めた著者が実践してきた現場主義のKPIマネジメント手法を解説している。
上で紹介した『イシューからはじめよ』の内容を、より実践的に紹介しているような内容で、第4章「さまざまなケースから学ぶKPI事例集」からは数多くのユースケースを学ぶこともできる。
ヘルステック・ベンチャーHakaliのデータサイエンティスト秦正顕さんも本書を推薦しており、幅広い職業の人に役立つと推測される。
最高の結果を出すKPIマネジメント
データをビジネスにどう活用するか、実例を交えて説明してくれる本です。
>『最高の結果を出すKPIマネジメント』のAmazonリンク
プロジェクト成功を阻む「壁」を乗り越える2冊
最後に取り上げるのは、実際にプロジェクトマネジメントを実行する際に「悩みごと」になりがちな課題を解消するための2冊だ。
【6】『自分の小さな「箱」から脱出する方法』(大和書房)
世界中で150万部超えのベストセラーとなっている本書は、プロジェクトの管理・進行で最大の壁となりがちな「人間関係」の問題を解決するための指南書だ。
相手の問題と捉えがちなこのテーマを、自分ごとに置き換えて建設的な解決手法を提言しており、三菱商事やA.T. カーニーなどで数多くのプロジェクトを経験してきたワンダーラボ鳥居亜紀さんは次のように推薦コメントを残している。
自分の小さな「箱」から脱出する方法
経営コンサルタントを目指す人というより、人間関係にもがいている方にお
>『自分の小さな「箱」から脱出する方法』のAmazonリンク
【7】『採用基準』(ダイヤモンド社)
本書は、マッキンゼー出身の著述家として人気の「ちきりん」こと伊賀泰代さんが執筆した、人材マネジメントに関する名著。
タイトル通り、採用やリーダーシップ教育についての本だが、パナソニックでスマートシティ推進プロジェクトに携わる岩井凌太さんは次のような点で「プロジェクトマネジメントの役に立つ」と述べている。
採用基準
本書は、マッキンゼーで求められる能力について同社OGの伊賀さんが記さ
岩井さんは、大規模プロジェクトを回す中で最も重要なのは「挑戦するマインドと挑戦しやすい環境を築くこと」と書いている。
下のインタビュー記事も参考にしながら、この環境づくりを「どう」行ってきたのかも勉強してみてほしい。
.jpg)
【OB訪問】パナソニックの先輩社員に聞く、社風や配属、伸びる人材
文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / IR_Stone