注目の新職種「HRBP」に出会うまで
—— 大嶋さんが担当する「HRBP」とは、どのような職種なのですか?
定義は一様ではありませんが、私の中では「事業部とバックオフィスの間に立ち、相互の関係を円滑に調整する仕事」だと思っています。
変化が激しい現代においては、新規事業が生まれたり、その一方で事業を畳んだり、組織も急激に変化するものです。
経営戦略が変わることも日常茶飯事で、その度に組織が多角化し、調整が難しくなります。HRBPは、そうした変化の激しい組織で力を発揮する職種です。
そもそも「HRBP」とは、「Human resources business partner」の略称。経営層や事業部門のパートナーとして、人と組織の面から働きかけやサポートを行い、成果を創出する人事のプロフェッショナルのことを言います。
企業の成長を支える根本は、人です。
人事と聞くと、裏方の色が強いように感じるかもしれません。しかし、イノベーションや付加価値を生み出す人材の確保・育成に従事し、事業の変化を見据えて人材ポートフォリオを構築して、経営戦略と適合する人材戦略の実行をしていくのが「HRBP」です。
いわば、経営に直結する人的資源活用のプロフェッショナルですから、表に出ることはなくても非常に重要なポジションだと考えています。
.jpg)
—— 専門性が問われる、非常に重要な職種なのですね。HRBPを目指すには、やはり人事からキャリアをスタートすべきですか?
いえ、そんなことはありません。
HRBPが担当する領域は、いわゆる人事の職域とは異なります。人の側面から経営をサポートするのがミッションなので、そこには労務管理やPMI(ポスト・マージャー・インテグレーションの略で、組織の吸収合併時に統合効果を最大化する業務)など多様な役割が含まれます。
経営の知識も必要になりますし、マネジメントや事業への理解も求められますから、幅広い経験があることのほうが重要です。人事以外の職務経験があることが、強みになる機会も少なくありません。
実際、私も新卒では経理を担当していましたし、人事の経験はそこまで長くありません。それでも、HRBPとしての職務を全うできていると思います。
—— 大嶋さんは現在に至るまで、どのような経歴をたどってきたのですか?
もともと、営業職を志望していました。きっかけは、行政から予算をいただいてカフェを経営したことです。
就職活動と並行しながら、地方自治体が主催する空き店舗活用を主題としたビジネスコンテストに参加したところ、自分のグループが提出した企画案が採択されたんです。「早速やってみてよ」とのことで、地域活性を目指したプロジェクトが発足しました。
とはいえ、過疎化が進む地方で、売り上げを立てることは簡単ではありません。行政からの支援があったとはいえ、当然のように販管費がかかります。売り上げを立てなければお給料も払えないので、飲食による売り上げ以外にも、商店街でのイベント企画や関連ビジネスなどにも挑戦しながら経営に打ち込んでいました。
しかし、自分の実力のなさもあって、売り上げは一向に伸びなくて……。雇用していたパティシエにお給料を払えなくなってしまう事態に見舞われ、個人で借金をしたこともありました。

—— お金を稼ぐことの重要性を感じ、営業職を目指された?
内定をいただいた企業の中で、商品ありきの営業ではなく、個人のスキルや経験による営業力が最も身に付きそうだと感じたのが、当時急成長していたネオキャリアでした。
人材業界に興味を持っていたわけではありませんが、「稼ぐ力を身に付ける」べく、ファーストキャリアを選択しました。
学生にしては色濃い経験をしていたので、実際に働く前から“数字をつくれる人材”になろうと、息巻いていましたね。
しかし、ふたを開けてみれば、配属されたのは経理でした。150人の同期がいた中で、管理部門に配属されたのは、たったの7人です。
やりたいことが明確だったので、「どうして自分が?」と落ち込みました。働き始めて3日目には、退職することも考えました。
しかし、結果的には、この経験が今につながるターニングポイントになっています。
予想外の配属も、最良の1年目に
—— ネオキャリアでは、具体的にどのような仕事をしていたのですか?
入社1年目は、経費精算の承認を毎日しながら、月次決算ではPL(損益計算書)とBS(貸借対照表)を作成すべく、残高確認や仮勘定の整理、経過勘定の計上などに対応していました。
日常業務は、書類の印刷や並び替えなどの単純業務も多々ありました。まだ経理業務が自動化されていない時代だったので、真夏にジャージを着て、膨大な数の書類を詰めたダンボールを運んだこともあります。
今ではいい思い出ですが、膨大な領収書にハンコを押し続ける毎日に、「こんなことをするために就職したわけじゃない!」と何度も思いました。
そんな毎日でも仕事を続けられたのは、複数会社の多様な商材をケーススタディに、会計の仕組みを学べる機会があったからです。

当時はグループ全体の売り上げや仕入の計上、請求や支払をする業務も任されていたので、各部門別や事業所別でお金の出入りを知るチャンスがありました。
自分の手で売り上げをつくる力は身に付きませんでしたが、経理の仕事を通じて、「どうやってお金を稼いでいるのか」が理解できました。
会計データを読む力が付き、データ分析もできるようになったことで、少しずつ仕事が楽しくなっていったんです。
入社1年目で会計に強くなれたことは、振り返ってみれば幸運なことでした。
—— ネオキャリアでは、そのまま経理を担当したのですか?
引き続き経理部門に所属していましたが、業務の内容は大幅に変わりました。
2年目からはマネジメントを任され、3年目には経理部門のリーダーに。このとき、新設した業務改善チームリーダーも担当しました。
もともとやりたかった営業職からはどんどん離れていきましたが、この頃から、バックオフィスの仕事に対してポジティブな感情を抱くようになっていました。
会社の売り上げに貢献するポジションを用意していただけたことがうれしかったですし、経営にダイレクトに影響を与える仕事にやりがいを感じていたんだと思います。
—— DMMでHRBPを担当していますが、どのような背景でジョブチェンジを検討したのですか?
職域を広げたいとは思っていましたが、人事職にジョブチェンジしようと思っていたわけではありません。たまたま、人事領域の業務にアサインされたのです。
入社時点で決まっていたのは、「バックオフィスの経験を生かして、子会社の管理業務をする」ということ。

—— 具体的には、どのような業務を?
株式会社から合同会社へと組織変更されるタイミングで、関連会社が一つにまとまることもあり、本社で運用していた人事評価制度を社内に浸透させる業務を任されました。
「人手が足りないから、まずはそこから」という流れです。
この仕事があらかたきれいになったタイミングで、今度はエンジニアの採用を任されました。これも、空いたポストを埋める形でアサインされたものです。
人事の経験はありませんでしたが、社内で話を聞いたり、自分で本を読んだりして、手探りで仕事をしていました。
苦労はしましたが、組織をつくっていく過程は魅力的で、このとき人事という仕事に強く魅力を感じました。
HRBPは、多角的な経験の結集
—— 多様な経験をしてきたことは、現在に生きていると感じますか?
経理、財務、労務、業務改善、そして人事。学生時代も含めれば、曲がりなりにも経営を経験しています。職種でいえば、およそ6つです。
全てを極められたわけではないものの、これらすべての経験があったからこそ、HRBPとしての職務を全うできているのだと思います。
HRBPは、経営層、各事業部の責任者、そしてバックオフィスと、あらゆる部門の橋渡しになる部門です。組織に落ちている“火中の栗”を拾い上げ、冷まして、渡すべき人に渡す。これができているのは、さまざまな職種の実務が見えているからです。
他社を含めHRBPの方と話す機会も多いのですが、やはり人事しか経験がないと、いわゆる人事業務以外の仕事に抵抗があるように感じます。
人事を拡張した仕事ではあるものの、人事を経験したからといって務まるものではないのです。

—— むしろ幅広い知識や経験がないと、務まらない仕事なのですね。
私の感覚値では、プロダクトマネージャーや事業開発に近い職種だと思っています。それらとの違いは、「視点がプロダクトに向いているのか、組織に向いているのか」です。
メンバーが最大限にポテンシャルを発揮してもらうには、常に最高のコンディションでいてもらう必要がありますよね。それを実現させるために、あらゆる手を尽くすんです。
現場で手が回らない仕事があれば、課題を可視化して改善のサポートをしますし、場合によっては巻き取ります。リソースが足りないのであれば、要件定義をして採用します。他部署と連携を取り、人事異動をサポートすることもあります。
全社方針を理解したうえで、可能な限りの個別最適を実現していくわけですから、やはり簡単な仕事ではありません。ある程度の専門性を持ちながらも、幅広い視点を持つゼネラリストであることが求められます。
尖りを持ったゼネラリスト
—— 転職が当たり前の時代に、軸となるスキルを持たないことに不安を覚える人は少なくありません。短期間で多様な職種を経験してきた大嶋さんは、その点についてどのように思いますか?
たしかに私は、胸を張って100点を付けられるスキルを持っているわけではありません。
また、「尖り」を持つことがキャリア形成に有用なのは、間違いないことだと思います。
ただ、ゼネラリストに尖りがないかといえば、そうではないと思います。あらゆる領域に知見を持っていて、ベクトルの異なる専門性をつなぎ合わせられることは、尖りの一つだからです。
強烈な専門性を持つ人だけでは、組織は成立しません。それらの潤滑油となり、相互に作用する土台をつくる人がいて、初めて組織として機能します。
HRBPは、まさに潤滑油のような職種です。
実際、採用を担当する身として、HRBPの市場価値は非常に高いと感じています。変化の激しい時代において、変化に耐えうる組織をつくる能力は、やはりどこにいっても重宝されるのです。
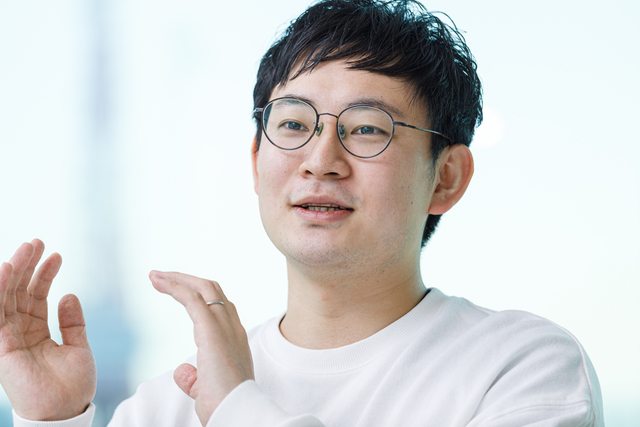
—— これからHRBPを目指す人は、どのようなスキルを身に付けるべきだと思いますか?
個人的な考えですが、まずは、現場を知ることが大切だと思います。
HRBPには、HRのプロとしての判断力・企画力・実行力はもちろん、人や組織の変化に瞬時に気付き、共感を生み出すコミュニケーションを継続して行っていくことが求められます。
HRの専門性は日々勉強して積み上げていくしかないですが、現場実務を幅広く知るために、自分も手を動かしてみるのが重要です。
過去を振り返れば、ひたすら経費精算の承認をしていたからこそ見えた景色がありましたし、とにかく採用面接に出続けたからこそ、分かったこともたくさんありました。
結局、現場の苦労や課題意識を肌感を持って感じられないことには、的確な相談に乗れないんです。
膨大な数の領収書を処理していたときは、さすがに頭がおかしくなりそうでしたが、毎月2000枚の紙切れが教えてくれたものは計り知れません。
また、重複した話ではありますが、“信頼のある人”になるのも大切なことです。
信頼がなければ、事業に対して心血を燃やす事業部メンバーと対等な関係でいることができません。コンサルティングではなく、当事者として一緒に事業を育てるためにも、日頃のコミュニケーションが重要だと思います。
注目されていて、なおかつ市場価値が高まりつつある職種とはいえ、結局は真摯さが物を言う仕事です。
今も昔も時代に合わせて職種のラベルは変わっていきます。そんな移ろうラベルに振り回されるよりも、目の前にある仕事に一生懸命になることが、後々の武器になるはずです。
私の場合、職種に縛られず、できることを確実に増やしてきた先に、HRBPという職種が待っていました。
もちろん、これから先も、できることを磨いたり、増やしたりしていくなかで、誰も知らない未来の職種を自分なりに探検していけるといいなと思っています。
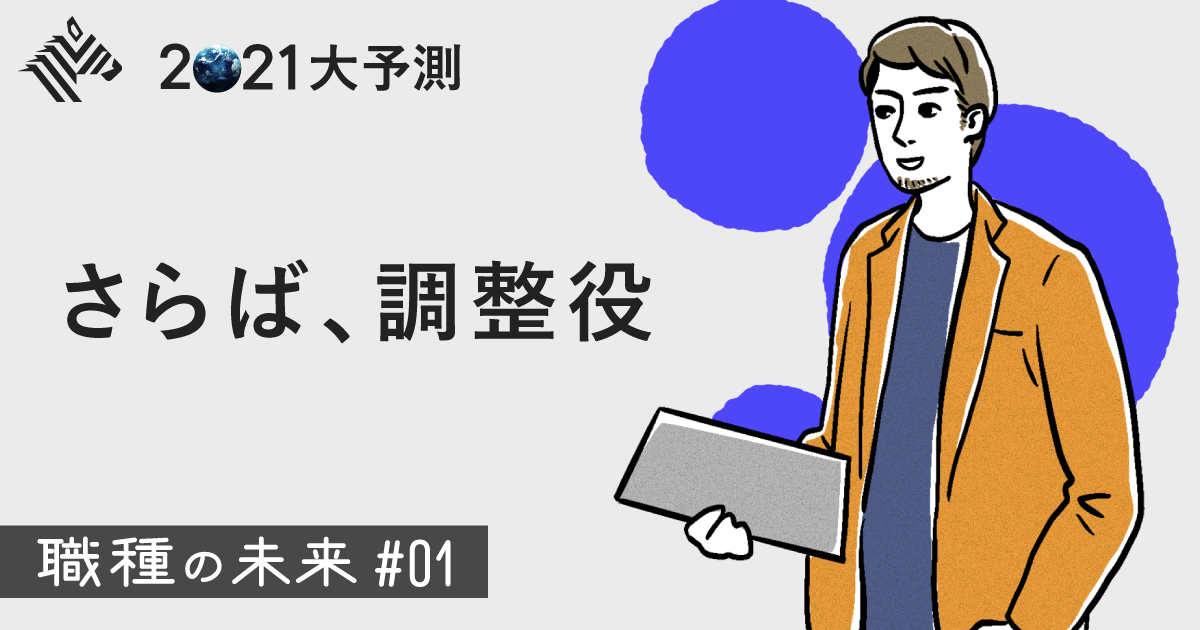
合わせて読む:【人事の未来】求められる、「経営者目線」の改革実行人
取材:平瀬今仁、取材・文:オバラ ミツフミ、編集:伊藤健吾、デザイン:岩城 ユリエ、撮影:是枝右恭