『イシューからはじめよ』著者と要約
2010年に出版され、35万部超のロングセラー本に。
『イシューからはじめよ——知的生産の「シンプルな本質」』(英治出版)は、出版から10年以上が経ち、時代の変化が起こる今も多くのビジネスパーソンに愛読されている。
著者の安宅和人さんは、東京大学大学院生物化学専攻で修士課程を修了後、マッキンゼーで経営コンサルタントに従事。2008年にヤフーへ転職し、現在はヤフーCSO(チーフストラテジーオフィサー)や慶應義塾大学SFCの教授を務めている。
専門分野は幅広く、中でもデータ分析を課題解決に結びつける視点が評判。データサイエンティスト協会理事も務める人物だ。

▶︎ 安宅和人さんのNewsPicksコメントを読む
そんな安宅さんの著書は、経済界のみならず、アカデミアや官公庁の世界でも高く評価されている。
メディアアーティストとして有名な落合陽一さんも、『イシューからはじめよ』に影響を受けた一人だ。
NewsPicksの動画シリーズ「WEEKLY OCHIAI」で安宅さんと対談した際は、「(東京大学大学院で師事した)暦本純一先生に必読書として『イシューからはじめよ』を薦められた」と述べていた。

【動画】落合陽一×安宅和人「日本再生を考える」(NewsPicks)
『イシューからはじめよ』がデータ分析にかかわるプロフェッショナルたちに広く支持されるのビジネス書である理由は、あらゆる課題解決に使える大事な思考法やアウトプットの手段が学べるからだろう。
安宅さんの言うイシューとは、「何に答えを出すべきなのか」について目的がブレることなくアウトプットを出すための仮説だ。
複雑に絡み合う問題を効率的に解決するには、まずイシューを見極め、論理的に課題解決のストーリーラインを構成する。これが、イシュードリブンで着実に成果を出し、効果的にバリューを出すための基本だ。
安宅さんは、本書の中でこう述べている。
世の中で「問題かもしれない」と言われていることの総数を100とすれば、今、この局面で本当に白黒をはっきりさせるべき問題はせいぜい2つか3つくらいだ。 ——『イシューからはじめよ』より
一方で、イシュードリブンな仕事と対極にあるのが、安宅さんの指摘する“犬の道”である。
解決するべきイシューを整理し仮説を立て、ストーリーラインを構成することなく、一心不乱に大量の仕事をして解を見つけようとするのは、時間も労力も無駄にする生産性のないアプローチだ。
上の対談動画でも、安宅さんは「とりあえず『頑張ってからモノを言え!』という“犬の道ドリブン”な人が多すぎる」と批判している。
では、本書から得られる学びは、具体的にどんな仕事で役に立つのか。
JobPicksのロールモデルの中で、『イシューからはじめよ』を薦める人たちのレビューコメントから読み解いていく(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。
経営コンサルタントの答え
クライアントの課題を分析し、問題設定から答えまでのストーリーラインを構成することがあらゆる業務の基礎となる経営コンサルタントは、『イシューからはじめよ』の内容がすぐに役に立つ職業の一つだろう。
2017年からアクセンチュアで働く井手啓太郎さんは、『イシューからはじめよ』を薦める理由をこう述べる。
イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」
この場で今更挙げるまでもなく、名著・必読書とされている一冊ではありますが、やはり敢えて1冊をお勧めするのであればこちらになるかと思います。 簡単に言うと、本著ではイシュードリブン・仮説ドリブン、つまり課題解決型、仮説検証型の思考様式が紹介されています。 コンサルタントは究極的には「思考した結果」に
井出さんは、「コンサルタントは究極的には『思考した結果』に対して報酬を頂いており、『思考した結果』は、思考様式により大きく左右されるため、どの思考様式を用いるかは非常に重要」とコメントしている。
多くの案件で「イシュードリブン・仮説ドリブンの思考様式をとることを前提にした『思考した結果』が求められる」という。
まさに仕事のベースになる考え方・分析法が身につくのだ。
また、ゴールドマン・サックス証券を経てA.T. カーニー(グローバル・ブランド名:カーニー)に入り、現在はAIベンチャーのWACULでCFO(最高財務責任者)と、多様なキャリアを歩んできた竹本祐也さんは、『イシューからはじめよ』の価値をこのように説明している。
イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプルな本質」
コンサルティングの業務は、顧客の経営課題に対して、あらかじめ決められた期間内に答えを出すことが仕事です。そして、顧客からの対価は、その期間に応じて支払われます。つまり、コンサルティングファームは、最短最速で優れた答えを出すことが求められています。その最短距離で答えを出す方法が「仮説思考」です。その「
このコメントからは、クライアントが悩み続けても答えが出なかった問題の数々を、イシューから効率的に整理し、理解することで解決へのアウトプットに導く武器になると読み取れる。
竹本さん自身、現在はCFOをしていることから、経営にかかわる仕事でもイシュードリブンの根本的な仮説思考法が仕事術に役立ちそうだ。
事業企画やマーケター、営業の武器に
問題解決の思考が不可欠な仕事は、経営コンサルタント以外にもたくさんある。
事業企画・事業開発やWebマーケター・デジタルマーケターなど、ユーザーの抱える課題を自社プロダクトを通じて解消する切り口を考えるプロジェクトに携わる職業でも、『イシューからはじめよ』から学びを得ている人が多い。
インターネットイニシアティブで事業企画・事業開発を担当する佐久間大さんは、「20代の社会人経験が浅い時に読んで、いろいろな経験が土台となっている30代になって、改めて読み直すことに大きな意味が生まれる」と述べている。
イシューからはじめよ
事業企画を考える上で、必要な要素を体系立ててまとめてあることがおすすめの理由です。 事業企画や事業開発を目指す入門書という観点では、20代の社会人経験が浅い時に読んで、いろいろな経験が土台となっている30代になって、改めて読み直すことに大きな意味が生まれる特別な一冊だと思います。 経験がないと本に書かれている内容は頭に入るだけで定着しないから実務で使えない。そんな経験がある人と、その予備軍の方にはおすすめです。 (20代の経験+本著) × (30代の役割+本著) = 事例のない新規事業のサバイブ
Webマーケター・デジタルマーケターでは、NewsPicksの小林将也が『イシューからはじめよ』を推薦。
マーケティングの仕事は「課題設定と解決へのロードマップ、そこにたどり着くまでの効率を求められる職業」だからだ。
イシューからはじめよ
「悩まない、悩んでいるヒマがあれば考える」 全てのビジネスパーソンへ推薦したいレベルの名著ですが、特にマーケターこそこの考え方をインストールすると良いのかなと思います。 マーケターは課題設定と解決へのロードマップ、そこにたどり着くまでの効率を求められる職業ですが、最も必要なことはまずイシューから
これら2つの仕事は、問題解決までの大事なストーリーラインをブラッシュアップする時や、分析結果からアイディアを実行し検証に移す、シンプルに要点を絞って相手に伝えることが求められる。
難しいことを分解し、シンプルにしていく過程で、『イシューからはじめよ』のエッセンスが役に立つ。
この文脈で考えると、顧客が抱える課題の原因を分析し、問いを立て、自社プロダクトがどう役立つのかを説明する営業の仕事でも生かせるだろう。
トステム、プレジデント社、NewsPicksで法人営業(フィールドセールス)を担当してきた佐久間亮輔は、未経験者へのおすすめ本として「この1冊しか思いつきません」と述べている。
イシューからはじめよ
この1冊しか思いつきません。 顧客に寄り添うための“イシュー”把握の必要性からストーリー構築、分析まで網羅されています。まさにこの職業における必携の書。 何度も読み返し、活用しながら自分の体に浸透させています。 この行動様式を得ることができれば、結果として問題解決の手法も手に入れることができま
佐久間の他のコメントを読むと、法人営業は「物理的に数多くの案件を動かすことになり、首が回らなくなりがち」という苦労があるという。
だからこそ、さまざまな顧客の課題を共通のイシューとして整理する仮説思考術が、仕事の生産性を上げるのだ。
UXデザインにも応用可能
意外なところだと、UXデザインの仕事にも生かせると述べるロールモデルがいた。
新卒でデザインファームのGoodpatchに入社し、現在はTBSテレビでUXデザイナーを務める野田克樹さんは「抽象と具体を行き来しつつ、不確実性を排除していきながらサービス・プロダクトを設計していく」プロセスで本書が役に立つという。
イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプルな本質」
UXデザインプロセスについての書籍を推薦するか迷いましたが、本質的には課題を特定する力が重要だという理由でこの本を推薦した。 「プロセスを組み上げる、サービスを設計する」等どんな時も現状の課題はなにか?つまり、イシューはなにか?という点から全ては始まります。この基礎的なポータブルスキルがあって初め
ユーザー体験やデザイン設計の良し悪しは、理屈より人の感情に大きく左右される。それゆえロジカル・シンキングよりも「センス」のようなものが大切だと思われがちだ。
だが、野田さんのコメントを読むと、情報設計の議論や仮説検証をする時こそ、感覚ではなく、論拠に基づいた、課題特定力なり構造化力による論点を整理することの重要性が分かるだろう。
この2つの力は、極論、あらゆる仕事でアウトプットする際に求められる実践的なベーススキルだだ。仕事のイロハを覚え、自分で課題設定からの問題提起、プロジェクトの構成を行うフェーズになった時期に、読んでみると明確な意義を持つのかもしれない。
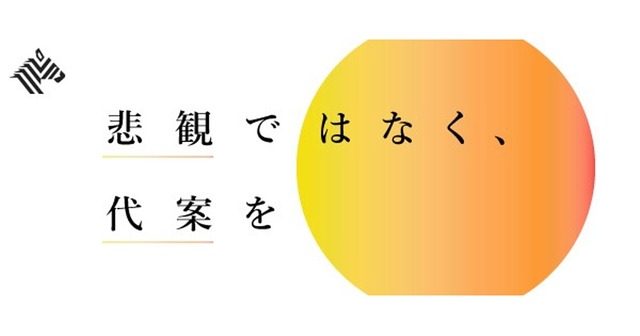
合わせて読む:安宅さんの新著『シン・ニホン』の「はじめに」全文公開
文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳