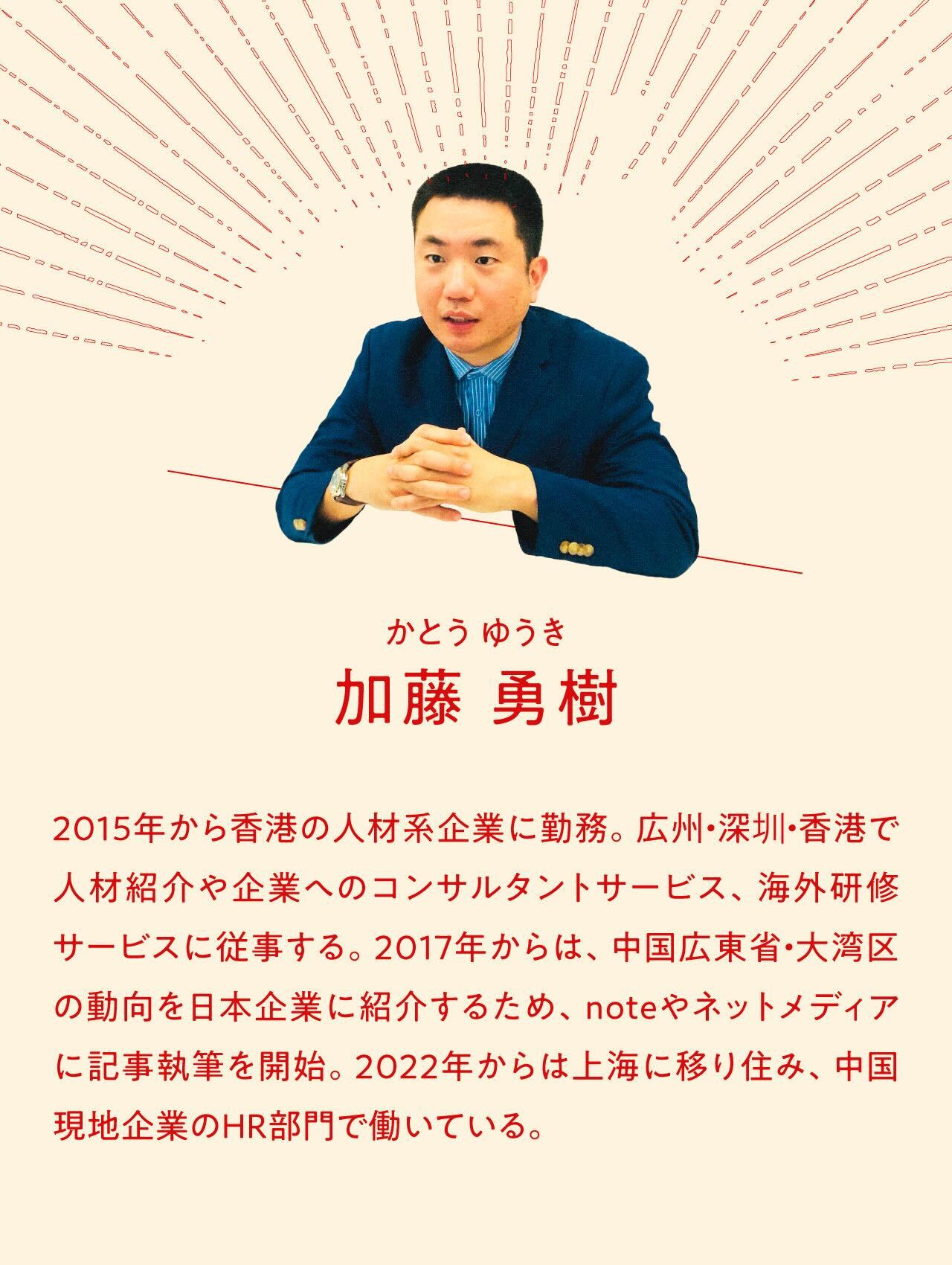
偶然の出会いを逃さず、中国に飛び込む
加藤さんは2015年に、香港の人材企業に就職。以来ずっと人材紹介や人材コンサルといったHRビジネスに従事してきました。2022年からは活動拠点を上海に移し、上海の人材企業で働いています。そもそも日本ではなく、なぜ香港や中国本土で働くことに?
──大学を出てから、何を考えて中国に渡ったのでしょうか。
加藤:大学時代に、馬に乗って「中央アジア横断の旅」をしたのがきっかけです。ロシアから出発し、シベリアやモンゴル、そして中国の内モンゴルまで長い道のりを旅していったのですが、その際に「華北」(北中国)よりも「華南」(南中国)の方が栄えていることを教えてもらって。
そこから、もっと違う「いま成長の真っただ中にある中国」を見てみたいと思うようになりました。もともと、日本の山形大学で国際関係論を専攻し、海外に興味がありました。新卒入社した会社では、海外事業部の営業に配属希望を出していました。しかし研修期間が終わって配属された先は、海外とは全く関係ない部署だったんです。
これでは、いくらがんばっても海外に行けない。どうにか海外と関わる方法はないか。
そう考えるなかで、偶然参加したビジネス系のイベントで、良い出会いに恵まれました。中国に現地法人を持つ社長とお会いし、「良かったら中国で働かないか」とお誘いを受けたんです。

当時は全く中国語ができませんでした。しかし、まず学費無料で、広東省の名門大学である中山大学で中国語を勉強させてもらうことができ、卒業後もその社長が経営する香港の会社で働かせてもらえるという条件でした。「またとないチャンスが舞い込んできたな」と思いました。
自分に付加価値をつけたい、中国でVISAを取得したい、世界中で活躍する華僑の原点である香港で働きたいといった思いもありましたが、やはり好きな海外で経験を積めるということにワクワクしました。勢いで中国へ飛び込もう、という意気込みが強くて、だからこそ中国へ行く踏ん切りがついたと思っています。
社長と「デート」させてください! 中国語で赤恥も
現地に引っ越し、まずは中山大学で学び始めた加藤さん。しかし平たんな道のりばかりではありませんでした。
──中国に引っ越して、生活や仕事をしていく上で、大変に感じたことや気持ちが折れそうになったことはなかったのでしょうか?
加藤:もちろんあります。まず、中山大学で出会ったのは、インドやパキスタン、アラブ諸国やアフリカ、インドネシアなど各国から来ている留学生たちでした。当然ながら国によって文化が異なり、考え方や価値観も違うからこそ、多様性を尊重した歩み寄りの姿勢が大事になります。
その後、香港の人材企業に入ったのですが、社長以外では私が2人目の正社員でした。しかも当然ながら日本人ではありません。
社長が中国経済の最盛期を経験した方で、「ビジネスは勢いでどうにかなる」と考えていたので、仕事も「習うより慣れよ」というスタンスでした。そのため、ほとんど研修期間がありませんでした。

──しかも当然、中国語で仕事をこなすわけですよね?
もちろんです。初めはうまく中国語を話せずに苦労しましたが、意識していたのは「相手に中国語を話してもらえるような振る舞い」をすることでした。時には取引先にも助けてもらいながら、中国語を少しずつ覚えていきました。
当時は電話営業の仕事もしていましたが、ちょっとしたエピソードがありまして。
電話口の女性が、僕の話す内容を聞いてくすくすと笑うんですよ。僕は「総経理(社長)に会わせてください」と話しているだけなんですが。それも1人ではなく、どこにかけても何人も同じような反応だったので「何がおかしいんだろう」とずっと思っていました。
中国語にも慣れてきて、日常会話も普通にできるようになった頃、ある会社の受付の女性に理由を聞いてみました。すると「だって加藤さん、最初の頃に使っていた『約会』という言葉は、中国語で“デート”という意味なのよ。『社長とデートさせてください!』と電話してくるんだもん、おかしくって」と教えてくれました。
漢字の並びから、「約会」はアポを取る約束という意味に捉えていたのですが、全然違ったのは本当に恥ずかしい気持ちになりましたね。中国語って難しいなと感じた、いい思い出です。

ロールモデルなんていない まさに“自分との戦い”
──日系企業ではなく中国系企業でキャリアを歩んできた加藤さんにとって、大変だったことはありますか?
加藤:中国系企業で働き、キャリアを重ねていく上で苦労したのは、「参考とするロールモデルが周りにいない」ことでした。
日系企業であれば、課長や部長、優秀な社員など、周囲に手本となる人がたくさんいます。でもそれが、海外の現地企業だと、日本人は明確な目指すべきキャリア像を見いだしにくいのです。
中国人であれば、仕事の成果を出すことで着実にキャリアを積んでいくことができる。でも、日本人の自分が中国人と同じようにキャリアアップできるのか。会社から前触れもなく解雇を命じられるかもしれないし、転職先が保証されているわけでもない。
本当に“自分との戦い”なんだなと、中国系企業で働き始めてから思うようになりました。
そのため、一年の初めに「自分が1年でどのくらい成長したのか」を振り返り、新たな1年の目標を立てています。人と比べるのではなく、去年の自分と今の自分を比べることで、自分自身を客観的に見ることができるんです。
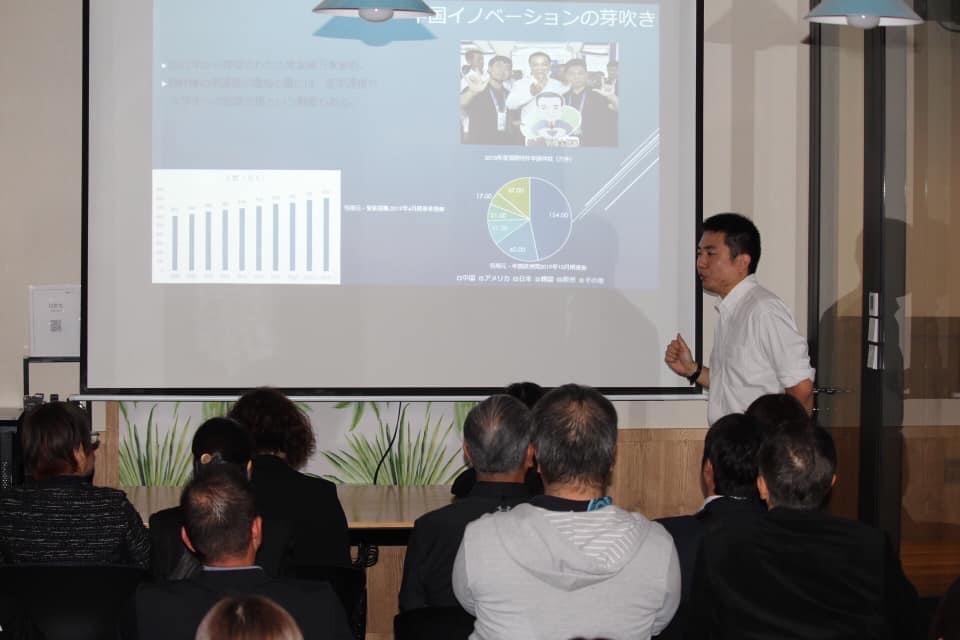
深圳に世界が注目、キャリアの転機に
──加藤さんにとって、キャリアの転機になったことはありますか?
加藤:自分にとってターニングポイントだったのは、2018年ごろでしょうか。広東省の深圳市が“中国のシリコンバレー”と称されて世界から注目を集めたことでした。日本からも新たなビジネスの種を探そうと、多くの企業が視察に訪れていました。
私も視察ツアーを企画し、日本企業のアテンドをしていましたが、そのときに感じたのが「中国では一般的な情報も、日本人にとってはものすごく価値がある」ということでした。
中国系企業で働くなかで入ってくる情報は、日系企業で働いている日本人では手に入らないもので、自分の立場でしかその情報を得られないことを実感したんです。
それを武器にすることで新たな活路が見いだせるのではと思いました。以来、お客様に対して営業する際も、サービスや商材だけを売り込むのではなく、自分の情報をエピソードとして盛り込んで売り込むように心がけるようになりました。
今振り返れば、この時期に海外でキャリアを築いていく上でのひとつの指針が決まったと感じています。

キャリアの生存戦略は「自分のエピソードを語ること」
──日本人に向けても積極的に情報発信されていますが、どういう意図を持って取り組んでいますか?
加藤:情報発信をする前の自分は、日本にいる日本人にとって、正体のわからない存在に見られていたと思うんです。やはり海外にいる以上、日本とのつながりが途絶えていくというか、孤独感を抱くようになって。もっと、日本や日本企業と何か新しい交流や接点が持てないかと考えていたんですよ。
そこで、中国系企業で働くなかで感じること、入ってくる最新情報などをSNSやnoteを使って情報発信し始めたことで、日本人とも関係性をつくることができ、ビジネスにもつながっていくようになりました。
──中国本土や香港と、日本の商習慣との違いについて教えてください。
加藤:中国本土や香港では、ビジネスの現場でその人が「誰とつながっているか」をかなり重視しますね。役職上の決裁者や責任者に提案を持っていくよりも、誰がキーパーソンかを見極め、直接交渉しにいく方が早い。
名刺交換の席でも、名刺を持ち歩いている人は少なく、WeChatでつながってやりとりするのが一般的です。SNSでコミュニティをつくり、そこで活発にビジネスの議論が行われているのをよく見ます。

──外から見て今の日本をどう感じていますか?
加藤:私が日本で働いていた頃は残業が当たり前でしたが、その頃よりも今の労働環境は改善されているのではないでしょうか。何より自分でキャリアや生き方を選択できるという点では、海外と比べても突出して優れている点だと感じます。
日本のパスポートも移動制限があるわけでもなく、行こうと思えばほとんどの国へ行ける。
これは日本ならではの魅力だと言えるでしょう。
──最後に今後の目標や成し遂げたいことをお聞かせください。
加藤:現在上海で働いている衆和グループでは、人材紹介や人材派遣のビジネスに関わっています。今後、日本に拠点を設立する計画があるので、その際は日本人として何か貢献できるかもしれません。また、将来的には中国で永住権を取得するのを目標にしています。
外国人が永住権を取るための条件はいくつかありますが「上海市における平均年収(約14万元=280万円)の5倍(約1400万円)を5年以上継続する」という条件がもっとも難しいです。今はまだとても届いていませんが、クリアできるように精進していきたいと考えています。
自分がいずれ、結婚して孫やひ孫ができたときに、歩んできたキャリアの証しやエピソードを、後世に残していきたいと思っているんです。「お父さんはこうやって頑張ってきたんだぞ」と言えるようになりたい。
今後、仕事で関わるサービスや商材が変わっても、自分のエピソードを語っていく「ストーリーテラー」になる。そしてそこからビジネスを作り出していく。これこそが、海外の現地企業で日本人として成果を出し、生き残っていくための生存戦略だと考えています。
(文:古田島大介、デザイン:高木菜々子、編集:富谷瑠美)