私が海外に出るのを勧める理由
近年のビジネスシーンでは、理学部生が身に付けている思考習慣が非常に重宝されるようになっています。
現状をとことん分析して成功や失敗の原因を探り、客観的なデータを基に次の一手を導く——。こういう科学的なアプローチが、多くの職種で求められるようになっているからです。
例えば、ゲノム解析の考え方は市場分析で非常に役立ちます。遺伝子情報がどのような性質に対応するか分析する作業は、マーケットの分析と実は非常に似ていると思います。
ただし、私の実体験として、学生時代に習得した思考習慣を実社会で生かせるようになるまでには、いくつかのステップを踏む必要があるでしょう。
その一つが、人間がつくる社会や組織についての理解です。まずは科学的な知識を生かす「場」と、それを形成する人間そのものを知らなければなりません。
なので、私がいま22歳の学生だったら、2年休学して世界中を回る旅に出ると思います。
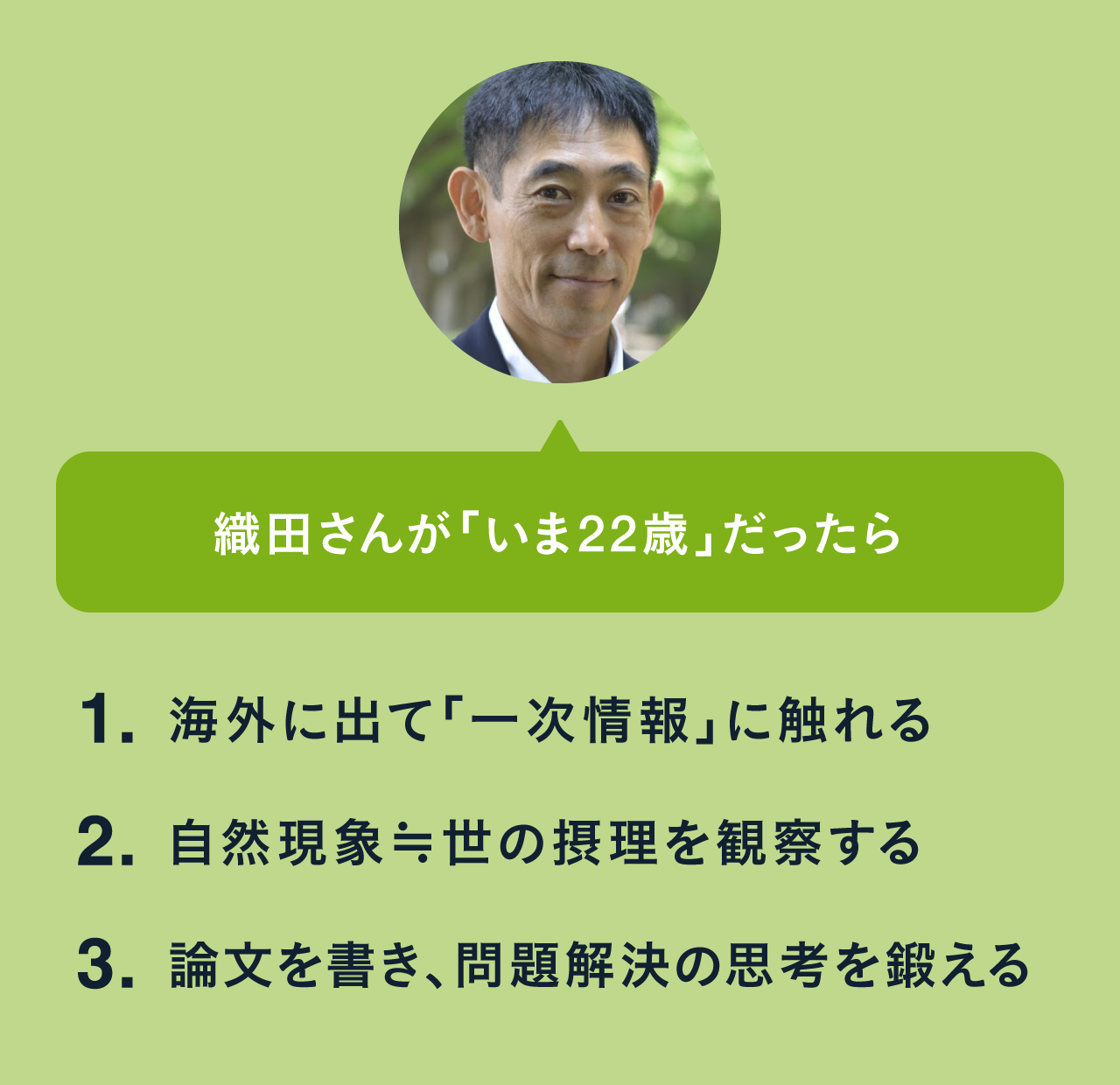
例えば、お金をもらいながら各国を回れるように、JICA(国際協力機構)の海外協力隊が募集しているプロジェクトに応募してみるとか。留学するにしても、トルコのイスタンブールやベルギーのブリュッセルなど、さまざまな文化が入り混じる都市を回ってみたいですね。
そういう場所で、レストランのウェイターをしてみるだけでも、日本国内で学生インターンをするより多くの気付きが得られるはずです。
自分とは全く違った考えを知ることや、異なる文化に触れることが、学校では学べない本物の知見を得るきっかけになります。
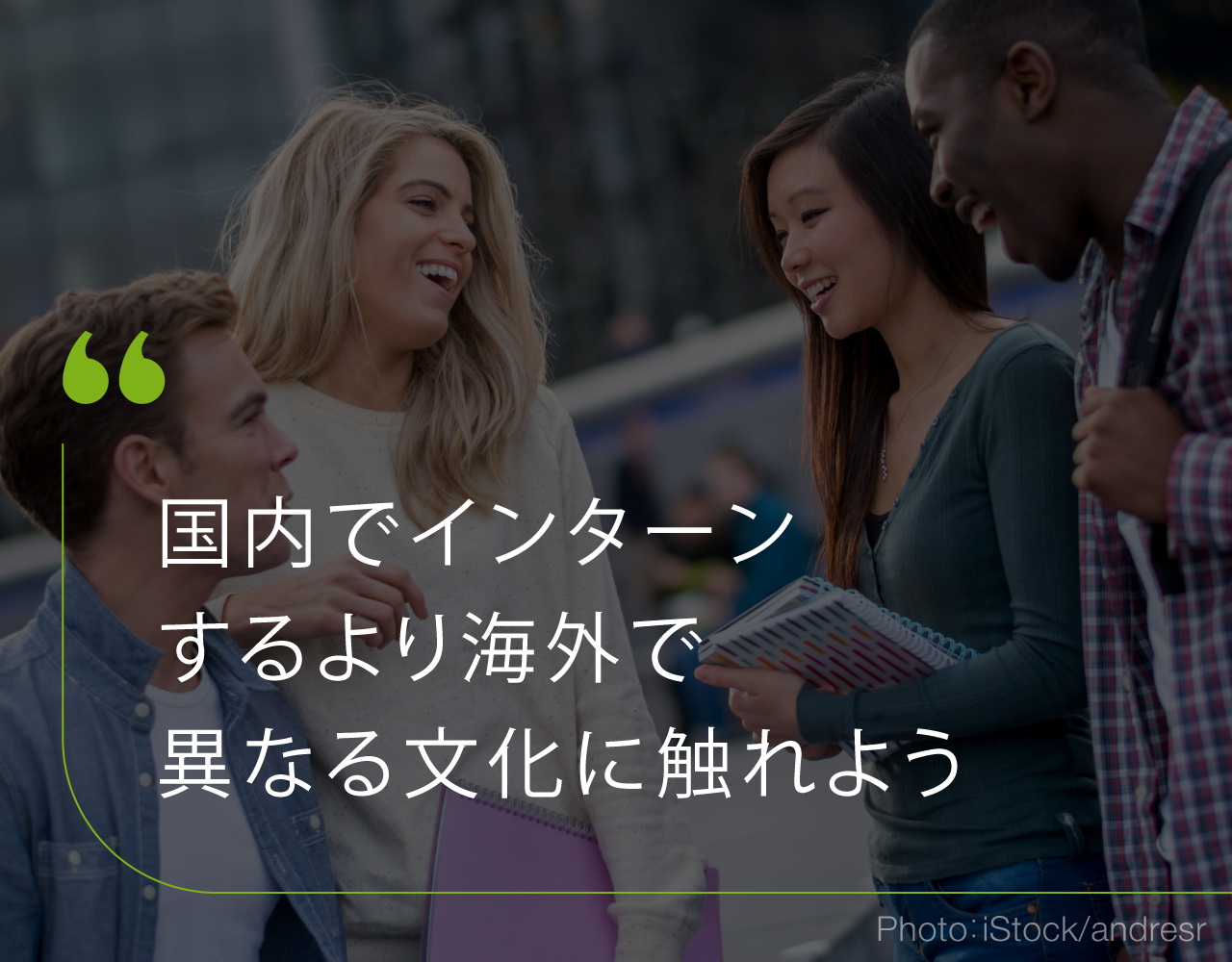
私がそう実感したのは、新卒入社したアンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア)の本社研修で、初めてアメリカに行った時でした。
当時は28歳になっていましたが、「もっと早く行っておけばよかった」と思ったのを覚えています。
その後、アンダーセンのアメリカ本社でいくつかプロジェクトを担当した時も、さまざまな気付きがありました。
例えば、日本人は真面目過ぎるということ。戦略コンサルファームの本社だけに、世界中から優秀な人たちが集まっていましたが、そんな彼らですら雑なところが多かったのです。
プロジェクトが佳境を迎えた金曜の夜、「明日もオフィスに集まろう」と皆で決めていたのに、次の日になったら誰も来ないこともありました。「だって土日は休日だよ」と(笑)。
文化が違うと言えばそれまでですが、「勤勉さ」と「優秀さ」は違うのだとこの時に学びました。
一方で日本人の場合、決められたことは無条件で守ろうとします。むしろ「ルールが間違っている時でさえ誰も文句を言わない」という問題があると感じています。
システムの中に組み込まれて思考停止になっていないかは、常に気を付けておくべきかもしれませんね。
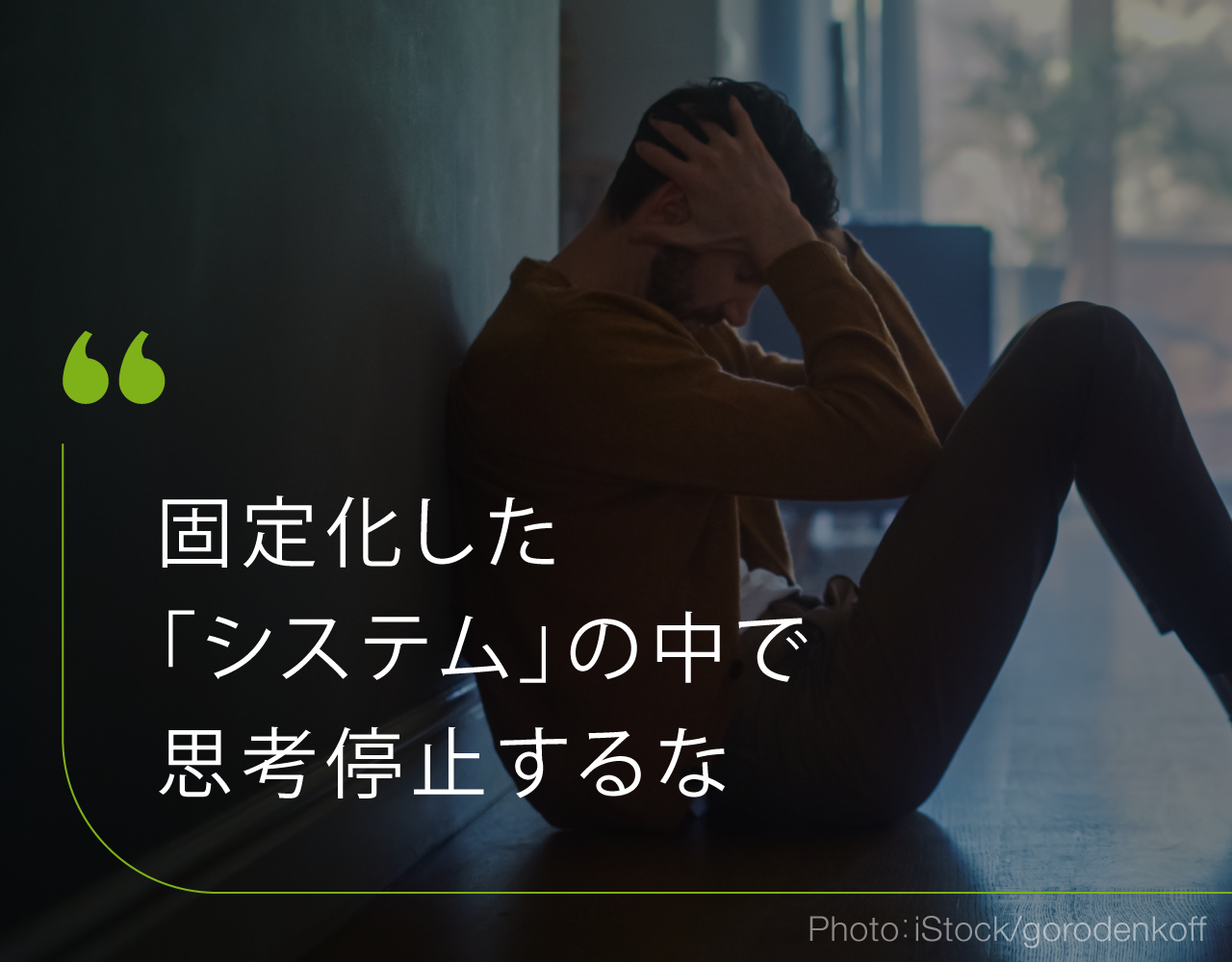
このような実体験に基づいた気付きは、とても大事だと考えています。
というのも、いまはネット上に氾濫する二次情報やSNSでの拡散によって、真実に近い一次情報に触れる機会が少なくなっているからです。
知識が溢れ過ぎているので、真実を見分けるスキルが必要になると思います。そのために大切なのは、実態に近い一次情報に直接触れることです。
「卒業が遅れて就職で不利になる」と不安になる必要はありません。いま22歳だとしたら、これから50年も働くわけですから。
20代のうちにこうした刺激を受けることは、とても有意義なのです。
仮説思考では甘かった
理学系の学生の皆さんは、日頃から自然界の論理を使って考えたり説明したりしています。この点も、社会に出てから強みになるでしょう。
しかし、実社会に入ってから使った論理は自然科学とは少し異なっており、私の場合は慣れるまで少し時間がかかりました。
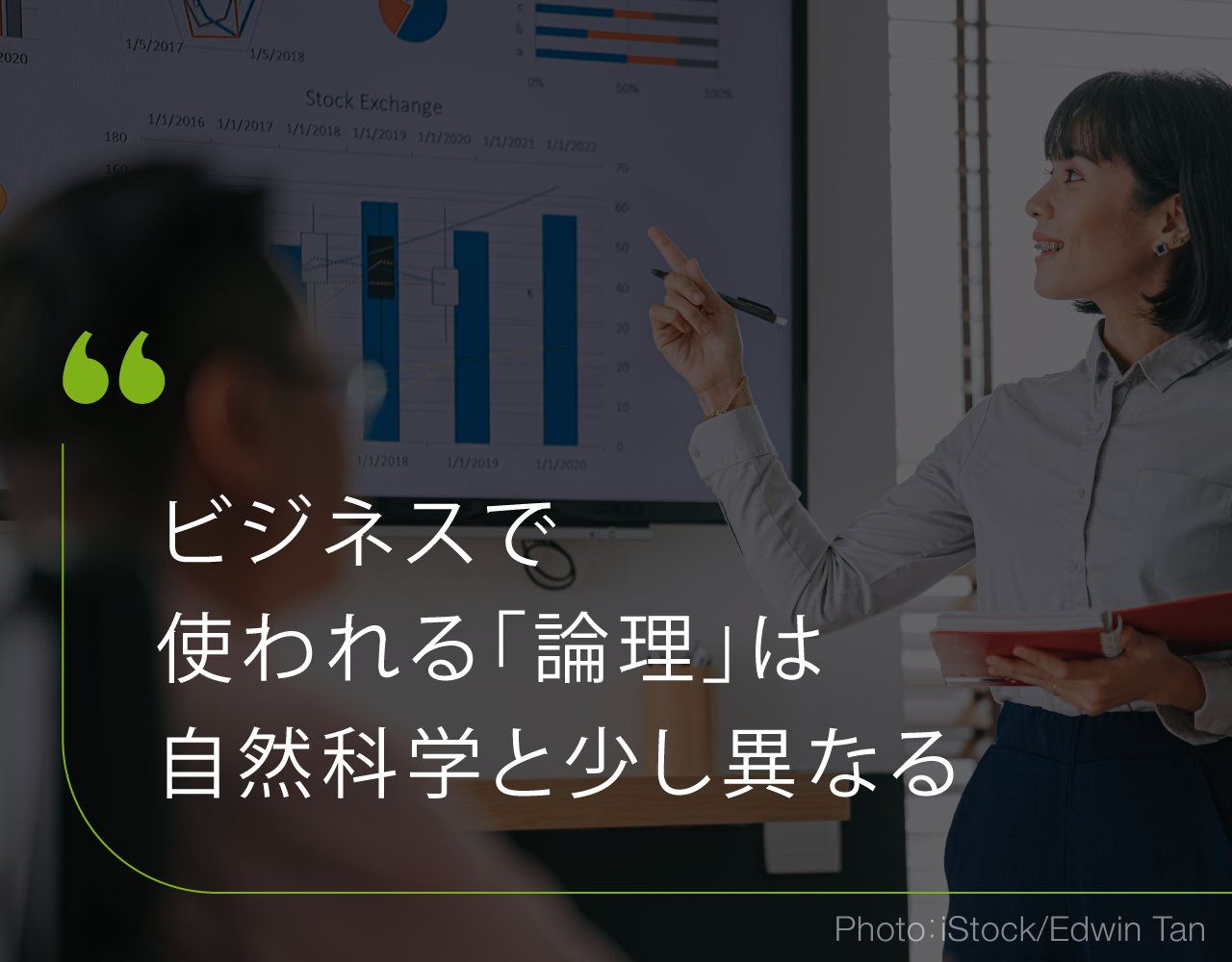
私はアンダーセンに入社してすぐ、ロジカルシンキングの研修を受けました。そこで、いわゆる「情報の構造化」と「仮説思考」の方法論を教わったものの、自分の中ではずっとモヤモヤしたものがありました。
例えば仮説思考では、早い段階で仮説を決めてしまいます。その後に状況分析のために情報を集めて、構造化しながら結論を急ぎます。
結論を早く出すという意味では実務的である一方で、このやり方では「自分の見たいものしか見ていないのではないか」という気持ちがずっとありました。
アンダーセンでひと通り論理的な思考方法を叩き込まれた後、リサーチ業務に携わっていた時も、膨大な量の企業や市場のデータを大量に分析しながら、背後にある自然法則を全くつかめていませんでした。

このような状況に対して、私の場合はもともと理学部時代に行っていた方法で適応しました。自然科学のアプローチで客観的に物事を観察し、さまざまな特徴の中から必要なものを見つけ出すやり方です。
まずは市場を中立的に観察します。そこから施策を打ってみてはフィードバックもらう。いろいろと試してみるうちに、少しずつ「市場の声」が分かってきました。
物理の実験も同じですよね。まずは自然現象を客観的に観察する。実験をして得られたデータを分析しているうちに、自然法則が浮かび上がってくる。
こうしてやり方を変えてからは、徐々に成果が出るようになりました。学生時代から染み付いていた科学的なアプローチが役に立ったわけです。
ポイントは、「ロジックツリー」や「ピラミッド・ストラクチャー」などを用いる時には、しっかりとどの“特徴”に注目して整理するか考えるということです。物事の背後にある法則を徹底的に観察すると、道理が分かるので解決策も見いだせるようになります。
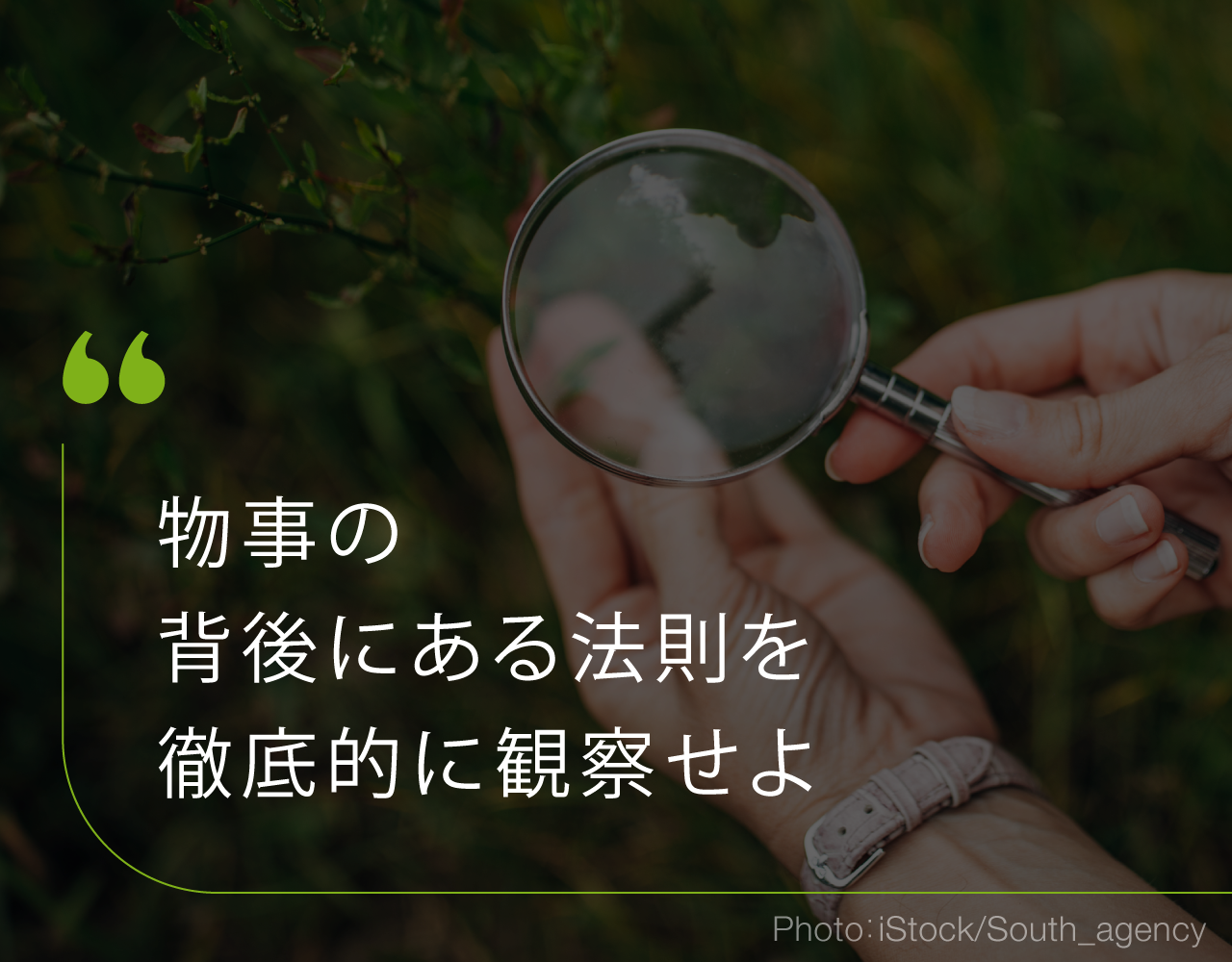
こうやって問題解決に導くやり方は、学生時代にやる論文を書くことでも磨くことができます。
自然科学系の論文を書く際には、新規性と論理的に説明できる客観性が必要となります。論文や教科書などの内容にオリジナリティを加える必要があるからです。
だからこそ、一次情報である自然現象を客観的に観察する必要があるのです。
「客観的に観察すると同時に論理的に考える」というプロセスは、学生時代に学ぶ基本中の基本。でも、それをビジネスの世界で生かすには、オフィスに閉じこもっていてはダメなのです。
ビジネスは知恵の輪と同じ
アクセンチュアを退職して独立した後は、共同創業者としてネット広告ベンチャーにジョインしたのですが、その時は「営業ができない」という壁にぶつかりました。
コンサル時代は多くのクライアントが大企業だったこともあって、そういう企業への営業方法はある程度理解していました。
予算獲得にはこういう社内承認が必要で、それをクリアするために準備しなければならない資料はこれ、というルールが分かっていたからです。
いま振り返ると、「コンサルの論理」が通用していたのです。
しかし営業する相手が一般企業になり、なおかつ広告という全く異なる商品になった途端、私の営業トークでは全く売れなくなりました。ロジックだけでは買ってもらえなかったのです。
なのでその時も、人情や義理を大事にするような中小企業の社長さんに対して営業するのが得意だった共同創業者や営業メンバーに同行しながら、現場感覚を学んでいきました。
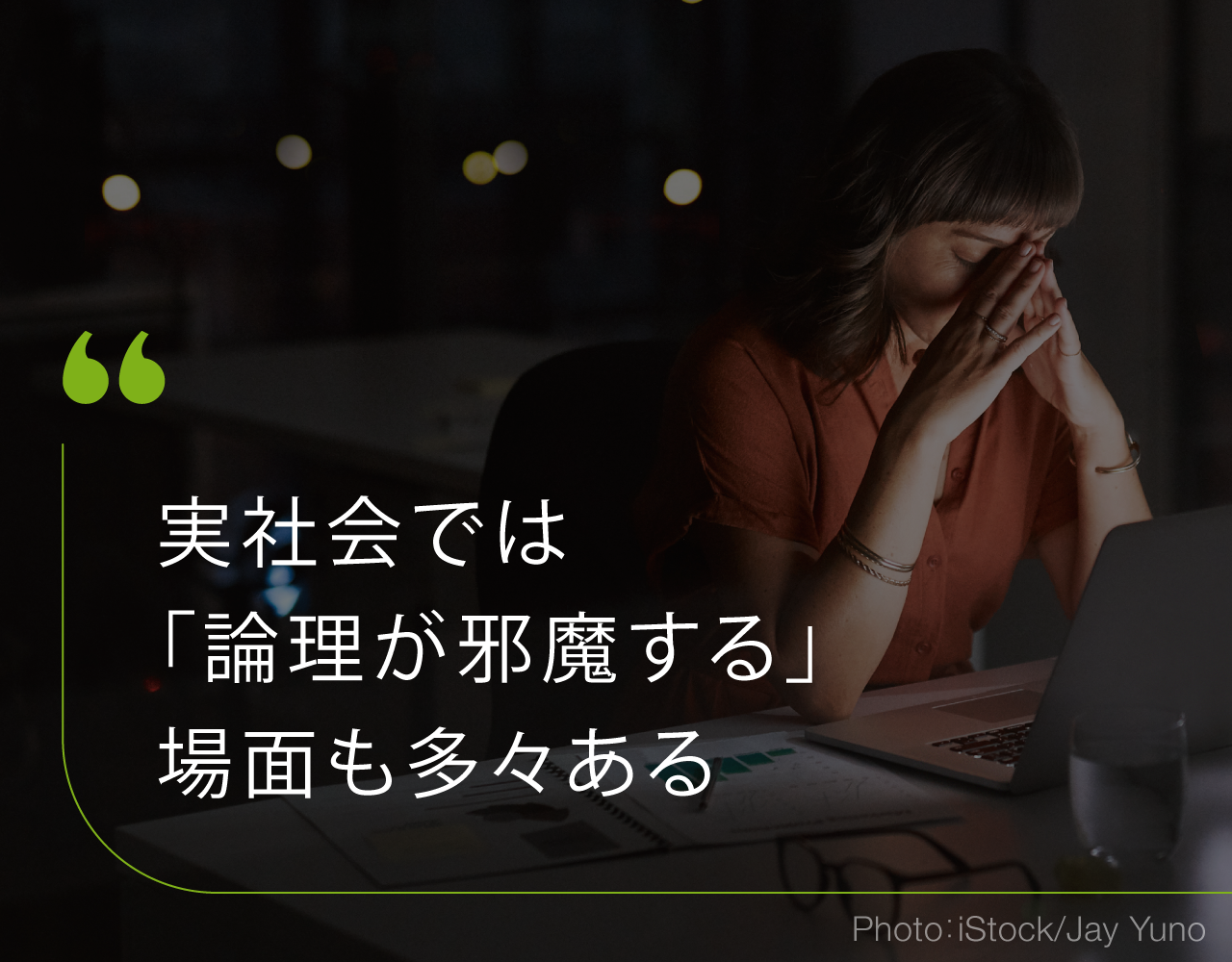
ビジネスにおいて、論理が邪魔をする場面は他にも多々あります。事業開発などが良い例でしょう。
私はアンダーセンを辞めて独立してからも、フリーのコンサルタントとして大手企業の新規事業創出を支援したり、自ら社員として大企業に入って働いたりしていた時期があります。
その時にほぼ必ず直面したのは、会議室に集まってアイデアを議論しても、良いプランが出てこないということです。
そういう時はよく、「温泉に泊まりがけで行って合宿しましょう」と持ちかけていました。
良いアイデアは、物事を論理的に考えている時ではなく、リラックスしている時に出るもの。例えば、温泉に入ってビールを飲んでくつろいでいる時などです。

アイデア出しのような場面では、分析業務に必要な思考プロセスとは異なる脳の領域を使うことが求められます。
論理的な作業は「左脳」で行われ、新たなアイデアを出すような創造的な作業は「右脳」で行われるからです。つまり問題解決の“回路”が異なる。
研究室で行っている論理的な分析も、ビジネスで武器になる一方で、それだけでは戦えないわけです。
例えるなら、ビジネスで必要な能力とは「知恵の輪を解く」ための能力と同じ。論理や分析と、試行錯誤によって得る実践力が両方必要です。

知恵の輪を解く時は、まず「これがこうなって、こことつながって」みたいな構造をロジカルに分析します。
だけど、それだけではありません。何も考えずに無心になって試行錯誤している瞬間もある。これはビジネスも同じではないでしょうか。
話半分で聞けばいい
「海外に行く」「論文を書く」といったアクションは誰しもが明日から実践できるわけではないと思います。
ただ、これから就活に臨む学生の皆さんが今日から即実践できることとして、人の話を鵜呑みにしないということがあります。
少し懐疑的な態度でいるくらいがちょうどいいのではないでしょうか。「この人はこんなことを言っているな」「そんな考え方もあるのか」といったような受け止め方です。自分にとって大切な情報を取捨選択する姿勢が大切です。
私はスローガンが運営する“もう一つの大学”としてのプラットフォーム「Goodfind」を通じてたくさんの学生を見てきましたが、100%情報を吸収してしまう学生が多いんです。
「コンサルはビジネスの基礎力が身に付く」「これから盛り上がる業界は●●だ」などという話を盲信する人が増えた理由として、受験競争があるのではないでしょうか。
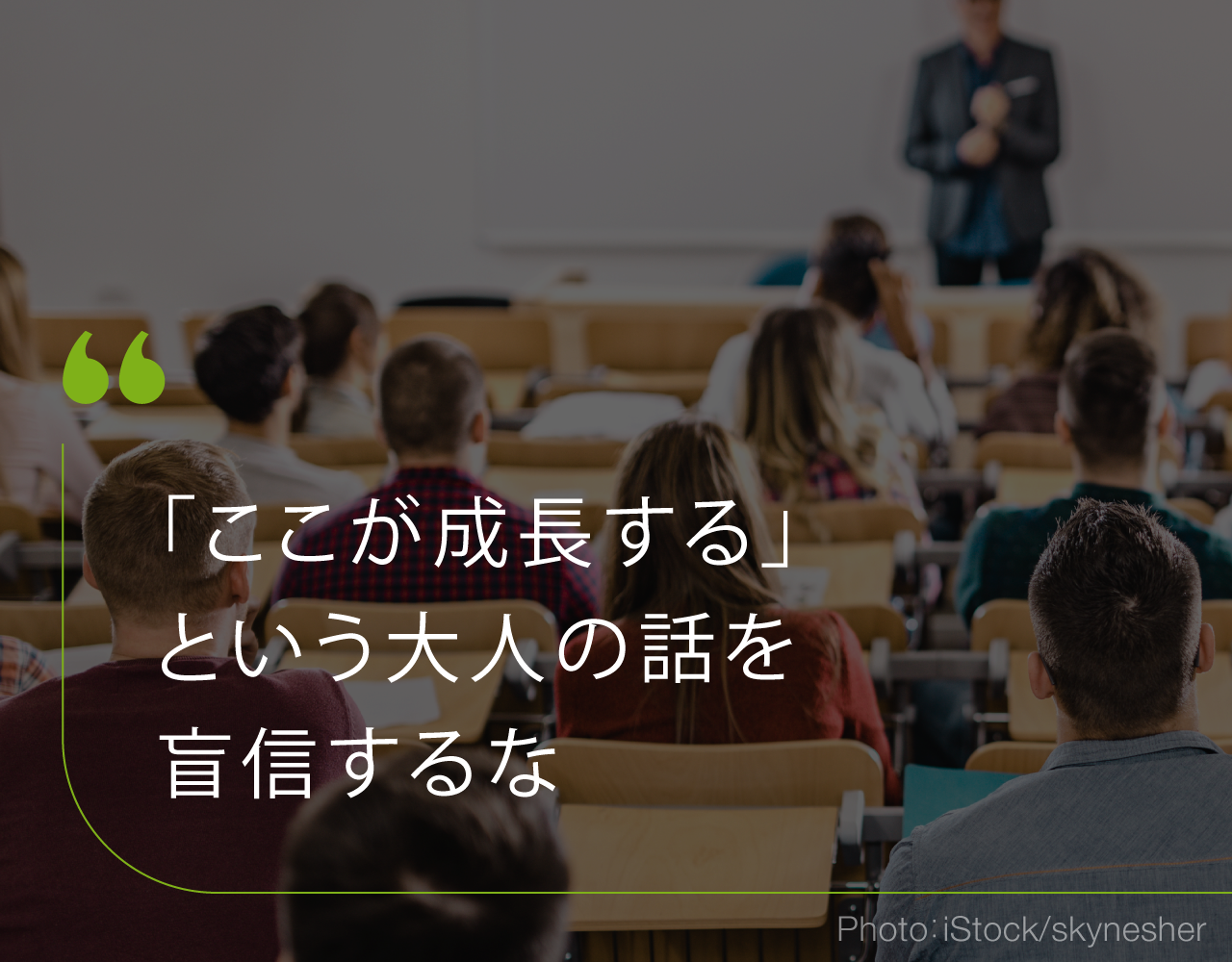
受験競争では、情報の取捨選択をせずに盲目的に覚えた人が有利になります。その結果、物事を常に別の角度から見る習慣を身に付ける機会が失われているように思われます。
また、意見自体ではなく「誰の発言か」で判断してしまいがちです。先生や実績のある人の発言を、内容に関係なく事実のように受け止めてしまうことは、皆さんにもあるのではないでしょうか。
加えて、どんな人も自分に都合の良いことを意識的にも無意識的にも擁護してしまいます。いわゆる「ポジショントーク」から逃れることが困難なわけです。
だからこそ、懐疑的な態度でいることが重要であると考えています。
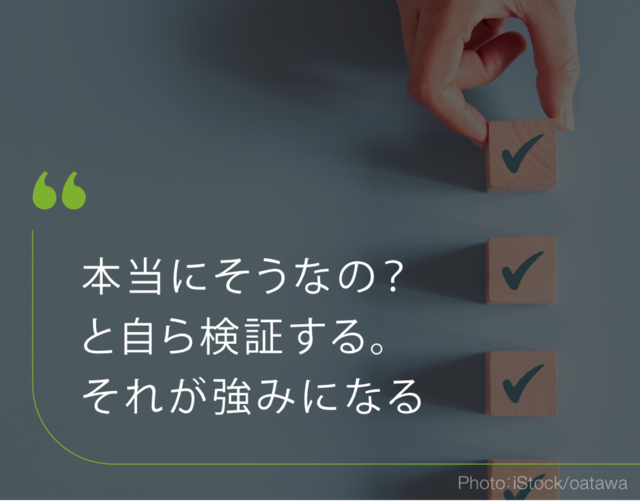
私だって例外ではありません。経歴を振り返れば、理系の学生として研究していた期間が長かったので、自然と科学的な見方をしてしまいます。それに加え、問題解決の考え方は、外資系コンサルでの経験がベースになっていたりもします。
だから、私の話にもバイアスがかかっていると思って聞かなければいけないはずなんです。過去の経験に考え方が依存するわけなので、必ず偏りが出る。
一方で、ビジネスにおいては客観的かつ中立的に現状を見ることが求められる時があります。
まず、自分を含め誰しもにバイアスがあることに気付くことが必要です。
ここで改めて「22歳に戻ったら海外に行く」という話にもつながってくるわけですが、多様な経験をして、フラットな視点で物事を見られるようになりたいですね。
失敗と成功の確率論
最近はGoodfindのセミナーで、事業創造の講座を担当したりしています。その際に、「どんなビジネスが将来伸びるかは私にも分からない」と正直に伝えています。
私の経験上、どれだけ入念に事業計画を立てても上手くいかない場合もある。逆に、実際やってみたら意外なことが分かったりもします。
実行に移す前に、事業の成功確率を高めることは難しいと思うんです。
だから私たちがやるべきは、何回もチャレンジして成功確率を高めることだと考えています。確率論で考えてみると、挑戦回数を増やすことの大切さがよく分かると思います。
.png)
例えば、1回起業して成功する確率が10%だとしましょう。すごく低いですよね。単純計算して、10人に1人しか成功しないわけですから。
それでは、成功確率10%の事業に5回挑戦したらどうなるでしょう?実は、少なくとも1回は成功する確率が35%にまで増えるんです。
10回挑戦した場合はどうでしょう?少なくとも1回は成功する確率が65%にまで増えます。理学部生の皆さんなら、何回もチャレンジすることの重要性が直感的に分かるでしょう。
起業にとどまらず、やってみないと分からないことは多々あるのではないでしょうか。完璧な計画を立てるよりも、挑戦回数を増やすことが肝要なのです。
これから臨む就活や、その後の社会人生活でも、この考え方を大事にしてたくさんチャレンジしていただけたらと思います。

合わせて読む:【完全図解】Z世代の就活、5つの大変化

取材・文:安保 亮、取材・編集:伊藤健吾、デザイン:浅野春美、写真提供:スローガン