若手時代は「何でも学ぶ」
—— 明円さんは電通での6年間で、たくさんのヒットCMを手がけています。ベテランのクリエイティブディレクターも多い職場で、どうやって実績を残したのですか?
とにかく勉強しました。
大学時代は、サークル活動が楽しくて、就職活動には消極的でした。 そんな私を見かねて友達が連れて行ってくれた合同説明会で、初めて見た会社が電通だったんです。
そこで、総合広告代理店って、イベントからSNSキャンペーンの企画・運用まで、何でもやっていると知りまして。
私は特にやりたいこともない学生だったので、会社に入ってからやりたいことが探せる環境が魅力的で、この会社に強く入りたいと思うようになりました。
ところが、当時の私には履歴書に書ける強みがなくて。そこで、履歴書に書けるようなエピソードを作らねばと、あえて1年間休学することにしました。
クリエイティブ関連の本を読むのはもちろん、スタートアップ企業でインターンをしながら広告案を考えて、企業に自主提案するような活動もしていました。
その時の提案で、焼肉チェーンの牛角さんと一緒に広告を制作したこともありました。
肉を焼く網の上にQRコードをつけて、それを読み取ると肉が焼かれている映像が流れるという、スマホ黎明期の紙媒体とデジタルを組み合わせた広告企画です。
これが、ありがたいことにSNSで話題になり、就活の面接でもこのエピソードは楽しんで聞いていただけました。
—— アイデア豊富な学生だったのですね。
クリエイティブなことに興味があったのは確かです。それでも、プロとして仕事ができるとは思っていませんでした。
無事に入社した電通では、企画の作り方を教えてもらうため、とにかく先輩に話を聞きに行っていました。
広告制作に関することは、何でも学ぶ姿勢で知識を広げた結果、入社5年目にKDDIの『意識高すぎ!高杉くん』シリーズなども担当させてもらいました。
—— 独立してからも、変わらず話題となる企画を数多く作っています。
直近でお手伝いしたのは、Duolingoという会社のプロモーションです。
この会社は、海外では有名な外国語を学ぶアプリを運営しています。
同社が日本でフランス語コースを開講するにあたって、プロモーションとして「フランス語の注文しか受け付けない ふしぎなパン屋」という企画を実施しまして。おかげさまで、盛況のうちに終えることができました。


—— 独創的なアイデアです。
ただ、私は企画をポンポン思いつくタイプではないので、他人の良いアウトプットを見て、インプットしながら、企画を考えることが多いです。
連休は1人で合宿したり、友達を呼んで勉強会をしたり。とにかく勉強することを大切にしています。
企画の「構造」を真似る
—— そんな明円さんに、影響を与えた書籍を教えてください。
最初に思いつくのは、私が一番好きな本でもある『メディアの実験集「モノサシに目印」』(毎日コミュニケーションズ)です。
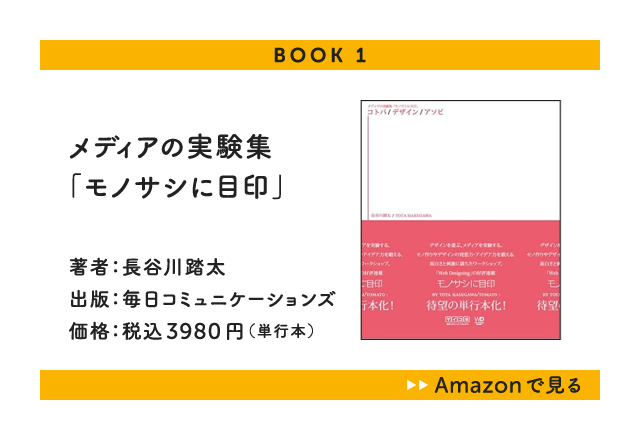
著者は、デザイン業界で活躍している長谷川踏太さんです。4年前、電通の先輩から「読んでみたらいいよ」と薦められました。
タイトルにもあるように、実験集のような本で、実際に各ページでいろんな実験が行われています。
例えば、「盗み見る」という項目では、電車で隣に座っている人が盗み見るのに適したレイアウトになっているんですね。
紙のメディア特性を考えた企画がたくさん載っている面白い本で、長谷川さんの思考実験が垣間見られます。
私もこの本に刺激を受けて、メディア特性から企画を考えることが多いです。SNSやYouTubeで新しい機能が出ると、すぐに試すようにしています。それが、新しいアイデアを生む一番の近道だったりしますから。
すごいクリエイターの「思考の構造」を真似るのは、とても大事なのだと実感しています。
—— 構造を真似るとは?
例えば、人が読んでいる本を「盗み見る」のは、普段の生活ではあまり行儀のよくないことですよね?
ただ、この本では、「ダメなことを許容する」という構造が面白いクリエイティブを生んでいます。
この構造に注目して、自分ならどうやるかを考えてみる。これが「真似る」という意味です。
著者の長谷川さんは、「盗めるアート展」という個展も開いていました。
ギャラリーに展示されるアート作品は、常識的には「盗んではダメなもの」です。でも、それを盗んでいいというふうにしてみたら、どんなことが起こるのか?という実験です。
結果、「盗めるアート展」にはたくさんの方が押し寄せて、やや社会問題になるほど話題を呼びました。
—— 企画の構造を考える上で、他に参考にしている書籍はありますか?
『日本の歴史的広告クリエイティブ100選』(宣伝会議)が参考になっています。
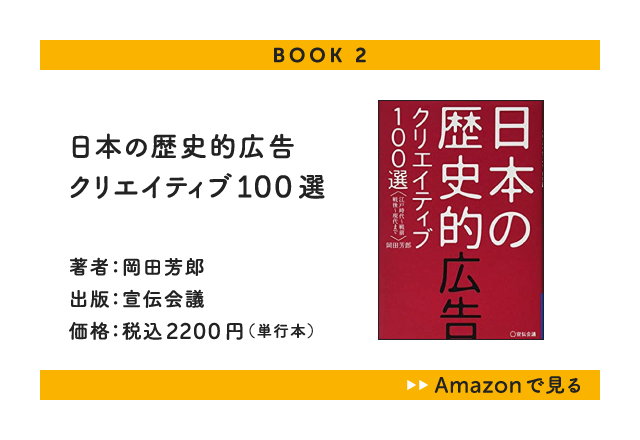
この本は広告の歴史本なので、100年前の広告も載っています。それを見ると、現代と同じことをやっているんですよ。
コロナ禍で増えた意見広告などもそうで、社会情勢への不安が増すと、意見広告が増えたりする。まさに歴史は繰り返すです。
私は広告の打ち合わせをする時、「あの広告のさ......」と具体的な事例を持ち出しながら行うことが多いです。
過去の広告は、イメージを共有する一番の近道。そういう意味で、歴史を学ぶのは大切だと思っています。
良い企画には「驚き」がある
—— そうやって企画を各論で練っていく過程で、参考にしている書籍はありますか?
CMプランナーの大先輩、高崎卓馬さんの『表現の技術』(中央公論新社)という本です。
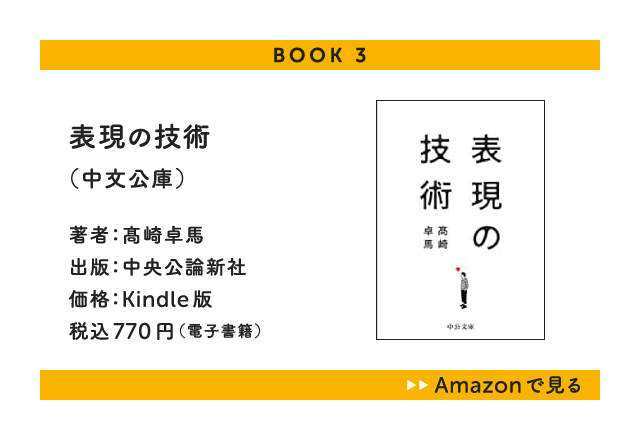
この本で、全ての良い企画には「驚きがある」と述べられています。
企画の中で予定調和がポンとズレる、みたいな部分があると、面白いクリエイティブになるという話です。
—— やはりというべきか、高崎さんをはじめとする業界の諸先輩の言葉には学ぶところが多い?
もちろんです。思い返すと、電通時代の師匠にも、仕事では必ず「チャレンジポイントを作りなさい」とアドバイスされました。
チャレンジするのは、企画以外の部分でもいい。例えば、クライアントのキーマンに好かれる、打ち合わせで誰よりも多くの案を持っていくなど、行動で驚きを提供することでもいいのです。
何より、仕事に1つでもチャレンジポイントがあるだけで、自分の充実度が違ってくる。この教えは、独立した今でも大切にしています。
—— メンターとなるような師匠の存在が、仕事の型をつくる手助けになると?
そうですね。一方的にですが、師匠と思っている人はたくさんいます。
入社1年目の頃は、所属部署を超えて、いろんな先輩に仕事のやり方を聞きに行っていました。新人の今しか聞けないと思って、「どうやって企画を立てるのか」「面白い企画を選ぶ基準は何か」と、とにかく聞いて回りました。
作ったものの良し悪しを判断する人の視点を学ぶと、自分の思考も深まります。 今でも課題に向き合う時は、「あの先輩だったらどう言うかな」と考えることが多いです。
思考の師匠をたくさん持っておくのが大切だと思います。
人生で大切なのは「外様の仲間」
—— 企画やアイデアの発想に限らず、明円さんに影響を与えた書籍はありますか?
『明け方の若者たち』(幻冬舎)という小説です。
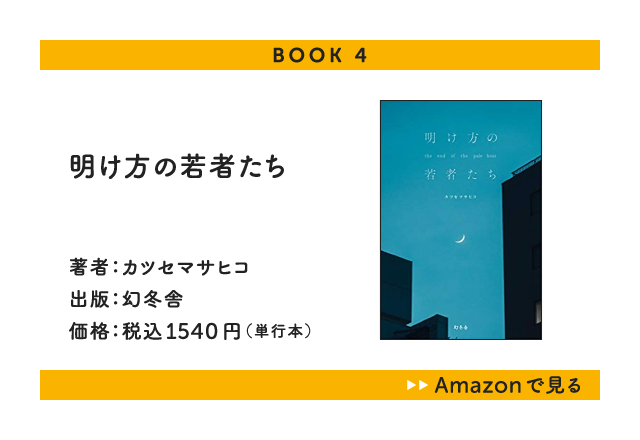
小説家カツセマサヒコさんのデビュー作で、実は彼と友達なんです。だから紹介したわけではなく、内容はもちろん面白い。近々、映画化もされる予定です。
友達が初めて書いた小説がめちゃくちゃ売れて、それが映画化されて、主演が北村匠海さんで。そんなドラマティックな展開を横で見ていたら、尊敬しかないですよね。 すごくエネルギーをもらっています。
ちなみに、彼を含めた4人ぐらいの友達グループがあって、誰かが何かを納品すると、その打ち上げをする会を開いています。
この会は、私の仕事に大きな影響を与えていて。広告業界の人に褒められるよりもずっと、違う業界の友達に、自分が作っているものをダサいと思われたくないからです。
—— 他に、明円さんの価値観や考え方に影響を与えた書籍はありますか?
平野啓一郎さんの『「生命力」の行方―変わりゆく世界と分人主義』(講談社)というエッセイが好きですね。
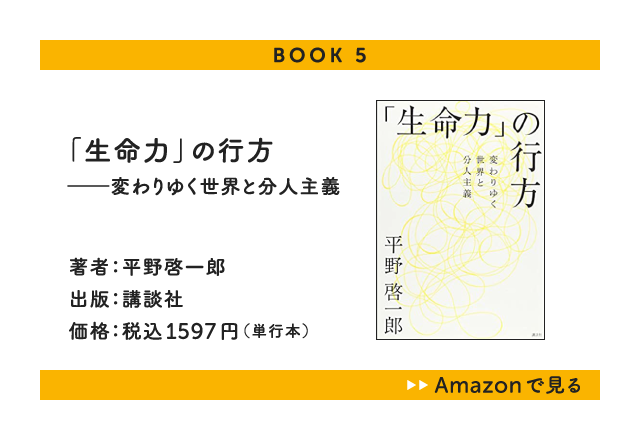
「分人」という考え方は、私の会社kakeruの思想ともすごく近いものがあります。
今って、1人の人間が、いろんなコミュニティに対して、いろんな顔を持っている時代じゃないですか。
例えば、会社での自分と、家族の中の自分、それぞれが違っていいよねという考え方が「分人」です。
このような生き方がすごく楽だと思うし、いろんな人生を楽しめる。
会社だけの人生だと、仕事がうまくいかないとつらくなります。でも、いろんなコミュニティに所属していれば、物事が1つうまくいかなくても、どれかが自分の心のセーフティネットになってくれます。
私の考えもこれに近くて、今はいろんなところに所属しながら仕事をしています。
こういう働き方は、メリットがたくさんあると感じています。自分1人で、自分だけの知恵でやっていると、どんどん古くなっていくからです。
例えば私はCHOCOLATE,inc.というクリエイティブブティックにも所属しているのですが、ここはさまざまなジャンルのクリエイターが在籍する会社で、常に新しい情報が飛び交っています。
単純に楽しいし、自分がずっと新しくいられるという点でも、すごくいいなと思っています。
私が代表をしているコーヒー屋「JANAI COFFEE」にも、連日さまざまな業界の方が遊びに来てくれるので、そこで知り合う人から日々新しい話を聞けるのが楽しいですね。

—— 最後に、読書を通じて得られるインプットは、キャリア形成にどんな意味を持つと思いますか?
本とは、人の試行錯誤のプロセスの凝縮した集積物です。そして読書とは、その人が試行錯誤したエッセンスをお借りする、もっとも良い体験の1つです。
人の努力した時間を、短縮して、知恵を借りることができる。なんてお得なんだと思いませんか? だから、本は絶対に読んだ方がいい。
私は、インプットのためにかなり時間をかけています。人の良いアウトプットを見て、インプットしながら、その型を参考に、企画を考えるという感じです。
だから私にとって、読書をはじめとするインプットは、アウトプットに欠かせないのです。

合わせて見る:【動画】時代を映せ!広告クリエイターの思考回路
取材・文:平瀬今仁、編集:佐藤留美、デザイン:黒田早希、撮影:遠藤素子