「計画外」の出来事とも上手に付き合う方法
うつ病を含む心身の病気・傷病を理由とする休職や、介護など家族の事情による一時的な退職、出産による産休・育休など。
長い社会人人生の中では、自分の意に反して仕事を休み、キャリアに一定期間の空白ができてしまうことがある。
休職・退職期間が長くなると、給与面での懸念はもちろん、問題なく復職できるのか?という不安も募るもの。終身雇用の文化が色濃く残る会社に勤めていたら、なおさらキャリア形成に支障が出ると思うものだ。
ただ、こうしたキャリアの空白期間を、その後の仕事人生をより良いものにするきっかけにした人たちもいる。
例えば、現在ピアニストとして人気のハラミちゃんは、音大を卒業後IT企業に就職したものの、頑張り過ぎで体調を壊し、若くして数カ月の休職を経験している。
その時期に「自分が一番しっくりくる場所を考え直した」(ハラミちゃん)結果、リハビリを兼ねてストリートピアノの演奏を開始。
当時は仕事にするつもりがなかったそうだが、YouTubeなどでの演奏配信が評判を呼び、小さな頃からの夢だったピアニストとしてキャリアを築くことになった(詳しい経緯は下の記事にて)。
【ハラミちゃん】自分らしく働くために見つけた「2つ目の武器」こうした転機は、ひと握りの人にだけ訪れる偶然ではない。意図的に内省や学び直しの機会を設けて、キャリアを大きく変える人は少なくないのだ。
そこで本稿では、休職や退職を人生の転機に変えたロールモデルの事例を4つ、紹介していこう。
1. 産休・育休時期の「内省」が転機に
最初に取り上げるのは、女性のみならず男性も取得することの増えた「育休」について。
女性の場合は産休も合わせて長期間職場を離れるケースもあるが、この時期をキャリアの振り返りに使い、復職後の働き方を変えた人はたくさんいる。
電通の新規事業「電通ビジネスデザインスクエア」の立ち上げメンバー西井美保子さんもその1人だ。
西井さんは、電通に新卒入社してからリサーチャーとして活躍。若者やギャルの消費動向を研究する「電通ギャルラボ」や「電通若者研究部(電通ワカモン)」を立ち上げたり、『パギャル消費』(日経BP)という書籍を出版するなどの実績を残していた。
しかし、新規事業の立ち上げで役割が変わり、担当する案件も幅広くなったことで、最初は戸惑いがあったという。

【コンサル】電通の新職種「ビジネス・デザイナー」とは
そんなタイミングと第一子の出産が重なり、自分自身と向き合う時間が良い方向に働いたそうだ。
詳しくは上のインタビュー記事に譲るが、次のような転機になったと述べている。
それまでは、自分の承認欲求を満たすために仕事をしていたんですね。「電通ギャルラボ」のような取り組みも、自分の興味が原動力になっていました。
でも、出産の前後から、自分以外のチームメンバーが輝ける場所を作りたいという思いが強くなっていきました。
電通ビジネスデザインスクエアでも、私とは違う専門性を持つタレントを、もっと外に出したいと考えるようになってから、私自身もポジティブに今の仕事に取り組めるようになりました。
産休・育休期間に資格取得やプログラミングの勉強をするなど、新たなスキル習得に励む人も多いが、働き方そのものを振り返るだけでもキャリアにメリットをもたらすという好例だ。
2. うつ病による休職・退職で働き方を見直す
次に紹介するのは、現代病の一つとも呼べるうつ病による休職・退職からの復活劇だ。
バリバリ働いてきた人ほど、メンタルの病によって空白期間ができるのはショックなものだが、理想の働き方を考え直すタイミングにもなり得る。
東京大学の大学院を修了し、世界的化学メーカーのデュポンに就職した佐川友彦さんも、うつ病になったことで自分に合う働き方を模索したという。
下のインタビューでは、当時の思いをこう語っている。
一人前に働くこともままならず、小さい頃から育ててきた自分という株券が、突然上場廃止になった感覚でした。プライドがへし折られ、価値がゼロになったと感じたんです。
でも、一度ゼロになり、今までつけていたレッテルが剥がれ落ちると、失うものが何もなくなります。気付けば『周囲から頭が良いと思われたい』だとか、『成功していると思われたい』だとか、そんな承認欲求が失くなっていました。
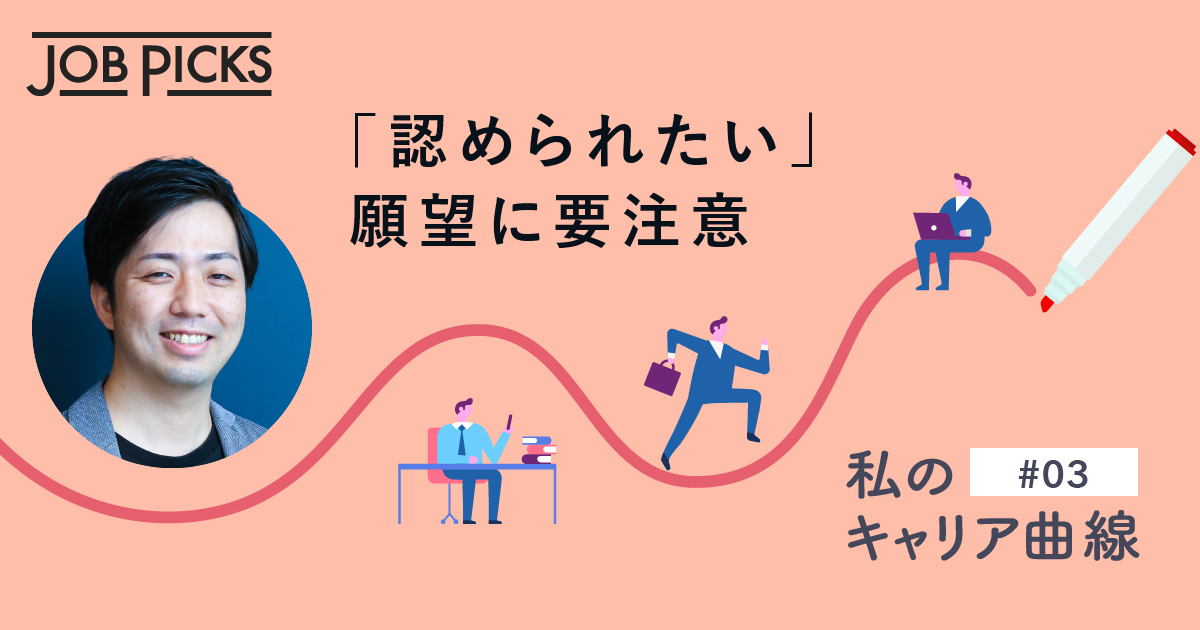
東大卒の研究者が農園の右腕に。20代「やりがい迷子」の抜け出し方
その結果、見つけたのが「農業×ローカルビジネス」というテーマだ。
自身の知識やIT活用の知恵を生かし、農業をきちんと“経営”するためのコンサルタント的な仕事に活躍の場を見つけ、2020年には自著『東大卒、農家の右腕になる。 小さな経営改善ノウハウ100』(ダイヤモンド社)を出版するに至った。
今になって振り返ると、デュポンで働いていた頃は大義名分にこだわりすぎていたのだと思います。
まずは家族や一緒に働く仲間など、目の前にいる人を幸せにできる仕事を選ぶべきでした。目の前の人を幸せにすることができれば、それと同じ手法でもっと多くの人を幸せにできますし、新たな挑戦をしにいけますから。
とはいえ、人は走り続けていると、案外目の前の幸せに気付けないものです。私の場合は、体調不良の期間があったからこそ、自分にとって何が大切なのかを見つめ直すことができましたし、あらゆる分野の勉強をつまみ食いしたことで、自分の可能性を広げることができました。
3. 社会人留学で視野を広げる
勤め先の狭い世界から抜け出して、視野を広げるという意味では、これまで紹介してきたタイプの休職・退職ではなく自らキャリアの空白期間をつくりにいく人もいる。
MBA留学など、社会人になってから学び直す機会がそれにあたる。
SmartHRのCOO(最高執行責任者)を務める倉橋隆文さんは、20代のMBA留学で「半径5メートルの環境」を変えたことが、キャリア形成に大きな影響をもたらしたと話している。
詳細は下のインタビュー記事で紹介しているが、新卒でマッキンゼーに入った後、MBA留学をして最も刺激的だったのは、経営理論そのものではなかったそうだ。
.jpg)
マッキンゼー出身COOに聞く「とりあえずコンサル」アリかナシか
ハーバードでの学びは、「コンサル最高!」と思っていた私の価値観を、想像以上に覆してくれました。印象に残っているのは、MBAの代表的な学習法と言われるケーススタディです。
例えば、2010年頃にアメリカで起こったトヨタ自動車の大規模リコール(アクセルペダルに不具合が生じた車体を回収、無料修理した一件)を題材に、「あなたがトヨタの経営者ならどう対応するか?」と議論を重ねるのです。
ケーススタディを通じて、事業計画と呼ばれるものがいかに机上の空論なのかを痛感しました。
他の授業でも、アメリカで大きな成功を収めたスタートアップ100社を研究したら、創業時に立てた計画通りに成功した会社は10%以下だったという話を聞き、衝撃を受けたのを覚えています。
ビジネスでは、計画や戦略以上に大切なものがある——。コンサル時代、この「当たり前」に気付かなかった理由を、倉橋さんは「多忙と仕事の面白さで視野が狭くなっていた」と自己分析している。
このような気付きが、実行力を磨くため楽天やSmartHRへ転職する原動力になったそうだ。
4. キャリアを好転させる「潜伏期間」のつくり方
高い留学費をかけて海外MBAを取得しに行かずとも、能動的にキャリアの空白期間をつくりながら「本当にやりたいこと」を見直す方法は他にもある。
ビズリーチ、メルカリ、スマートニュースなどメガベンチャーを渡り歩いた経験を発信し、自身のTwitter(たいろー @tairo)フォロワーが2万を超える森山大朗さんは、「IT×先端分野」でキャリアを築いていく前に1年ほど、キャリアの“潜伏期間”を取った。
新卒で入ったリクルートで人事や営業を経験し、その後に転職したネットベンチャーでマーケティングを学ぶうちに、「自分はどんな仕事でキャリアをつくっていきたいのか?」を整理したいと思うようになったからだ。

【新説】スマニューのマネージャーが28歳で「適職」を見つけた意外な方法
何となくではなく、心から「この世界で食っていきたい!」と思える仕事を模索したい。そう考え、ITの世界とは縁遠い飲食店でアルバイトをしながら「感覚を試してみた」結果、森山さんは「人が喜んで使ってくれるような仕組みやサービスそのものをつくりたいんだ」と確信。
迷いが吹っ切れてからは、常に最新の技術を学びながら、上記したようなメガベンチャーで活躍してきた。
こうした転機をもたらす「潜伏期間」のつくり方について、森山さんはこうアドバイスしている。
僕はキャリアに空白をつくり、それが結果的にキャリアの転換点になったのは事実です。そういう意味で潜伏期間には意味があったと思います。
とはいえ、いきなり会社を辞めるのは無謀です。現実的には、会社勤めをしながら夜の時間や休日を利用して「疑似潜伏期間」という学びの時間を設けることになると思います。
ただ、注意してほしいのが、まずは会社が求めていることを全うするということ。本業をおろそかにしてしまうのは本末転倒なので、まずは今いる現場で、成果を出すことが最優先です。
その上で、会社の仕事とは違う方向に好奇心が疼いているのなら、余力を残して潜伏してみると、思わぬ方向にキャリアが進んでいく場合もあるので、あえて流れに乗ってみるのも良いでしょう。
森山さんの話す「擬似潜伏期間」のつくり方は、上のインタビュー記事で詳しく解説してあるので、ぜひ読んでみてほしい。

合わせて読む:【超解説】あなたの価値を上げる「アンラーニング」実践講座
文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / girafchik123