永遠の課題「業務効率」と向き合う
働き続ける間は必ずつきまとう「業務の生産性向上」の話題。
就職・転職の文脈で考えても、新たな仕事、異なる職場で存在感を発揮するにはアウトプットの質のみならずスピードがモノを言う。
だが、日本では長時間労働が是とされてきた期間が長く、国際的に見て労働生産性は非常に低いと言われ続けている。
「もっと効率的に時間を使いたい」「働き方を変えてもっと成果を出せるようにしたい」。そう思ってはいても、すぐには自分を変えられないという人も多いはずだ。
そんな背景もあり、生産性に関する書籍やノウハウはいつの時代も人気があり、下で紹介するような記事にも多くの反響があった。
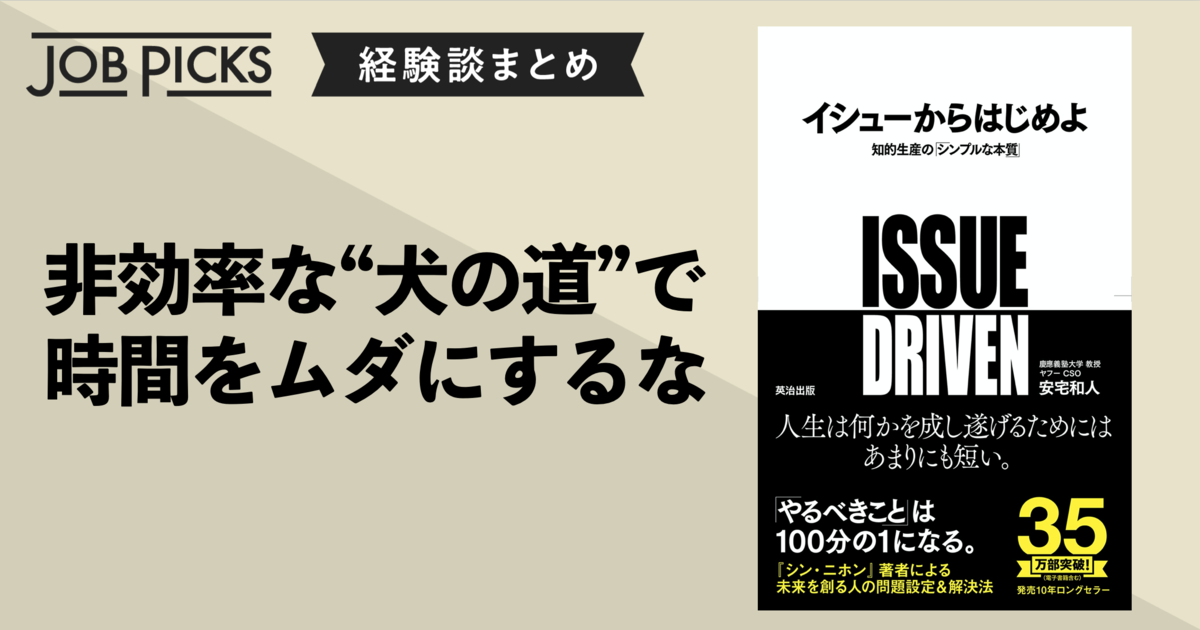
【証言6選】『イシューからはじめよ』で生産性が劇的に上がるワケ
【プロ推薦】仕事の生産性がアップ。2021年「最高の買い物」とはいえ、思考を変える系のインプットは、なかなか身になりにくいというのも事実。
そこで本稿は、JobPicksのロールモデルが投稿してくれた経験談の中から、すぐにマネできそうなtipsをピックアップしてみた(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。
今日から活用できそうなやり方をインプットして、業務効率を改善しよう。
仕事の目的から整理し直す
まず紹介するのは、仕事の大上段となる部分から見直すことで、動き方を変える方法だ。
鈴木豪介さんが下の投稿で述べているように、KPI(重要業績評価指標)を適切に設定することで組織全体の業務効率を上げる取り組みは、多くの企業が取り組んでいるだろう。
KPI
フィールドセールスだけではありませんが、セールス工程においての、見込み客の数値化や可視化されての管理は、欧米に比べて日本は遅れています。 そのため、旧来の属人的な営業スキルに依存する組織がまだまだ蔓延っています。 組織として、人員の影響による脆弱さを避け、安定した成果を出し続けるために、昨今ではSFAの導入が進んでいます。 1人のレジェンド的な営業よりも、10人で12~13人分の成果を継続的かつ効率的に出力するために、KPIの管理が重要になります。 フィールドセールスの前工程であるインサイドセールス、ひいてはマーケティング、また後工程のカスタマーサクセスの領域まで、シームレスに情報伝達がなされなければなりません。 特定の工程にのみフォーカスしKPIの達成にこだわり続けると、質の悪いリードの醸成に繋がってしまいます。 サブスク型の売り方が主流になる今、成約率や継続率が低いリードは非効率です。 各工程がぞれぞれの前後工程とKPIの質も含めたイメージを共有し、単純な数字だけではない部分も可視化することが大切です。
だが、こういう目標設定は「偉い人が行うもの」と考えてはいけない。
経営コンサルタントの藤熊浩平さんは、若手時代の上司に教わった「バリュー(価値提供)ベースで業務を捉えろ」というアドバイスによって、自ら仕事の「What(何をすべきか)」や「Why(なぜすべきか)」を考えるようになったという。
この習慣を持つことで、分析業務のような日常の仕事でも「最終的にどんな価値につながるのか」から逆算して業務設計をするようになった(詳細は下のインタビュー記事にて)。
バリュー(提供価値)ベースで仕事をする
「そろそろ、タスクベースではなく、バリューベースで仕事をしてみようか」 これは、私が新卒2年目の時に、当時のメンターだった人からいただいたアドバイスです。 私は新卒でコンサル業界に飛び込んだので、最初の1年は、ただ目の前の与えられた仕事に全力投球して、相手の期待値を超えることで精一杯の日々でした。 この時の「仕事」とは「タスクをこなす」ことで、今振り返ると当時の自分は、「便利な作業屋」になっていたと思います。 学生あがりだった私は、まだ何者でもなく、誇れるのは体力くらいだったので、コンサルスキル以前のビジネススキルを身につけるのに必要な期間だったとは思います。 ただ、この仕事の本分は、クライアントを介して世の中に新たな価値をつくり出していくことで、その目的のために目の前のタスクや作業がある、というのが本来の順序です。 そんな当たり前のことに、改めて気づかせてくれた言葉でした。 「バリューベースで仕事をする」、言うは易しですが、実際の行動に移すにはハードルがあります。 まず、そもそも何がクライアントや世の中にとっての「バリュー(価値)」になるのか、がクリアになっている必要があります。 その上で、自分がどういう活動に、どれだけの時間を使えば、どれくらいのペースで価値が積み上がっていくのか、が分かって初めて、リソース配分ができるようになります。 そういう意味では、今もなお、「バリューベース」で仕事ができているか、日々模索中ですが、その意識を持つことで、仕事に向き合う姿勢は間違いなく変わります。 「タスクベース」で仕事を受けると、「How(どうやるか)」が気になります。そのタスクありきで、いかに効率的にこなすか/いつまでに終えられるか、が関心事になるからです。 「バリューベース」で仕事をすると、「What(何をすべきか)」や「Why(なぜすべきか)」が気になります。最終的に価値につながる仕事でないと、意味がないからです。 時が経ち、私がチームを率いて、メンバーをマネージする立場になった時、先ほどの言葉をいただいた人から、また貴重なアドバイスをいただきました。 「メンバーを、スキルセットの集合体と捉えるか、バリューの集合体と捉えるか、それによってマネジメントの仕方は変わるよ」 コンサルファームでは、各コンサルタントは、プロフェッショナルとして日々成長が求められ、「Development needs」という言葉がよく飛び交います。 そうして、コンサルスキルのレーダーチャートのパイを、大きく、正多角形に近づけていこうとします。 なので、ともすると、コンサルタントを「スキルセットの集合体」と捉え、あれはできている/これはできていない、というような見方をしてしまいがちです。 他方、コンサルファームに集うメンバーは皆個性豊かで、好きなこと・得意なこと、情熱を傾けられるもの・夢中になれるもの、それぞれです。 プロジェクトも、クライアントの業種や取り組むテーマ、働き方など、さまざまです。 マネジャーの仕事は、チームとしてのバリュー(提供価値)を最大化することです。 そのためには、「スキルの塊」としてではなく、意思や感情を持った個性豊かなメンバーの力をいかに最大限引き出すか、そして、それを価値に転換するために、彼ら・彼女らを含めたチームとクライアントとの化学反応をどうデザインするか、が重要だということを教わりました。 世の中に対する「バリュー(提供価値)」を日々意識しながら、それに貢献しうる/矛盾しない仕事を、これからもしていきたいと思います。
.png)
【超実践】「成長実感がない」の壁を破る、たった一つの教え
目的から考える癖が、アウトプットの精度を高めると同時に、本来のゴールに素早く到達する道筋を示すのだろう。
効率化のツールは身近なところに
業務効率を上げるためのツールは多々あるが、「会社が導入してくれなくて」「使い方がよく分からなくて」と思い悩む前にできることから探してみよう。
すぐにできる小さな工夫はたくさんあるものだ。
YouTuberマネジメントなどを手掛けるUUUMに所属していた小野田昌史さんは、トップクリエイターとして知られるHIKAKINさんから次のようなアドバイスをもらったそうだ。
「自分の夢や仕事で使う道具にはしっかり投資を行え」
こちらのコメントを頂いたのは 以前所属していたお世話になった事務所 UUUM の最高顧問を行っている HIKAKINさん から頂いた言葉です。 「僕は自分の実現したい夢や仕事に使うものは 妥協せずに一番いいものを買ってる。」 という言葉を聞き そこから "自分が叶えたい夢、仕事に使うものは最高のものを使う" という考えになりました。 HIKAKINさんは実際にそれで結果を出していますし その「妥協しない考えあってここまで来れた」と その言葉を聞いて 感銘を受けて今でも教訓として残っています。 より良いものを作っていくためには良い道具を使う。大事なことだと思います。
「お金で解決できることはお金で解決するべし」という話だが、初期投資すらいらないやり方もたくさんある。
例えばメンズスキンケアブランド「BULK HOMME」の広報・神田真季子さんは、日々の情報収集を下記のように行っている。これは、知ってさえいれば誰もができるライフハックだ。
Googleアラート
自社のニュースのモニタリングはもちろんですが、指定キーワードを入れておくだけで関連ニュースを拾ってくれるので、競合他社名や業界キーワードを入れておくだけで、業界のトレンドがわかるようになっていて便利です。 Googleニュースで拾っているニュースは、ニュースサイトの記事だけではなくて、リリース配信サービスの更新情報も拾っているので、ニュースになる前の一次情報に触れることもできます。 私は slackに連携して、関心のあるものを業界動向としてシェアするようにしています。効率的にキーワードでニュースをザッピングできますし、気になる記事はストックすることができます。 頻度の設定や言語の設定も可能です。
また、NewsPicks パブリッシングの書店営業を担当する岡元小夜さんは、ベストセラー本の『ゼロ秒思考 頭がよくなる世界一シンプルなトレーニング』(ダイヤモンド社)を参考に、メモ帳を次のように使いこなしている。
ゼロ秒思考(ダイヤモンド社)
本書は一言で言えば「A4の用紙にメモ書きをする本」です。 このメモ書
アナログツールを侮るなかれ、ということだ。
躊躇せず人を頼る
生産性を高めるには、黙々と集中して作業する時間が大切と思いがちだが、「困ったら人に頼る」を実践するのも効率化のヒントになる。
ニューズピックスのWebマーケター菊地幸司さんは、効率よくインプットを増やすために対人コミュニケーションを重視しているそうだ。
インプットを増やすために、人に会う
「インプットを増やすために、人に会う」 マーケは実施するかどうかは別として、たくさんアイディアを考える必要があります。 どんどんアイディアが湧いてくる天才ならいざ知らず、私のような凡人はアイディアが浮かばなくて苦労します。 そんな時に、上司から「アウトプットを増やすには、インプットを増やすことが必要。インプットを効率よくするには人と会って話すこと」とアドバイスされました。 もちろん、本を読むでも、セミナー行くでも、インプットの方法はいくらでもあります。 ただ、私も人と話すと仕事がうまく行く、という(若干胡散臭い?)実感もあります(笑) 困ったら人に会おう!※ ※withコロナ時代なので、臨機応変に〜
また、UXデザイナーの盛亜耶さんは日々の業務にルール化して取り入れている。
3分悩んで分からなかったら質問する
同僚のエンジニアの方にアドバイスしていただいた言葉です。 入社した
これと似たワークルールとして、Googleには「15分ルール」という不文律が浸透しているという。「質問」は最強の問題解決手法となるのだ。

ソフトウェア開発の最重要スキルとは?グーグルのエンジニアに聞く
他人の効率「も」上げるメリット
最後に、自分のみならずチーム全体の生産性を高めるための工夫を見ていこう。
シンプルに「雰囲気をよくする動き」が生産性を変えると述べるのは、DMM.comのソフトウェアエンジニア釘宮愼之介さんだ。
ネガティブメンバー
ネガティブメンバーのいるチームに所属することはとてもしんどいですね。 少し意味は違うかもですがブリリアントジャークとも言ったりします。 恒常的に周りにネガティブな行為を行う人の総称です。 いくらスキルがあっても、攻撃的なメンバーがチームにいる場合、当人とのコミュニケーションに全体が疲弊し、チーム全体の生産性ががっつり低下。 マネージャーもその対応にすべての労力を持ってかれる。 他チームとのコミュニケーションにも支障がでてきますし、最終的には席替えすらにも注意を払う必要。などといったような様々な悪循環を生みます。 何をするにも一番大事なのは人です。そして、自分がそうならないように心掛けるのも重要だと感じています。 自分がそういう気配があるかもと感じている人は、アンガーコントロール系の本などを読むとよいかもしれません。
同じDMMの事業部長・石垣雅人さんも、異口同音にチームの雰囲気の重要性を語っている。石垣さんは中でも1on1を重視しているそうだ。
チームのモチベーションが低くなってしまっているとき
プロダクトを作る上で、エンジニアやデザイナーといったモノを作る存在は必要不可欠です。 私自身もエンジニアであるため、エンジニアがモチベーション高く開発できているときは、スピード感をもってイテレーティブな改善をどんどん回せますし、それによって事業が成功することもあります。 一方、開発プロセスがうまく整備されていなかったり、エンジニアが開発しづらい環境だとモチベーションがどんどん低下していきます。そうなると、チームの雰囲気も悪くなり悪い方向にメンタルモデルが形成されていきます。 逆に少しの壁があったとしても、エンジニアやデザイナーがモチベーション高くいれば意外にすっと超えられます。 なので、できるだけエンジニアリングマネジメントにも力を入れるようにし、1on1を中心とした会話の量を増やしたりアジャイルを中心とした開発プロセスの整備に力を入れています。
デンソーのYasuzaka Taikiさんは、具体的なエピソードを用いて効率化のカギを投稿している。ポイントは「仕事相手の要望の真意を確認すること」だ。
自分なりのプラスアルファを発揮する
全ての業務に通じることと思いますが、顧客/上司からの指示に従うだけでなく相手の望むこと、期待を自分なりに把握、理解してそれを上回るアウトプット(プラスアルファ)を出すことが次の仕事やステップアップにつながります。 自身の例を挙げると、北米拠点スタッフからの"顧客向けに報告書を作成してください"という曖昧な問い合わせに対して、背景、状況を理解した上で相手がほしいと思われる報告のイメージを作成して事前提案することで相手の理解をスムーズに得られることを実感しました。 北米拠点赴任中はメールだけでは伝わりづらい拠点や顧客の状況、考えを自身の意見を交えて本社に説明することで拠点間のコミュニケーションレベルが深まり、業務が効率よく推進することを実感しました。
仕事を共にする仲間の生産性まで考えて作業することで、チーム全体の生産性が上がっていく。ソフトウェアエンジニア佐野貴之さんの下の投稿を見ても、これは間違いない。
リーダブルコード
ほとんどの開発が複数人でコードを書きながら進めていくことになるので、
そして、こうした意識を持って動くことが、結果的に自分の身も助けることになるのだ。
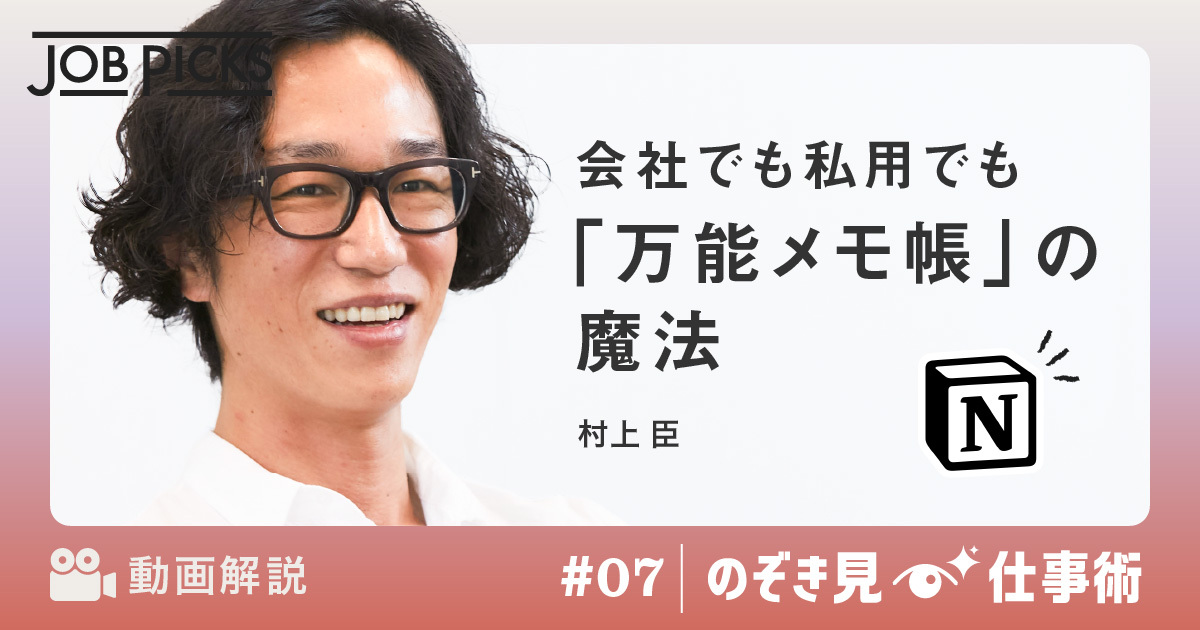
合わせて読む:【村上臣】仕事効率が10倍に「Notion」私の使い方見せます
文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー写真:iStock / lankogal