「入社後ストレス」の原因と向き合おう
納得して就職したつもりが、いざ働き出してみると違和感が拭えない。思い描いたような活躍ができず、ダメ出しされる毎日に心が折れそう。
新社会人として働き出した人や、心機一転、転職・異動をして新たな仕事に取り組む人は、入社2〜3カ月後くらいに多かれ少なかれ理想と現実のギャップに悩まされるものだ。
近年は「入社3カ月未満」で会社を辞める若者が増えていると話題になることも多く、「自分はそうはなりたくない」という気持ちもモヤモヤに拍車をかける......。そんな状況で悶々としてしまうのだろう。
【完全図解】20、30代に急増中「燃え尽き」を防ぐ5つの方法事実、転職サービスの「doda」が転職直後(入社後1~3カ月程度)のストレスの有無を調べたところ、約500人の調査対象者のうち80%以上が何かしらのストレスを感じていたという(参考記事)。
その多くは入社前に聞いていた仕事内容とのギャップや上司・社風とのミスマッチが原因とのことだが、これらの悩みは自分のアプローチ次第でも解消できる。
そこで本稿では、新人時代の悩みを自らの行動で払拭してきたロールモデルの経験談をピックアップ。「想定外」を乗り越えて活躍する道を見つけた先輩たちのやり方を学ぼう。
ルーティンワークに疑問を持った時は...
「憧れの会社に入ったつもりなのに、なかなか自分が出せない」
エンタメ業界への就職を希望し、第一志望だったエイベックス・エンタテインメント(以下、エイベックス)に入社した西木沙織さんは、1年目でこんな違和感を抱いていたという。
下のインタビューでは、「目の前の仕事をこなすことに必死で、自分らしさを表に出せず、毎日萎縮して働いていた」と述懐している。

【エイベックス・25歳】インスタグラムとアルバイトで、第一志望に内定
そんな西木さんの気持ちを変えたのが、周囲の“大人”の言葉だったそう。
まず、上記したような状態を抜け出すきっかけは、就活前に内定獲得に向けて頑張ってきたことを知っていた先輩だった。
笑顔を失って働いている私に「仕事は楽しんでやるものだよ」と声をかけてくれたので、「本当はこんなことがやりたいんです」と素直に話したところ、私の個性を生かすポジションを導いてくれました。
その日から、自分らしさを表現できるようになり、毎日の仕事が本当に楽しくなりました。夢を語り、もがいている人には、必ず応援してくれる人が現れるものなのです。
臆せず自己開示することで、思っている以上に「すぐ解決できる」悩みもある。そんな行動原則を学んだそうだ。
そして、ある程度仕事に慣れてきた2年目には、同社の役員にかけられた次のような言葉に感化され、今でも座右の銘にしているという。
トンネルを掘っているのか、未来を作っているのか。
__ とある旅人が 山でトンネルを掘っている人に「何をしているのですか?」と尋ねると 「見ればわかるだろ、トンネルを掘ってるんだ」と答えました。 しばらく歩いていると また別の場所で同じような事をしている人を見かけ 「何をしているのですか?」と尋ねると 「未来を作ってる!ここにトンネルが開通したら街の未来が変わって多くの人が幸せになる。」と答えました。 __ 同じことをしているように見える二人の異なる回答。 今自分がやっている業務に対しても 、どこまで”想像” を膨らませられるか。 ”想像” 次第でやりがいもモチベーションも、そして行動も変わるのではという例え話でした。 入社2年目でルーティン業務には慣れてきた頃の私にとって この話はとても刺激的でハッとさせられました。 この話をしてくれたのは弊社の役員です。 他にも上司からは「自分が楽しめなきゃお客様を楽しませられない」という言葉を頂けたりと、、 常にエンタテインメントな想像力と心を持った先輩方がいる環境で 働けることをとても幸せに感じます。
何のために働くのか?という目標設定を見直すことが、アウトプットのみならず「やりがい」を変える転機になるという好例だ。
萎縮し過ぎは個性を殺す
「自分には知識も経験もないのだから、まずは言われたことをこなそう」
新人時代のこうした考えは、殊勝な態度として褒められそうに感じるかもしれない。
しかし、貴重な戦力として採用された以上、自らの考え・主張をしないことはチーム貢献できていないことにもつながる。何より、自分を押し殺して働くのは精神衛生上もよくないことだ。
ラクスルの運用型広告事業「ノバセル」で新卒2年目からマネージャーとして活躍する楠勇真さんも、新人時代はこんなジレンマに悩んだ1人だった。
下のインタビューでは、当時の気持ちを次のように吐露している。
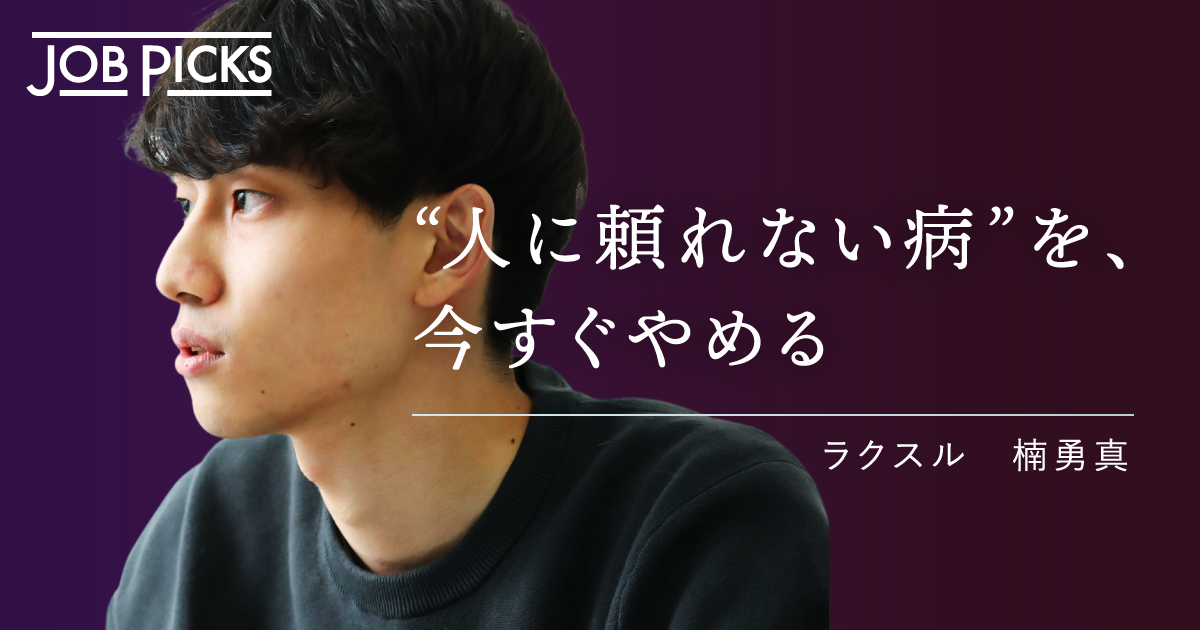
ラクスル最年少マネージャーが見つけた、最速で結果を出す3つの視点
最初にぶつかった壁は、「自分で決められない」というものでした。
事業部には、広告業界歴が長い先輩社員がいます。彼らは経験も多く、業界のことをよく理解しています。
一方、入社当時の自分には、知識も経験もない。そのため、「自分が下手にアイデアを出すよりも、サポートに回る方が会社にとって良いことなのではないか」と感じました。
その解釈は間違っていなかったかもしれませんが、まずかったのは、御用聞きのような存在になってしまったこと。「先輩が出したアイデアが優れている」という思いから、自ら模索し、働きかけることをやめてしまっていました。
するとある日、上司の田部(ラクスル取締役CMO・田部正樹さん)から、「しゃべらないなら、ここにいる意味ないですよ」とメッセージが送られてきました。クライアントの打ち合わせで、一言も発言しなかったからです。
こんな状況を抜け出す転機となったのは、「自分なりに目の前の仕事にどう取り組むか?」というスタンスを決めたことだったという。
スタンスがないまま仕事をしていても、大した貢献はできません。また、スタンスを明確にできない理由が「事業への解像度が低い」だけなら、それは単なる甘えです。そんな当たり前のことに、気付かされました。
楠さんはその後、マネージャーとして成果を出そうと孤軍奮闘し過ぎたあまり、「“人に頼れない病”で大失敗したこともある」と語っている。
こうした若手あるあるを乗り越えるには、目標達成に向けて「どんなスタンスで臨むべきか」を真剣に考えることが突破口になる。
文字通り「腹を括る」ことも大切というエピソードだ。
妥協をなくすという選択も大事
この「腹を括る」ために、思い切って環境を変えるというやり方もある。
M&Aの仲介業を手掛けるGrowthix Capitalで働く坂本 匠さんは、学生時代にプロを目指して取り組んだラグビーでの挫折を乗り越えて、同社で“第二の春”を謳歌している。

【再起】ラグビーのプロを諦めた僕が、なぜM&Aのプロになったか
ラグビーの本場ニュージーランドへの留学も経験し、プロ契約の一歩手前まで進んだ坂本さんは、トッププロとの実力差を感じて夢を断念。
その後の就職では「とりあえず生活できること」を念頭に大手電機メーカーに入社したものの、仕事内容より福利厚生などを重視した結果、やりがいを感じない日々を過ごしていたという。
そんな状況を変えたのが、大学のラグビー部の先輩だったGrowthix Capital社長・中島光夫さんとの会食。「やりたくないことをやって悶々としているなら、ウチに来いよ」と声をかけられ、全く知識のなかったM&Aの世界に転じた。
知識どころかコネもゼロという状態ながら、何とか仕事に食らいつくことができたのは、「決断した以上は本気でやる」という思いとともに、次のような魅力があったからだという。
未経験でM&Aアドバイザーになったので、イメージも何もない状態から学び続ける毎日でした。
でも、大変ではあっても「できない」「合わない」と思ったことはないです。
ラグビーもM&Aも、チームプレーが求められるからです。
私がラグビーに没頭していた一番の理由は、チーム全員でトライを目指す競技だから。M&Aも、買い手企業と売り手企業の間に我々が入り、密にコミュニケーションを取りながら成約を目指します。
この点が、意外にハマったのかもしれません。
仕事内容より、働き方に「やりがい」を見いだす。これも、新人時代のモヤモヤを解消するヒントになるかもしれない。
モヤモヤの原因を他責にしないために
ここまで紹介してきたロールモデルのエピソードは、あくまでも「他人の話」。そんな思いが拭えない人に向けて、人事コンサルとして多くの組織変革に携わってきたコーン・フェリー・ジャパン松下晴香さんの投稿を紹介しよう。
松下さんは、人事コンサル未経験者におすすめの勉強本として以下の書籍を紹介しているが、ここに記してある「失敗から学習する方法」は個人のキャリア形成にも役立つものだ。
『失敗の科学 ―失敗から学習する組織、学習できない組織―』
この本は、人事・組織コンサルティング業界の入門書というわけでもなく
「そのつらさや怒りを“個”に帰着させたくなります。今回は誰が悪い?と犯人さがしをしたくなる。しかし、それでは何も解決しておらず、失敗が起きた構造や要因に目を向け、よりよくするために何ができるかに目を向けなければならない」
ここで重要なのが、「自責で考える」とはすなわち「失敗が起きた構造や要因に目を向ける」ということ。
もし、新たな環境でモヤモヤを感じているなら、まずは要因分析から始めてみよう。その上で、他人や環境のせいにせず「自分でも変えられる部分」を探してみる。
こんな一歩が、その後の活躍を生み出すのだろう。
最後に余談だが、松下さんの新人時代の失敗談も非常に生々しく共感できるものなので、ぜひ参考にしてもらいたい。
「始まりよければすべてよし」
昔、私がジュニアのコンサルタントだったときに、先輩からこっぴどく怒られたことがあります。 プロジェクトを序盤・中盤・終盤に分けたときに、100・100・100という具合に、私はほぼすべて同じウェイトで仕事をしていました。序盤にちょっと“見えない”ことが何個かあったのですが、“まぁ他にも考えなければならないこともあるし後回しに・・・”という感じで。 結果として、全然パフォーマンスを上げられていませんでした。 すると、先輩から言われたんですね。 「ナメてんのか。お前100・100・100で仕事してるだろ?」と。 「ダメダメ。150・70・100ね!序盤ですでにプロジェクトの着地点が見えていなければならない。そのためにはどんな些細なことであっても“良く分からない”“気持ち悪い”と感じる点をすべてつぶせ!」と。 当時は言われて腹も立ちましたし、 150・70・100ってそもそも合計300超えてんじゃん、と心の中で突っ込んでました(苦笑)。 ですが、これを意識すると、 お客様やチームのメンバーから信頼されると中盤や終盤非常に進めやすくなるだけでなく、予期せぬことにも対応しやすくなります。 また、この150のなかにはプランニングも含みますが、「先の読めない世の中でなぜプランニングするんだ」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。計画を立てるのは、万事計画通りに進めるという意味ではなく、むしろ突発事項に柔軟に対応するために、取捨選択をするためにこそ必要だと考えています。 「終わりよければすべて良し」ということわざがありますが、コンサルティングは「始まりよければ・・・」だと考えています。

合わせて読む:【完全図解】就職、転職、副業。「良い仕事」に出会う3原則
文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / yuoak