仕組みでなく自ら「稼ぐ」経験を
まず前提としてお伝えしたいのは、会社選びに「絶対的な正解」はないということ。就活生一人一人が自分にとっての「優良企業」を定義する必要があります。
私にとっての「優良企業」は、事業と投資の両方に携われる会社でした。
事業をやっていく中で、投資したい事業に投資する。逆に、投資する中で、面白そうな事業には自分で挑戦してみる。この両軸で活躍したいという気持ちが強くあったのです。
私が就活生だった当時、事業と投資のどちらかで活躍されている方はたくさんいました。一方で、どちらもやられている方はあまり多くなかった。そのため、純粋に「両方できたら格好いいな」と思っていました。
しかし今振り返ると、「自立的に働けるか」という観点も重要だと感じます。
IT業界のM&Aの支援者として、そして経営者として働いていて痛感するのは、「売上を作れなければ会社がつぶれてしまう」ということ。
責任のある立場になればなるほど、会社を存続させていくために何をすれば良いかを考え、自分から行動しなければいけません。至極当たり前のことです。

ですが、特に若手のうちは、実は自立的に働かなくても何とかなる場合が多い。「自分が売上を作らなければつぶれてしまう」というような切羽詰まった状況は極めてまれです。
というのも、多くの会社では「仕組み」が出来上がっています。
営業であればそもそも商材が優れていたり、「誰でも結果を残せる」ような営業メソッドがすでに確立されていたりする。
そのため、自身の営業力が実はそこまで問われていない場合もあります。
そういった環境でキャリアを積むと、仮に全く仕組みが出来上がっていない会社に移ったとき、今まで通りの営業成績を残すことは難しくなってしまう。
つまり、仕組みが出来上がっている会社に長く身を置くことはリスクにもなり得ます。そのため、今もう一度就活生に戻ったとしたら、自立的に働ける会社を選ぶと思います。
では、自立的に働ける会社とはどんな会社なのか。
条件の一つとして「伸びている」ことがあげられます。具体的な指標でいうと、売り上げと社員数ですね。この二つが伸びているかを有価証券報告書などで確認すると良いと思います。

こうした成長フェーズの会社はまだ仕組みが出来上がり切っていないことが多いので、いろいろな仕事を任せてもらえる可能性が高まります。
特に私がおすすめしたいのは、一つの職種を幅広く任せてもらえる会社。営業なら、企画・提案から新規開拓まで一通りやれる、という感じです。
仕事が細分化され過ぎると全体像を見失ってしまいがちですが、一方で幅広い職種を短期間でジョブローテーションしてしまうと、専門性を高めることが難しい。
職種という専門性を確保しつつ広範な仕事に取り組める環境が、プロフェッショナルを目指す上でベストだと思います。
どうせ働くならプロでありたい
今までお話ししてきた観点に加えて、「人」も就職先を選ぶ際の非常に重要な要素です。
就活生の皆さんは、できるだけ多くの社会人と接点を持ち、「イケてる大人」を見つけると良いと思います。
私が「人ドリブン」での会社選びという考えを持ったきっかけに、学生時代のベンチャーキャピタルでのインターンがあります。

そこにはコンサルや投資銀行出身者など、さまざまなバックグラウンドを持った人が集まっていました。彼らと一緒に仕事をする中で、「将来こんなふうになりたい」という自分の中での像が明確になったんです。
特に、「この方々はイケてるな」と感じたのは、勝ちパターンを知っているということ。
コンサルや投資銀行は、とりわけ結果を出すことをシビアに求められる環境と認識しています。だからこそ、彼らは各々の出身企業の経験から勝ちパターンをたくさん知っています。最後まで「勝ち」にこだわる方が多い。
このような「イケてる」仕事ぶりに学生のうちから触れるのは、とても有意義なことだと思います。
それから、プロ意識を持っていることも大切です。プロ意識の有無で仕事への取り組み方が大きく変わるからです。
例えば、「自分は会社の一営業マンにすぎない」と思って営業していたら、「自社の商品や顧客について理解を深めよう」とはならないかもしれません。自分の意識はお客さんにも伝わります。
一方、プロ意識がある人は徹底的に自社の商品を理解し、顧客についても調べ尽くす。だから、「私はこの商品を誰よりも知っていて、あなたの気持ちも分かります」という自信のある伝え方ができます。
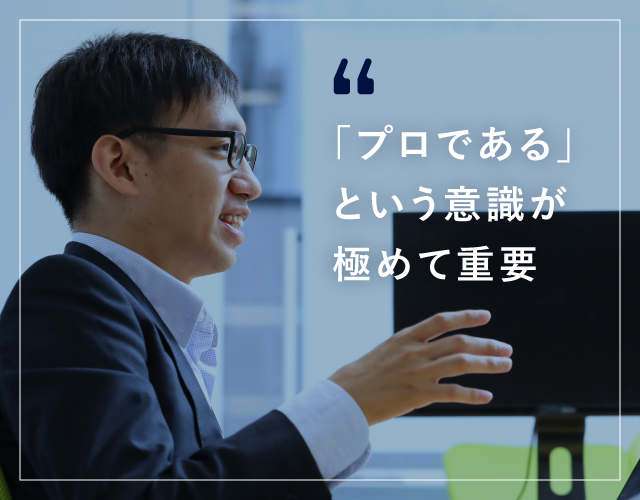
では、会社選びの際に、どのように「プロがいるかどうか」を確かめればいいか。
一つの方法として、面接の最後に聞かれる「逆質問」を活用するのがいいと思います。例えば、「仕事でこだわっていることは何ですか」と聞いてみる、とか。
結局、「プロかどうか」は「こだわっているか」で分かります。
思考停止になるのではなく、自分なりに試行錯誤をしていることが大切です。プロ意識を持って仕事に取り組んでいる人は、きっと独自のこだわりを語ってくれると思います。
プロがいる環境で働くと、自分自身の仕事への取り組み方も変わります。会社の業績なども大切ですが、自分が憧れるような先輩がいるかどうかをチェックするのも一つのポイントです。
アウトプットは最強のインプット
とはいえ、インターンできる企業の数も限られていますし、逆質問をする機会もそう多くはないと思います。だからこそ、実際に社員と会わなくても、SNSで情報を入手する方法も知っておきたいところです。
特にスタートアップの場合、社長のインタビュー記事や自らSNSで発信している場合もありますから、社長の投稿内容には目を通すと参考になります。社長の価値観や考え方を踏まえ、自分に合うかどうかを判断できます。
ただ、大企業の場合は、規則で社員がSNSをやっていない場合もあると思います。その際はYouTubeの会社紹介動画などを確認してみるのも一つです。動画であっても、社員の人柄が何となく伝わってくると思います。
さらに、最近はSNS経由の採用も増えてきています。

この前もTwitterで、新卒学生の募集はあまり多くないPE(プライベート・エクイティ)ファンドで働きたい学生を募集するツイートを見かけました。興味があれば、直接連絡を取って相談してみることも可能です。
そして、こうした有益な情報をつかむのにはコツがあります。
それは、「自ら情報発信すること」です。
そもそも自分1人でできるインプットには限りがあります。
だからこそ、アウトプットとインプットのサイクルを回すことが必要なんです。
アウトプットすることで、思考の整理にもなりますし、「自分はこういう人間です」というポジションも取れる。先人達からコメントを頂くことで「あ、そういう世界があるんだ」と教えてもらうことも多いです。
結局、アウトプットが一番のインプットになります。
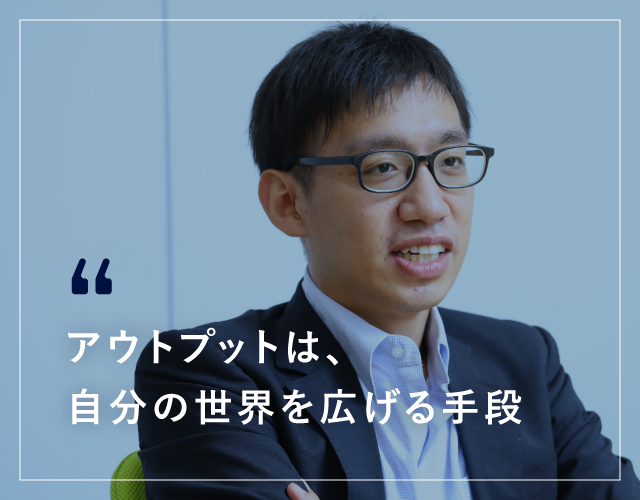
私の場合、常に「事業だけでなく投資もやりたい」と周りに話したり、ツイートしたりするようにしていました。その結果、新規事業創出に力を入れているXTechのメンバーの方を紹介してもらい、最終的に入社するに至りました。
自立的に情報発信や夢を話していれば、必ずチャンスは来ます。そして、「こんな仕事をしたい」というものが明確なイメージがあるなら、SNSで発信してみるといいと思います。
就活生の皆さんはぜひ、自立的に動いてチャンスをつかんで欲しいです。
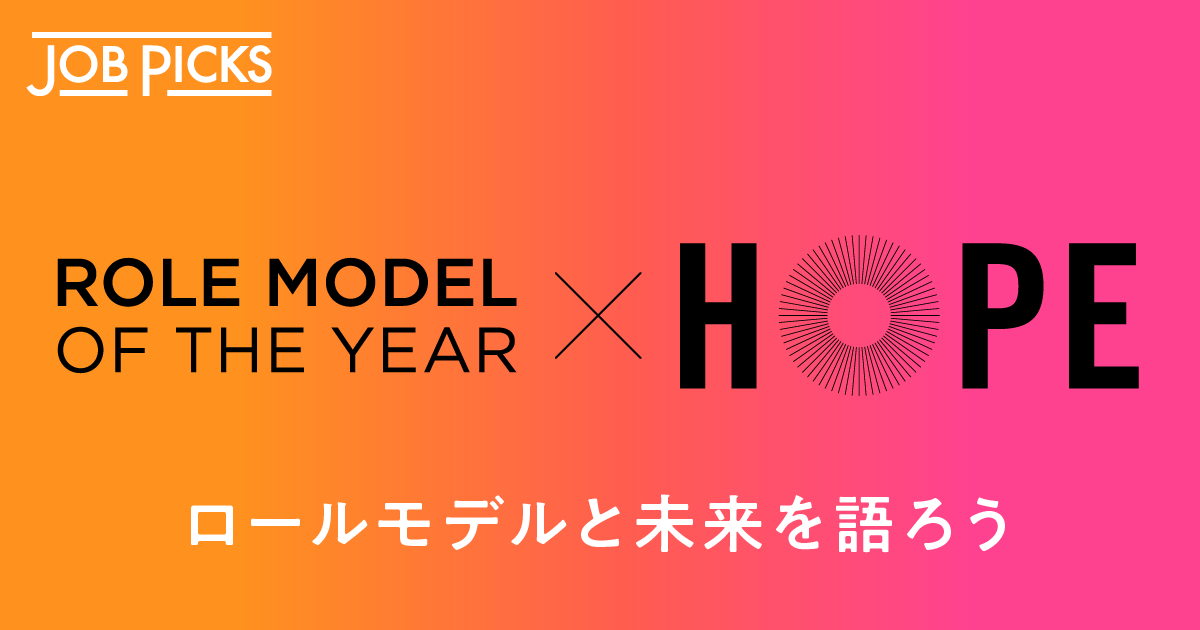
【10月開催】学生・20代が「最高のロールモデル」と出会う1日
取材・文:安保 亮、編集:高橋智香、デザイン:松嶋こよみ、撮影:遠藤素子