職業力の基礎を固めよう
大学生のみなさん、こんにちは。
法政大学でキャリア論を教えている田中研之輔です。ゼミ生からは“タナケン”と呼ばれているから、みなさんも“タナケン”で覚えてね。
大学での勉強は、順調かな? 新型コロナウイルスの影響で、今年一年、大変な思いをしたよね。
1年生のみんなは、大学受験に合格し、晴れて大学生になったのに、キャンパスに一度も通えなかったという人もいるはず。
学部の同級生にも会えず、課題に追われる日々だったよね。上級生のみんなも、対面での講義がオンライン講義に変わり、何かとストレスを感じた一年だったよね。
これまでであれば、教室間の移動や、最寄り駅までの行き帰りに、授業の相談や将来の選択肢について、気軽に会話して気づきを得ることができました。
しかし現状、それができない。
オンラインで講義に慣れてきたといっても、一人で孤独に画面越しの講義を受講していると、少なからず将来についての不安を抱えてしまうでしょう。
大学を卒業した後に、どうやって働いていくのか。どんな仕事に就き、どんな人生を歩んでいくのか。働き方だけでなく、生き方に悩む学生が少なくないと思います。
そこで、みんなの力に少しでもなれたらと思い、この連載をはじめることにしました。
テーマはずばり、「ジョブトレ」!
キャリア論の観点から、これからの働き方や生き方について、みんなと一緒に考えていきます。
そして、考えるだけではなくて、トレーニングを重ねていきます。就活力を身につけ、これからの時代を生き抜く職業力の基礎を、タナケンと一緒に固めていこう。
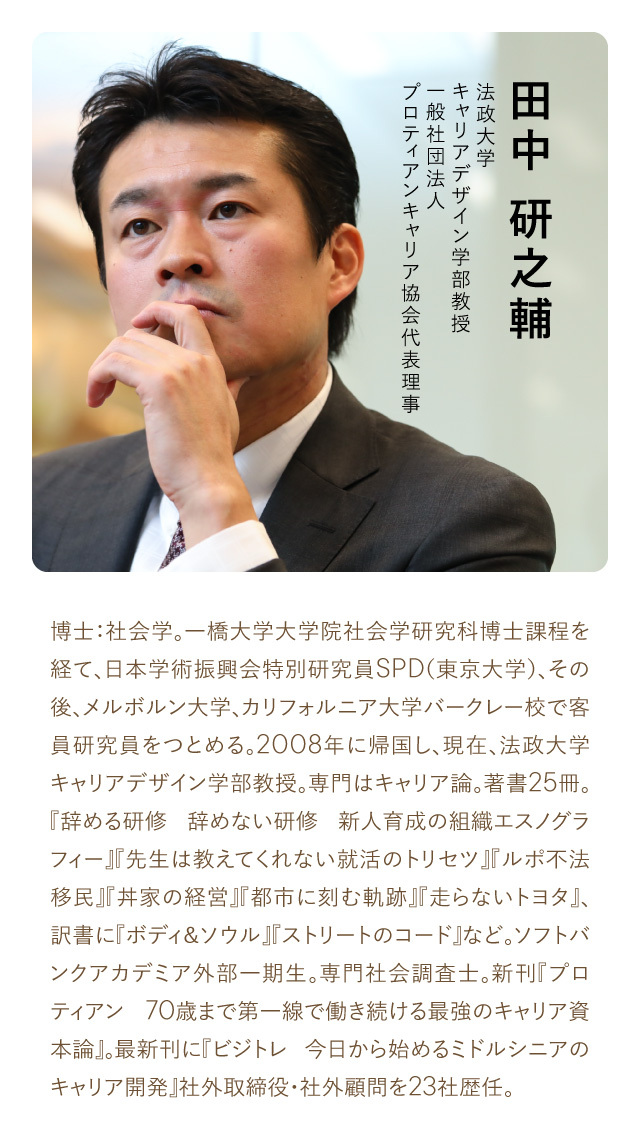
就活は“ハイブリッド型”へ
では早速、連載1回目、本題に入ります。
先日、ゼミ生から「これからの就活はどうなりますか?オンライン就活になるんですか?どんな準備をしたらいいですか?」と質問を受けました。
結論から言うと、これからの就活は“ハイブリッド型”になります。
1次選考やグループワークはオンラインで実施し、役員面接や最終面接は対面で行うという選考スタイルが増えていくと思います。
もちろん、中には対面のみで選考を進める企業もあります。そのような企業の選択についても、関心を持つようにしておこう。
というのも、「テレワークを推進している」と宣言している企業が、対面のみで選考を進めるということは考えられないからです。選考スタイルには、これからの働き方に対する企業の考え方が色濃く反映されています。
これらの前提を踏まえた上で、学生のみんなには、「オンライン就活への対応は、大きな心配はない」と伝えたいです。
もちろん、これまでと同様に、準備や練習は大切です。自分の声が相手にどう聞こえているのか、画面越しにどう見えているのか、音量やライティングは工夫しましょう。
とはいえオンラインでの授業に真剣に臨んでいれば、それらは大した問題ではないはず。
みんなが「これからの就活」で考えるべきことは、「対面就活」なのか、「オンライン就活」なのかというテクノロジカルシフト(技術的な変化)ではなく、これからの働き方に関するエッセンシャルシフト(本質的な変化)です。

エッセンシャルシフトを見落とすな
これからは、「就社活動」ではなく、「就職活動」が重要視されるようになります。
これまでの就活であれば、就職した会社で一生働く終身雇用が一般的でした。もちろん、それ自体が悪いということではないですし、それだけの会社にめぐりあえるのは幸せなことです。
とはいえ、就職活動という言葉はあれど、実質的には「就社活動」をしている学生が少なくありません。
しかし、時代は変わりました。これからは、自ら主体的にキャリアを形成していく時代です。
大手企業が副業や兼業を解禁しましたが、それらは「キャリアとは個人が創るものであり、組織が管理するものではない」というメッセージでもあります。
自分自身でキャリアを創っていかなければならない時代が到来した今、会社名で就職先を選び、会社にキャリアを委ねるのは、大変盲目的で危険な選択です。
これから就職活動をするみなさん、「人気企業ランキング」を参考に、「なんとなく」で選考エントリーをしようとしていませんか?
このような就職活動を分かりやすく例えるなら、大学名で受験して、その大学の複数学部を受験して、受かった学部に入学するようなものです。
こうして受験して合格した先の大学生活は、どうなるでしょうか?
学びたい学問と違っていたなら、長く感じた4年間になるはずです。でも、「働く」は40年なんです。
「なんとなく」で選択したキャリアの先にあるのは……言わなくても、想像がつきますよね。
だから、人気企業ランキングからなんとなく企業を選ぶのは避けましょう。
みなさんがまずやるべきことは、「職=JOB」を見つめることです。どこの「会社」に勤めたいのかではなく、どんな「職=JOB」をしたいのかを軸にして就活を進めていくのです。
「ハコ」ではなく、「ナカミ」が大切なのです。
では、そんな就活をどのようにして実現していくのか。一つの方法として、「働く先輩=人」から学ぶというスタイルを提案します。
.jpg)
リアルな声こそが、道しるべ
キャリア論の中に、「キャリアモデルケーススタディー」という学び方があります。企業で働いている先輩のリアルな働き方から「職=JOB」について学んでいくものです。
キャリア論での学びは、よりリアルな声に迫るところに強みがあります。すでにみなさんが気づいているように、キャリア形成に正解はありません。
自らの選択を、自ら正解にしていくのがキャリアなのです。
そのためにも、まずは、「職=JOB」を広く捉えていきましょう。
みんながこの記事を読んでいるJobPicksには、先輩社会人のリアルな声が掲載されています。
まずは、空いている時間に興味を引かれた「職=JOB」をクリックして、先輩の声を読んでみてください。
すると、本人のリアルな言葉として「職=JOB」が投稿されていることが分かると思います。
一つの「職=JOB」を読み進めれば、共通点や違いを発見できる。ここで得られる学びこそが、みなさんの就活力になるのです。
たとえば、1日1つ「職=JOB」を見ていくようにしよう。そうするとみんなの中で、「職=JOB」に対する具体的なイメージが湧いてくるようになります。
.jpg)
人気ランキングでなんとなく企業を選ぶよりも、より実践的な学びが得られるはずです。
私も「就活に向けて、どんな本を読んだらいいですか?」という質問を何度も受けますが、人によってさまざまであり、正解はありません。
だからこそ、自分の興味がある「職=JOB」を見つけ、JobPicksで先輩たちが紹介している入門書に目を通すのもいいでしょう。
キャリア論は覚えることより、実際に使いこなすことを大切にしている考え方です。私のゼミ生には日頃から伝えているのですが、情報をインプットして終わりではなく、アウトプットとセットで考えるようにしよう。
たとえば、フューチャーワーク指数で1位にランクインしている「CMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)について調べたら、一言感想をまとめて、ツイッターで発信してみる。
ハッシュタグ #JobPicks をつけてくれたら、タナケンが見にいきます。みんなで「職=JOB」についての学びを共有しよう。

今は不安でいっぱいかもしれないけど、「就活」であなたの人生は、決まりません。だから、安心してください。就活は、これからのあなたの人生のごくごくわずかな期間のことに過ぎないのです。
言ってみれば、就活は「点」にすぎない。とはいえ、手を抜くわけにはいかない。この難しい問題に、一緒になって取り組んでいこう。
第1回の締めくくりに、これから就活をはじめるみんなに知ってほしいことを伝えます。
キャリアを組織に預けない。だからこそ、「就社」ではなく、「就職」。
そう、会社ではなく、職業を選ぼう。きわめて、本質的で大切なこと。でも、これまで就活をしてきた先輩たちは、なかなかできなかったこと。
JobPicksのロールモデルとなっている社会人の先輩たちのリアルな声にヒントを得ながら、これからのあなたのキャリアを、あなたが創り出す出発点にしよう!
では、また次回。

第2回:【助言】「周囲の価値観」が気になる就活生の共通点

合わせて読む:【図解講義】あなたの“不満”こそ、次なるキャリアの道しるべだ(NewsPicks)
編集:オバラ ミツフミ、佐藤留美、デザイン:九喜洋介、写真:遠藤素子