周囲の価値観に惑わされるのは悪い?
みなさんは、周囲の価値観に惑わされることを、どう思いますか?
結論から言うと、「気になってしまうこと」自体は、悪いことではありません。
「周囲の価値観」は、誰でも気になりますよ。それは、社会人として働きだしてからも変わりません。
ただ、その前提を理解した上で、大事なことがあります。大学生から社会人になっていく過程でのキャリアトランジッション(=キャリアの移行)としての就職活動において、物事の本質を理解しようとする思考を日頃から鍛えておくことです。
「周囲の価値観」については、次の二点を考えておく必要があります。
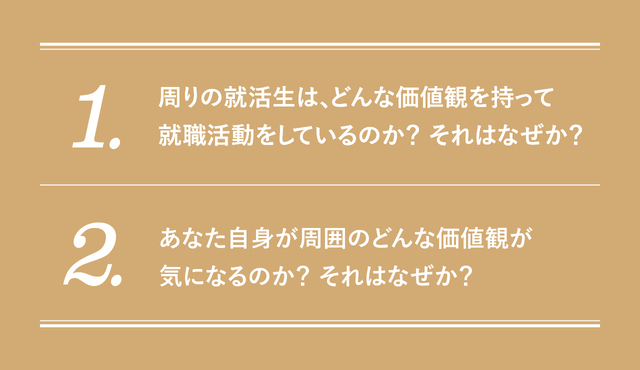
前提として、価値観とは、暫定的につくられたものにすぎません。例えば、10年前の就活生と、みなさんでは入社を希望する就職先は異なります。なぜでしょうか?
社会の変化、産業の変化、ビジネスモデルの変化、情報の変化。私たちの価値観は、さまざまな変化を内包する日常の中から醸成されるからです。
「周囲の価値観」は、つくられたものにすぎない、ということを心にとめておくことは大きな意味があります。それによって、少し気が楽になるはずです。
その上で、あなた自身がどんな価値観が気になるのか? この点も一度、この機会に考えておくといいでしょう。
私が就活生にすすめている方法は、「気づきの就活メモ」です。
就活をはじめると、自己分析、企業分析、市場分析、社会分析などを行っていきますね。
その際に、あなた自身の心がどう揺れたのか、何を感じたのかをメモしておくようにするのです。
そのメモを見直すことで、あなた自身の価値観を客観的に理解することができます。
.jpg)
周囲の価値観で、キャリア選択をしない
周囲の価値観を客観的に把握することの重要さは、理解できたと思います。
その上で、大切なことは、「流されてはいけない」「あなた自身の意思でキャリア選択をする」ということです。
大学を卒業して社会に出るのは、誰ですか? あなたの友だちですか? サークルやゼミの仲間ですか? あなたの親ですか? 違いますよね。
大学を卒業して働いていくのは、あなたです。つまり、あなたの人生です。大学は4年ですが、働くのは40年です。
就職活動がうまくいって、複数の企業から内定をもらったものの、その後数週間悩んでいる就活生が毎年います。
社会人になるということは、意思決定も含めて、あなたが自律的にキャリアを形成していくことなのです。
友だちや両親に相談することは悪いことではありませんが、あなたの価値観に従って意思決定しましょう。それが、自律的にキャリアを形成していく第一歩になります。
.jpg)
自分の価値観で意思決定をするには?
そのためにも、まずは判断軸を自分の中につくっておきましょう。
具体的なアクションとして、JobPicksに掲載されている「先輩たちのリアルな声」をのぞいてみてください。
就活で苦労する学生に共通していることは、就活のことを学生同士で話しているケースです。
社会人になったことのない仲間同士がどれだけ親身になっても、具体的なアクションにはつながりません。
前回も触れましたが、JobPicksは「会社」ではなく「JOB=職」のリアルを学べる点において、非常に有意義です。就活時に、一番知りたいことが書かれています。
どんな想いで、どのように仕事をしているのか——。先輩たちの経験を一つ一つ吸収しながら、あなたが大切にしていきたい価値観を育てていくのです。
働き方や生き方への、あなたなりの向きあい方をレベルアップさせていくのです。
自分の価値観で意思決定した先にある未来
「周囲の価値観」に流された意思決定では、仕事での苦しい場面を乗り越えることができません。
仕事がうまくいかない理由を、他責にしてしまうからです。他責にしているうちは、成長もありません。
キャリア自律という考え方があります。キャリア自律とは、自らのキャリアにオーナーシップを持ち、仕事の一つ一つを自分事として捉えて働いていくことを意味します。
組織にあなたのキャリアを預け、働かされるのではなく、あなた自身が一つ一つキャリア形成の意思決定をしていきながら、自ら主体的に働いていくのです。
その最初の一歩が、就職活動だと捉えてみてください。それでもまだ、「周囲の価値観」に流されますか?
質問は随時、受け付けています。それではまた次回にお会いしましょう。

合わせて読む:【図解講義】あなたの“不満”こそ、次なるキャリアの道しるべだ(NewsPicks)
編集:オバラ ミツフミ、デザイン:堤香菜、写真:遠藤素子