面接中の「コース変更」もある
—— まずは、自己紹介と、現在の仕事について教えてください。
田中:新卒1年目の田中 涼(たなか りょう)です。大学では工学部に通っていましたが、現在はソニー株式会社の人事総務部門で働いています。よろしくお願いします。
井上:新卒2年目の井上 南(いのうえ みなみ)です。ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社のイメージング&センシングデバイス開発部門で半導体エンジニアとして働いています。大学院では原子核物理学を専攻していました。
廣瀬:新卒1年目の廣瀬文香(ひろせ あやか)です。就活ではセールス&マーケティングコースに応募しましたが、今はソニーグループ株式会社の秘書部に所属しています。今日はよろしくお願いします。
—— 田中さんは理系学生だったわけですが、応募の時点で人事を希望したのはなぜですか?

田中:大学時代に学生団体に所属していた経験から、人材や組織を活性化させる仕事に強い興味を持つようになったからです。
人事の仕事がやりたくて、コース別で採用をしているソニーに応募しました。
職種別ではない採用だと、理系学生が人事系の部門に配属されることはめったにないんじゃないかと思いまして。
—— 工学部卒だと、メーカーやソフトウェア開発の仕事に就く人が多い印象です。
田中:私自身、今でもエンジニアリングやソフトウェアの仕事には強い興味があります。
けれどまずは、広い視野で経営を見てみたいと考えました。
—— 井上さんは理系の大学院からソニーに就職しています。そのまま博士の道を進もうとは思わなかったのですか?

井上:修士から博士に進むかどうかは、かなり迷いました。
でもある日ふと、「自分はモノを作ったり、データを解析したりすることが好きなだけで、対象は原子核でなくてもいいんじゃないか」と気づいたんですね。
そこから企業への就職に舵を切りました。
—— 原子物理学の研究から製品開発の世界に移って、戸惑うことはありませんでしたか?
井上:ソニーでは応募する段階で、担当する製品を絞ることもできます。そのため、同じ職種で働いている先輩の姿を入社前に想像しやすく、違和感を覚えることはありませんでした。
また、研究は10年後、20年後に結果が出る世界です。メーカーではそれよりずっと短いスパンで、自分の作ったモノが世の中に広がるという点に魅力を強く感じています。
—— 一方で、廣瀬さんはお2人と違い応募時と現職が異なる職種です。なぜそうなったのですか?

廣瀬:私はコース別採用に興味があったというより、ソニーのPurpose(パーパス)自体に惹かれて応募しました。
就職活動中に「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」というPurposeを知り、社会人になったら、感動を届けることを仕事にしたいと考えていたこともあり、絶対にソニーに入社するんだと心に決めていました。
それで、コース別採用への応募時は、顧客に感動を与えるソニーの製品に直接かかわることができる仕事は何かという観点から職種を探して、セールス&マーケティングを選びました。
ただ、面接を数回重ねるうちに、「秘書部はどうですか」と声をかけていただいて。
秘書部という部署自体をよく知らなかったので驚いたのですが、適性を見いだしてもらえたと感じ、そこから秘書部の仕事内容を詳しくヒアリングさせてもらいました。
—— ソニーグループのコース別採用では、廣瀬さんのように応募職種の変更を提案されることもあるのですね。
廣瀬:「ポテンシャル確認希望」制度というものがあり、私のように確認希望を出した学生には、会社から職種を提案してもらうケースもあるようです。

—— 応募したコースと違う職種を勧められたことに、不満はなかったのでしょうか?
廣瀬:はい、応募動機が「ソニーに魅力を感じたから」でしたので。
もちろん、セールス職やマーケターとしてソニー製品に携わること自体は魅力的だと感じていました。
しかし秘書部の先輩方と話していくうちに、役員をサポートするからこそ見えてくる、ソニー全体の軸があるとわかったんです。
私も自分の中に経営の目線を取り入れてみたいと思ったので、秘書としての入社を決意しました。
入社前の不安解消法
——コース別採用で入社した社員の約1割が、入社前は不安を持っていたという調査結果が出ていましたが、皆さんは何か不安を持っていましたか?
井上:ソニーのコース別採用は98コース(※2023年卒採用時)にも分かれているので、希望して入ったのに自分の職種理解が浅かったらどうしようという怖さはあった気がします。
でも、ソニーはコース紹介動画が充実していて、応募する前からある程度は働き方を理解しておくことができました。

廣瀬:コース紹介動画、私も見てから応募しました。
職種についての理解が浅くても、働いている姿が具体的にイメージできますよね。
井上:加えて私の場合は、希望する職種の現場で活躍している課長が直接採用面接をしてくれたので、それも不安を払拭する一つになりました。
面接の段階で、「画素設計コースに応募してくれたけど、画素設計で実際に何をやっているか、どのくらい知っている?」と聞いてくれて。
拙い知識で答えたのですが、自分の今まで学んできたことまで見てくれているという実感が湧いて、とても嬉しかったことを覚えています。
入社後に担当するであろう仕事内容も具体的に教えてもらえたので、働くイメージが持てたんです。
—— コース別採用に対する社内調査では、「入社後のキャリアが制限されそう」という声もあったそうですが、この点は皆さんどうでしたか?
田中:僕はまさにこの点が一番の不安でしたね。
人事として働きたいと応募したとはいえ、退職時までずっと続ける想像はできなくて。人事を経験した後にキャリアをどう作ればいいのか、わかっていなかったからです。
希望の職種での採用だとしても、1つの製品の1つの部分だけを退職まで極める……みたいな働き方も違うと思っていたので。
けれどソニーでは、現在の仕事を継続したままで公募の仕事やプロジェクトに参画できる「キャリアプラス」という制度や、社内人材を公募する「社内募集」制度など、社内で異動できる体制が充実しています。

もし、違う仕事に挑戦したいと思っても、異動できるというのを知って、心に余裕を持てました。
井上:私の周りにも、キャリアプラス制度や社内募集制度を利用している社員が多くいます。かなり制度として社内に浸透している印象を受けますね。
—— そういう制度はあっても、形骸化している企業は少なくありません。
田中:なので、自分から働きかけて「確認」するプロセスは必要だと思います。
私は、入社前に、実際に人事から経営管理に異動した先輩社員の話を聞かせてもらったりもしました。
その結果、人事から商品企画、エンジニア職に異動した人もたくさんいることを知りました。
最初のスタートが人事ではキャリアが制限されるかもしれないという考えが杞憂だとわかり、ちょっと安心しました。
—— 廣瀬さんは応募時点で希望した職種と違う秘書部に入ったわけですが、入社前に不安はありましたか?
廣瀬:自分の適性が本当にセールス&マーケティングなのか、心の中では少し怖かったです。だから、先ほどお話ししたようにポテンシャル確認希望にチェックをつけて応募していました。

今の仕事には満足しているので、もしポテンシャル確認希望を出していなかったら、不安を抱えたまま働いていたかもしれないと思っています。
田中:私は人事希望だったのでポテンシャル確認希望は出していませんが、特定の職種にとらわれなくて、良いですよね。
廣瀬:実際に秘書部に向いていると太鼓判を押されて、自分に自信を持つこともできました。そのため、入社する時点で不安は完全に消えていたんです。
入社後ギャップはこう乗り越えろ
—— では、実際に入社してから感じたギャップはありますか?
田中:人事の仕事の認識自体に、入社前からの大きなズレはないですね。でも能力的に自分のできることと、仕事でしたいことのギャップは強く感じています。
以前、採用イベントの企画運営を任された時に、全体像をわかっておらず大きなミスをしてしまって。結果的に先輩にフォローしてもらったことがあるんですね。
その時の反省から、取り組む業務の「背景理解」に重きを置くようになりました。
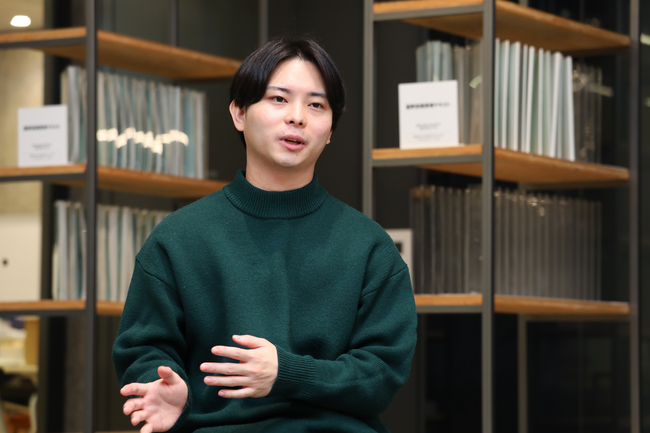
—— 具体的にどんな取り組みを?
田中:まず上司や先輩に積極的に1on1ミーティングを頼んで、わからない業務内容について聞くようにしました。
こういうところで詰まっていて……と相談すると、昔の資料を見つけてくれたりするんです。自分のこれからやることと、完全に同じ事例はなかなかありませんが、類似していることが過去にあったりします。
それでもわからないところは、社内ポータルでひたすら検索して、たくさん記事を読んで探しました。
加えて、ソニーに入った同期たちと、情報共有することも大事にしています。つい先日は、ソニーグループの経営陣が四半期ごとに社員にメッセージを発信しているオンラインミーティングを教えてもらって。

知らない情報だったので助かりました。
全体の情報をキャッチアップしておけば、自分の担当する業務範囲でも軸から外れた行動をしなくなると思っています。
—— 井上さんも入社後に何か取り組んだことなどはありますか?
井上:疑問をメモに取り、1個ずつ潰して理解することを心掛けています。
当たり前かもしれませんが、本や教科書を読んで新しい技術を学んだり、同期との勉強会で知識を深めたり。

でもそれと同じくらい、田中さんのように、いろいろな会議に顔を出して情報収集することも大事だと思っています。
今でも、隣の課の技術相談ミーティングや、技術講演会などには時間が空いている限り自発的に参加していて。いつもの部署ではインプットできない範囲は、学んでいても面白いです。

コース別採用の「向き・不向き」
——近年はソニー以外にもジョブ型採用を実施する企業が増えていますが、どんな人にお勧めしますか? 逆に「こういう人は向いていない」という点もあれば教えてください。
廣瀬:こういう大人になりたい、という明確な目標がある人にコース別採用は向いているかと思います。
私は学生時代にずっと、誰かに感動を届ける仕事がしたいと思っていました。でも一括採用だと、そのビジョンを実現することができる、自分が納得した部署に配属されるとは限りません。
コース別採用では、具体的な仕事内容を職種の先輩たちに教えてもらった上で配属されますし、私のように職種へのこだわりが弱い人も、適性を見てもらうことができます。
最終的にソニーに就職しないとしても、職種を学ぶためにエントリーしてみるというのもあっていいのではないかと思っています。
井上:私は学生時代から技術畑で知識を積んできたので、やはり技術に特化した理系職種に就きたい人に向いていると思っています。
コース別採用で具体的な仕事内容が前もってわかる分、自分の持つスキルと相性の良い職種を選ぶことができますから。
コース別採用だと、募集要項も「CADを触れる人」や「C++が使える人」などと求められるスキルが明確です。大学で学んだことをダイレクトに生かしたいと思っている方には、とてもお勧めできます。
田中:自分で職種を選択できる分、主体的にキャリアを作っていく姿勢が求められていると感じます。
特にソニーは、希望の部署や仕事には手を挙げて、自分でつかんでいく社風です。入社してから、振られた仕事をこなすだけでは少しもったいない。
自分軸で働き方を模索したい人は、コース別採用の企業に応募してみることをお勧めします。
【意外】ジョブ型の落とし穴?5つの誤解を解く取材・編集:伊藤健吾、文:藤原環生、デザイン:岩城 ユリエ、撮影:遠藤素子