仕事にまつわる癖や習慣は?
JobPicksは「みんなでつくる仕事図鑑」をコンセプトに、さまざまな職業のロールモデルに経験談をご投稿いただき、紹介してきました。
その投稿内容や過去のインタビュー記事から、テーマ別にコメントをまとめる連載「JobPicks Voice」では今回、忙しい年末の息抜きとして「職業別あるある」を集める企画を実施します。
やっている職業の特徴によって、生活や日常業務でついつい出てしまう「癖」や「習慣」。
例えば雑誌や書籍編集者なら、出版前に何度も校正する習慣があるので、日常生活で文章を読んでいても、誤字・脱字があるとすぐに目が行きツッコミを入れてしまいます。
.jpg)
本稿ではいくつかの職業別に、ならではの癖・習慣を紹介していきます。ぜひ皆さんの「職業あるある」も教えてください。
JobPicks Voice
「みんなでつくる仕事図鑑」JobPicksは、さまざまな職業のロールモデルが投稿してくれたリアルな経験談を多数掲載している。本連載では、その投稿内容を参考に、仕事やキャリアの悩みを解消するヒントを探っていく。今回は、人気職種で活躍する先輩の未経験者へのオススメ本を紹介する。
資料づくりが多い職業あるある
最初に紹介するのは、営業やコンサル、マーケターなど、社内外の人に向けた資料づくりをする機会の多い職業あるあるです。
■資料の保存は「決まった命名規則」で
IT業界でプレゼンの神として知られる円窓代表の澤円さんは、下の動画の中でプレゼンの極意を12個上げていますが、その一つが「データ命名規則」。
【実践仕事術】プレゼンの神、澤円の資料作りを全公開プレゼン用に作った資料は、必ず「日付_プレゼン内容」というファイル名にして保存しておくそうです。
理由はシンプルで、「カレンダーを見れば、すぐに資料を探し出せるから」(澤さん)。この手法を採用している人はけっこう多いのではないでしょうか。
■Excelを見たら「クレンジング」したくなる
ExcelやGoogleスプレッドシートに入力したデータを加工する機会の多い人のあるあるとして、入力データをできるだけ「あとで加工しやすい形」にしておきたいという声をよく聞きます。
元・経営コンサルで、現在はAIベンチャーのWACULでCFO(最高財務責任者)を務める竹本祐也さんも、下の記事でこう話しています。
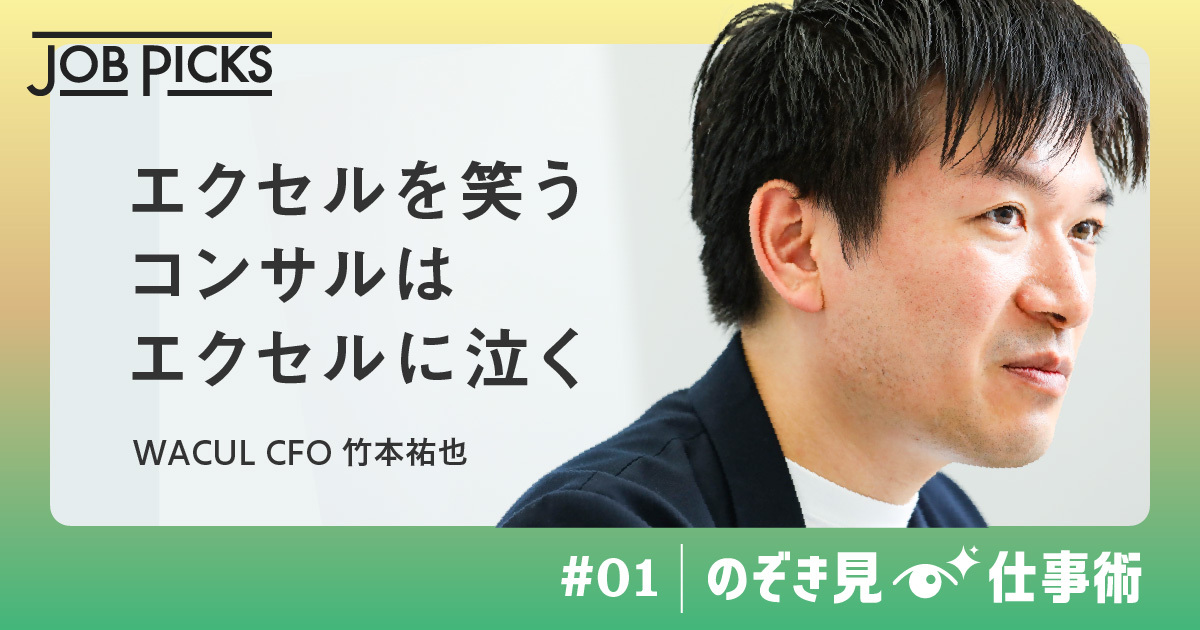
【超実践】コンサルが知っておくべきエクセル関数5選
データ分析の業務には、大別すると3つのステップがあります。
最初に行うのが、バラバラなデータを統一する作業です。この作業をコンサルは「クレンジング」と呼びます。
基本的にクライアントは大企業であり、さまざまな事業部と人がかかわります。そんな状況でデータを集めると、表記のルールや計算式が統一されていないことがほとんどです。
コスト削減で経費精算のデータを集める場合も、部署によって書き方がバラバラだったりする。まずはそれをクレンジングするために、エクセルを使います。
この記事では、データクレンジングを行う際によく使うという「TEXT・VALUE関数」や「SUBSTITUTE関数」について解説しているので、日頃データの表記揺れに困っているという方はぜひ使ってみてください。
コンサル、商社パーソンあるある
竹本さんのコンサル時代の話に続けて、経営コンサルの職業あるあるをもう一つ紹介しましょう。
■相手にも自分にも「なぜ?」を連呼する
これは、複数のコンサルがよく話す仕事習慣です。
種々の問題が起きている原因を探る機会が多いためか、他人に対してだけでなく、自分自身にも「なぜ?」と問うのが日常化するそうです。
例えばEYストラテジー・アンド・コンサルティングのIshii Yukiさんは、下の投稿で「自問自答する癖」がついたと明かしています。
知ってるつもり 無知の科学
コンサルティングにおいては、論理的思考力や論理的説明力が強く求められます。論理性を担保するためには、「自分の主張・説明を客観的にみる力」が重要です。その力を育み、より深く考えるためのきっかけとして、この書籍をお勧めします。 詳細な内容についてはぜひ読んでいただきたいのですが、自分がいかに「知っているつもり」「説明できているつもり」でいるのかに気づかされる本です。 この本を読んでから、打ち合わせなどでお客様とお話しする際に、自問自答をする癖がつきました。 「これは当然」と思いこんでいないか、自分は本当に理解した上で説明をいるのか?その「当然」は、お客様にとっても「当然」な内容なのか? 思考力や説明力を強化したい方はぜひ一度読んでみてください。
総合商社で事業を生み出す商社パーソンも、似たような癖がつくと話すのは、丸紅の細江康将さんです。
下の投稿を読むと、ビジネスでは必ず「相手のWant・Needがあり、それを満たすために実施しているはずであり、それを理解せずにやる仕事は何も生まない」という理由があるそう。
世の中に理由のないものは存在しない
「因果」という言葉の通り、原因と結果は関係で結びついており原因のない
物事の核心を見いだすためにも、「なぜ」を繰り返す習慣が染み付いていくのでしょう。
クリエイターあるある
この「なぜ思考」は、デザイナーや動画クリエイターのようなアウトプットの多い職業の人も形を変えてやってしまうそうです。
ここでは、2人のクリエイターの“職業病”を紹介しましょう。
■中吊り広告を見ると「キャッチコピー」を考えてしまう
元・任天堂のデザイナーで、昨年『勝てるデザイン』(幻冬社)を出版したNASU代表の前田高志さんは、下の記事で「電車に乗るとついやってしまう癖」を明かしています。
【実践】人の興味を引く「デザイン力」を磨く習慣僕は、自分の感情を動かすものを見た時に「何でだろう」と自問自答するように意識しています。
電車に乗っていて目が留まった中吊り広告は、どんな意図で作っているんだろうと考える。企画の意図や、誰に向けたキャッチコピーなのか、会議では何を話してこういうデザインにしたのか、と想像を巡らせるのです。
この習慣を続けることで、クリエイターとしての「自分の好き嫌い」も見えてくるとのこと。よく言う美意識のようなものを磨く訓練になると言います。
■今いる場所で動画を作るなら......
同じような習慣として、動画クリエイターの庫本太樹さんは、飲食店などにいても「このVTRを作るなら何分くらいの尺になるか」と考えてしまうそうです。
「60分最後まで、見せきるための工夫」を常に考えよ
テレビ局時代に、プロデューサーから最初に言われた教えです。例えば「世界の様々な乗り物を紹介する番組を作ろう」と思った時に、どうすれば60分のVTRを作れるでしょうか?「それは何のために作られたの?」というヘンテコな乗り物を紹介するとして、それで5分作れる。後は「みんなが毎日乗るモノ」を題材にすれば興味があるだろうから、世界の地下鉄事情を取り上げよう、それで7分。一番早い乗り物、一番高額な乗り物とか、一番○○な乗り物を取り扱えばそれでも5分は持ちそう。ロケに行けばもっと長いVTRが作れるだろう、そしたら誰をどこに行かせようか。このままだと、「軽い情報」ばかりだから感動系も入れて、重みを持たせたいな。「番組冒頭15秒」のインパクトが大事だから、未来の乗り物のCGで引き付けようか。何かに挑戦するくだりも入れて、その結果を最後まで隠して60分引っ張ろうか。時事性も入れたいから、どこかでリニアの今を追うか。このままだと企画全体が散漫だから、どうまとめていこうか…。などなど一つの企画でも様々な工夫を考えないと、そもそも見てもらえないし、また最後まで見てもらえない。動画はよく、「文字情報だと1分ですむものを引き伸ばしているので、時間の無駄」と言われます。それはその通りだとも思いますが、逆に「1分ですむ文字情報で、何分楽しく見てもらえるか?」。この工夫をし続けることが「動画(番組)制作の醍醐味」だと思います。上司のこの言葉を聞いてから、「今いる飲食店で、何分VTRを作れるか?」など「思考のクセ」がつき、自分は本当にまだまだ未熟ですが、多少の成長のキッカケになったと思います。
常にアウトプットへの工夫=切り口を考える仕事だからこそ、つい出てしまう癖なのでしょう。
TBSの有名なディレクターで、ドラマ作品『グランメゾン東京』や『MIU404』など数々のヒット作を世に送りだしてきた塚原あゆ子さんも、他のドラマ作品を見ると次のような“職業病”が出てしまうと話しています。
.jpg)
TBS『MIU404』担当Dが語る、ディレクターという仕事のリアル
私自身、AD時代に見た作品にインスパイアを受けることは多いですし、今でも休みの日はたいてい映画やドラマを見て過ごしています。
そして、見ている最中に、カット割りやBGM、CGなど気になったことはメモし、後からとことん調べる。気になった俳優さんがいれば、その人が出てくる作品をさらにチェックする、とかですね。
ただ、好きなことを仕事にしているので、「いやいや勉強している」感覚はなく、職業病に近いです(笑)。
仕事を離れても仕事につながることを考えてしまうというのは、どの職業でも成長していく人の共通項かもしれません。
企画系の職業あるある
最後は、商品企画や新規事業企画など、常に新しいアイデアが求められる職業のロールモデルが明かす習慣です。
■何事も「連想ゲーム」をしてしまう
これは、判決を取ってくる犬用おもちゃ「勝訴マスコット」(下のTweet)や「セクシー大根抱き枕」など、ユニークな企画でSNS上での話題をさらっている「企画デザイン2時」の田中桃子さんが話すあるあるです。

下の記事では、アイデアを着想するための思考習慣として、次のようなことをよくやると話しています。
.png)
私は「関係ないもの同士を、連想ゲームのように結びつける」ことが多いですね。
実際、アイデアを思いつくのはPinterestやTwitter、Instagramの写真を無作為に見ているときが多くて。
一つ一つは全然関係ない写真なんですよ、たとえば、ティッシュと水しぶきとか(笑)。
でも、「これとこれをくっつけたら面白いかもな」と1人であれこれ考えているうちに、アイデアを着想することが多いです。
一見、全く関係ない事柄を見ながら、目の前の問題を解決していくというのは、他の企画系職種でもやっている人は多いでしょう。
例えば、D2Cのシューズブランドとして有名なAllbirdsでマーケティング本部長を務める蓑輪光浩さんは、過去の印象的な事柄をすぐにメモに残す習慣と合わせて、次のように語っています。
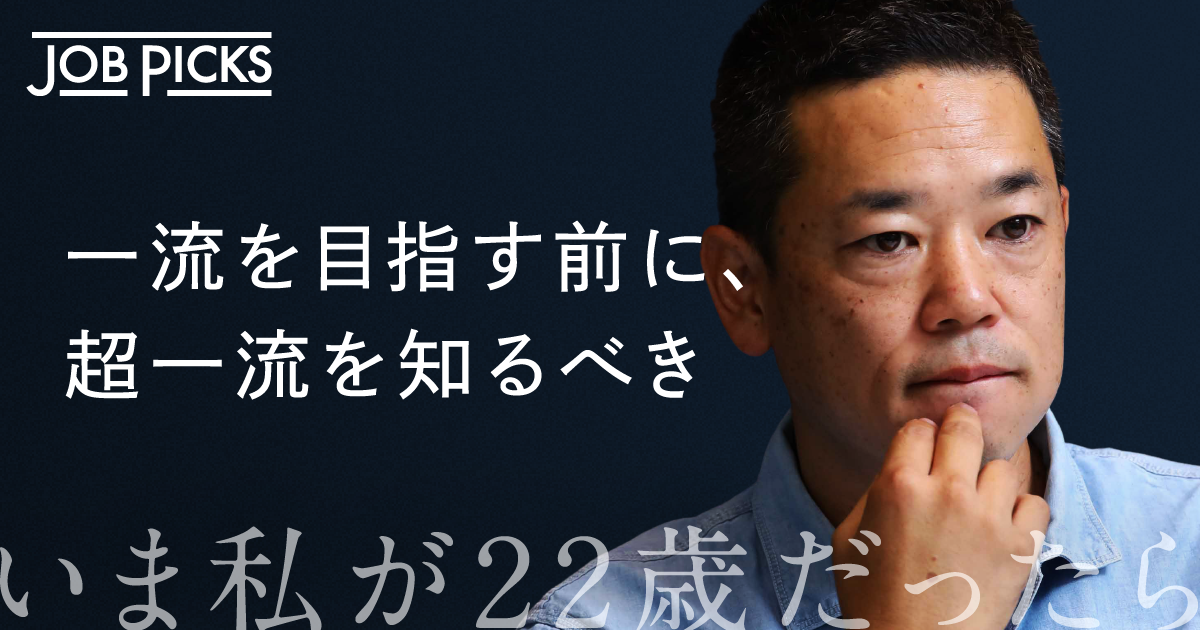
【Allbirds蓑輪光浩】ナイキやユニクロで知った「世界で通用する力」の鍛え方
ノートをつける習慣ができたのは、Nikeで働いていた頃、上司から「書いて残すこと」を勧められてからです。
振り返ってみると、たしかに「書く」ということがすごく重要でした。タイプするだけだと、どうしても忘れてしまうんです。
今でも仕事に困ったときは、過去につけたメモを見返しています。柳井社長の言葉ですが、「美意識のある超合理性」なんて、普通の人からは絶対に出てこないですよね。
日々ものすごいスピードで過ぎていく日常も、メモをつけるだけで意味のある毎日に変化します。もちろん、仕事に限った話ではありません。
例えば僕は、部下が出張をする際に、「その地域で最も有名な美術館やイベントなどに行ってみなさい」と声をかけていました。アスリートであれ、アーティストであれ、いわゆる“超一流”からインスピレーションを受ける経験が、自分を飛躍させてくれるからです。
■担当事業と「縁遠い人」に仕事の話をする
このインスピレーションの創発方法について、別の形を習慣にしていると話すのは、今年10月に新規事業担当者者向けの書籍『異能の掛け算』(NewsPicksパブリッシング)を上梓したSun Asteriskの井上一鷹さんです。
自身も前職のJINS時代、メガネ型ウェアラブルデバイス「JINS MEME」の開発や、会員制ワークスペース「Think Lab」の立ち上げを担ってきた井上さんは、事業企画担当として心がけている事柄を下のように投稿しています。
①健全な不安感 ②再定義し続ける意識 ③振り切る勇気 ④遠い人に仕事
この中で、「④遠い人に仕事について話す」とあるのは、例えば自分の母親に担当事業の構想などを話すことで「意外な視点をもらえることがある」からだそう。
たまには家族や仕事以外の知人に、今やっていることを話してみるというのも、突破口を見いだすきっかけになるのかもしれません。
JobPicks Voice
「みんなでつくる仕事図鑑」JobPicksは、さまざまな職業のロールモデルが投稿してくれたリアルな経験談を多数掲載している。本連載では、その投稿内容を参考に、仕事やキャリアの悩みを解消するヒントを探っていく。今回は、人気職種で活躍する先輩の未経験者へのオススメ本を紹介する。
文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / alashi