友だち100人できるかな
—— 経営経験のない人材をグループ会社の代表候補として採用するスタイルは、どのようにして誕生したのですか?
穐田 私の生きがいは、素晴らしいサービスを世に送り出すこと、そして優れた人材を輩出することにあります。
素晴らしいサービスが増え、優れた人材が活躍するようになると、社会は昨日より良くなっていきますから。初めて起業した1999年から、この思いは変わっていません。
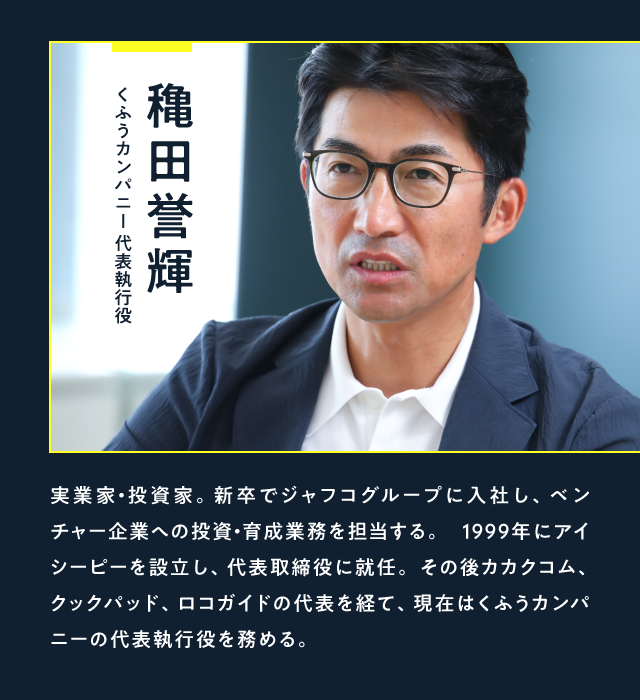
また、自分とかかわったことで社会に大きな影響を与える人材が増えれば、それだけで毎日が楽しくなるじゃないですか。
「穐田さんには世話になったので、飯でもご馳走しますよ」という人が365人いれば、毎日おいしいご飯が食べられる(笑)。
社会にとって良いこと、そして、自分にとってうれしいことの2つを同時に満たしてくれます。
—— では、365人の経営人材を輩出することが、現在の目標に?
穐田 最初はそう思っていましたが、目標は100人に修正しました。毎日外食はきついですから(笑)。でも、100人だったら、3日にいっぺんくらいおいしいものが食べられる。
「友だち100人できるかな」じゃないですが、年の離れた経営者の友だちがたくさんいて、みんなで世界をどんどん良くしていって、毎日を楽しく一緒に過ごせる……そんな世界を実現させたい。
あえて経営経験のない人材を育てているのは、「優秀だけれど、経営に関与しない人」が多いと感じているからです。
日本には、経営者になり、社会を良くしていく能力を持っているけれど、それを発揮する機会を持たない人がたくさんいます。
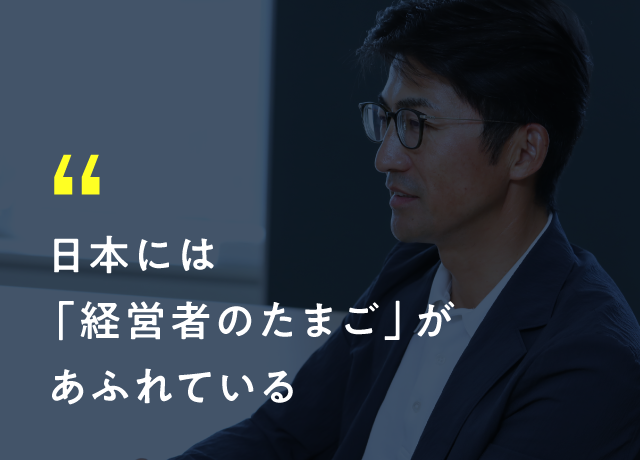
経営者というと、特定の領域に大きな熱量を持つ人の仕事のように受け取られてしまう向きもありますが、それに限りません。
「社会の役に立ちたいと考えていて、その手段として経営をするだけの能力はあるが、手掛けたいテーマがないために経営していない」人だって、実は会社経営に向いているかもしれない。
そういった人たちに経営という手段を提供したいし、それこそが使命の1つだとも思っています。だから、新しく採用した人材にもグループ会社の経営を任せるようにしているのです。
意思や利他の精神>数字の知識
—— 立石さんは、どんな経緯でくふうカンパニーに転職を?
立石 学生時代の私は、穐田が言う「手掛けたい事業テーマ」がないタイプの人間でした。そうした背景もあり、前職はVC(ベンチャーキャピタル)でキャピタリストとして働き、世の中がより良くなるサービスに対して投資を行ってきました。

そこから一転、経営者になる道を志したのは、「経営と投資は表裏一体であり、経営をせずに投資の仕事を続けていくのは難しいのではないか」と感じるようになったからです。
それで起業を考え始めた矢先に、穐田からも同じ話をされまして。投資家であり経営者でもある彼の下で経営を学びたくなり、くふうカンパニーへの入社を決めました。
つまり、くふうカンパニーは、私の意思を貫いて、過去の経験も生かせる環境だったんです。
穐田 彼女は学生の頃から「投資家を目指している」と言っていました。当時は8年前で、今にも増して、女性のキャピタリストが少なかった時代です。
それにもかかわらず、キャピタリストを目指すという話に興味を持っていました。だから、年に一度くらい会って話をしていたんですね。
するといつも、「新規事業が楽しいです」「キャピタリストは学びが多い仕事です」と言っていたので、先々を見据えて事業を創れる人材だと思っていました。
また、キャピタリストとして「社会の役に立つこと」を軸に投資を続けていたので、信用度合いもどんどん深くなって。「うちに転職することで、キャリアにプラスになるかもしれない」と、私から入社を誘いました。
—— くふうカンパニーで経営人材を採用する際は、何を重視しているのですか?
穐田 決算書や事業計画書を理解できるといった、経営に求められる最低限の素養は見ます。とはいっても、それがなければ不採用というわけでもありません。
例えば、ユーザーサービスやホスピタリティを重視した事業を運営するのであれば、変に数字だけを意識しすぎないことも重要だからです。
その人が持つ個性と事業の相性を熟考した上で、採用するか否か、どのような事業を任せるのかまでを決定しています。
立石 穐田には、「立石には邪悪さがない。うそをつかないところがあなたの武器だ」と言ってもらっています。これが本当だとしたら、利他の精神というか、素直さみたいなことも採用要件なのかもしれませんね。
繰り返しになりますが、私はキャピタリスト時代、世の中がより良くなると私自身が信じられるサービスにしか投資をしませんでした。穐田と話していても、同じ思いを持っているように感じました。
ポリシーを決めることは、何かの可能性を捨てることと同義ですが、私自身はこの思いに強く共感していますし、くふうカンパニーには同じ思いを持った経営者が多いと感じています。
穐田 起業家には、自己実現型リーダーと、社会問題解決型リーダー、2つのタイプがいると思っています。
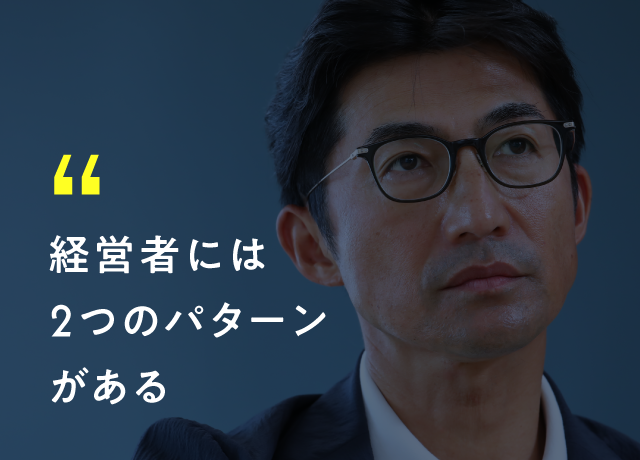
前者はアーティストやアスリートのように、「自分の能力を世に問いたい!」というモチベーションで生きています。私が支援せずとも、自分で事業を立て、動かせるタイプです。
しかし、後者の「社会問題解決型」のリーダーはそうとは限らない。だから、応援しているのです。
ともすれば地味かもしれないけれど、社会問題に対して真摯に向き合い、組織を統率することもできる。どちらかと言えば、自分もこのようなタイプなので、感情移入しているのかもしれません。
—— 新卒の学生も、未来の経営者候補として採用しているそうですね。具体的にどんな点をチェックしていますか?
穐田 「本気で経営者を目指しているか」を見ています。ファッションとしての経営者志望は、採用できません。
本気度を見極めるには、質問をした際に、踏み込んだ回答ができるかを見ればいい。
例えば、興味があると言った事象に対して「あなたの考えはAですか、あるいはBですか?」と問えば、大半の人はそれに答えられます。
しかし、「なぜAなのですか?」という問いには、答えられない人もいる。経営者を目指しながら、その問いに答えられないのであれば、考えが浅いと感じてしまいます。間違っていてもいいので、自分なりの答えを持っていてほしい。
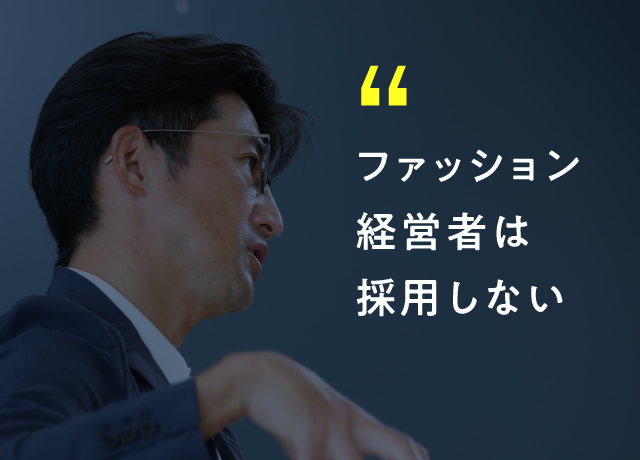
また、「自分の言葉で話しているか」も非常に重要な観点です。
面接やミーティングで、「LTV(Life Time Valueの略で、顧客生涯価値のこと)が〜」とか「ARPU(Average Revenue Per Userの略で、1ユーザーあたりの平均売上のこと)が〜」などと横文字を連発する人を、私はあまり信用していません。
「それ、ユーザーに対してどんな価値を生むのか、きちんと理解して話していますか?」と思ってしまうんです。
思慮深い人は、話をする時に、自分の経験を踏まえて、自分の言葉で話ができます。部活で挫折した過去を持っていたり、身近な人が喜んでくれた経験を糧に生きていたりと、原体験を持っているパターンも少なくありません。だから、ファッションになりにくい。
もちろん努力した経験も見ますが、本気度がないのであれば、経営を任せることはできませんし、採用してもお互いが不幸になるだけかなと思います。
経営人材を生み出す、2つの約束
—— 経営経験を持たない人材を、経営者に育て上げるのは簡単なことではないと思います。穐田さんが心掛けていることは何ですか?
穐田 くふうカンパニーの軸は「ユーザーファースト」と「自立・自律」の2つです。これらを徹底的に意識できれば、自然と職能が身に付くと思います。
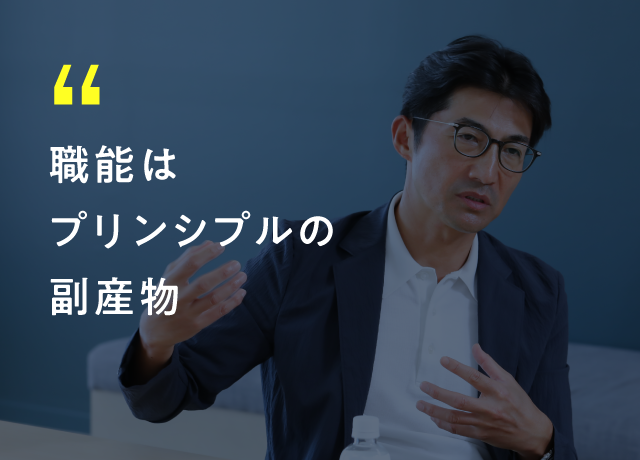
「ユーザーファースト」とは、自らが積極的に使い、大切な人にも勧めたくなるサービスを提供することです。そうでないのなら、ユーザーファーストを謳う資格はありません。
例えば、当社が運営しているサービスに、「エニマリ」というサービスがあります。「結婚式の素晴らしさをもっと多くの人に伝えたい」という思いで立ち上げたメディア事業を母体に、現在は結婚式のプロデュースやドレスの販売なども扱う総合サービス事業となっています。
ウェディング領域には、解決すべき課題がたくさんあります。挙式のあり方は多様になっているのに、選択肢を狭め、言葉巧みに不必要なオプションを付けて単価を吊り上げる事業者が少なくない。結婚式の値段が上がりすぎて、式を挙げない・挙げられないカップルも増えています。
これ、まったくもってユーザーファーストではありませんよね。
「エニマリ」では、大規模なホテルウェディングだけでなく、レストランや神社、庭園や洋館までさまざまな挙式場所の提案や、小規模の挙式にも積極的に対応しています。
単価の高い挙式に絞ったほうが収益性は高いかもしれませんが、それでは多くの顧客を切り捨てることになります。
立石 ユーザーファーストを貫きながら利益を上げることは、一般的には簡単ではありません。特に、事業立ち上げ早期は難しい。
キャピタリストとして多くの会社にかかわってきた経験からも、そのように感じています。

それでもくふうカンパニーでは、ユーザーファーストを大事にします。穐田を含む私たち全員が、その戦い方で勝てると信じているからです。
実際、穐田には「とにかくユーザーファーストで考えて」ということ以外、細かく仕事の指示を受けたことがないんですよ、本当に(笑)。
穐田 ただ、過去には、失敗もあります。
一例を話すと、前に保険事業の立ち上げをしていた際、保険の見積申込者にアイスクリームの引換券を配っていたんです。それを知った時は、唖然としました。「アイスが欲しくて保険に入る人がいるか?」と。
もちろん、現場の気持ちは分かります。数字を稼がないことには始まりませんから。でも、ユーザーファーストになっていませんよね。「お客様の気持ちになって考えてよ」という話です。
—— 「お客様の気持ちになって考える」というのは、自立・自律にもつながってきそうです。
穐田 その通りです。自立していないと、ユーザーファーストを実現できません。目先の数字欲しさにアイスを配っている時点で、数字ファーストじゃないですか。その誘惑に乗らないためにも自立と自律が重要です。
また、自立と自律を掲げる背景として、私はそもそも、誰もが人生の個人事業主だと思っているというのがあります。
1つの会社で働き続けるなら話は別かもしれませんが、今はそういう時代ではないですよね。会社に依存している人間は、転職しても市場価値を上げられず、廃れていきます。経営者を目指していなくても、自らを律せないと話にならない。
—— 穐田さんは長年にわたって経営人材を育ててきたわけですが、苦労していることは?
穐田 苦労というか、重要で難しいなと感じているのは、権限委譲です。何が正解なのか分かりませんし、経営人材として活躍しているメンバーも、きっと悩んでいると思います。
でも、これが上手くいくと、組織としての成長速度が上がります。多くの失敗を重ねてきて、大切なことは、大きく2つだと感じています。
まずは、上司が部下に対して、信じて任せる「度胸」です。
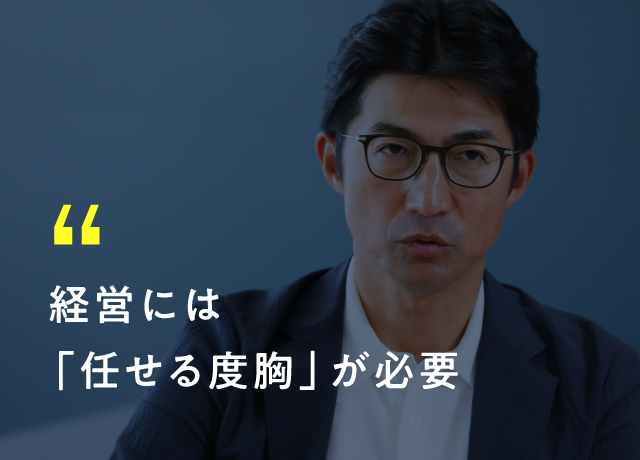
「まだまだだな」「自分がやったほうが早い」などと思いながら仕事を任せるのは、勇気がいります。でも、だからといって、ずっと自分が担当しているようでは部下が育たない。責任を取る覚悟と度胸を持って、仕事を任せていかなければいけません。
第2段階は、良い結果が出るように、見えないサポートをする「技術」です。
信じて任せることは重要ですが、仕事を丸投げしただけでは成果は出ませんし、自信や成長にはつながらないと思っています。
見えないようにサポートしたり、あえて分かりづらいヒントを出しながら、あくまで自分で気が付き、自分の力で結果を出せたと思える環境をつくる「技術」が重要だと思います。
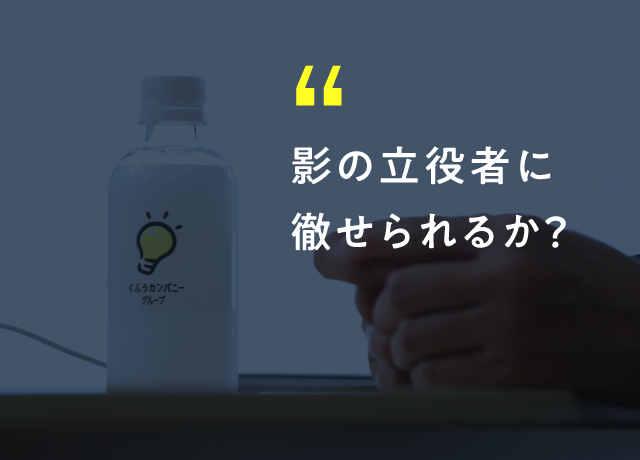
「会社のお金で失敗できる」
—— 特別なことをするより、当たり前のことを当たり前にやり切ることが、経営人材を目指すステップになるのですね。「優れた人材を輩出すること」が生きがいの穐田さんから、若い世代に伝えたいことはありますか?
穐田 どんどん打席に立って、失敗経験を積んでほしいです。
偉そうに話していますが、私は学校を卒業して最初に入社した投資会社で、何1つ結果を残せていません。最初の出資先は倒産しましたし、最終的に1社も上場させることができませんでした。
でも、その時の悔しい経験があるから、失敗をさせてくれた会社があったから、今の自分があります。同じように経営者を目指す若い人には、転んだところから立ち上がる状況を楽しんでほしい。

くふうカンパニーでも、失敗を味わった経営人材がたくさんいます。
先ほど例に出した「エニマリ」でも、コロナ禍初期の頃から、事態が収束するには最低でも3年以上かかることは理解していました。それでも新郎新婦の希望に応えるために、何とか挙式に踏み切ろうとして、何度も延期を繰り返したり結局中止となった事例が多くありました。
本来なら、「宴会」「密集」という従来型の挙式を望むお客様にストップをかけたり、屋外などでの挙式を提案することで、新しい結婚式のあり方を問う絶好の機会だったのに、思い切った策を打てませんでした。経営者としての私の失敗です。
事業の現場リーダーには特に、失敗を恐れず挑戦してほしい。前向きな失敗は次の成長への大きな糧になります。
「会社のお金で失敗できるのが、サラリーマンの醍醐味だ」と思うくらいで大丈夫。くふうカンパニーでは、引き続き、前向きな失敗を讃えるような企業文化をつくっていきたいです。

合わせて読む:【最新版】ゲイツ、ザッカーバーグ…起業家10人の愛読書136冊
取材・文:藤原環生、編集:オバラ ミツフミ、取材・編集協力:伊藤健吾、デザイン:松嶋こよみ、撮影:遠藤素子