中国の大起業家も学ぶ
さる8月30日、京セラ創業者でKDDI(旧・第二電電企画)の設立や日本航空(JAL)の再建でも知られる稲盛和夫さんが死去したことがニュースになった。
偉大な経営者として数多くのビジネスリーダーに影響を与え、彼の経営哲学を学んだ人は枚挙にいとまがない。
下の追悼記事でも紹介しているように、中には日本国内のみならず、中国のファーウェイ創業者の任正非さんやアリババ創業者のジャック・マーさんも含まれる。
【追悼】経営の師範「稲盛和夫」の哲学そんな稲盛さんはいくつもの書籍を遺しているが、同氏の哲学が詰まった1冊として多くの人に愛読されてきたのが『生き方』(サンマーク出版)だ。
2004年に出版されて以降、国内で120万部以上、中国では翻訳版が200万部超えのベストセラーとなっている。
本稿では、本書から学んだというJobPicksのロールモデルのコメントを紹介しながら、リーダーシップの真髄を紹介していきたい(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て記事掲載時の情報)。
『生き方』が教えるリーダーの姿勢
新卒入社したサイバーエージェントを経て、2017年に人事・採用分野のテクノロジーベンチャーを立ち上げたZENKIGENの野澤比日樹さんは、『生き方』を通じて、志を軸に仲間を集め、事を成すという基本を学んだと述べている。
生き方
起業する目的は千差万別。 ・有名になりたい ・好きなことをしたい
野澤さんが引用している
「利を求める心は事業や人間活動の原動力となるものです。しかしその欲を利己の範囲にとどまらせてはなりません」
という一節は、経営者のみならず、社会人として働く上でも土台となる教えと言える。
医薬会社の海外子会社で社長を務める三宅孝毅さんが紹介している
「人生・仕事の成果=考え方×熱意×能力」
という“方程式”も、稲盛さんの有名な金言だ。
生き方
稲盛さんの人生の目的は心を高めること、魂を磨くことという言葉に非常に
この「考え方」の一つとして、事業を成長させるにはまず「関わる人の幸せ」を追求するという助言に感銘を受けたと語るのは、「テクノロジーと人をつなげる」を社是に掲げるITベンチャーのストリートスマート代表・松林大輔さん。
『生き方』に学んだ点を、次のように投稿している。
生き方
もともと書籍は読まなかったのですが、20歳を超えて社会人になってから
厳しさと優しさの両立を学ぶ
この「人に対する姿勢」について、実際に稲盛氏と共に働いた人物の証言も紹介しよう。
KDDI(旧・第二電電企画)の創業を主導した千本倖生さん(現・レノバ取締役会長)は、下のインタビュー記事で、稲盛さんに教えてもらった「京セラが行ったアメリカ企業の買収話」を通じてリーダーに問われる姿勢を学んだと語っている。
【KDDI創業者】私が共に働いた「経営の神様」たちの教え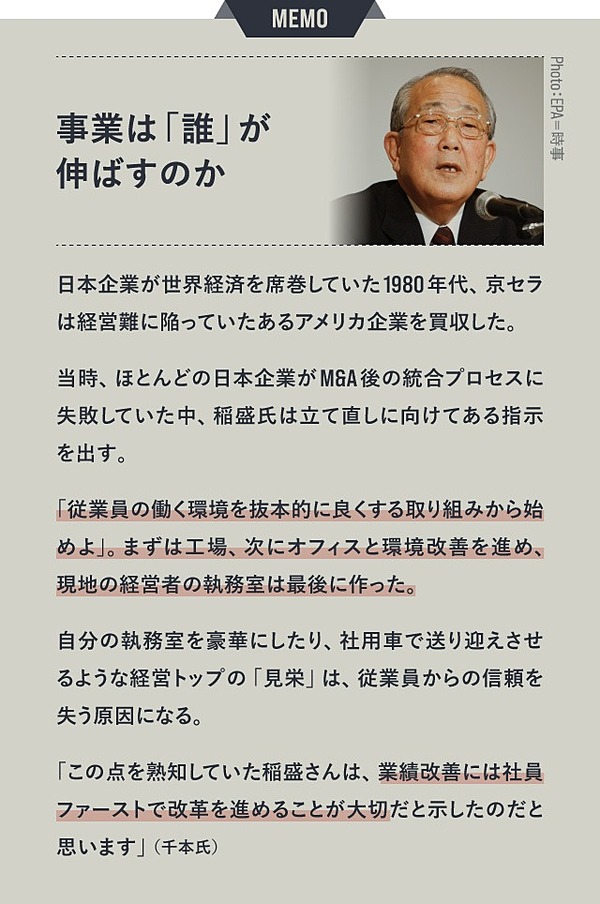
また、稲盛さんと共にJALの再生を手掛けた後、回転寿司チェーンの「スシロー」などを傘下に持つFOOD & LIFE COMPANIESのCEOとして事業再生を成し遂げた水留浩一さんは、稲盛さんの持つ「厳しさと優しさ」についてこう語っている。
【水留浩一】稲盛経営の神髄は、業績報告会にあり稲盛さんは、うまくいっている部門は手放しでほめる一方で、そうでないところはものすごい勢いで叱責する。同僚の面前で叱責されるとプライドは傷つくし、場合によってはその後の人事にも影響する。
そうすると何が起こるか。
稲盛さんに叱責されないように、必死で業績を上げようとします。
もっと言うと、最終利益の出来栄えだけでなく、なぜそういう結果になったか、何に余計なコストが生じ、売り上げ計画にどこで狂いが生じたかという細かい点まで稲盛さんは質問をしていく。
すると、ちゃんと答えられるマネージャーと答えられないマネージャーに分かれる。自分の部門の業務や数字の中身が分かっていないから答えられないわけで、それに対しても強く叱責される。
今、やんわりと表現していますけど、実際、稲盛さんは相当激しいですからね(笑)。
(中略)もっとも、稲盛さんはただ厳しくしているだけではない。
どこかでパフォーマンスとして褒めたり叱責したりしている部分もあって、厳しく叱った人を後でフォローしたり、声を掛けたりしているようでした。
そうすると社員はほだされて「次は頑張ろう」と思う。褒められた人も頑張るし、そうでない人も頑張る。
そういう人心掌握術は非常に勉強になりました。
こうした人心掌握のベースとなる考え方も学べる『生き方』を未読の人は、ぜひこのタイミングで読んでもらいたい。
【ピンカー来日】「世界の理性」と希望ある未来を創りませんか?文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳