組織開発の旗振り役を目指して
—— 羽田さんはもともと、人事ではなかったと聞いています。どのような経緯で、人事へのジョブチェンジを考えたのですか?
新卒で入社した会社に勤めているときに、「同じ目標に向かって一致団結する組織づくり」に興味を持ったことがきっかけです。
新卒入社した会社は、数字重視の会社で、社員を軽視していると感じる機会が少なからずありました。
理不尽な人事異動により、一生懸命働いていた社員が、涙を流して退職していく姿を目の当たりにしたこともあります。
企業で働く人は多くの時間を仕事に費やします。せっかく働くのであれば、その時間は幸せなものであったほうがいいですよね。
そうした考えから、まるで甲子園を目指す高校球児のように、仲間と熱くなって働く組織をつくってみたくなったのです。

当時は営業や営業企画として働いていたので、人事の仕事内容について理解していたわけではありません。それでも、思いを抑えきれず、組織づくりに挑戦するために人事へのジョブチェンジを決意しました。
とはいえ、当時は「組織をつくるなら人事だろう」くらいにしか考えていませんでした。完全にイメージ先行でしたね(笑)。
ただ、今になって振り返れば、最良の意思決定をしたと思っています。
—— 転職先にLIFULLを選んだ理由について、教えてください。
組織の立ち上げに関わりたかったので、ベンチャー企業を中心に転職先を探していました。
ただ、当時のベンチャー企業の多くはミッションや社会的意義よりも企業の成長を重要視していた印象があります。
そうしたなか、偶然にもLIFULLの創業エピソードを耳にすることになります。
LIFULLが運営する不動産・住宅情報サイト「LIFULL HOME'S」は、「不動産物件を選ぶときの、拭いきれない不透明さや不安感を解消したい」という、代表の井上高志の思いから生まれました。
彼がまだマンションデベロッパーで営業として働いていた当時は、不動産業界は今よりも情報の不透明さが深刻な時代で、理想とする物件を見つけるのが大変だったと聞いています。
そのせいで、彼のとある顧客は、なかなか自分たちが望む物件を見つけられずにいたそうです。
そこで井上は、顧客の幸せを願って、あろうことか他社が取り扱うマンションを紹介しました。
もちろん、上司から大目玉を食らうことになります。
ただ、顧客に幸せを届けられたという感情に満たされ、不思議と幸せな気持ちになったそうです。

この経験から、誰もがあらゆる物件の中から自分にぴったりの物件を見つけられるようにと、「LIFULL HOME'S」を立ち上げたのだといいます。
最初にこの話を聞いたときは、数字重視の会社で働いていたこともあり、にわかに信じられませんでした。「まるで漫画の話じゃないか」と思うくらいに、きれいすぎると思ったんです。
そこで、創業エピソードの真偽を確かめるために、井上に直接会って話を聞いてみることにしました。
—— 対面してみて、いかがでしたか?
本当に、びっくりしました。
これまでは年収がどうこうとか、数字がどうこうとか、そういう話ばかりを耳にしていたのに、井上はひとり「不動産業界の“不”を解決したい」「社員にとって日本一の会社をつくりたい」と熱量高く語っていたからです。
井上の話を聞いているうちに、人事に挑戦してみたいという私の気持ちは確固たるものになりました。
また、「社員のため」を本気で考えるこの会社なら、自分のやりたいことが実現できるかもしれないと、転職を決意しました。
「人」によって「事」を成す仕事
—— LIFULLで働き始めてから、人事として組織づくりを続けてきたそうですね。羽田さんは、人事をどのような仕事だと考えていますか?
読んで字のごとく、「人」によって「事」を成す仕事だと解釈しています。
会社の目標を達成するためには、組織の能力を高めることが必須です。
組織の能力を高めるためには、短期的な目線と長期的な目線の双方を組み合わせる必要があります。
短期的な目線でいえば、たとえば人材配置がありますよね。注力したい事業に人材を集中し、目標達成に向けてギアを入れるなど、組織目標から逆算して施策を決定します。
長期的な目線だと、たとえば人材育成が挙げられます。組織は個人によって結成されるチームですから、個人の能力が高まれば、組織の能力は必然的に高まっていく。

このように、人材の力を結集させて、会社の目標達成に貢献する仕事が、私にとっての人事です。
—— 個人の能力を高めるために、LIFULLの人事組織はどのようなアプローチをとっているのですか?
担当する業務や今後のキャリアに、社員の内発的動機が反映されているかを重視しています。というのも、自発的に学ぶと、成長スピードが速くなると考えているからです。
苦手なことや、やりたくないことばかりに挑戦していると、モチベーションを失ってしまいますよね。
ときには苦手を克服することが重要なケースもありますが、それは本人の意思があればの話です。
LIFULLでは基本的に、個人の意思に沿わないキャリアを用意しません。
—— 社員の意思を尊重するあまり、組織としてのまとまりがなくなることはないのですか?
まとまりがなくなったわけではないのですが、過去に1度、一部の組織でカルチャーが乱れてしまったことがありました。
LIFULLでは「利他主義」を掲げているのですが、会社の規模を拡大するなかで、一部の部門長がビジョンとカルチャーに合わない人を採用してしまったのです。
その結果、必ずしもユーザーの利益とならないようなアイデアが提案されるようになりました。

例えば、「クライアントがLIFULLに支払う金額が大きいほど、そのクライアントが掲載している物件がユーザーに優先的に表示される」といったようなアイデアです。
こうしたアイデアを採用すると、LIFULLにとって短期的には経済的なメリットがあります。
しかし、物件を探しているユーザーのメリットはありません。クライアントがLIFULLに支払った金額は、「理想の物件に出会えるか」には関係がないからです。
ユーザーの利益より会社の利益を重視したアイデアであり、これは当社の考え方に反しています。
短期的な利益が得られ、また社員が自分のやりたいことを実現できる可能性はあったものの、長期的な視点で見れば何も成果を得られないのです。
この経験を踏まえて、社員の意思を尊重しながら組織としての一体感を保つには、ビジョン・カルチャーの浸透が不可欠だと考えるようになりました。
—— 社員の意思を尊重しながら、それでいて組織の一体感を保つ方法として、ビジョン・カルチャーの浸透に力を入れたと。具体的には、どのような取り組みをされたのですか?
まずは、採用において、ビジョン(経営理念)とカルチャー(企業文化)への共感を絶対条件にしました。

どれだけ優秀な方で、社内におけるニーズが高かったとしても、当人の意思と会社のビジョン・カルチャーがフィットしなければ、採用しないことにしたんです。
すると、社内の一体感が保たれ、それでいて事業が成長していく組織をつくることができるようになりました。
社員の人生を背負うということ
—— 苦労を重ねて、「同じ目標に向かって一致団結する組織づくり」に成功したのですね。人事の仕事をしていて、やりがいを感じる瞬間はどのようなときですか?
設計に携わった組織が成果を上げたり、コーチングをしている社員の仕事が上手くいくようになったりしたときなどはやりがいを感じますね。
また、社員に「LIFULLに入社してよかったです」と直接言ってもらえたときは最高です。社員の幸せを心から願っているので、これ以上ないくらいにうれしい気持ちになります。
このように、「経営理念の実現に近づいている」と感じられることと、「社員がWell-beingを実感している」と感じられること、この双方を満たすことが、私にとっての人事のやりがいになっていると感じます。

一方で、人事の仕事をしていて苦しいと感じる瞬間もあります。
どのような仕事も葛藤は付きものですが、この仕事は人事として表情がよく見える社員同士が対峙する場面を目の当たりにすることが多いので、対峙する双方の気持ちが痛いほど伝わり、悩ましい判断を迫られることがあります。
たとえば、経営陣と社員、上司とメンバー、事業部門の意見と管理部門の意見、社員の要望と法令順守、短期の成果と長期のビジョンなど。
ほかにも、「短期的には苦労をかけるけど、長期的には」とか、「短期的には嫌なフィードバックだと思うけど、乗り越えれば長期的には」というような時間軸のズレは、長期的によくなる確証がないため説明が難しく苦労します。
もしそれが伝わっても、短期的にネガティブな気持ちにさせてしまうのは気持ちの良いものではありません。
—— 仕事の中で葛藤を感じる瞬間も多いんですね。どのような気質を持った人であれば、人事として活躍できると思いますか?
まず重要なのは、「組織人事オタク」のような人です。すなわち、組織と人への強い興味関心のある人なら、どんどん学んで、どんどん経験を積んでいけると思いますので、活躍するチャンスがあると感じています。
また、当事者意識が強い人は向いていると思います。人事は組織のすべての部門と人を支援して、より良くしていく仕事ですので、全部門、全社員を「自分の部門、自分の仲間」と捉え、思ったことがあれば提案したり質問したりといった行動が必要になるからです。

一方で、当社の人事部門への転職を受け入れる際には、人事の専門知識の有無はさほど重要視していません。転職後にキャッチアップすることは、十分に可能です。
事実、未経験から人事になった社員も活躍していますよ。
人事が経営を担う時代へ
—— 採用をするにあたって、ハードスキルはそれほど重要ではないのですね。
人事として成果を上げるために、人事の専門性は非常に重要です。
しかし、それだけでなく、ポータブルスキルと呼ばれる職種が変わっても持ち運び可能な能力……たとえば課題を見つけ、計画を立て、解決する力、答えが1つではないような課題について相手の共感を得る説得力なども非常に大切だと思っています。
具体例を1つ挙げるならば、先ほど挙げた「葛藤を感じる場面」で、周囲を合意に導くリーダーシップです。
たとえば、事業部門と管理部門の意見の対立や、短期の成果と長期のビジョンの対立などが発生することがありますが、誰もが会社を良くするために一生懸命考えていますので、「どの社員の意見にも一理ある」という場面がほとんどです。
こうしたときは、「経営理念を実現するためにはどの選択が最適かな?」という質問を投げかけ、対立する社員の意見をまとめていく必要があります。
これは分かりやすい例ですが、人事は組織を束ねる職業ですから、リーダーシップを発揮しなければいけないシーンが非常に多くあります。

そうした意味で、人の気持ちを理解する力や、仲間の協力を得ながら仕事をリードして結果を出していく力などが必要不可欠だと感じています。
—— ハードスキルを磨いても成果を上げられるとは限らない、クレバーさが要求される職種なのですね。
経営において、「戦略」ではなく「人」、「ハード」ではなく「人の知恵」で差がつくということがよく言われるようになりました。
ある雑誌でも、経営コンサルタントの方が、戦略をつくるスキルがコモディティ化してきており、今後何で差が生まれるのかというと、人である、ということをおっしゃっていました。
そうした背景から、「人」を扱う人事に向けられる注目度は日に日に高くなっているのかもしれません。ボードメンバーにCHRO(最高人事責任者)ポジションを置く企業が増えているのも、そうした背景からでしょう。
今後も注目度は高くなっていくでしょうから、人事を極めるというキャリアはぜひお勧めしたいですし、そうした人が増えることは、私にとってもうれしいことです。
不確実な時代と言われて久しいですが、そんな時代を組織が生き抜くためには、すべてのメンバーが自律して、自分の頭で考え、主体的に情報を集め、自分の意思で挑戦し、仲間と協働していく必要があります。
そんな組織づくりに、人事という仕事は多大な貢献ができます。それでいて、メンバーひとりひとりの人生や成長に関わることもできる。本当に魅力的な仕事です。
チームをつくることに関心があったり、人が好きだったりする人は、ぜひ挑戦してみてください。
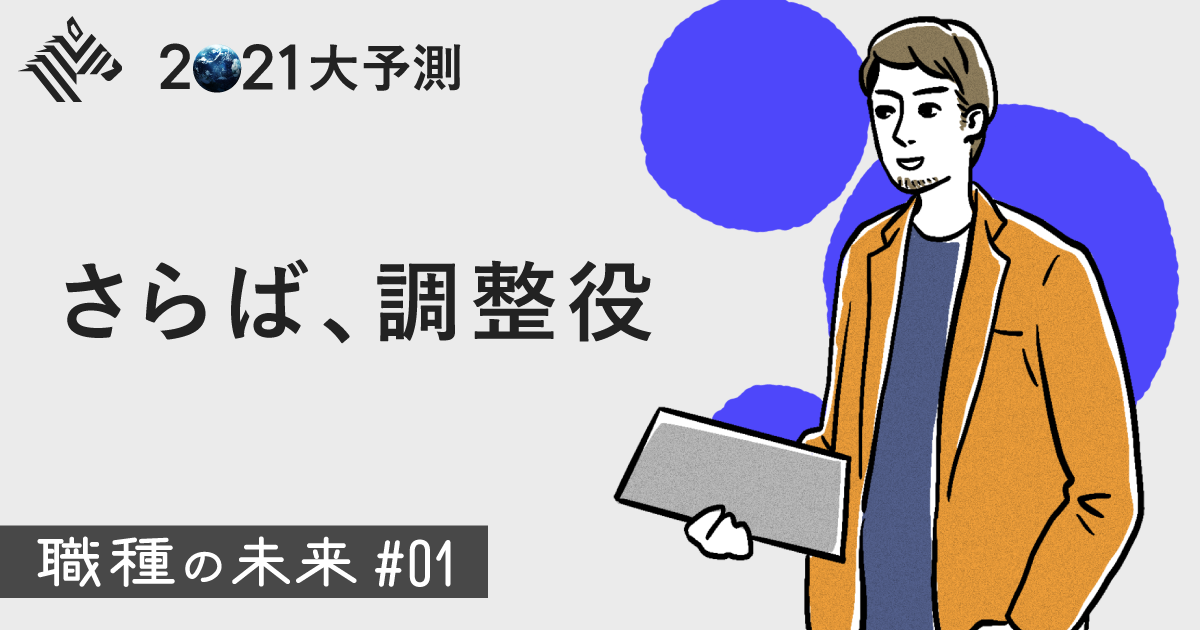
合わせて読む:【人事の未来】求められる、「経営者目線」の改革実行人
取材・文:安保 亮、編集:オバラ ミツフミ、デザイン:石丸恵理、撮影:羽田幸広(本人提供)