クレームが軌道修正のヒントに
古賀さんは2008年に新卒入社したソニーで、ブルーレイのディスクレコーダー向けのコンテンツ管理データベースやファイルシステムなどを開発していた。
「ソフトウェアの力で社会を変えるような仕事をしたい」。そう考えて就職したが、当時はテレビ録画のマーケットがすでに縮小傾向にあった。
そのため、次第に「事業のコンセプト設計から行うような仕事がしたい」と思い始め、社内の新規事業コンテストに挑戦するようになる。
その後、2014年に新規事業開発の部署に正式に異動した後、知人だったリクルートの社員から、こんなアドバイスをもらった。
「新事業をやるなら命をかけること、自分が絶対に逃げないことをやるべき——。そうアドバイスされ、衝撃を受けました。それまでの自分は、ビジネスを作りたいと言っても、命をかけるほどの覚悟はなかった。甘かったのかもしれない。ここから、自分は何者になって、何をやるのかを真剣に考え始めたんです」
この「命をかけたい仕事」を模索する過程で、副業を経験してみたのが、現在の仕事につながる。

気軽に社外の仕事を経験できれば、仕事人生を変えるきっかけになると実感した古賀さんは、2014年にリクルートがサンカクをリリースしたのを知り、すぐに転職を希望。ビジネスプロデューサーとして入社を果たす。
だが、初期のサンカクは、まだまだ発展途上だった。
副業として参加する人たちにはある程度の評価を得たものの、受け入れる企業側から「負担が大きい」「フィットしない人が来た時は成果も出ない」などとクレームが来ることもあったという。
そこで古賀さんは、コンセプトに「中途採用候補との接点ができる」というポイントを加え、社会人のインターンシップ参加サービスとして軌道修正。それが奏功し、利用者増につながった。
若い頃から抱いてきた「社会を変える仕事をする」という目標に向けて、現在も新たな企画を生み出し続けているが、どんな1日のスケジュールを送っているのだろうか。
【ある1日】対話が企画を生む

古賀さんの1日は、コロナ禍の現在、主にオンラインワークが中心になっている。
朝9時、自宅でのメールチェックから始まる。9月の某1日のスケジュールは、メールチェックの後、事務ワークを片付け、11時からメディア取材があった。
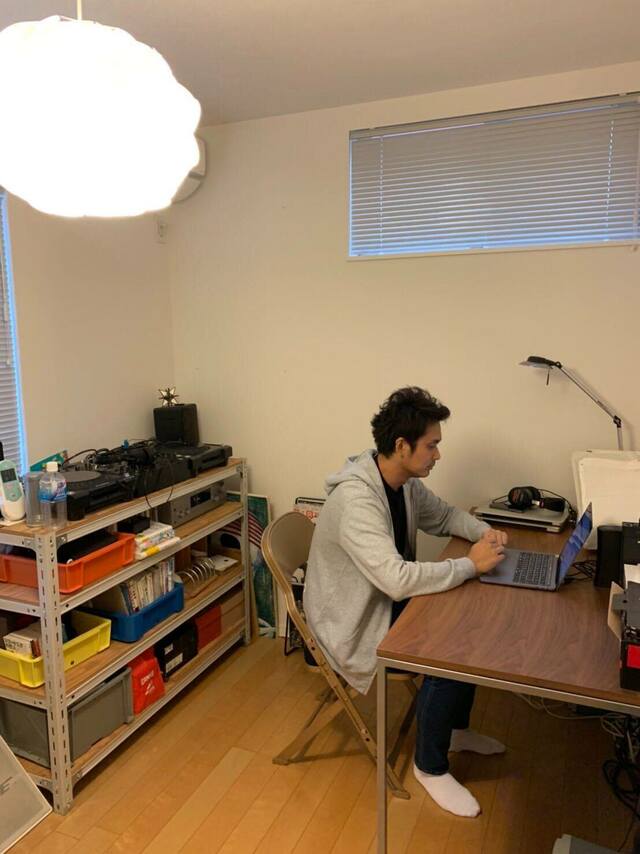
「取材のテーマは、サンカクの新サービスの一つ『ふるさと副業』です。今、コロナの影響もあって、東京から地方へ引っ越す人も多く、地方×副業という文脈でふるさと副業が注目されているんです」
このサービスは、和歌山出身の古賀さんが地元の酒造メーカーに勤める友人が毎月、販路拡大の為に東京に出張していることを知り、「だったら東京在住の和歌山県人が副業でやればいいのではないか」というアイデアが実ったものだ。
2018年にスタートしてから、古賀さんの予想を超える応募が来ており、多くの企業・団体でマッチングが生まれている。
「仮説を基にして行う定量調査で良い傾向が出たり、実際にマッチングが続々生まれた瞬間は、やはり大きな手応えを感じます」
この取材の後、自宅で奥さんと一緒に昼食を食べ、午後1時からオンラインでの打ち合わせが続く。
「この日はリクナビNEXTの社員と一緒に、転職サービスとサンカクをセットでお勧めする作戦会議をしました。最近は部署を横断した企画が増えていますが、立ち上げ時期は社内でも『新しい潮流が生まれるだろうか』という不安な声も多かったです」
それでも、社会人インターンシップが副業への後押しになったり、中途採用候補探しにもつながる可能性があると説明し続けた結果、今ではサンカクの主力サービスになっている。
事業開発の仕事では、アイデアを形にする上で社内外の関係者を巻き込む地道な作業が必要なのだ。
欠かさず行う「モニタリング」
その一環として実施しているのが、関係者たちと行うサンカク事業の「モニタリング」だ。
「サンカクの開発、営業担当の人たちと、アクセス数や営業の進捗具合などを確認します。自分はマネージャーなので、それぞれのメンバーから今後の方針を聞き、アドバイスしたりします」

30分のモニタリングが終わった後、30分の事務ワークをして、午後2時30分からは客先へ営業チームと共にオンラインで打ち合わせをした。
「目的は、社会人インターンシップに対するニーズを発掘するためのヒアリングです。このヒアリングを元に、例えば『データ利用による地銀の課題解決にサンカクを!』など、新しい企画を練っていきます」
社会人インターンシップのサービスを立ち上げた当初は、古賀さんが1人で営業、企画、サイト構築までを行っていた。
古賀さんはもともと営業とは無縁のエンジニアだ。それでも、自分が営業をやらないと事業が前に進まないと思い、震えながら、汗をびっしょりかきながら、飛び込み営業を行っていたという。
「今では人材紹介事業の営業部隊(エージェントの人)から、サンカクを導入できませんか?と相談が来て、一緒に提案に行くという形が多いです。当初と比べると、営業も慣れてきて楽にできるようになりましたね」
社会人インターンシップは、転職を考えていない人に転職も視野に入れたインターンシップを売るという、マッチング的に見ると非効率に映るビジネスモデルだ。
それだけに、当初は社内から全く賛同が得られない状態だったが、古賀さんはこの時も状況を打破するため、1人で提案書を作って飛び込み営業を敢行。
結果、売り込みは成功し、そうして積み上げた実績をもって正式にサービスを事業化することができたのだという。
「サンカクへの参加時点では転職意向が高いわけではないので、マッチングという観点においては非効率に映るかもしれません。しかし、サンカクの参加者は会社が嫌で転職活動をしている人とは対極で、エネルギー溢れるイキイキ感が半端ない人たちです。
自身の経験を生かす方法が意外と身近にあると実感されれば、副業で生かしたり、転職を通じて別の機会にチャレンジをしたいと思うはずです。このことから、絶対にうまくいくと思っていました」
この日は営業先から午後3時30分に戻った後、オンラインでもう一件、営業提案を行った。その後は、部長とオンラインで1on1のミーティング。
「自分のチームのメンバーのモチベーションは下がっていないか、メンバーそれぞれの目標設定は適切かなど、部長には広く相談しています」

午後4時からはインキュベーション部内で実施しているオンライン勉強会に参加。社外から専門の人を呼んでマーケティング講座やSQLの勉強会などを定期的に開催しているという。
「事業開発職は、様々な分野の情報インプットが大事な仕事なので、多くのスキルをみんなで共有しようと多くの多種多様な勉強会を部内で自主的に開催しています」
午後5時からは社内報(メルマガ)の取材を受ける。
「事業開発という仕事は、社内で自分の仕事を広く知ってもらうことが非常に重要です。社内で戦略的に目立つことが必要な仕事だと思います。なので、社内での認知度がグッと上がる社内報(メルマガ)で扱ってもらうことも大切に考えています」
営業の立場から見ると、自分がよく知らないサービスを担当顧客に提案したいとは思わないだろう。しかし、社内報で知って共感したサービスなら、積極的に売りたいと思うはずだ。
実際、魅力的な記事が社内メルマガに載ると、社内で応援者が増えて、営業提案の調整がしやすくなるのだという。
「そこで、当社の社外広報部と連携して、『ミラキャリ通信』というサンカクの活動を紹介するニュースレターを定期的に発行しています。その内容をどうするか、事前打ち合わせも含めて、社外広報とはほぼ毎日、入念にコミュニケーションを取っています」
30分のメルマガ取材の後、午後5時から6時半までメンバーとの1on1を3つこなして、6時半から8時まで再び顧客企業へオンラインで社会人インターンシップの企画提案を行った。
この日の仕事はこれで終了。このあと、家族よりも遅い夕食を一人で取り、午後11 時に近所の公園に30分ほど縄跳びをしに行く。そして、寝る前には動画配信サービスなどでドラマを見るのが日課。毎日、朝から夜までスケジュールがぎっしりだが、「仕事でストレスは溜まらない」という。
「僕にとって仕事はドラマを見たり、運動をしている時と同じで、楽しんで自発的にやっているから、ストレスは溜まらないんです。なので、仕事を終えてパソコンを閉じたら、その1分後には熟睡できてしまう(笑)」
忙しくても「何でもやる」理由

古賀さんの仕事ぶりを見ると、非常に多忙なだけでなく、企画から社内外への営業活動、アイデアを生み出すための情報収集など、幅広い仕事をカバーしていることが分かる。
中には前職のソフトウェアエンジニア時代には経験しなかったであろう仕事もあるが、どうやって事業開発に必要な動き方を覚えていったのだろうか。
「スキルについては、実際に仕事をやりながら覚えていけばいい。また、(他の事業企画職の)先輩たちに比べて『できないこと』で悩みすぎないというのも大切です。事業の成長に向けて、できることからやる。そうやって、実地で学んできました」
そして、スキルや知識の習得よりも大切なのが、前述した「何があっても逃げないと思えるテーマを選ぶ」ということだという。
古賀さんは、ソニーで新規事業の部署に異動する前後に、長い仕事人生で本当に取り組みたい仕事のテーマをノートに書き出したことがある。
約1カ月をかけて、何があっても逃げないテーマは何かを考えに考えた結果、行き着いたのが、メーカーとはあまり似つかない内容だった。
「音楽系、スポーツ系、映像系とバーッと紙に書き出して、自分が命をかけられるテーマを必死に考えましたが、結局『働く』ことからは逃げられないと気付いたんです。だから、『働く』をテーマにしたビジネスを作ろう、と。その時、ついに『何者かになりたい自分』から脱して『何者かになる』入り口に立ったという心境でした」
ここから人事論や組織論をテーマにした論文を読みまくり、コミュニケーションが活性化するテレワークのシステムから、働き方改革系のビジネスなど、新規事業の企画を温めていった。
そこには、サンカクのコンセプトと同じく「モヤモヤ感から自らを解放したい」という切なる気持ちがあったという。
「これは後から知ったことですが、多くの組織で優秀な人たちが、心理学的に言うと『過剰適応』という状態になるそうです。学生時代に成績の良かった人が、会社でも成績を上げる働き方に終始してしまうと、やりたいことや社会に対する価値よりも、社内評価を上げることが第一になってしまう。それが行き過ぎてしまうと、他人からは輝きを失っている人に見えてしまうこともあります」
過剰適応状態は多くの大企業で等しく起きている現象だろう。常に社内の上を見るというベクトルで働いていると、確かに世の中の流れから取り残されやすい。
「ところが、自分自身、社外で働いてみるという体験をすると、心のデトックスというか、リセットできたという感覚を強く感じました。この時、緩やかに締め付けられていくみたいな感覚の危機が、実は僕だけでなくてみんなにもあるのではないかと思ったんですね。この閉塞感を何とかするのが、僕の使命だと考えています」
そんな使命感が、多忙な古賀さんを支えている。

■合わせて読む:【独占】リクルート、60年秘伝の「ロール型」組織を初公開(NewsPicks)
取材・文:栗原 昇、取材・編集:佐藤留美、デザイン:九喜洋介、撮影:遠藤素子