学生ならではの強みで一点突破
—— まずは起業を決めた背景について教えてください。
第1志望の企業に内定をいただいた翌日に、起業しました。
就活が終わって、社会に出るまで残り1年。教育学部の家庭科専攻だったこともあり、ビジネスとは何かを理解しないまま1年目を迎えることに不安があって、それなら起業しようと考えたのです。
当時は「起業すれば、人事や法務、会計から経理まで全部学べる。一番手っ取り早いじゃん」くらいの気持ちでした。

—— 実際に起業してからのことを詳しく教えてください。
まず、起業してからの半年間はほとんど売り上げが立たず、とにかくつらい思いをしました。
ビジネスパーソンとしての経験がなかったので、人脈もなければ、スキルもないし、お金もない。経営資源と言われるヒト・モノ・カネ全てが足りない状況だったので、いきなりうまくはいかなかったのです。
立ち上げたのは、コンサルティング事業です。内定先が教育系のコンサルティング会社だったこともあり、就職後の活躍に直結するのではないかと考えていました。
具体的には、当時興味があった「お花屋さん」に対して、「コンサルティングさせてください」と営業していました。自分に実績がないことは重々理解していたので、「成果報酬型でゼロ円でやります」と。
「無料ならやらせてもらえるだろう」と考えていたのですが、考えが甘かった。これが全くダメで、門前払いでした。
無料ほど怖いものはない、という考え方もそうですが、そもそも実績のない学生から「コンサルティングします」と言われても、時間の無駄だと考えるのが一般的な発想ですよね。
当時を振り返ると、自分とのやりとりによって発生するオペレーションであったり、相手側のコストを考えられていませんでした。
—— 失敗を経験して、どのように行動を変えていったのですか?
当時の僕は、お花屋さんへのコンサルティング営業の失敗から学びを得ても、実績のない学生であることに変わりありませんでした。
そこで、どうすれば対価をもらえるようになるのか、自分は何に対してなら価値を発揮できるのかを必死に考えました。「実績のない学生」が持つ強みを探したんです。
僕が出した結論は、「大量に時間を使うこと」でした。

コンサルティングを提供しようとした場合、コンサルティングのノウハウを持つ社会人のほうが、僕よりも優位性があります。
でも、「何かに対して大量に時間を使うこと」この1点だけは、実績のない学生に優位性があると思ったんです。
それに気付いてからは、大量に時間を使ってできることに注力しました。
まず、人に会ってつながりをつくること。
興味のある方にお声掛けして、成功している事業の裏側を教えてもらったり、自分の考えている事業の壁打ちをお願いしたり。
僕の場合、対話の中でアイデアを出したり思考を深めることが好きなので、他者と話すことそれ自体が楽しく、価値があったんです。
あとは単純に仲良くなることが多かったです。
現在“Z世代の企画屋”としていくつもお仕事をいただいていますが、僕の企画の根幹には「友達」がいるので、時間に余裕がある時にたくさんの方と仲良く対話を深めることができたのは非常に有意義でした。
—— 「企画の根幹に友達がいる」とはどういうことですか?
マーケティングの施策を考える上で重要なのは「顧客がどうすれば喜ぶか」です。はじめは顧客が具体的に想像できず難しかったのですが、「友達が喜ぶにはどうすればいいか」を考えるようになってからは、次々にヒットを当てることができました。

「友達マーケティング」と呼んでいるんですが、例えば、友達にプレゼントをあげるならダンボールでは渡さない。きれいにラッピングして、メッセージを添えて渡したいですよね。
それに、商品のことを伝えるときは、「発売したよ!」と伝えるのではなく、「君のためにつくったんだ」と正面から伝えられたほうがいい。
たくさんの方と対話を重ねた結果、少しターゲットの異なるクライアントさんのご依頼にも、「彼ならこうしたら喜ぶぞ」「彼女ならこれをしたら喜んでくれそうだ」と想像ができるようになったんです。
また、お会いした方々に自分の名前を知ってもらったことで、仕事にもつながりました。
「友達マーケ」3つのキモ
—— 人とのつながりをつくることも、簡単なことではないと思います。
もちろん、相手から興味を持ってもらえるだけの準備はしていました。
具体的にやったことは3つあります。
1つ目が、Twitterアカウントをつくること。基本的にTwitterを活用してつながりをつくっていたので、定期的に自分の情報を発信したり、いろんな人の良いところを見つけては、それをツイートしていました。
2つ目は、自分だけが語れる専門領域をつくること。僕の場合は、「花贈りを語らせたら日本一の花クリエイター」を名乗っていました。
コンサルティング事業で売り上げがつくれないと理解してから、花言葉の書籍を作ったり、街中でゲリラ的に花を配ったりして、誰かに花を贈る活動をしていたんです。
僕や友人の母校の入学式に合わせて、花束を何百本も買って車にパンパンに詰め込んで、ただただ配り歩いて。
普通、こんな経験している人いないじゃないですか。こういったエピソードは非常に興味を持ってもらえました。

3つ目は、名刺を作ること。「お花を配っている学生です」と「花贈り事業で代表をしています」では、受け手の感じ方がまるで違いますよね。
相手がどれだけ地位の高い方だとしても、「花贈り」に関しては僕のほうが話せるので、情報を提供する側になれる。つまり、対等に話せるようになるんです。
この3つを準備したことで、本当に多くの人とのつながりを得ることができ、結果的に仕事を生み出すこともできました。
得意の掛け合わせで売上をつくる
—— 最初の売り上げは、どんな事業で得たのですか?
レストランへのコンサルティングだったと記憶しています。
かっこよく言っていますが、具体的に言うと「エアレジの導入のサポート」です。
もともとアルバイトに誘われたレストランだったのですが、紙で伝票を書いていたり、レジも全てアナログだったので、「効率的にした方がいい」と伝えたんです。
すると「機械が苦手で全然分からない」と言われたので、「それなら僕がやります」と、電子機器の導入から、メニューを全部テキストにしてPCに打ち込んでクラウドにアップロードするところまでをサポートしました。
—— 花贈りに限らず、さまざまな事業を展開していたのですね。
コンサルタントに加えて、ライターや編集者、グラフィックデザイナー、フォトグラファーなどフリーランスとして興味のあること全てに全力で挑戦しました。
—— 創業事業にこだわらず、手段を増やした理由について教えてください。
キャリアの考え方の1つに「希少性」というものがあります。
1つの分野で100万人に1人レベルの能力を付けるのと、3つの分野で100人に1人レベルの能力を付けるのは同じ希少価値だという考え方です。
1つの仕事をマスターするのにかかる時間を、およそ1万時間と仮定します。例えばコーヒーについて1万時間勉強すると、ものすごく詳しくなると思うんです。
その知識量を、業界で100人に1人レベルの希少価値だとします。
じゃあ、コーヒーについて追加でもう1万時間勉強したら、1万人に1人レベルの希少価値になるかというと、そうとは限りません。
単一のスキルにおける希少価値は、費やした時間ときれいに比例して伸びるわけではなくて、上に行けば行くほどピラミッド型になって競争が激しくなるからです。
しかし、もう1万時間は別の知識の勉強に使って、100人に1人レベルの分野を2つつくると、希少価値を掛け合わせることで1万人に1人レベルになれます。
これは教育改革実践家の藤原和博さんが提唱する理論で、すごく僕の価値観にフィットしています。
藤原和博の「100万人に1人」になれる働き方大学で家庭科を専攻した理由もそうで、海外には日本の「家庭科」のような学問がないんです。かつ、国内でも家政学部や調理学校はあれど、「家庭科」を専攻する学部は少ない。
僕が通っていた横浜国立大学の「家庭科」専攻は、国内で偏差値が高い。それはつまり、世界1位を意味すると思います。
大学選びもこういった考え方で選んだくらい、もともとオンリーワンを突き詰めるのが好きなんです。
事業としても、実際に先ほど挙げた仕事で一定レベルの結果を出せるようになると、その掛け合わせが売り上げへとつながっていきました。
—— 掛け合わせが売り上げにつながるとは、どういうことでしょうか?
例えば、フォトグラファーができるようになると、モデルさんとのつながりができます。モデルさんとのつながりがあると、キャスティングができるようになります。
いくつかキャスティングを行うと、事例を基に成功の法則を見つけ出すことができます。成功の法則が分かると、マーケティングのコンサルティングができるようになります。

マーケティングのコンサルティングができると、モノを売れるようになります。モノを売れるようになると、自分でブランドを立ち上げることができます。
こうやってかけ算を積み重ねた結果、立ち上げからかかわったYouTubeチャンネルは登録者1年で25万人を超え、自社ブランドは1日で800万円を売り上げるまでになりました。
全てが連鎖的につながっていったんです。

—— きれいに連鎖していますね。フォトグラファーとコンサルなど、一見するとバラバラに見える仕事ですが、どのような基準で選んでいたのでしょうか?
基本的には、自分が好きになれそうなことを選んでやっていたので、最終的に売り上げにつながるかどうかはまた別で考えていました。
お金になるかを基準に仕事を選んでいたら、たとえもうかったとしても、幸せになれないと思っていたからです。
「大量に時間を投下する」なら、なおさらつらい。
僕は自分が好きで得意なことしかやらなかったので、睡眠時間を削って働いていても、働くことそれ自体は苦になりませんでした。むしろ、寝るよりも仕事をしているほうが楽しかったくらいです。
—— 希少性の理論は、定期的にトレンドになる一方で、実際に体現できている方は多くないと思います。
単純に一つ一つが中途半端になっているケースも少なくないと思います。
僕の場合、結果的にライターとしてはメディアの編集長を務めたり、フォトグラファーとしては『週刊プレイボーイ』の写真を撮るところまでスキルを高めました。
—— 一つ一つのスキルを中途半端にしない。簡単ではないと思います。
マインドセットの問題もあるかもしれませんが、まずは自分が好きな仕事を選ぶこと。あとはとにかくチャレンジの数を増やして、スキルのレベルを高めるのがいいと思います。

仕事の機会をもらう方法は、「自分の能力に合った仕事をもらう」と「依頼に対して自分の能力を追いつかせる」の2種類あります。
僕は後者のチャレンジングな仕事を増やすことで、どんどんスキルを高めました。
一人前と言えるくらい勉強してから「グラフィックデザインができます」と言って仕事を探すのもいいのですが、とにかく手を挙げて、依頼された水準のものをどうにかつくり上げていくやり方も、スキルを伸ばす上では大事だと思うんです。
もちろん、期待値調整は重要です。依頼主には、「完璧にこなすことができます」ではなく「時間があるので、どうにか完成させられるよう頑張ります」のように伝えていました。
そもそも僕に依頼してくれたということは、ベテランのクオリティよりも若さを求めているんだと解釈したり、若者の特権を生かすことも大切だと思います。
まとめると、まずは自分の強みを明確にしました。そこから大量の時間を投下して、得意なことをつくり、それらを掛け合わせることで売り上げを生み出したんです。
得意を見失う「時間軸の働き方」
—— 仕事は楽しいほうがいいとは分かりつつも、苦しい側面が大きい方もいます。仕事を楽しめる方と、そうでない方の間には、どのような差があると思いますか?
働く価値観は人それぞれでいいと思いますが、僕は、時間軸で働くのではなく、得意を軸に働くことを大切にしています。
というのも、得意じゃないことをやる可能性が出てくるからです。
一般的な企業に勤めると、出勤時間が決まっていたり、労働時間が決まっていたりしますよね。平日5日間で合計40時間働くとすると、大抵の場合は時間が余るので、苦手なこともやらなければいけなくなってしまう。
僕は、自分がやらなくてもいいこと、得意じゃないこともやらなきゃいけないのが、時間を軸にしたときの働き方の弊害だと思っています。

一方で、僕の会社では、みんな得意なことを軸に働いています。時間の制約なく、必要なアウトプットに対して自分が得意なことだけをやっていればいい。
なので、成果を上げていれば週40時間働く必要はないし、納得いくまでクオリティを高めるために時間をかけてもいい。得意なことをやっていれば、どちらにせよ苦ではないんです。
これって精神衛生上いいし、効率もいいと思うんです。
会計が得意な人がいれば、全プロジェクトの会計を見る。マーケティングが得意な人が、全プロジェクトのマーケティングを見る。単純ですが、この組み合わせが一番強い。
実は自分が苦手だと思っている仕事が得意な人は、探せば絶対にいます。

今の時代、Twitterで募集するとDMが来ることもありますし、調整が難しいかもしれないですが、会社内でも相談してみたらいるはずです。
—— 業務上発生する、楽しくない仕事に対してはどう向き合っていますか?
仕事を楽しむのは、スキルだと思っています。
細かいルーティンワークや、人によってはクリエイティブな業務がつらいなど、仕事に対する得意不得意はそれぞれです。
ただ、それをいかに楽しむかは、ある程度までは努力で変えられるはずです。
周囲とコミュニケーションをとって緩和するとか、その後に愚痴を言ってお酒を飲むのを楽しみにするとか。
現実がつらくて環境を変えるのが難しいのであれば、解釈を変えるか、行動を加えるのが良いと思います。それでも無理だったら、身近な誰かに相談をする。本当に心を壊しそうなら、辞めてもいいと思います。仕事は無限にありますから。
特に若い方に関しては、仕事の時間が楽しくなくて幸せになれないなら、好きなことで起業するのも一つの手だと思います。
失敗すらも価値ある経験に変わりますし、個人としては一番おすすめの選択です。
—— ここ数年、「起業家人材」や「アントレプレナーシップ」が必要だという報道を多く目にします。
そういったチャレンジャー精神がある人は人材として魅力的ですよ。
たとえ1年間頑張ってダメでも、大量の時間を投下して得意なことを増やせたら、転職後も得意を軸に働けますから。
一度得たスキルは、基本的に失われません。僕の場合、実は就職するタイミングで一度事業をクローズしていますが、半年後に再度起業して、すぐに売り上げを立てることができました。
副業でも、4000万円の売り上げを立てることができたんです。
本業でフルタイムで働きながらだったので、シンプルに2人分の時間働いていましたが、それでもやっぱり好きなことだったので、楽しくて、幸せな時間でした。
眠るよりも、好きなことをしていたい。得意なことを軸に、仕事を楽しみたい。そんな人が増えたら、もっと日本は明るくなると思っています。
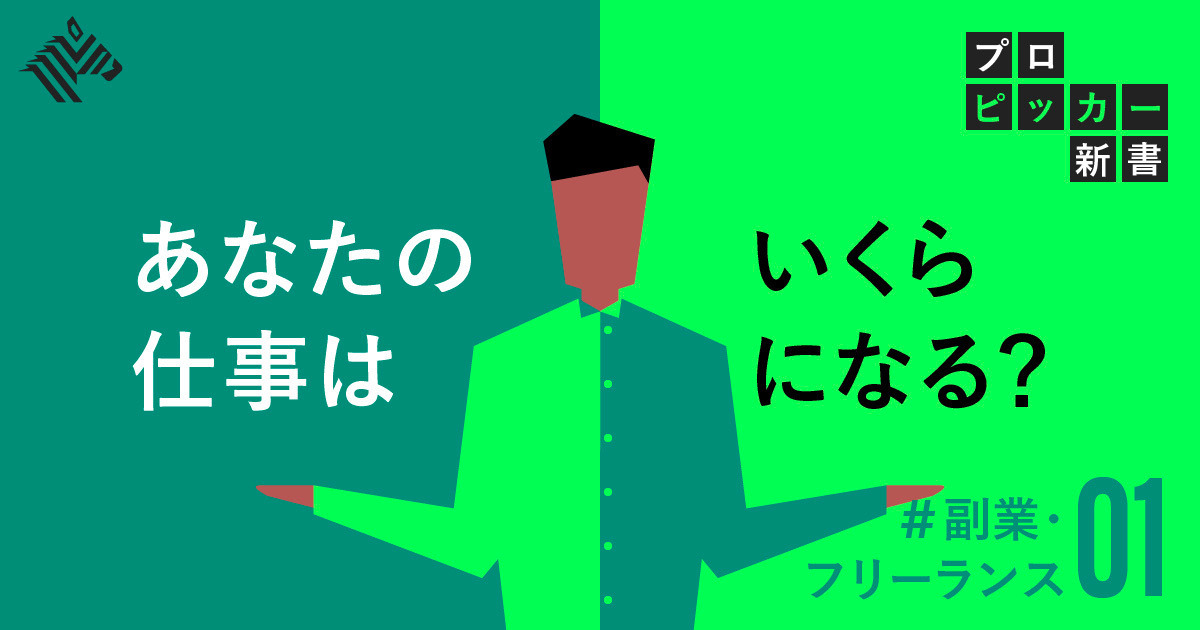
合わせて読む:【完全解説】副業、フリーランス。新しい働き方へ踏み出す方法
取材・文:日野空斗、取材・編集:オバラ ミツフミ、デザイン:浅野春美、撮影:遠藤素子