マーケに特別な能力は必要ない
—— 鹿熊さんは、20代ながら、上場企業の取締役だと聞きました。現役のマーケターでもあるそうですが、どのようにしてキャリアをつくってきたのですか?
マーケターとして特別な能力を持っていたわけではなく、「売り上げをつくる」という最重要課題と真摯に向き合ってきた結果が、現在のキャリアだと思っています。 マーケティングの定義は複雑ですが、マーケティングの権威として広く知られているフィリップ・コトラーの言葉を借りれば、「ニーズに応えて利益を上げること」です。 その意味で、マーケターとは「売り上げをつくり、利益を上げる活動をする人」だと言えます。 僕が優れたマーケターであるかはさておき、少なくとも売り上げをつくることにはこだわってきました。取締役という、経営ポジションにつく以前からの話です。
—— 「売り上げをつくる」という思考を持って、そのための試行錯誤を続けていれば、必然的にマーケターとしての動きができてくると。
「マーケティング」と聞くと、“瀕死の企業やブランドをV字回復させる魔法の一手”を想像してしまう人がいるかもしれませんが、もっとシンプルだと思っています。 僕自身、これまで「優れたマーケターになろう」といった考えで仕事をしたことはありません。「ビジネスパーソンとして成果を出そう」「経営の視点に立って仕事に向き合おう」というように、すごくシンプルに考えてきました。

個人的な意見ですが、マーケターだからといって、何か特別な知識や能力が求められるわけではありません。 本日のテーマにある書籍に関しても、「マーケターの道を極めたくて読んでいた」というより、ビジネスパーソンとして成果を上げるための手引き書として読んでいたものです。 ただ、そのどれもが、マーケターとしての役割を果たすうえで参考になるものばかりでした。 書籍で学んだノウハウを日々の仕事に取り入れ、ある種の鍛錬をし続けた結果、キャリアの早い段階で大きな貯金ができました。それらは複利的に増えていて、今も僕のキャリアを支え続けてくれています。
論理的思考力だけでは不十分
—— キャリアを振り返り、ビジネスパーソンとして、そしてマーケターとしてご自身を成長させた書籍について教えてください。
まずは、あらゆる思考のベースとなる知的能力「地頭力」について解説した、『地頭力を鍛える』です。
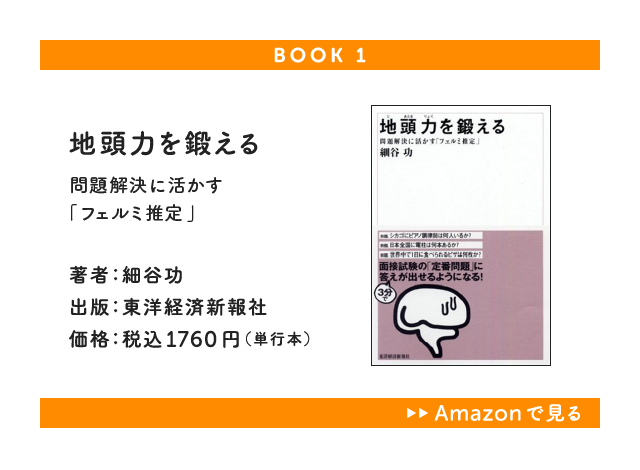
本書では、地頭力は「仮説思考力」「フレームワーク思考力」「抽象化思考力」の3つから構成されるとしています。 実は、ここで紹介される能力は、優れたマーケターの思考そのものです。 まず、「仮説思考力」について。少ない情報で仮説を構築し、スピーディーに結論を出すことの重要性が語られているのですが、これはまさに昨今のマーケターに求められる能力です。 マーケターの役割は、新しい市場をつくることだったり、存在する市場の中で新しい売り上げをつくることだったりするのですが、いずれにせよ未知の領域で成果を上げなければいけません。 そのためには、限られた情報で仮説を構築し、スピーディーに検証を続けていく必要があります。何が正解かは誰もわからないので、“正解らしきもの”を早期に見つけ、試行錯誤しながら本当の正解にたどり着くのが鉄則です。 まさに、書籍で解説されている「仮説思考力」そのものであり、この能力が欠けていると、移り変わりの早いマーケティングの世界で生きていくのは困難だと思っています。

続いて、「フレームワーク思考力」です。「全体から考えること」の重要性が語られているのですが、これもマーケターに求められる能力だと思っています。 マーケティングは、要素が複雑に絡み合って成果を生む仕事なので、全体的な思考がなければ結果が出ません。 仮に商品が売れなかったとして、商品の価格設定が問題なのか、集客の手法が問題なのか、カスタマーサポートの対応が問題なのか、あるいはそのすべてなのか。それを明らかにしない限り、商品がいきなり売れるなんてことはありえないのです。 しかしながら、例えば「商品が売れないなら価格を下げてみよう」といったように、どうしても個別最適で考えてしまう人が少なくありません。 優秀なマーケターの方とお話しする機会がよくあるのですが、これは業界のあるあるです。 そうした意味で、書籍を通じて「フレームワーク思考力」を鍛えるのは、駆け出しの方でなくとも重要なのではないかと思っています。

最後の「抽象化思考力」とは、事象の本質的な特徴を切り出して単純化し、それを再び具体化して個別解を導く思考法です。 「仮説思考力」と「フレームワーク思考力」はマーケターとして働くうえで前提の能力であるのに対し、この「抽象化思考力」は差別化の大きな要因になると考えています。 というのも、論理的に考えて物事を実践するだけでは、結局たどりつく答えが同じになってしまうからです。それでは、飛躍的な成果を上げることはできません。 でも、誰も真似できないような、創造的なアプローチを見つけることができたらどうでしょうか。 僕がマーケターとしてクライアントワークに対応する際は、まったく異なる案件の成功事例からヒントを得て成果を上げることがよくあります。 例えば、「エンジニアの採用がうまくいきません」というお客様がいたときに、建築業界の成功事例を活用して成果を出すといった具合です。 普通ならエンジニア採用の成功事例に学ぶのですが、それではブレイクスルーは起きません。誰もが同じような行動をしますから、結局のところ横並びの成果しか出ないのです。 書籍の中で触れられていますが、地頭力を構成するのは、論理的思考力だけではありません。知的好奇心や直感も重要であることが指摘されていて、僕はその点が特に参考になると思っています。
早さと柔らかさで勝ち抜ける
—— マーケターは若い世代からも人気の職種ですが、成果を上げて活躍するのは、簡単なことではないんですね。
たしかに「少ない情報で仮説を構築する」なんて言われても、最初はなんのこっちゃ分からないですよね。もちろん僕にも、そうした時期がありました。 そんな当時の僕を助けてくれたのが『ゼロ秒思考』です。

本書が言わんとしていることは非常にシンプルで、「時間をかけたからといって、考えが深まるわけではない」ということだと僕は解釈しています。 ビジネスシーンのあるあるですが、「3時間考えました」という人と、「5分で考えました」という人のアウトプットが、さほど変わらないということがあります。3時間考えたからといって、必ずしも質のいいアウトプットが生まれるわけではないのです。 変化の早い時代ですし、競合も少なくありませんから、スピーディーに物事を進められるなら、それに越したことはありません。そのサポートをしてくれるのが、『ゼロ秒思考』です。 ゼロ秒思考というのは、書籍のタイトルであり、「瞬時に現状を認識し、瞬時に課題を整理し、瞬時に解決策を考え、瞬時にどう動くべきか意思決定する」能力のことでもあります。 具体的な内容については、ぜひ書籍を購入していただければと思いますが、本書で紹介されているトレーニングには、「少ない情報で仮説を構築する」能力を鍛えることにもつながります。 若手時代に読んだ本でいえば、『鬼速PDCA』で学んだスキルも、現在のキャリアを支えてくれています。
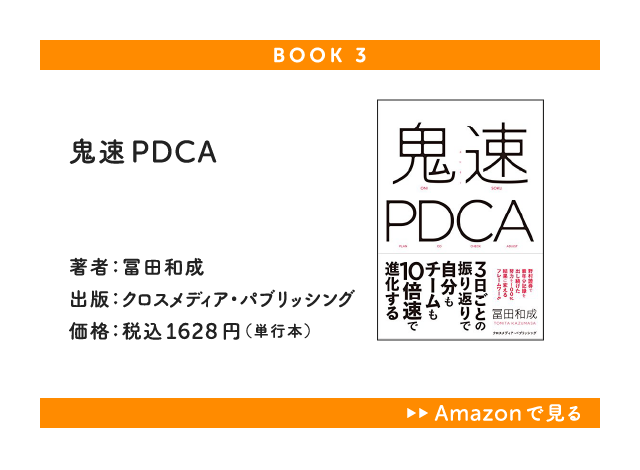
仮説思考力があっても、いかに意思決定スピードが上がっても、ビジネスの世界では「調整」が必要になるんですね。「考え抜いた結果としてAという道を進んでいたけれど、どうやらBという道を進んだ方がよさそうだ」といったケースに度々ぶつかるんです。 『鬼速PDCA』には、調整(Adjust)という考え方があり、こうしたブレを修正していく能力を鍛えてくれます。 一度立てた計画が、そのままうまくいくことは99%あり得ません。外部環境はコロコロと変わるし、内部環境も状況が変化するからです。 だから、完璧な(に思える)計画を立てるより、早く意思決定して柔軟に進路変更をする方がよっぽど重要です。 『鬼速PDCA』では、そのフレームワークを学ぶことができます。プロジェクトを成功させるためにも有用ですし、先々のキャリアを描く意味でも活用できるので、一度読んでおいて損はないと思います。
マーケターは“経営者の目”を持て
—— 駆け出しだった鹿熊さんの成長を支えた書籍を紹介してもらいましたが、マーケターとして飛躍するためのヒントが得られる書籍があれば、そちらも教えてください。
『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』を紹介させていただきます。
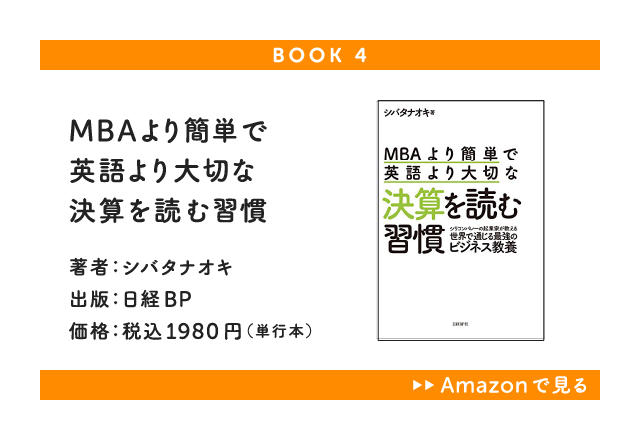
ビジネスの構造を数式で理解することの重要性や、それをするために必要な考え方を解説している基礎的な書籍です。 マーケターとして駆け出しの頃は、例えば広告運用やSNS運用といった手法を極めることから始めると思います。ただ、個々の技術に習熟しても、キャリアにブレイクスルーを起こすには難しいんです。 職人的に生きていくことも可能なのですが、やはり上には上がいます。それよりは、経営的な視点を持ち、何をどう変えれば売り上げをつくれるのかを考えられる方が、マーケターとしての価値を上げやすいというのが僕の考えです。 そのためには、絶対的にビジネスモデルを理解する能力が求められる。『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』は、そのヒントが得られます。 僕の場合、経営視点を身に付けてから、それまでの自分がいかに表面的で一部のデータしか見れていないかを思い知りました。 すると何が起こるかというと、今いる領域からはみ出していかなければいけないことに気が付くんです。 広告の数字だけではダメで、SNSの反響にも目を向けなければいけないし、PRにも関心を持つ必要がある。いくつもの要素が重なってエコノミクスが形成されていることが理解でき、必然的にケイパビリティが広がっていくんです。 すると、冒頭でご説明した「売り上げをつくり、利益を上げる活動をする人」としての、つまりマーケターとしての使命を果たせるようになっていくと思います。 あまりにも著名な書籍ですが、『イシューからはじめよ』にもたくさんの学びをいただきました。

ざっくり要点を説明すると、「問題を解く前に、本当にそれが解くべき問題(イシュー)であるかを見極める」「仮説を持つことで、答えを出し得るイシューになる」「いきなり分析や検証の活動をはじめず、重要なサブイシューで検証する」といったことが説明されています。 話の中で、僕が最も学びになったのは、「自分のスタンスを取る」という点です。 例えば、「外食産業の市場規模はどうなっているか」という単なる設問に答えを見つけるのではなく、「外食産業の市場規模は縮小しつつあるのではないか」という自分なりの仮説を立てれば、オリジナルな戦略が見つかるということを説明しています。 書籍の中でも言われていることですが、常識的なイシューを設定しても、何も新しい価値を生み出すことはできません。他人と同じことばかりしていても、ビジネスの世界で生き残ることはできないのです。 イシューを見つけることが重要だということはもちろん、どのようなイシューを設定するかで得られる答えが変化し、それによって勝敗が決するということを肌覚をもって理解できたことは、マーケターとして生きていくうえでの教訓になりました。

—— 『地頭力を鍛える』で解説されている、知的好奇心や直感の重要性にも通底する話ですね。
みなさんに身近な例でいうと、日本を代表するYouTuberのヒカルさんに投資を依頼した、「究極のブロッコリーと鶏胸肉」が参考になると思います。 同社はもともと、テイクアウトとデリバリーで商品を販売する、いわば王道の戦略で売り上げを伸ばしていました。 もちろんそのまま経営しても事業は成長していたと思いますが、ヒカルさんが商品を「美味しい」と紹介したことをきっかけに、協業を依頼。最終的には、1.5億円を投資してもらうことになりました。 単に資金を調達するとしたら、普通であれば銀行借り入れやファンドを利用します。しかし、日本でも有数の知名度を誇るYouTuberとタッグを組むことで、事業を飛躍的に成長させる意思決定をしたのです。 こうした戦略は、論理的に考えただけでは導き出せなかったものだと思います。 まだ描いた成長を達成できるかどうかは確実ではありませんが、王道を突き進んでいただけではたどり着けなかったかもしれないゴールに、なおかつ短時間で行き着く可能性は十分にある。 このように、売り上げをつくる、つまりマーケターとして活躍するには、右脳と左脳の双方を活用する必要があると思っています。また、継続的な鍛錬が必須です。 本日紹介した5冊は、どれもがそれを鍛えるのに役立つものです。これからマーケターを目指すみなさんには、ぜひ手に取っていただければと思います。

合わせて読む:【リクルート出木場】100倍の結果を出す、成長戦略3つのポイント
取材・文:オバラ ミツフミ、デザイン:石丸恵理、撮影:遠藤素子