SaaSの台頭で注目のカスタマーサクセス
—— 求人が急増している職種の一つに、カスタマーサクセス(CS)があります。どのような背景で注目が集まっているのでしょうか?
いくつかの要因が考えられますが、SaaS(Software as a Service)ビジネスが、世界中で成長していることが一番に挙げられます。
SaaSビジネスは、パッケージのソフトウェアを販売する従来のビジネスモデルとは違い、導入後のチャーンレート(解約率)を下げ、顧客に長期間にわたってサービスを利用してもらうことで成長します。
そのためには、顧客の不満に耳を傾け、サービスを改善して価値を生み出し続け、顧客のビジネスを成功に導く必要があります。このプロセスに責任を負う職業がカスタマーサクセスなので、SaaSビジネスが成長し続ける限り、カスタマーサクセスの需要は絶えないのです。
また、「SaaSビジネスが成長している」ということは、「顧客に選ばれ続けるビジネスモデルに注目が集まっている」ということの示唆でもあります。
顧客満足度を高め、LTV(Life Time Value:1人、あるいは1社の顧客が、生涯を通じて企業にもたらす価値)を最大化することの重要性が浸透しつつあるのも、カスタマーサクセスのニーズを高騰させている要因になっているんです。
—— カスタマーサクセスという職業を語るうえで、「SaaS」や「サブスクリプションモデル」といった枕詞がセットになっている印象があります。こうしたビジネスモデル以外でも、カスタマーサクセスのニーズはあるのでしょうか?
【新】もはや一般教養。なぜ「SaaS」が急拡大しているのか基本的にはBtoBのビジネスと相性が良いのですが、BtoCのビジネスであっても、少なからずニーズがあります。
例えば、BtoCビジネスの代表格である消費財では、顧客に選ばれるためのアクションをマーケティング部署が担当します。
しかし、どのようなアクションを取るべきなのかが、プラクティスとして整っているわけではありません。ここで、カスタマーサクセスの発想やメソッドが生かされるケースは多々あります。

つまり、カスタマーサクセスという職種が誕生する以前から、その役割を担う職種は存在していたわけです。消費財であればマーケティングでしょうし、腕のいいフィールドセールスは、深い顧客理解によって顧客を成功に導いてきました。
近年のカスタマーサクセスの盛り上がりは、概念としては従来から存在していた「顧客に選ばれ続ける」というアプローチを、効果的に実践しようという流れなのです。
カスタマーサクセスはPMFの伝道師
—— 学生からも人気のカスタマーサクセスですが、カスタマーサポートとの違いを明確に説明できないなど、その役割を正確に把握できていない人が少なくない印象があります。カスタマーサクセスという職業を、山田さんの言葉で定義するなら、どのような表現になりますか?
カスタマーサクセスという職種を一言で表現するなら、「プロダクト(サービスも含む)をPMF(Product / Service Market Fit)に導く人」です。
PMFとは、提供している製品やサービスが、顧客の課題を解決できていて、市場に受け入れられている状態を指します。つまり、顧客に選ばれ続けるためには、避けて通れないポイントです。

PMFに至るには、プロダクトに顧客の声を反映し、顧客体験を改善し続けなければいけません。
エンジニアやマーケターも顧客の課題解決に向き合う職種ですが、顧客の一番近くにいるポジションがカスタマーサクセスです。つまり、顧客に近い立場にいるからこそ得られる示唆や、顧客の声が集まってきやすい。
これらを開発サイドやマーケティング部署に届け、プロダクトの機能が向上していくサイクルを生み出せれば、PMFを達成する速度が速まります。カスタマーサクセスの究極的な存在意義は、ここにあるというのが私の解釈です。
顧客に選ばれ続けるには、自社の製品やサービスの価値を正確に把握しなければいけません。
例えば、スターバックスはコーヒーショップですが、彼らが売っているものは「サード・プレイス」と呼ばれる快適な空間です。顧客はコーヒーそのものではなく、コーヒーを片手にリラックスする時間を買っています。
【水口貴文】スターバックスCEOが学んできたブランドビジネスこの「顧客の真のニーズ」を高い解像度で捉えることに、カスタマーサクセスの存在意義があります。それに気が付けば、マーケティングのプロセスも、接客の方法も、あるべき方向に導くことができますから。
ただ、SaaS業界においてすら、このような視点でカスタマーサクセスを捉えるには至っておらず、そのためのプラクティスも未整備です。「PMFの伝道師」としての役割が明確に認知されれば、カスタマーサクセスの重要度はより高まっていくと思います。
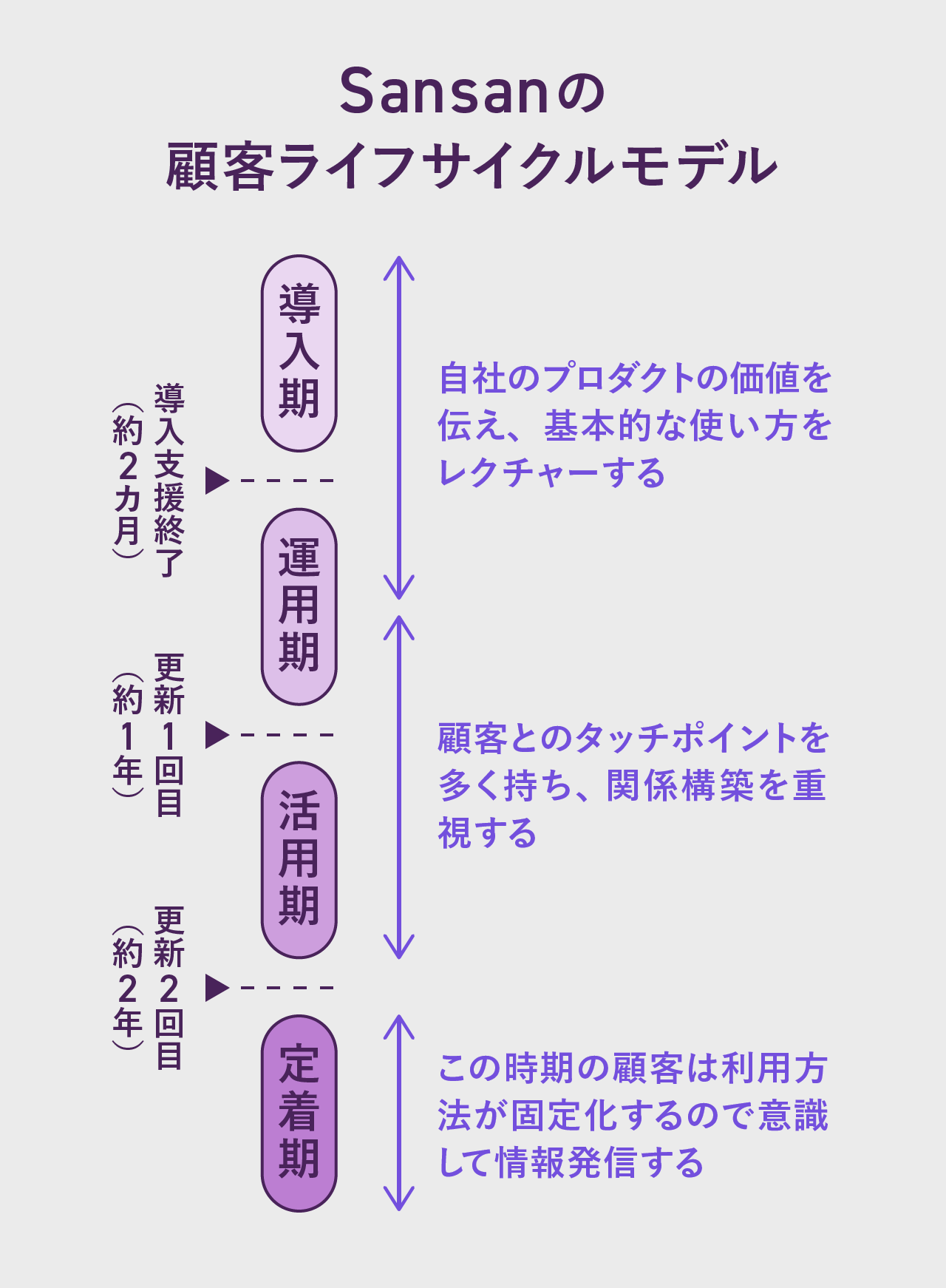
—— 営業プロセスモデルの「The Model」では、カスタマーサクセスは営業職に分類されています。アップセルやクロスセルで売上や利益に貢献するのも役割に感じられますが、それらは本来の目的からそれているのでしょうか?
もちろんそれらも重要な役割ですが、一部であって全てではありません。細かな売上を積み上げることよりも、顧客に選ばれ続けることの方がよっぽど重要だと思います。
ホスピタリティよりも大切な“お母さん感”
—— 山田さんは、ファーストキャリアがゲームのプログラマーだったとお聞きしています。一見まったく異なる職種ですが、カスタマーサクセスになるには、バックグラウンドは関係ないのでしょうか?
既存顧客のフォローを担当していた営業職であれば、業務内容が近いので、即戦力になり得る可能性があります。とはいっても、比較的バックグラウンドを問わない職種です。
私はプログラマーだったので、業務内容が直結していたわけではありません。ただ、しいていえば、プログラマーからシステムエンジニアになり、そのときにプロジェクトマネジメントを経験していたことは役に立ちました。

自社の製品やサービスを導入してもらうには、先方の担当者だけでなく、決裁者や関係者など多くのステークホルダーを巻き込む必要があります。組織が大規模になればなるほど、その傾向は顕著です。
つまり、大きな成果を上げるには細やかな調整が必要になるので、プロジェクトマネジメントスキル、いうなれば“段取り力”がなければいけないのです。
カスタマーサクセスは、ご購入いただいた製品やサービスを一定期間内に定着させる責任があります。導入するまでにダラダラと時間をかけていたら、結局活用されずに終わってしまうこともありますからね。やはり、スピードは大切です。
でも、「忙しいので、具体的な取り組みは1カ月後にお願いします」と顧客に言われてしまうこともあります。そのときに「それでは1カ月後にご連絡します」で終わらせず、担当者とタッグを組み、スムーズな段取りを組むスキルがあれば、売り手と買い手、双方のメリットをなくさずに済むんです。
—— 成果を上げるためのスキルセットとして、段取り力が求められるのですね。顧客の一番近くにいるポジションなので、ホスピタリティが重要だとも思うのですが、どうでしょうか?
顧客の立場で考えられることも大切です。それを失ってしまっては、カスタマーサクセスの役割は果たせません。
その意味で、ホスピタリティは非常に重要なのですが、「優しければいい」というわけでもないんです。

段取り力にも通じる話ですが、導入すれば顧客にメリットがあるとわかっている状態で、「忙しいので1カ月後にお願いします」という依頼を真に受けているようでは、本当の意味で顧客の立場で考えられているとは思えません。
自社のサービスを導入することで、先方の売上が上がったり、業務フローが改善されたりするチャンスを逃してしまうわけですから。
「この1カ月間で体制を整えられなければ、結果的に導入されず、成果を上げることにつながらないと思います」というように、ときには、耳の痛いことをいう勇気も必要です。
——「顧客に寄り添う」ことは、単に御用聞きになるということではないのですね。
僕なりの言葉で表現するなら、カスタマーサクセスには“お母さん感”が求められます。
お母さんに限らず、大人の多くがそうだとは思いますが、「ちゃんと言わないと、この子のためにならない」というお節介をすることがありますよね。子どもは「うるさいなあ」と思うわけですが、実際は従った方がいい結果になるじゃないですか。それと同じです。

あるあるですが、ご購入いただいたにもかかわらず、時間が経つにつれ、顧客がその製品やサービスを導入する意義を失ってしまうことがあります。
これがカスタマーサクセスの大変なところで、インサイドセールスやフィールドセールスの握りが甘いと、自分ではどうしようもできないシーンに出くわすこともあるのです。私も、その事例をいくつも見てきました。
こうした事態を乗り越えるには、相手のニーズを握り直し、スキームを組み直す段取り力が求められます。
もしくは、「勇気あるお節介」で顧客を動かせるかが問われる。ここがカスタマーサクセスの腕の見せ所で、うまくいけば、顧客と自社の成果を同時に実現することができます。
「ホスピタリティ」の意味を誤解した結果、成果を残せない人もいますから、能動的な姿勢が求められるという事実は知っておいてほしいです。
カスタマーサクセスとして活躍する人の特徴
—— 山田さんから見て、成果を上げるカスタマーサクセスに共通点はありますか?
カスタマーサクセスは、一撃で数千万円、数億円の売上をつくる職種ではないので、なにをKPI(組織の目標を達成するための重要な業績評価の指標)に置くのかを決めるのは簡単ではありません。実際、組織によってまちまちです。
そうした前提のうえで、私が優秀だと思うのは「やめさせないカスタマーサクセス」です。つまり、担当する顧客が解約をしないことに、カスタマーサクセスの手腕が表れると思っています。

例えば、お気に入りのファッションブランドがある人は少なくありませんよね。「値段が高くても、好きだから買う」という意思を持っている人です。
でも、その人たちがファストファッションを買わないかといえば、そうではない。「なんだかんだ言って、コスパがいいよね」と、アンダーウェアやTシャツを買ってくれることがあります。
ファストファッション側としては、アウターからパンツまで、すべてのアイテムを買ってもらっているわけではないので、大きな売上をつくれているわけではない。けれど、顧客の頭の片隅に存在し続け、継続的に売上をつくれているわけです。
—— 頭の片隅に存在しているだけで、「カスタマーサクセスしている」ということですね。
カスタマーサクセスの人たちに話を聞くと、「自分が支援をした結果、お客様が心から喜んでいる姿が、私の仕事のやりがいです」と答える人が多くいます。とても素晴らしいことであり、それがモチベーションになっているのは、うそ偽りのない事実でしょう。
とはいえ、プロフェッショナルとして仕事に向き合っている人は、NPS(Net Promoter Score:企業やブランドに対してどれくらいの愛着や信頼があるかを測る指標)が非常に高い顧客だけではなく、「やめないでいてくれる」という弱いつながりに目を向けます。

どの顧客が、どれくらいの金額を発注しているのかを可視化するツールも存在するので、自社と相性の良い顧客は一目でわかります。
そこに目が行く気持ちはわかりますし、発注金額の大きい企業に時間を割くのは当然ですが、視野を広く持つ必要はあるでしょう。
「発注金額は小さくとも、継続利用してくれる顧客」のほうが大多数ですから。
繰り返しになりますが、カスタマーサクセスは、一撃で数千万円、数億円の売上をつくる職種ではありません。だからこそ、顧客に好奇心を持って接し、コツコツと成功体験を一緒に積んでいける人に、カスタマーサクセスの素養があるといえます。
人気本『カスタマーサクセス実行戦略』を書いたわけ
—— SaaSビジネスの成長によって、カスタマーサクセスの需要が増え続けると、それを目指す若い世代も増えていくと思います。今後、カスタマーサクセスの市場価値は高まっていくのでしょうか?
日本のカスタマーサクセスは黎明期で、正しいプラクティスが存在するわけではありません。まだまだ解明できていない点が多くあるので、可能性にあふれた職種だと思います。
欧米諸国に比べると、職業としていまだ正しい評価がされていないとも思うので、いずれは市場価値も高くなっていくでしょう。
私は現場を離れてしまいましたが、それでもカスタマーサクセスを主軸に仕事をつくっているのは、可能性を感じるからです。

「いい営業とは?」と問われると、「売る営業です」という大多数が納得する回答がありますが、「いいカスタマーサクセスとは?」という問いには、しっくりくる答えがありません。
私はその問いに誰もが納得する答えを見つけたいですし、その過程が面白くて、カスタマーサクセスを世の中に広めることをミッションに活動しています。
個人的な話になりますが、2020年に「カスタマーサクセス」という概念を実行戦略に落とし込んだ、『カスタマーサクセス実行戦略』という書籍を出版しました。筆を執った理由は、「型をつくることで、発展させられる」と考えたからです。
型をつくると、真似してくれる人がいれば、アレンジしたり、否定する人もいます。つまり、なんにせよ、「いいカスタマーサクセスとは?」という議論が深まっていくんです。
このインタビューでお答えした内容は、私が考える現時点の正解ですが、記事を読んだことがきっかけで、よりよい定義や考えが生まれるかもしれません。
私の話が、まだまだ黎明期のカスタマーサクセスがさらに盛り上がり、カスタマーサクセスの価値が正しく認識されていくきっかけになれば、それほどうれしいことはありません。

合わせて読む:カスタマーサクセスの若手社員は「どんな1日を過ごしているのか?」
取材・文:オバラ ミツフミ、編集:伊藤健吾、取材協力:齋藤知治、鈴木朋宏、デザイン:浅野春美、撮影:遠藤素子