1. ワークショップで不安を払拭
—— 五ヶ市さんがGoodpatch Anywhereに参画することになった経緯を教えてください。
子どもが産まれたのをきっかけに、東京から故郷の北海道に戻ることにしたのですが、なかなかUX関連の仕事をやれる会社がなくて......。
地元のシンクタンクやEC企業に入ってUXの仕事を“開拓”しようとしたものの、うまくいかなかったんですね。
それでフリーランスとしてUX関連の仕事ができないか?と考えていた頃、グッドパッチ社長の土屋(尚史さん)のSNS投稿を見かけました。
そこには「フルリモートのデザイン組織をつくる」と書いてあって、「これしかない」とすぐさまエントリーしました。
現在のGoodpatch Anywhereには、フリーランスや業務委託といった就業形態も居住地もさまざまなメンバーがそろっていますが、私は初期メンバーとしてチーム運営の土台づくりから携わっています。
なので、リモート案件で使うツール群も、私自身が試しながら活用法を考えてきました。
〈よく使うツール群〉
例えば、今ではデザイナー界隈でよく使われるようになった「Figma(フィグマ)」は、Goodpatch Anywhereが立ち上がった2018年頃から使い始めました。
立ち上げ後すぐ、フルリモートで働くクライアントとお取引する機会に恵まれて、最初だけオフラインでワークショップ(はじめの顔合わせ)をやりましょうとなった時、付箋や模造紙を手にした私たちに「Figmaが便利だよ」と教えてもらったんです。
私たちもそこから、「こういうツールがあるなら使い方も広がりそうだ」と活用法を考え、フルリモートが一気に浸透していきました。
—— クライアントとやりとりをする際、他にはどんなツールを使っていますか?
最も使うのは「miro(ミロ)」ですね。オンラインホワイトボードのツールとして、全ての情報を1カ所にまとめることができるので便利です。
カスタマージャーニーマップや先方の企画書、そこから抽出されるWebサイトへの掲載情報、ナビゲーション構造、ワイヤーフレームといった、デザインプロジェクトに必要な要素を1つの画面に書き出すことができます。
—— Figmaやmiroは、デザイナー界隈には広まっているものの、使ったことがないというクライアントもいるのでは?
そうですね。なので、プロジェクトを始める時はほぼ必ず、私たちと一緒にツールに触れていただくワークショップを行います。
画面越しに「カーソルを動かしますよ」と声をかけ、「私が動かすカーソルについて来てください」と作業をなぞってもらうんです。
画面に映るアルファベットを動かしながら、「まずPに行き、次はDです。その次はC。もう一回ついてきてください。はい、Aに行ってPDCAを学べましたね。おめでとうございます」といったやり取りをしながら、お客さまにも覚えてもらっています。
もちろん、動かし方だけでなく、データやファイルを追加・削除する体験もしていただきます。
すると、だんだん「あ、パワーポイントと一緒じゃん」となる(笑)。多くの場合、不安は「ツールが難しそう」ということに集約され、画面越しでも対面で話して説明すれば簡単に慣れるものです。
逆に言うと、プロジェクトをご一緒する最初の段階で、いかにリモートワークへの抵抗感を減らすかが鍵を握るということです。
2. 自己開示とリアクションが鍵
—— チーム運営における「抵抗感」はどうでしたか?フリーランスや業務委託の方々だけで構成されるGoodpatch Anywhereの場合、リモートでチームを運営するのがいっそう難しいのでは?
この話題はよく聞かれるのですが、チーム運営でもリモートによる壁はほとんどありませんでした。
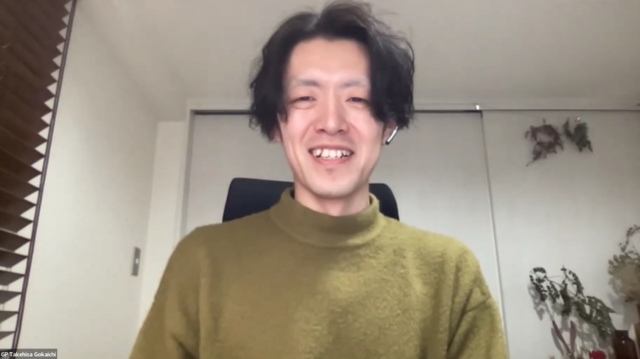
最も大事なのは「リモートのせいにしない」というマインドセットをチーム内に広めること。そのために、よく使われる言葉ではありますが、私たちは心理的安全性について立ち上げ初期から本気で取り組んできました。
UXデザインでは、リサーチからプロトタイピング、ユーザーインタビュー、運用の改善を続けながら、ユーザーを知り、学びを蓄積していきます。
インプットした学びをプロダクトに反映させていくには、「こっちのほうがいい」とメンバー誰もが言い合える状態をつくらなければなりません。そのためには心理的安全性が不可欠なのです。
“ゆるふわ”コミュニケーションだと敬遠されたりもする心理的安全性ですが、私たちは伝えるべきリスクを伝えるため、そして学びを積み上げるための姿勢として、必要な要素だと捉えています。

何かしらのリスクを感じた時にしっかりと本音で話せるか。より良いものがあると思った時に意見を言えるかどうか。私たちは難しい選択をしなければならない時でも、リスペクトがあれば言い合えると考えています。
こういうマインドセットへの理解を得るため、新たなメンバーには、はじめに心理的安全性を重視したオンボーディングを行うようにしています。
—— 具体的にどんなオンボーディングを行うのですか?
概要は、以前とある勉強会で発表した際の資料に記したので、下のスライドをご覧いただけたら幸いです。
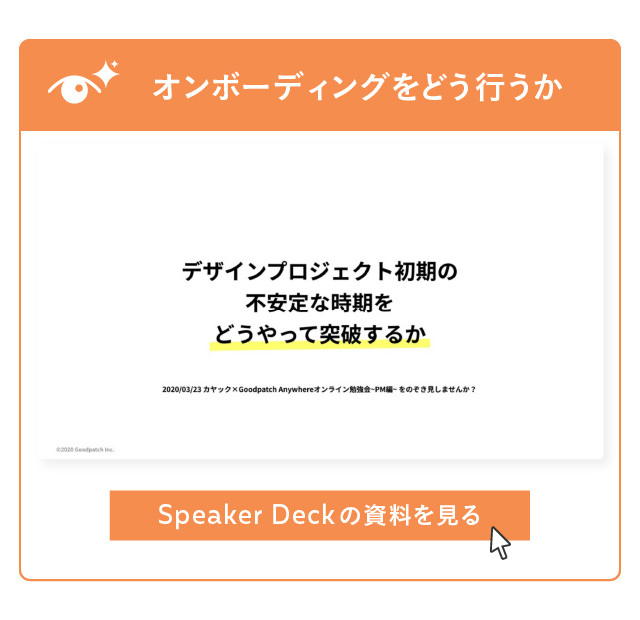
中には、プロジェクト開始直後から心理的安全性を高める取り組みとして、体験型のイベントも取り入れています。
その一つが、メンバー同士の「ポートフォリオ見せ合いっこ会」です。
クリエイターとして開発に携わってきたプロダクトや、過去に手掛けた作品を見せ合うのですが、初対面の同業者に見せるのは意外と勇気がいるものなんですね。
私自身も、できれば自分のポートフォリオを他人には見せたくありません。Goodpatch Anywhereのメンバーは強者ぞろいなので、「マネージャーなのにこんなレベルなのか」と言われかねませんから(笑)。
—— それでも自己開示することに意味があると?
そうですね、まさに「自己開示」という感覚が近いと思います。
もう一つの狙いとしては、スキルセットや経歴、こだわりなどを開示し合うことで、正しく互いを知ろうということです。
これ以外に「Wevox values card」や「Monica」のような価値観を自己開示できるコミュニケーションツールを活用したり、メンバー同士で1 on 1を自由にできる「ご指名1 on 1制度」といった仕組みを積極的に取り入れています。
また、Slackなどで発言しやすいよう、リアクションは積極的かつポジティブにするように心掛けています。

小さなことの積み重ねですが、こういう配慮が心理的安全性を高めると実感しています。
3. 率先してセカンドフォロワーになる
—— そんなオンボーディングを経た後は、どのようにプロジェクトを進めていくのでしょう?
メンバーの強みや得意分野に違いがある上、中には海外在住の方もいて働く時間は人それぞれです。なので、チーム編成はこれらの要素を意識して行うように心掛けています。
とはいえ、メンバーがそろって作業をする時間も意識的に設けるようにしています。みんなで集まって一緒に作業する時間は、一体感を生む上でとても大切だと考えているからです。
ツールは「Discord(ディスコード)」やSlackのハドルミーティング、Zoomなどを使用します。共同作業ではパートナーを巻き込むこともたびたびあります。
また、日報・週報的に「KPT(ケプト)」の実施も推奨しています。
〈KPTとは〉
業務を振り返りながら
Keep(できたこと・継続すること)
Problem(改善するべき問題点)
Try(挑戦したいこと)
の3つの要素を洗い出し、仕事やプロジェクトの改善につなげていく方法論。
これを日報・週報代わりにすることで、チーム内で具体的な次のアクションを引き出すきっかけにするのです。
他にも週次の全体レビュー会や隔月で行う360度フィードバックなど、メンバーの状況をシェアし合うタイミングは複数用意しています。
—— はじめにマインドセットを理解してもらい、その後も心理的安全性をキープし続ける仕組みづくりをしているのですね。
メンバーの目線を合わせるタイミングがたくさんあるからこそ、プロジェクトがスタートしてからも問題が起こりにくい。そんなイメージです。
これらは、業務が滞りなく進んでいる要素の30%くらいを占めていると思います。
週次のレビュー会は、私たちマネージャー陣が引っ張る形ではなく現場メンバーで運営するなど、ボトムアップを意識している点もうまく回っている要因と言えそうです。
—— 先ほど「メンバーがそろって作業をする時間も意識的に設ける」と話していましたが、この効果についても詳しく教えてください。
テーマとしては「不信感を生まないため」ですね。
途中経過のシェアはもちろんですが、一緒に作業をしているとツーカーで分かることがどんどんと増えていくものです。
私自身、かつて開発会社でエンジニアとともに働いていたこともあり、アジャイル開発の手法は体に染み付いています。
当時は今ほどツールが整っておらず、リアルタイムにすべてを共有できませんでした。そんな中でも、毎日15分ほど顔を合わせる時間を設けていたので、進行状況の共有や困りごとをその場で話し合う習慣が身に付いているんです。
—— リモートワークだと、知らない間にメンバーそれぞれが見えない努力をしている場合もあります。そこに光を当てる意味でも大切なプロセスですね。
おっしゃる通りで、もし、何かしらの良い「見えない努力」があったら、拾い上げてチーム全体に広めることにも気を配っています。
これは明文化しているわけではありませんが、Goodpatch Anywhereは「セカンドフォロワー」という考え方を大事にしているんですね。
セカンドフォロワーの重要性は、TED Talksで有名なデレク・シヴァーズの「社会運動はどうやって起こすか(How to start a movement)」を見ていただくと一発で伝わるかと思います(下の動画参照)。

大勢が集まる広場で1人、突然「裸踊りを始めた男」は周囲に嘲笑されるけれど、最初のフォロワーが現れた途端、彼は“踊る阿呆”からリーダーに変わる。
私たちも、誰かが発信した時は必ずフォローするというカルチャーをつくるように意識してきました。
反応してくれる2人目がいると分かっていれば、1人目になりやすい。そんな好循環が生まれるからです。
Goodpatch Anywhereが立ち上がってから最初の半年ほどは、人数が少なかったこともあり、「我々が率先してセカンドフォロワーになるべきだよね」という話をよくしていました。
その結果として、今はカルチャーとして明文化しなくても、初期メンバーが行動で示すことで自然と新しいメンバーにも浸透しています。
—— チームのカルチャーは明文化して伝えるのが大切と考えていましたが、不文律のようなものを態度で示すのも重要だと?
その通りです。言語化したからといって、それだけで伝わるわけでもないので、実践によって理解してもらうのが大切です。
ただ、メンバーが増えて一緒に作業する時間やタイミングが減ると、浸透スピードが落ちる可能性があります。
リモートワークではよく「雑談が減った」と言われるので、オンラインでも雑談できる環境をつくるなど、コミュニケーションのすべてをデザインする大変さはリモートならではと言えます。
リモートワークで大切なのは文化
—— 五ヶ市さんは心理的安全性やチーム運営の方法論を幅広く勉強していると感じます。これからリモートチームの運営を改善していきたいと考えている人に向けて、おすすめの情報源や書籍はありますか?
これまで雑多に情報収集してきたので、「これ!」というイチオシを選ぶのは難しいですが......。
しいて挙げるなら、Googleをはじめとする様々な組織が実践してきた働き方の先進事例を集めたサイト「Google re:Work」ですかね。

書籍だと、『プレイフル・シンキング』が私にとって非常に重要な本です。
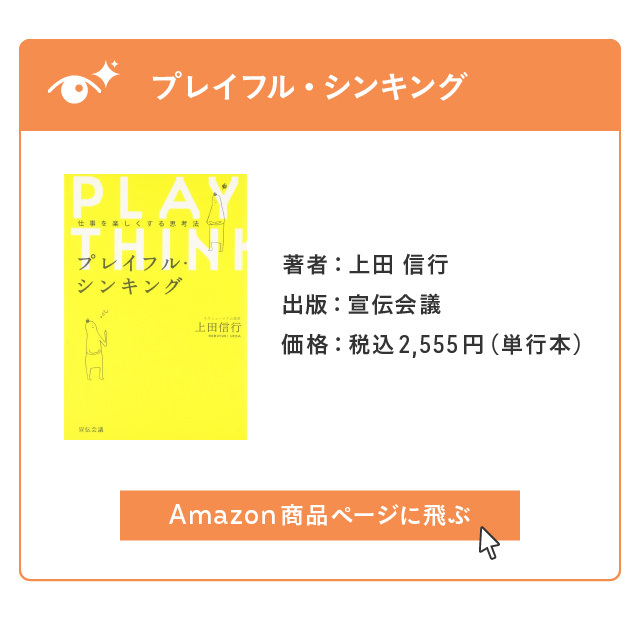
本書はラーニングデザインを研究する同志社女子大学の上田信行教授が著者で、努力の先に夢中があり、夢中である状態のほうが学習効果も高いため、いかに仕事に夢中になれるかが記されています。
—— 最後に、五ヶ市さん自身のリモートワークにおけるこだわりを聞かせてください。
まずプライベートと仕事の垣根をはっきりさせないことです。例えば、「宅急便が届いたから、少し席を外します」などは、日常茶飯事なので全く気になりません。
聞くだけのミーティングであれば、カメラとマイクをミュートにして参加するなど、メンバーも仕事に影響のない範囲で家事を並行し、私たちもそれらについて詮索することは特にありません。
Goodpatch Anywhereには、子育てや介護をしているメンバーもいれば、別の仕事を持っているメンバーもいます。そもそも居住地も世界中に散らばり、ポーランドやカナダに住んでいるメンバーもいるため、時間が合わないことも当たり前にあります。
普通の企業であれば、定時に出社させ、遅刻するのであれば必ず理由も報告するものだと思いますが、私たちは「この時間は動けません」と宣言するだけで済みます。
それぞれが時間の裁量を持って仕事するのは当然だという考えで、一方「この時間は調整してくれ」と伝えたり、どんな時間であってもメンションが飛んでくるなど、遠慮がないというカルチャーでもあります。
「あなたの時間はあなたの時間だから、自由にしていい」「でも、案件上、この時間は頑張ろう」と言い合いながら、落としどころを見つけるコミュニケーションとも言えます。
後は、ソーシャルプレゼンスという言葉があるように、自分自身の可視化というか、今やっていることをきちんと示す工夫も問われます。
他人を褒めたり、ユーモアを見せたり、自分語りをしたり。SlackやFigma、miroといったツール上での返事が早かったり、そこへの登場頻度が多かったりと、ソーシャルプレゼンスを高めるための手法は様々です。
1人の人間が実在する感覚を持てるかどうかが重要なことに、リアルでもリモートでも変わりはないでしょうね。
.jpeg)
合わせて読む:リモートワーク時代の「良いマネジメント」とは
取材・編集:伊藤健吾、文:小谷紘友、取材協力:日野空斗、デザイン:岩城 ユリエ、撮影:五ヶ市 壮央(本人提供)