人事界隈で話題になった「トレンドが分かる」記事

1. 電機大手、「ジョブ型」加速 一般社員に拡大、人材獲得激化(時事通信社:2022年2月17日)
2. 日立製作所、全社員ジョブ型に 社外にも必要スキル公表(日本経済新聞:2022年1月10日)
〈注目した理由〉
ジョブ型ブームが到来し、社会が一斉に「組織のOS」を変えようとしています。
しかし、NewsPicksで【1】の記事のPickコメントにも書きましたが(詳細)、ジョブ型の理解が「部分的」であるため、
「ジョブ型で専門性を高めると言っているのに、定期人事異動は残す」
「ジョブ型の給与制度にするはずなのに、学術的専門性や配属にかかわらず新卒採用社の年収は一律」
などと、チグハグな制度設計をしようとしている企業も見受けられます。
本来、人事制度は自社の歴史や社風、産業特性、掲げるパーパスに沿って考える必要があります。ジョブ型の人事制度を導入する際も唯一解があるわけではなく、自社組織の根本的な課題は何か?から考えるのが大切です。
人事担当者がこの議論を怠ると、メンバーシップ型の人事制度(一律昇給・定年退職など)のまま、いびつな「ジャパニーズ・ジョブ型」が広まってしまう懸念もあると感じています。
安田さんが「人事の未来」を考えさせられた記事
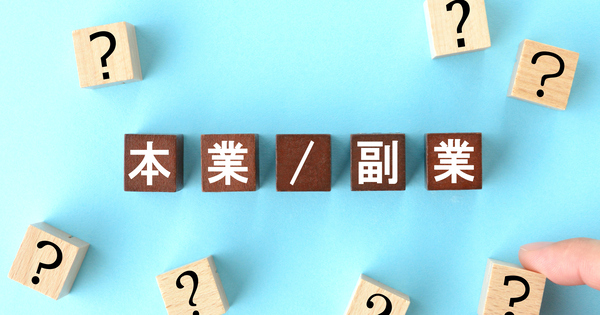
3. 【衝撃】三井住友海上、管理職に「副業」「出向」を求める理由(NewsPicks:2022年3月31日)
4. 人生100年時代に「ずっと稼げる人材」でいるために、選ぶべき業種と必要なスキルは何か(PRESIDENT WOMAN Online:2021年11月7日)
〈注目した理由〉
副業の位置付けは良い方向に変わりつつあります。
キャリアアップのためのスキル・ケイパビリティを身に付けたいという働き手の傾向は顕著になり、【3】で取り上げた三井住友海上のように副業を促進するケースも増えていくかもしれません。
しかし、これも「他社が始めているから我々も」と紋切り型に捉えるのは間違いです。人事担当者は他社事例が大好きなので、なおさら注意が必要でしょう。
副業大礼賛時代が訪れ、「おい、もっとマジメに副業しろ」などというトンチンカンな会話が生まれたりしないように、自社のスタンスをしっかり制度に落とす工夫が求められます。
また、【4】のPRESIDENT WOMAN Onlineの記事について追記すると「なぜどこにも英語の重要性が説かれてないんだろう」というシンプルな疑問があります。
英語ができるだけで年収は100万円以上変わりますし、スモールビジネスや副業においても英語ができるだけでチャンスの数が断然違います。
多様性の深耕という意味でも重要です。こんな世の中だからこそ英語は必須だと感じます。
最近、個人的に気になった注目記事

5. 【挑戦】時価総3倍、「サステナビリティ経営」成功の秘訣(NewsPicks:2021年12月31日)
6. ラッシュは一部のSNSからサインアウトします(ラッシュジャパン:2021年11月22日)
〈注目した理由〉
「パーパス経営」は、ジョブ型と並んで2022年・流行語番付、西の横綱が期待されるバズワードです。
【5】の記事で紹介したポール・ポルマンさんの言葉は、企業の価値観と個人の価値観が一致していることの重要性を最も明確に表しています。
企業が経営理念をはっきりとさせた「パーパス経営」を行うことが、社員に自主性を持った「パーパス人間」に成長してもらう助けにもつながるのではないでしょうか。人は環境に染まっていくものだからです。
私自身、【6】でピックアップしたラッシュで数年間働いたことで、生き方そのものの価値観が変わりました。
NewsPicksで同社の“SNS断ち”に対するコメントを見ると(詳細)、「良く練られたブランディング戦略だ」などと書いている方もいらっしゃいますが、ラッシュはビジネス面でプラスがあるとは1ミリも考えていません。単純に、自分たちのパーパスに従った結果です。
パーパス経営とは、要するにこういうことだという好例でしょう。
「ニュースとの接し方」安田さんのやり方
日頃のニュースは、TwitterやFacebookのタイムライン(つまりフォローしている方々の視点)のほか、Yahoo!ニュース、ハフポストなどのメディアでチェックしています。
ただ、SNSは自分の知り合いコミュニティの中で話題になるニュースしか流れてこないため、間違いなく情報が偏ります。そのため、NewsPicksのコメントを見ながら、裏取り・答え合わせをすることも多いです。
NewsPicksはニュースのカテゴリーが分かれており、見たいニュースが分かりやすくて便利です。コメントでつかんだ一般的な理解や反応は、社員や顧客へのアプローチの参考にしています。

合わせて読む:広告費ゼロでブランドのファンを増やす「LUSH」驚異のPR術
構成:藤原環生、編集:伊藤健吾、デザイン:岩城 ユリエ、撮影:安田雅彦(本人提供)