例文のコピペでは見つからない「働く動機」
3月に一般解禁となった就職活動。企業によって選考フローはさまざまだが、6月からの「選考開始」に向けて、履歴書・エントリーシートの提出や面接準備を進める就活生が増えている。
その際に必ず考えるのが、応募企業への志望動機。徐々に広まるジョブ型就活で、希望の職種を選ぶ際も、「なぜこの仕事に就きたいのか?」を整理しておく必要がある。
いわゆる「ガクチカ(学生時代に力を入れた経験)」に絡めながらアピールする人や、自分なりに感じる魅力を訥々と語る人、はては例文をググってアレンジする人まで。
ただ、志望理由の書き方・伝え方で最も大事なのは、「自分の言葉」で「採用担当者の心に残る」動機を伝えることだ。
日テレのアナウンサーで、同社の新卒採用にもかかわる森圭介さんは、下の記事でこうアドバイスしている。
(森さん自身が面接での自己紹介を実演した後で)まずは冒頭で「自分がどんな人なのか?」を伝えようと考えました。自分のビジョンというか、なぜ伝える仕事をやりたいのかという志望動機を、自分のルーツと絡めて説明した格好です。
まず自分のビジョンを伝える
次にその正当性を説明する
最後に名前を言う
気をつけたのはこれだけです。
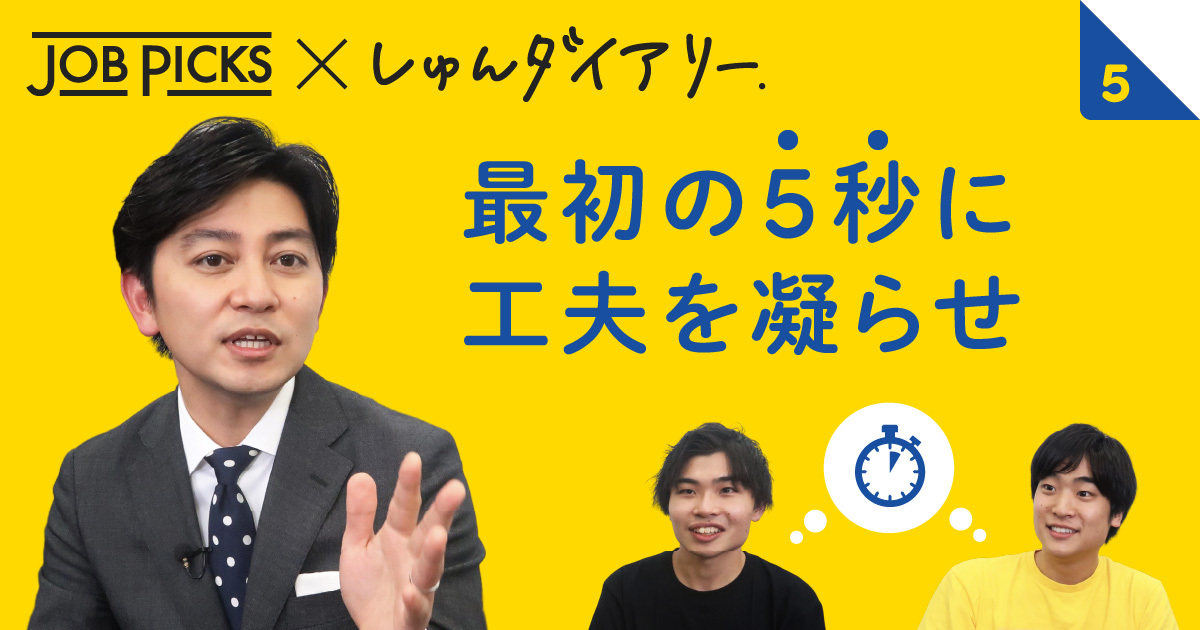
【10分動画】面接プレゼンで「心をつかむ伝え方」日テレ森アナが伝授
国内外の有名企業数社で人事を務めた経験を持つWe Are The People代表の安田雅彦さんも、面接で志望動機を語る際のアドバイスを次のように話している。
どんな質問に対しても、本音で、事実に基づいて答えるのが大事です。面接官は、過去にあったことから、その人の行動特性を知りたいんですよね。
ポイントは、自分の原動力が、応募先の方向性、優先順位にマッチしていることです。

【就活動画】面接で聞かれる「難問・奇問」かしこい答え方教えます
では、2人が話す「自分のビジョン」「自分の原動力」を、どう言語化していけばいいのか。
ここでは、JobPicksの先輩ロールモデルが投稿している経験談を参考に、就活でどんな志望動機を語ったのかを3つのパターン別に分析していく。
自分の強みや熱意を、どう言葉にしていったのか?という思考のプロセスを参考にしてほしい(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。
【1】将来の目標+適性を伝える
はじめに紹介するのは、志望動機の王道とも言える「将来への布石」系の経験談。明確な目標がある人、将来やりたいことがある人が参考にできるパターンだ。
■新卒でアクセンチュアに就職→その後に起業した横山俊さん
横山さんは、学生時代に描いた「将来は起業したい」という思いをかなえるため、コンサルティング企業のアクセンチュアに就職。志望動機は大きく2つあったという。
起業家への武者修行
学生時代から、将来は起業家を目指したいと考えていた。一方で、新卒でいきなりスタートアップに挑戦するほどの自信がなく、経営視点や事業戦略に関する知識・経験を養うため、戦略コンサルタントを志望した。 戦略コンサルタントの中で、アクセンチュアを志望したのは大きく2つの理由があった。 ①よりエキサイティングな案件が舞い込む環境 これからは、事業戦略や経営を語る上でテクノロジーは不可欠だと認識していた。様々ある戦略コンサルティングファームの中で、最もテクノロジーに対して先行投資をしていると感じたのがアクセンチュアであったため、アクセンチュアを志望した ②社風へのマッチ 実際にお会いした社員を通して、固すぎない人柄や、風通しのよさなどが自分いフィットしている、と感じた点も大きい
願望を伝えるだけでは一方通行になるが、注目すべきは応募企業とのフィット感も合わせて伝えたことだろう。
「実際にお会いした社員を通して、固すぎない人柄や、風通しのよさなどが自分にフィットしている」と感じたことを、素直に伝えたことが、採用担当者に「弊社に合うかも」というプラスの印象を残したと思われる。
■NTT東日本に就職した一場杏里紗さん
「何かの形で街づくりに携われないか」。漠然とそんな思いを抱いていた一場さんは、NTT東日本が展開しているスマートシティの取り組みに興味を持ち、同社に応募。
今後成長していくであろう「通信」分野で、広く影響力のある仕事に就きたい。
企業選びの軸として、「社会において遍く必要とされる、縁の下の力持ちのような分野で仕事をしていきたい」という想いがありました。それに加えて「通信」という分野は、目に見えないけれども今後必ず必要になるという見通しがはっきりしている分野だと思いました。 昨今のコロナ禍も当時就活していた時はまったく想像だにしていなかった事象が現実に起きてしまっていますが、「通信」はむしろより求められている存在になっています。 また、何かの形で街づくりに携われないかという気持ちもあったので、NTT東日本でもスマートシティの取り組みに関わり始めているということを聞いたのも決め手になりました。 「営業」という職種については、お客様にもっとも近い存在として、企業が生き残る上で重要な顧客志向の知見を得るには避けては通れない職種だと感じています。まずは営業で顧客志向を学ぶことで、今後の経営企画やサービス開発にも必ず生きると思っています。
加えて、学生時代に合唱サークルやゼミでリーダー役を担う中、「泥くさい調整役に回ったり、メンバーの細やかなケアをすることが得意なほうだ」と自己分析していたこともあり、通信インフラで社会を支える仕事が向いていると考えたそうだ(下のインタビュー記事参照)。

【NTT東日本】経営を志す私が、現場に立ち続ける理由
一場さんも、横山さんと同じく「目標と適性」をセットで伝えていたのがポイントだ。ぜひ参考にしてほしい。
【2】生い立ちと課題解決を結び付ける
続いて紹介するのは、幼少期からの思いを志望動機に絡めて伝えるパターンだ。
ただ「これがやりたい」という思いを伝えるのではなく、小さな頃から感じていた疑問や課題を解消したいという動機が強みの一つになっている。
あらゆる仕事は、課題解決のためにある。この原理原則に則った志望動機とも言えるだろう。
■建築系の学部卒→Webサービス制作の仕事を選んだ神村将志さん
神村さんが就職時に考えた「働く動機」は、地元・静岡への思いだったそうだ。
出身地の魅力を伝えたい、地域の発展に貢献したい。けれど、自分独りの力では難しい。そう考えた結果、まず「広く物事を伝える技術」を学ぶことがモチベーションになっていった。
そこでWeb制作会社に就職する道を選んだという。
私の地元にきっと人は来ない、と思ったこと。
静岡の田舎の出身です。 太平洋に面した広い砂浜があり、港では新鮮な
こうしてWebサイトのUI設計という「情報を伝える手段」を学んだ後は、「情報の伝え方」そのものを学びたくなったと語る神村さんは(下の記事参照)、現在アパレルブランド「マザーハウス」のコミュニケーションデザイン部門で執行役員になっている。

マザーハウスの「すごい顧客体験づくり」試行錯誤を支えた良書5選
就職時の思いが、課題解決のスキルを磨く原動力になっている好例だ。
■「地方育ち」を広報の志望動機に変えた水野理菜さん
新卒で「マナラ化粧品」を展開するランクアップに就職した水野さんも、地方で育ったという原体験を仕事選びの軸に変えた1人だ。
水野さんの場合は、広報を志望する際、次のような理由で「伝えるスキルを身に付けたい」と語ったそうだ。
どんな仕事でも必要なスキル
今でもテレビなどの大型メディアが持つ影響力は 計り知れないものがありますが、 インスタグラムやツイッターなど SNSで全個人が広報になりうる時代になっていますよね。 仮に違う会社に転職するにしても、 何か自分で事業を立ち上げるにしても、 ”知ってもらうこと”はどんなビジネスにおいても必要だと思います。 しかしどのように発信したら伝わるのか、 そもそもどこに向けて発信したらよいのか、 わからずに埋もれているものは多いのではないかと思います。 私は地方出身者ですが、地方にこそ、 すごく価値があるのにうまく発信ができずに、 その価値を地元の人にすら理解されていないものが 多いように感じながら育ってきました。 やり方は一つじゃなく無限に広がっていて、 社会に必要とされる発信の仕方を知ることで 救われる文化や企業や地方はあるのだと思っています。 「発信する力」を学んで、自分が今まで 幸せを分けてもらってきたものに返していきたい というのが、広報部で学びたいことです。
■デザインへの興味→UX設計の仕事に就いた黒崎由華さん
黒崎さんが就職時に抱いていた「働くことへの初期衝動」は、多くの人も共感できるものだろう。小さな頃に好きだったことを仕事にしたい、というものだからだ。
ユーザー中心の考え方が自分が今まで大切にしてきた軸と通じていたから
小さい頃から絵を描いて友達や両親に喜んでもらうことが好きでした。 例えば絵を描くにしても、「描くのは楽しいけど、あの人(たち)が喜んでくれたらもっと嬉しいな」という考え方が根底にあり、描いて終わることは少なく誰かに見せたり反応をもらうことがモチベーションとなっていました。 芸術大学への道を志したのはその原体験がきっかけとなっていて、デザイン学部にいきたいと思ったのは「自分が生み出すクリエイティブの先には常に人がいてほしい」という思いがあったためです。 その後、UCD(ユーザー中心設計)やHCD(人間中心設計)という概念を学んだとき「まさしくそれだ!」と思ったことは今でも印象に残っています。 設計者がユーザーにデザインを押し付けたり、逆にユーザーの意見を一方的にプロダクトに反映させたりする関係性ではなく、私たちは常にユーザーと協力関係にあることが望ましいと考えます。 そういった考え方を大切にしながら、今後もお仕事に臨んでいきたいです。
この思いで、ファーストキャリアではジュエリーデザイナーの仕事を選んだ黒崎さん。その後「より将来性のある産業で仕事をしたい」と考えるようになり(下の記事参照)、VRソリューションを展開するジョリーグッドに転職している。
UXデザインに専門領域を広げながら、「誰かに見せたり反応をもらうことがモチベーション」という働く動機を維持している。

SNSを活用して5職種マスター、20代で実現する変幻自在キャリア
【3】就労体験で見つけた「自分の性分」を伝える
志望動機をアピールする際、自分のモチベーションの源泉と合致するからと伝える人は多いだろう。
だが、説得力を持ってそれを伝えるためには、アルバイトやインターンなどで「実際に働いてみた結果、自己理解が進んだ」と伝えるのがベターだ。
ここでは、上手に体験談と志望動機を連動させたロールモデルの事例を紹介しよう。
■就活中の自己分析で軌道修正した沼田 暁さん
沼田さんは就活を始めた頃、「人に何かを伝えるのが好き」という思いで応募企業を選んでいたそうだ。
そこから、新卒でNTTデータの人事職を希望することになった背景を、次のように語っている。
「モチベーションの源泉」に向き合った結果
就職活動の初めは、マスコミ、メーカー、商社、金融など、さまざまな業界
さまざまな情報に接する中で、自身のモチベーションをきちんと因数分解できたことが、人事志望という目標を明確にするきっかけとなった。
■「働き方の特徴」から志望業界を見いだした佐藤史織さん
マーケティングエージェンシーのオプトに新卒入社した佐藤さんは、出版社とWeb制作会社でインターンを経験し、PDCAを回すスピード感の違いを知る。
結果、自分には「紙のビジネスよりWebビジネスが性に合う」と感じ、Webマーケティング業界を中心に就活したそうだ。
とにかく早く・広く見ることができる
学生時代に2ヶ月程、出版社でインターンした際にその期間を丸々かけて1冊の雑誌の発刊に関わりました(実際はもっと長かったと思います)。 その雑誌ができた時に、喜びや達成感の一方で「もっとスピード感をもってアウトプットしていきたい。自分には10のスピードで10のものを作るよりも、5のスピードで7を作ってPDCAを回していくほうが合っているかも。」ということでした。 そのインターン時代にWeb制作会社の打ち合わせに参加させていただいたことがきっかけで、媒体を紙からWebに移して就活をしました。 その後、広告代理店の様々な業界を知ることができる事業モデルを知り魅力を感じ、この業界を志望しました。
■機械系の専攻→ITエンジニアとして就職した吉村勇輝さん
佐藤さんと同じく、アウトプットのスピード感に引かれてIT企業のユナイテッドに就職したのが吉村さん。
大学では機械工学を専攻していたが、いわゆる「学部・学科推薦」では候補に挙がってこないユナイテッドに就職した理由をこう語っている。
スピード感を持ってものづくりがしたい!機械系学部からWebエンジニアを志望
私は小さい頃からものづくりが大好きで、小学校時代はよく家で図画工作をしたり、LEGOのロボット大会に出たりしている少年でした。 そんな過去から自然とロボットを作ってみたい!と理系を目指すようになり、大学は機械工を専攻しました。 大学3年生ではメーカーを中心にインターンをたくさん受けたのですが、基本的にメーカーは組織の規模が大きく、ロボットアーム1つ取ってもモーターだけを開発する部署だったりハンドだけを開発する部署だったりと業務がかなり細分化されていました。 もちろんジョブローテーションがあって2,30年かけて色々な開発に携わることはできるのですが、ガツガツ働きたいせっかちな自分としては待てませんでした。。 一方で、当時はビジネススクールに通って友達とビジネスめいたことをしており、ネット業界で成功するスタートアップには憧れがありました。 そして気がつけば、スピード感を持ってものづくりができるWebエンジニアを志望するようになり、今はWebエンジニアとして働いています。 周りの友達は皆メーカーに就職する中で自分は1人だけWeb系の道に進んだ訳ですが、働き方も業務内容もとても自分とマッチしているなぁと思いますし、悔いのない選択ができたなと思っています。 「ものづくりが好き」「スピード感持ってガツガツ働きたい」「裁量が大きい環境で働きたい」そんな方はもしかすると(比較的少人数のチームで開発している)Webエンジニア が合っているかもしれません!
インターンに参加して知った「会社のリアル」を、就活にうまく生かした好例と言えるだろう。
■複数のインターンを経て「適性」を見つけた楠勇真さん
こちらもインターンでの経験を就活に生かした1人だが、楠さんの場合は「職業を絞る」ためではなく「可能性を広げる」方向に動いている。
学生時代にエンジニアやWebマーケティングなどの業務を経験した結果、特定の業務が好きというより「世の中に残る事業づくりに興味がある」と気付いたそうだ。
世の中に残る事業創りをしたかったから
学生時代のインターンで、エンジニアやWebマーケティングなど様々な業務を様々な事業で経験するなかで、自分は特定の業務が好きというよりも「自分が死んだあとも、世の中に残る事業」に関わりたいのだと理解しました。 そしてそういった事業を自分で創りだす仕事が出来たらこれ以上ない幸せだと思い、様々な企業や仕事を見ていく中で「事業開発」という職種に出会い「これだ!」と思いました。 事業開発では、非連続に事業を成長させていくことを志向しています。そのために必要なことはなんでもやるため、仕事の内容は多岐にわたりますし、フェーズによってもやることがどんどん変わります。なので、自分もそういった事業創りをしていきたい、事業を伸ばすためになんでもやれるという志向性の方にはピッタリの仕事だと思います。
この軸で就職先を選んだ結果、ITベンチャーのラクスルで広告領域の新規事業「ノバセル」の最年少マネージャーを任されることに。
詳細は下の記事に譲るが、学生時代に気付いた「本当にやりたいこと」が、社会人としてのスタートダッシュを助けた形だ。
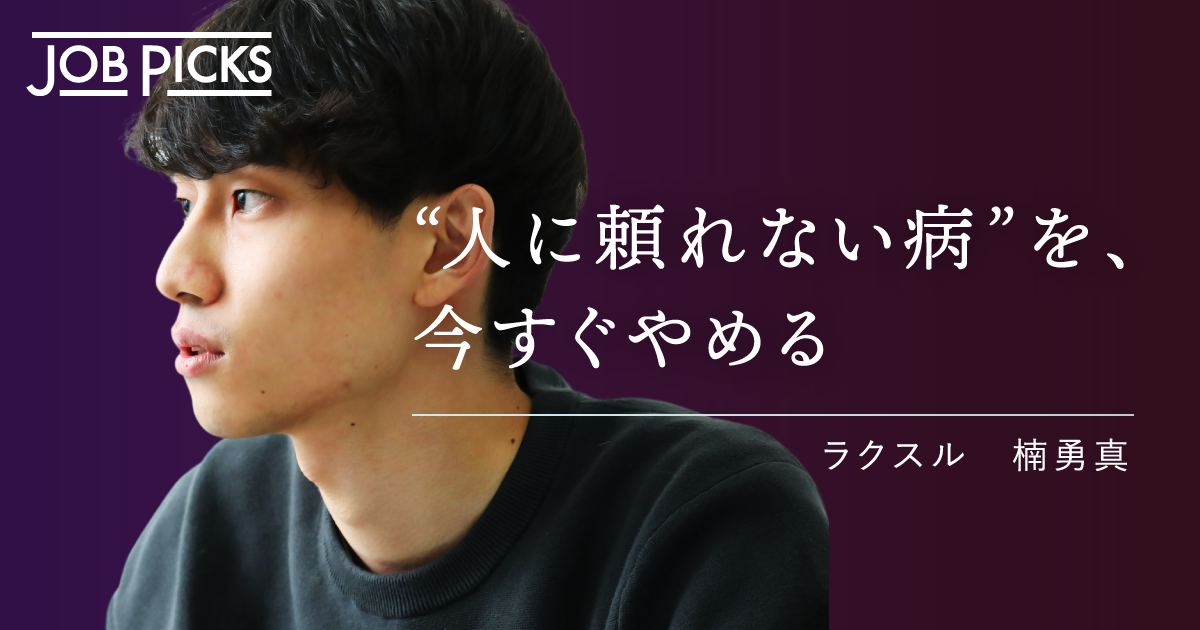
ラクスル最年少マネージャーが見つけた、最速で結果を出す3つの視点
これから就活の面接に臨む学生も、こうした事例を参考にしながら、うわべではない志望動機を見つけてほしい。

合わせて読む:【完全図解】就職、転職、副業。「良い仕事」に出会う3原則

文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / Golden Sikorka