「会社を使い倒す」という考え方
1人目は、フェムテックブランド「Nagi」を展開するBLASTのCOO(最高執行責任者)下條友里さんだ。
新卒でリクルートに入社し、セールスや営業推進、投資業務などさまざまな仕事を経験した下條さんは、就職する段階から「自分がなりたい大人になれるのか」を基準に会社選びを行っていたという。

【元リク】Willがなくてもうまくいく「会社を使い倒す」技術
入社1年目、5年目、10年目の社員に会わせてもらい、「仕事を楽しんでいるのか」「年次に合わせて仕事がどう変わっているのか」など、人に焦点を当て、会社選びをしていました。
結果、リクルートを辞めるまでに「会社を使い倒した」と言い切れるほど、さまざまな経験をさせてもらったという。
その後、改めて心から没頭したいと思える仕事を模索していた時期にBLAST創業者の石井リナさんを紹介され、その出会いが現在につながっている。
生産管理や物流のコントロール、バックオフィスやコーポレート周りの整備まで、COOとしての仕事は初めてだ。異業種・未経験の仕事にキャリアを広げられた理由を、次のように振り返る。
これだけ多くの領域を担当できているのは、リクルートでの経験があったから。目の前のことに一生懸命になった過去が、いまになって生きていると感じています。
(中略)例えばあまり好きになれなかった飛び込み営業の経験がなければ、苦手なことでも成果を出す方法や、やりたいことを仕事にできる楽しさを知ることはなかったと思いますし、そこでがむしゃらになった経験は、COOとしての仕事の基礎になっていますから。
自分がやってみたいと思えなかったことでも、誰かに「やってみたら」とか、「向いているよ」とか、そういうアドバイスをもらったときは、素直にやってみるのがいいんだと思います。
方法論より「ありたい姿」が大事
下條さんと同じく、新卒入社したリクルートで仕事に取り組んだ末に、起業する道を選んだ青木想さん。
営業がしたくてリクルートに新卒入社したものの、経営企画部門に配属となり、新人時代は「正直仕事が面白くなかった」と語っている。
にもかかわらず、その後成果を上げ、出産・離婚も経てもなお起業家として活躍しているのは、キャリア形成の「How(手段)」を考えるより、その時々の「What(ありたい姿)」を前提にゴールを決めてきたからだ。

【決断】31歳で外資生保に転身。元リク経営企画の戦略的キャリア
キャリアにおいて「無駄な経験」は一つもないと思っています。当初は興味が湧かなかった経営管理の仕事で身に付けたスキルは、仕事における大きなアドバンテージですし、(その後転職した)外資保険時代に得た営業力は、今でも生きています。
ただ、先ほどもお伝えしたように、経営企画で働いていた当時は「このスキルは今後生きるかも」とは、想像だにしていませんでしたけどね(笑)。
よくある勘違いは、戦略における「How=手段」に重きを置き過ぎることです。
今は環境に恵まれていて、Twitterや書籍、Web記事などを通して多くの人のHowを知れますし、どうやったら成功できるのかを簡単に学ぶことができます。
だから、「Howをギチギチに組み立てること」が戦略だと考えている人が多いように思えるんです。でも、そのHowは置かれた状況によって、変えざるを得ないこともあります。会社が突然倒産したり、出産や親の介護などで自分のライフスタイルが変わることもあるでしょう。
だから、転職しようが、今の会社にいようが、手段はどんな形でもいい。一番大事なのは、「What=ありたい姿」を決めることです。将来こうなりたいとか、半年後にこういう状態になっていたいという、到達したい「点」ともいえます。
マラソン選手は、最初から42.195km先のゴールを目指すのではなく、「次の信号まではペースを上げよう」「次の給水所まで耐えよう」などと目先の目標に向かって走るという。
キャリア形成も似ていて、その積み重ねがいずれ「点と点がつながる瞬間」をもたらすのだろう。
「学びと行動」が不安解消の糸口
次に紹介するのは、就職した時点では安定を求め、NTTでエンジニアとして働いていた小島未紅さん。「大企業で手に職」という最強と思えるポジションを得て、将来は安心だと思っていたそうだ。
だが、実際は入社後、「このままでは、結婚や出産を機に職場を変えざるを得なくなった時に、自由に転職先を選べなくなってしまう」と危機感を覚え始めたという。
下の記事では、新卒2年目に感じた焦りを次のように語っている。
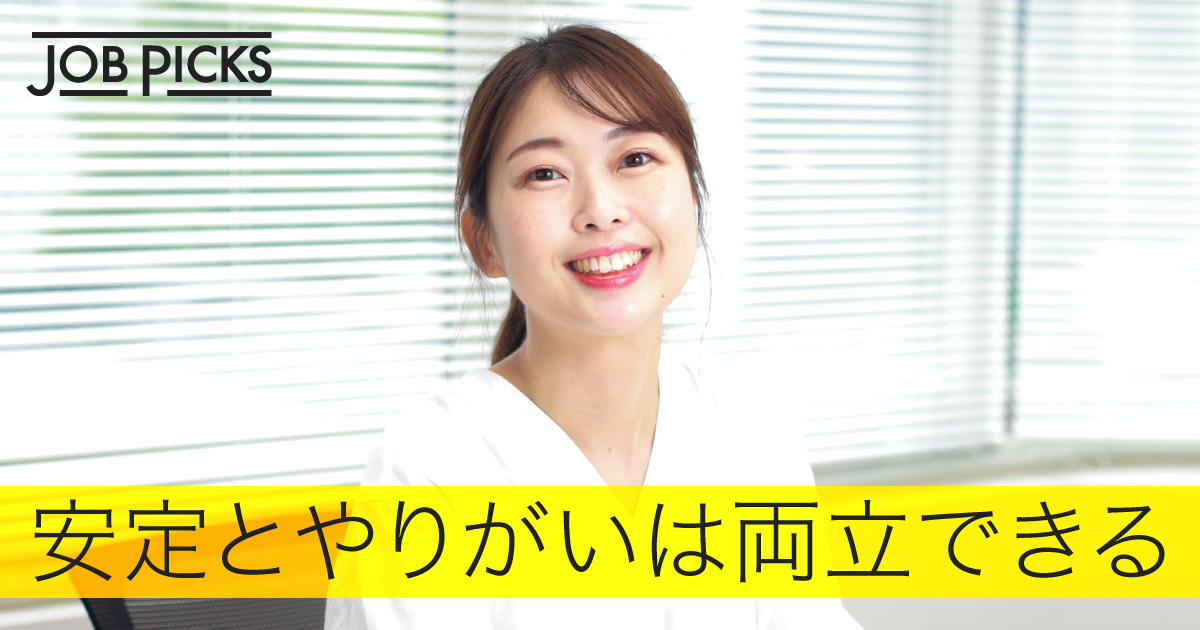
【必見】安定志向のエンジニアが、大企業のモヤモヤから脱出できたワケ
数ある企業の中からNTTを選んだ理由は、私が“究極の安定志向”だからです。結婚や出産をしても仕事を続けたいと考えていたので、福利厚生が整っていたNTTは、当時の私にとって最適なファーストキャリアだったのです。
(中略)とはいえ、大半の大手企業がそうであるように、業務の多くは縦割りです。私でいえば、設計からコーディングを一貫して担当する機会は少なく、胸を張って自分のスキルや実力を語れるほどの実戦経験を積むことはできませんでした。
また、そもそも携わるシステムの大半は、NTT周辺の回線や社内システムです。つまり、社内でキャリアを積めたとしても、それを社外で生かせる保証はありません。究極の安定志向だからこそ、どこでも活躍できるスキルが身に付かない環境に、不安を感じたのです。
このモヤモヤを解消しようと始めたのが、自らが残業中に違和感を持っていた「ブラジャーの着け心地の悪さ」を解消する商品づくり。
文字通りゼロからの経験だったが、とりあえず「ブラジャー OEM」で検索をかけ、ヒットした生産工場200件に片っ端から電話をかけることから始めた。
興味を持ってくれた工場とのやりとりや、行動する中で得た人脈を頼りながら試作を重ねた結果、なんと独立してランジェリーブランド『BELLE MACARON』を立ち上げることに。
安定志向だった小島さんが、20代で起業することになった経緯を、次のように振り返っている。
1人で会社の経営をするとなると、企画書の作成や、マーケティングリサーチ、開発、生産管理、宣伝や広報、経理、法務など、幅広い知識が必要になります。
NTT時代にスキルが身に付かず不安な気持ちを抱えていた分、どこにでも応用できるスキルを身に付けている感覚が充足感につながっていたのかもしれません。
そして何より、自分が欲しいものをつくっていたのは大きかったと思います。就活生時代から一貫して持っていた「新しい価値を届けたい」という想いも相まって、プロダクトに対し情熱を持ち続けたからこそ、最後まで妥協することなくやり遂げられたのだと思います。
この「目指したい目標のために学ぶ」という姿勢は、キャリアを好転させる大事な要素だ。その結果が起業だったというだけで、小島さんは「経営者になりたい」という願望があったわけでもない。
まず「なりたい姿」から考えるというのは、前述した青木さんの経験談とも合致する。
目の前のことを頑張れない人にチャンスはない
定額制パーソナルフードブランド「GREEN SPOON(グリーンスプーン)」を展開するGreenspoon執行役員の小池優利さんも、これまで紹介してきた3人と同じく「結果的に」ベンチャーの役員になった1人だ。
新卒で入社したのはサイバーエージェント。在籍した8年間、メディア営業や人事などいろんな仕事でハードワークをした後、転職を決意したのは「30歳を前に、そろそろ体や時間を大切にし、自分らしい人生を歩もう」と考えたからだという。

食のD2Cを始めた元サイバーエージェント営業の「未経験で結果を出す習慣」
にもかかわらず、再びハードワークが求められるベンチャーに転職したのは、GreenspoonのCEOでサイバーエージェントの同期入社組だった田邉友則さんに誘われたから。
田邉の「アメリカでは当たり前に意識されている『セルフケア』の習慣を、日本でも定着させたい」という思いに強く共感しました。
彼も、私と同じように20代の頃は相当なハードワーカーでしたが、退職後に行った海外留学で「予防医学」の重要性に気づいたそうで。
いわく、海外では医療費の高さもあり、多くの人が「セルフケア」としてトレーニングを日常的に取り入れたり、健康的な食生活を意識したりしている。
反対に、日本では忙しい人ほど食事にあまり気を使わず、コンビニやファストフードで済ませる傾向があり、あまりにもったいない、と。私も、まさにその1人だったので耳が痛くなるとともに、それを解決するプロダクトを作れたらいいな、と思いました。
現在担当している業務は、食材の調達から工場とのやり取り、物流、品質管理まで、商品を作りユーザーに届けるまで全ての工程だ。
経験したことがない仕事も多いそうだが、それでもチャレンジできる理由は、サイバーエージェントで教わった仕事の基本があったからだと振り返る。
今でこそ「ストイックに最後までやりきる人」というイメージを持たれることもありますが、実は新卒時代は真逆だったんです。
もともとtoC事業をやりたくてサイバーエージェントに入社したのに、配属されたのはメディア営業。はなから「営業が向いてない」と諦めていて、半年間は個人売上もほとんどゼロに近い状態でした。
そこで、当時の上司に「本当に営業をやりたくないので、toC事業に異動したいです」と言ったところ、「目の前のことを頑張れない人にチャンスはないよ」とスパッと言い切られて。
その時はじめて、「ああ、その通りだな」と、目が覚めました。これは業界が変わろうと業種が変わろうと、結局同じなんですよね。
未経験ではじめた食品開発も、目の前の「やるべきこと」を一つ一つクリアしていった結果、今こうして商品を展開できているので、なおそう感じます。
なので、もしやりたい仕事ができていないと悩んでいる人がいたとすれば、「今は準備期間だ」と捉えて、まずは目の前の仕事に打ち込んでみることをおすすめします。
そのうちに、やりたいことをできる機会が必ず訪れるはずです。
今回はベンチャーの経営リーダーになった女性を紹介したが、会社の規模、性別に関係なく望む仕事を手にするには、4人のような考え方が大切になる。
フリーランスとして働きたいと考えている人も、その際に強みとなるスキル、経験を手にするには、短期的なゴールを決めて目の前のことを頑張るのが不可欠だ。
そこに、転職や起業のような「勇気を持って行動する」ことをうまく組み合わせれば、働き方の自由はきっと手にできる。
出産、育児などのライフイベントがキャリアに及ぼす影響が大きい女性の場合は、なるべく若い時期に(つまりライフイベントの影響が小さいうちに)動く、という考えも重要になるだろう。

合わせて読む:【検証】ミレニアル女性とキャリア
文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、堤 香菜