思ったような成果が出せない、やりたい仕事ができていない、リモートワークばかりでいまいちモチベーションが上がらないetc.。
経験も知識も少ない若手時代は、このような仕事のモヤモヤを抱えることが多いだろう。
ハイパフォーマーの先輩や、自分より成果を出している同期を見ると、焦りと悩みが募るもの。そんな状態が続くと、無自覚にバーンアウト(さまざまな職場のストレスが起因する症状)してしまうリスクもある。
『バーンアウトの心理学』(サイエンス社)の著者・久保真人さんによると、「仕事に燃えたかったのに燃えられなかった、不完全燃焼の状態」が心身に悪影響を及ぼすからだ(詳しくは下の記事参照)。
【完全図解】20、30代に急増中「燃え尽き」を防ぐ5つの方法そうならないためにも、時には他人の力を借りてみよう。抱えていたモヤモヤが、先輩のふとした一言ですーっと消え去る瞬間を経験したことがある人は多いはずだ。
そこで本稿では、JobPicksに経験談を投稿するロールモデルが、「Q. 同業の先輩や同僚にアドバイスされたことで、最も仕事上の教訓になったことは何?」という問いに答えた内容に注目。
回答の中で、ユーザー評価の高い(たくさん「いいね」された)もの上位10個を選んで紹介していこう(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。
仕事に思い悩む若手は、自分自身の壁を破るために。若手メンバーと働く先輩たちは、成長をうながすきっかけをつくるために。いろんな立場で参考になる至言ばかりだ。
「トンネルを掘っているのか、未来を作っているのか」
これは、エイベックス・エンタテインメントに務める西木沙織さんが、新卒2年目に役員からもらったアドバイスだそう。
新人を卒業し、仕事に慣れてきた時期に言われてハッとしたという。
トンネルを掘っているのか、未来を作っているのか。
__ とある旅人が 山でトンネルを掘っている人に「何をしているのですか?」と尋ねると 「見ればわかるだろ、トンネルを掘ってるんだ」と答えました。 しばらく歩いていると また別の場所で同じような事をしている人を見かけ 「何をしているのですか?」と尋ねると 「未来を作ってる!ここにトンネルが開通したら街の未来が変わって多くの人が幸せになる。」と答えました。 __ 同じことをしているように見える二人の異なる回答。 今自分がやっている業務に対しても 、どこまで”想像” を膨らませられるか。 ”想像” 次第でやりがいもモチベーションも、そして行動も変わるのではという例え話でした。 入社2年目でルーティン業務には慣れてきた頃の私にとって この話はとても刺激的でハッとさせられました。 この話をしてくれたのは弊社の役員です。 他にも上司からは「自分が楽しめなきゃお客様を楽しませられない」という言葉を頂けたりと、、 常にエンタテインメントな想像力と心を持った先輩方がいる環境で 働けることをとても幸せに感じます。
どんなに小さな仕事でも、見方を変えれば意義を見いだせる。そんな気付きが得られるアドバイスだ。
西木さんは過去のインタビューで、学生時代、ある経営者に言われた「失敗の反対は成功ではなく、何もしないこと」という金言も支えになっていると語っている。詳しくはぜひ記事を読んでもらいたい。

【エイベックス・25歳】インスタグラムとアルバイトで、第一志望に内定
「バリュー(提供価値)ベースで仕事をしよう」
これは、A.T. カーニー(グローバルブランド名:カーニー)やボストン コンサルティング グループを経て、コンサルティング会社のフィールドマネージメントでマネージングディレクターになった藤熊浩平さんの投稿。
コンサル2年目にアドバイスされたそうで、新人としてタスクをこなす毎日から脱却するきっかけを得たという。
バリュー(提供価値)ベースで仕事をする
「そろそろ、タスクベースではなく、バリューベースで仕事をしてみようか」 これは、私が新卒2年目の時に、当時のメンターだった人からいただいたアドバイスです。 私は新卒でコンサル業界に飛び込んだので、最初の1年は、ただ目の前の与えられた仕事に全力投球して、相手の期待値を超えることで精一杯の日々でした。 この時の「仕事」とは「タスクをこなす」ことで、今振り返ると当時の自分は、「便利な作業屋」になっていたと思います。 学生あがりだった私は、まだ何者でもなく、誇れるのは体力くらいだったので、コンサルスキル以前のビジネススキルを身につけるのに必要な期間だったとは思います。 ただ、この仕事の本分は、クライアントを介して世の中に新たな価値をつくり出していくことで、その目的のために目の前のタスクや作業がある、というのが本来の順序です。 そんな当たり前のことに、改めて気づかせてくれた言葉でした。 「バリューベースで仕事をする」、言うは易しですが、実際の行動に移すにはハードルがあります。 まず、そもそも何がクライアントや世の中にとっての「バリュー(価値)」になるのか、がクリアになっている必要があります。 その上で、自分がどういう活動に、どれだけの時間を使えば、どれくらいのペースで価値が積み上がっていくのか、が分かって初めて、リソース配分ができるようになります。 そういう意味では、今もなお、「バリューベース」で仕事ができているか、日々模索中ですが、その意識を持つことで、仕事に向き合う姿勢は間違いなく変わります。 「タスクベース」で仕事を受けると、「How(どうやるか)」が気になります。そのタスクありきで、いかに効率的にこなすか/いつまでに終えられるか、が関心事になるからです。 「バリューベース」で仕事をすると、「What(何をすべきか)」や「Why(なぜすべきか)」が気になります。最終的に価値につながる仕事でないと、意味がないからです。 時が経ち、私がチームを率いて、メンバーをマネージする立場になった時、先ほどの言葉をいただいた人から、また貴重なアドバイスをいただきました。 「メンバーを、スキルセットの集合体と捉えるか、バリューの集合体と捉えるか、それによってマネジメントの仕方は変わるよ」 コンサルファームでは、各コンサルタントは、プロフェッショナルとして日々成長が求められ、「Development needs」という言葉がよく飛び交います。 そうして、コンサルスキルのレーダーチャートのパイを、大きく、正多角形に近づけていこうとします。 なので、ともすると、コンサルタントを「スキルセットの集合体」と捉え、あれはできている/これはできていない、というような見方をしてしまいがちです。 他方、コンサルファームに集うメンバーは皆個性豊かで、好きなこと・得意なこと、情熱を傾けられるもの・夢中になれるもの、それぞれです。 プロジェクトも、クライアントの業種や取り組むテーマ、働き方など、さまざまです。 マネジャーの仕事は、チームとしてのバリュー(提供価値)を最大化することです。 そのためには、「スキルの塊」としてではなく、意思や感情を持った個性豊かなメンバーの力をいかに最大限引き出すか、そして、それを価値に転換するために、彼ら・彼女らを含めたチームとクライアントとの化学反応をどうデザインするか、が重要だということを教わりました。 世の中に対する「バリュー(提供価値)」を日々意識しながら、それに貢献しうる/矛盾しない仕事を、これからもしていきたいと思います。
「タスクベースで仕事を受けると、How(どうやるか)ばかりが気になる」と話す藤熊さん。仕事をいかに効率的にこなすかが関心事になるからだ。
他方で、「バリューベースで仕事をすると、What(何をすべきか)やWhy(なぜすべきか)が気になるようになる」という。
目先の仕事のゴールは何で、提供するべき価値は何なのか。これを意識するようになってからが、本当のキャリアの始まりだと言えるだろう。
「耳触りの良いことだけを提案するのはBCGの価値ではない」
続いて紹介するのも、コンサルタントの経験談だ。
BCGとは、上でも名前が上がったボストン コンサルティング グループのことで、ヤフーやレッドブル・ジャパンを経てBCGに入った打越武さんはこの言葉で「プロフェッショナルとは何か」を学んだという。
「耳触りの良いことだけを提案するのはBCGの価値ではない」
「プロフェッショナルである以上、クライアントから期待されている以上の価値を出すことにフォーカスするのがBCGでの仕事の基本」だということ。 クライアントから頼まれたこと、作業を請け負うことを徹底するのはクライアントワークの最低限の仕事であり、「BCGでの価値の出し方」はときに「クライアントにとって耳触りが良いことだけでなく、目をそらしていた課題やストレスのかかることも価値として示す必要がある」という言葉が働く上での金言となっている。
コンサルに限らず、さまざまな仕事に通じる仕事の基本だ。
打越さんは、社会人になる前にインターンをしていたベンチャー企業の社長から、次のような一言を聞いたことも印象に残っているそうだ(下の記事参照)。
自分がこれからどうキャリアをつくっていくかより、今、世の中は何を求めていて、それに対して何をアウトプットしていくかを意識して仕事をしよう。
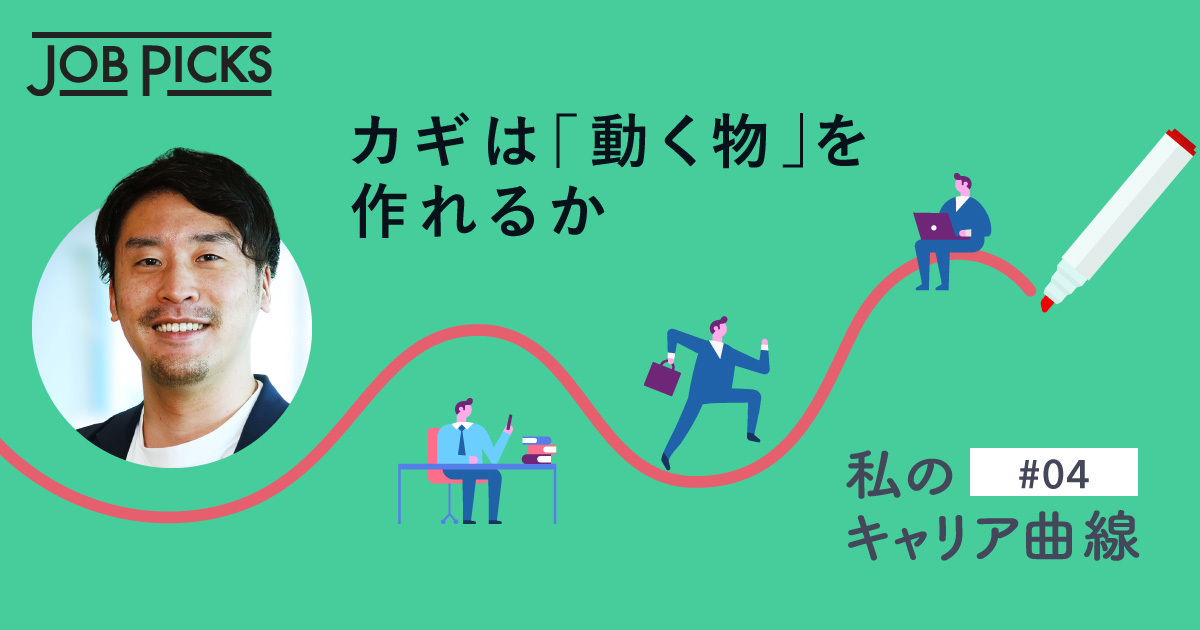
打越さんインタビュー:BCG「新型UXコンサル」の仕事の中身
若い時期にこのような視点を持つことが、継続的な成長を後押しするのかもしれない。
「資料はゼロか1割がよい」
次は、マインド面での教えではなく、実務におけるアドバイスになる。
現在ニューズピックスのCSO(最高戦略責任者)を務める杉野幹人さんが、A.T. カーニーのコンサルになりたての頃、先輩に教わったというプレゼンのコツだ。
杉野さんはこれを「プレゼンに限らず、ビジネスコミュニケーションの極意だと思っている」と投稿している。
資料はゼロか1割がよい
これは、わたしが経営コンサルタントの先輩から教えてもらったプレゼンの
プレゼンに限らず、どんな仕事でも「頑張っているのに報われていない」と感じるシチュエーションはごまんとある。
そんな時、この話のように「伝えたいこと、かなえたいことは何か」から逆算して仕事ぶりを見つめ直すと、思わぬ突破口が見つかるかもしれない。
「数字に意志を込め、細部にまでこだわれ」
これは、30代で起業したLoveableの青木想さんが、新卒入社したリクルートで経営企画職に就いていた頃にアドバイスされた言葉だ。
もともと営業がやりたくて入ったリクルートで想定外の配属となり、「ザ・スタッフ職」の仕事に不完全燃焼だった時期に言われたという。
数字に意志を込め、細部にまでこだわることがプロの仕事
「神は細部に宿る」という言葉と、「数字に意志を込める」という言葉です。 経営企画という仕事は、とにかくExcelと向き合う、ザ・スタッフ職です。目立たないですし、数値を扱うのでミスは許されないですし、ミスした時には経営判断にも影響するため非常に緊張感の高い仕事です。売上を生み出さないコストセンターにも関わらず、ミスができない仕事で、売上の根幹を担う仕事でもあるため、いかに効率よく丁寧に仕事をするか、が求められます。その中で「神は細部に宿る」という言葉は、私の中で印象に残る言葉で、例えばExcelを人に送付するときに、相手が開いた時にちゃんと全体が見えるように、必ずカーソルを左上に置いた状態で保存して送る、みたいな細かい気遣いから、数値設計をかなり細かいKPIにまで因数分解して何パターンも分けてつくる、ということまで、プロとしてのマインドセットをこの言葉を通して鍛えてもらったなと思っています。 また同様に「数字に意志を込める」もとても含蓄のある言葉で、結局ただの作業屋さんになるな、数値にちゃんと経営の意志を込めて実現できるような形にしていくことが経営企画なんだ、という教えは起業した今でも、非常に痛感する言葉です。
真意は、どんな仕事だとしても「ただの作業屋さんになるな」ということだろう。
この教えを受けて、今は自身がワーキングウーマンの活躍支援を行う立場になるまで成長した青木さんのキャリアヒストリーは、下の記事で読むことができる。

【決断】31歳で外資生保に転身。元リク経営企画の戦略的キャリア
「60分最後まで、見せきるための工夫を常に考えろ」
次は、クリエイティブ関連職に就く人にとって、耳が痛いけれど非常に大切な教えだ。
投稿主は、映像クリエイターの庫本太樹さん。中京テレビ放送で駆け出しのスタッフだった頃、あるプロデューサーに次のようなアドバイスを受けたそうだ。
「60分最後まで、見せきるための工夫」を常に考えよ
テレビ局時代に、プロデューサーから最初に言われた教えです。例えば「世界の様々な乗り物を紹介する番組を作ろう」と思った時に、どうすれば60分のVTRを作れるでしょうか?「それは何のために作られたの?」というヘンテコな乗り物を紹介するとして、それで5分作れる。後は「みんなが毎日乗るモノ」を題材にすれば興味があるだろうから、世界の地下鉄事情を取り上げよう、それで7分。一番早い乗り物、一番高額な乗り物とか、一番○○な乗り物を取り扱えばそれでも5分は持ちそう。ロケに行けばもっと長いVTRが作れるだろう、そしたら誰をどこに行かせようか。このままだと、「軽い情報」ばかりだから感動系も入れて、重みを持たせたいな。「番組冒頭15秒」のインパクトが大事だから、未来の乗り物のCGで引き付けようか。何かに挑戦するくだりも入れて、その結果を最後まで隠して60分引っ張ろうか。時事性も入れたいから、どこかでリニアの今を追うか。このままだと企画全体が散漫だから、どうまとめていこうか…。などなど一つの企画でも様々な工夫を考えないと、そもそも見てもらえないし、また最後まで見てもらえない。動画はよく、「文字情報だと1分ですむものを引き伸ばしているので、時間の無駄」と言われます。それはその通りだとも思いますが、逆に「1分ですむ文字情報で、何分楽しく見てもらえるか?」。この工夫をし続けることが「動画(番組)制作の醍醐味」だと思います。上司のこの言葉を聞いてから、「今いる飲食店で、何分VTRを作れるか?」など「思考のクセ」がつき、自分は本当にまだまだ未熟ですが、多少の成長のキッカケになったと思います。
アウトプットの質にこだわりたいけれど、能力的、時間的な制約とうまく付き合うことも求められるのがクリエイティブの仕事。
仕事に少し慣れてきて、日々のアウトプットに前ほど情熱を注げなくなった時に思い出したい言葉だ。
「マネジメントとリーダーシップの違い、分かるか?」
若くしてチームやプロジェクトを引っ張る立場になった人が、ほぼ必ず突き当たる「リーダーとは何か?」という問い。
阪急阪神ホールディングスの石村康二郎さんは、社内ベンチャー制度を利用して介護事業を立ち上げた際に、この疑問に突き当たったという。
その時期に学んだ、マネジメントとリーダーシップの違いを次のように語っている。
マネジメントとリーダーシップ
新規事業では、「マネジメント能力」ではなく、「強いリーダーシップ」が
役職や肩書を問わず、「人を巻き込む」ことが求められる人に役立つ話だ。
「バカだと思われてもいいから何でも質問しよう」
次に紹介するのは、LINEに新卒入社してすぐに、プロダクトマネージャーとしてスマホ投資サービス「LINE証券」の機能改善を担当することになった大嶋泰斗さんの投稿だ。
自分には専門性がない状態で、エンジニアやデザイナーなど高い専門性を持ったチームメンバーと協働することになった大嶋さんは、こんな学びを得たという。
バカだと思われてもいいからなんでも質問しよう
職種の特性上、若手でも多様な職種のことと協業することが多いです。その
恥ずかしさやプライドを捨てて「結果志向」で動くようになってから、どんな変化があったのかは、下のインタビュー記事に詳しく載っている。合わせて読んでほしい。

【LINE・24歳】若手プロダクトマネージャーの仕事の中身
「想定外はつきもの。成功か学びしかないと思え」
これは、経営コンサルを経てスタートアップのREADYFORに転職した中山貴之さんが、初めて事業企画・事業開発を担当した時、あるベンチャーキャピタリストから教わった話だという。
失敗はない。成功か学び
スタートアップなので、会社にこの職業の先輩や同僚はいないのですが、 もともと新規事業をたくさん手掛けられた、あるVCの方から教わった “新規事業に想定外はつきもの。成功か学びしかないと思え” という言葉は仕事上の教訓になっていると感じます。 新規事業はとにかく凹むことが多いです。 企画は社内で没になるし、営業に行っても売れないことも多いです。 いざ事業が始まっても、最初の想定の甘さから思わぬ不手際でお客様に迷惑をかけてしまうことや、仲間にハードワークを強いらざるを得ないことも少なくありません。 昨年初めて、新規事業におけるサービスオペレーションの構築を行った際に お客様の要望の細部までの理解が十分でなかったためにサービスを世に出す前日に深夜までお叱りを頂いたこともありました。 この時は社長に連絡してお客様に謝ってもらい、何とか場を納めてもらったのですが、お客様にも、一緒に謝ったチームメンバーにもふがいない気持ちになりました。 ただ、そこで“失敗”ととらえて落ち込んだところで事態は好転しないので、 それ以降毎週、“今後起こるかもしれないこと会議”という ただただ今後起こりそうな“しくじり”をブレストしてそれが起こらないような対応策を考えるようにしました。 それ以降は、お客様からお叱りを頂く機会は減り、連続して複数社に対して提供させて頂く形のサービスだったのですが2社目以降のお客様からはお叱りを頂くことなく進行することができました。 業界の大先輩が“新規事業に想定外はつきもの。成功か学びしかないと思え” とおっしゃってくれていたおかげで、 僕も“あんなスゴイ事業を起こした人でも失敗するとか言っていたな、まあ凹んでいてもしょうがないし頑張ろう”と気持ちを立て直すことができたのは良かったと思います。
コメントにもあるように、事業企画は失敗が日常茶飯事で「とにかく凹むことが多い」仕事だ。
そんな中でも、チャレンジして「ユーザーにとっての新しい何か」を生み出すために、このアドバイスが役立ったそうだ。
何かしらの意思決定をする時は、常に不安がつきまとう。精神論と思ってしまいそうな話だが、「自分が決断しなければいけないシチュエーション」を経験したことがある人なら、このアドバイスがいかに本質的な課題解決法なのかが分かるはずだ。
「常にスタンスを取れ」
最後に紹介するのは、新しい形の教育コンテンツを企画・開発するワンダーラボの事業マネージャー鳥居亜紀の経験談だ。
上の見出しにある言葉は、前職のA.T. カーニー時代、メンターだった先輩から教わったという。次のような意味だ。
常にスタンスを取る
『今、結論を出すとしたら結論は何なのかを常に考え、 「私はXXと考え
このような思考法は、コンサルのみならず、他者と働く全ての仕事で求められる。
全ての仕事が課題解決であるという前提に立つなら、「過去の誰か(主に偉い方)の意見に固執し、最善の選択をする=方向転換をすることができていないことが多い」という一文は、とても耳の痛い話だろう。
モヤモヤを解消するとはつまり、現状を変えること。そのきっかけとなる考え方とも言えるので、ぜひ参考にしてほしい。

合わせて読む:【完全図解】就職、転職、副業。「良い仕事」に出会う3原則
文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / emma