ジョブ理論とは?著者紹介と要約
「なぜあの商品は売れているのか」「顧客はなぜ競合他社のサービスを評価するのか」
経営者や事業開発担当者だけでなく、ほとんどのビジネスパーソンが興味を持つであろうこの問いに、一つの答えを示してベストセラーとなった『ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム』(ハーパーコリンズ・ ジャパン)。
イノベーション研究の権威として知られたハーバード・ビジネス・スクールの故クレイトン・クリステンセン教授らの共著で、日本では2017年に翻訳版が出版された。

クリステンセンの名を知らない人でも、彼の処女作の邦題にもなった『イノベーションのジレンマ(The Innovator's Dilemma)』という言葉は聞いたことがあるかもしれない。
イノベーションのジレンマの副題は「技術革新が巨大企業を滅ぼすとき」。各産業で起きる下克上のメカニズムを解き明かし、原書が出版された1997年以降、世界的に影響を与える理論となった。
世の中を一世風靡する製品を生み出した大企業は、その強みを磨くことに専念するあまり、消費者が抱く異なるニーズに気付けなくなる。その結果、新たな魅力を持つ製品を開発した新興企業に、取って代わられてしまう。
クリステンセンはこれを「破壊的イノベーション」と呼び、その後も企業活動や新規事業開発における“革新の起こし方”を研究し続けた。
その過程で導いたのが、冒頭に記した問いの答えとなるジョブ理論だ。
クリステンセンが共同創業したコンサルティング企業・米イノサイトと提携し、本人とも親交のあったインディージャパン津嶋辰郎さんによると、ジョブ理論とは「顧客ニーズの本質を捉えるための視点」である(下の記事参照)。
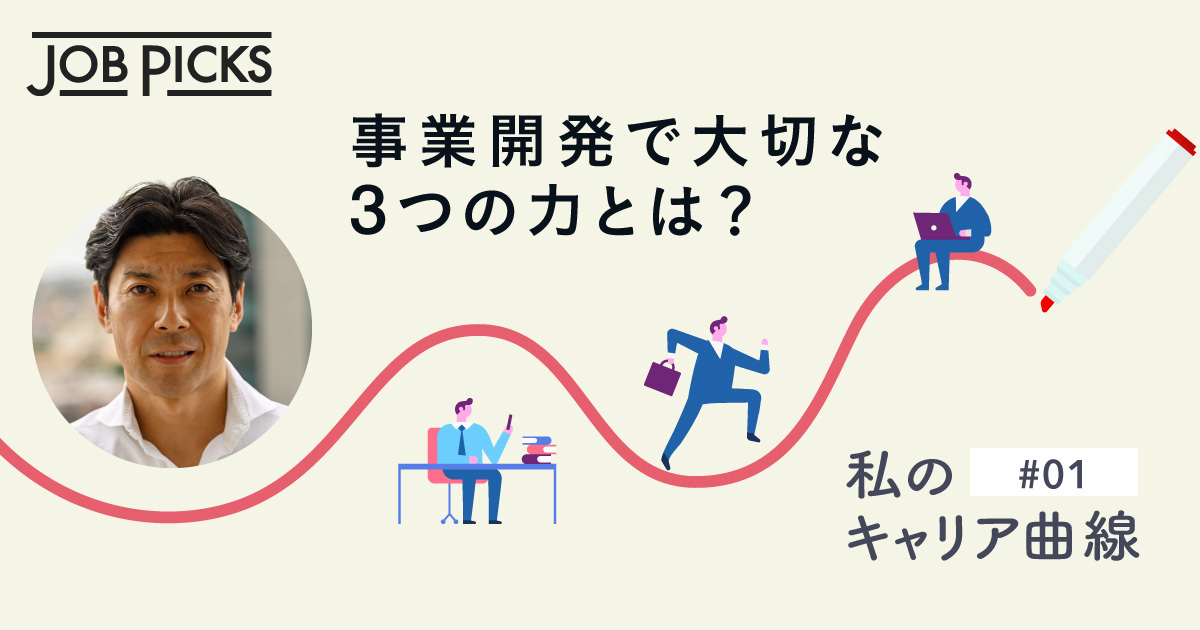
【事業開発】日本で唯一、クリステンセンが認めた「事業立ち上げ人」の仕事術

上にある「シェイクを買う理由」の話は有名で、書籍では1章:ミルクシェイクのジレンマで詳しく説明されている。
あるファーストフード店が、シェイクの売上拡大を狙って味や量、価格帯を変更したが効果が出ない。そこで改めて購入者の傾向を観察したら、「朝9時前、車で来店した客が、店舗内で飲まずに持って帰る」パターンが多かったという。
これをクリステンセンは、「運転中の気を紛らわせる」という【ジョブ】を解決するために、顧客がミルクシェイクというゆっくり飲める商品を【雇用】していたと説明。
ビジネスでは、こうして顧客が片付けたい【ジョブ】を特定すること(ジョブ・ハンティング)が大切で、ジョブを解決するため自社商品を【雇用】するまでのストーリーを示すのが事業戦略になると説いている。
では、本書から得られる学びは、具体的にどんな状況で役に立つのか。
JobPicksのロールモデルの中で、『ジョブ理論』を薦める人たちのレビューコメントから読み解いていく(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。
営業関連職に役立つジョブ理論
はじめに紹介するのは、モノを売る仕事の代表格である営業関連職に就くロールモデルのレビューだ。
近年は「モノがあふれかえる時代」と言われている。そんな中、自社サービスの機能や価格面の差別化ポイントを売り込むだけでは顧客に買ってもらえない。顧客が抱える課題を見抜き、それを解決するためのストーリーを提案することが、営業の肝となる。
あるロールモデルは、ジョブ理論を読んで「モノ売り・御用聞き営業」から脱するために必要な理論を学んだと述べている。
もちろん、商品・サービスの継続利用を促すカスタマーサクセスの現場でも、ジョブ理論の内容は役に立つ。
クラウド型のSaaSを提供するスタディストの須藤徹治さんは、カスタマーサクセスの仕事で重要な「顧客の課題定義」についての仮説を立てる際の検討軸が学べるという。
ジョブ理論
顧客が「商品Aを選択して購入する」ということは、「片付けるべき仕事(
マーケティング職に役立つジョブ理論
『ジョブ理論』は事業開発や営業だけでなく、作ったモノの認知〜購入を促すマーケティングの仕事にも役に立つ。
NewsPicksのWebマーケター・デジタルマーケター、菊地幸司さんは、本書を通じて「顧客ニーズ」という言葉の解像度が高まったと述べている。
ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム
「なぜ人はその商品を買うのか?」 この問いに対して、一番しっくりし
本書を読んだことで、集めたユーザーデータの分析でも「なぜこうなるのか?」がイメージしやすくなったそうだ。結果、具体的なマーケティング施策を考える時の補助線が、頭の中に描きやすくなるのだろう。
ユーザーが言葉にしない「埋もれたジョブ」は何なのか。その埋もれたジョブに対して、自社サービスはどんな解決策を提供できるのか。こうした思考の軸が、マーケティング施策のストーリーを企画し、実践する上で役に立つ。
UX設計にも使える普遍的な一冊
この「ストーリー」を練るという意味では、ユーザビリティの向上を担うUXデザイナーの仕事にも有益な一冊となるようだ。
新規事業の立ち上げやプロダクトのUI/UX改善コンサルティングを行うグッドパッチの岩田悠さんは、『ジョブ理論』をUXデザイナー志望者への推薦本に挙げている。
ジョブ理論
顧客が持つ真の課題を捉えるためのフレームワークが、実例を伴って解説さ
岩田さんの言う「フレームワーク(仕組み)」を知れば、応用問題も解きやすくなる。この点で、『ジョブ理論』はさまざまな職業の仕事に役立つはずだ。
最後に、冒頭で紹介した「日本で唯一クリステンセンが認めた日本人」の津嶋さんが推薦する本も紹介しておこう。
新規事業の立ち上げ支援を生業にする津嶋さんは、クリステンセンが遺したいくつかの書籍の中から『イノベーションへの解』(翔泳社)をピックアップする。
イノベーションへの解
クリステンセン教授の複数ある著書の中で、事業開発向けに一冊だけ選べと
「クリステンセン教授の著書は単なるHow toではなく、社会の基本原理の理論化を目指しているので、自分自身の成長やその時の問題意識に応じて学びや気付きが変わる」(津嶋さん)
このコメントは、『ジョブ理論』にも当てはまる。
上で紹介したミルクシェイクの話だけでなく、Uberの成長秘話や、近年の経営・ブランディングでビッグイシューになっているパーパス(社会的な存在意義)など、具体的な事例を豊富に紹介しながらジョブ理論の原理を説明している。
トレンドの変化に踊らされず、事業開発やマーケティングを行うための基礎が学べる普遍的な一冊になるだろう。
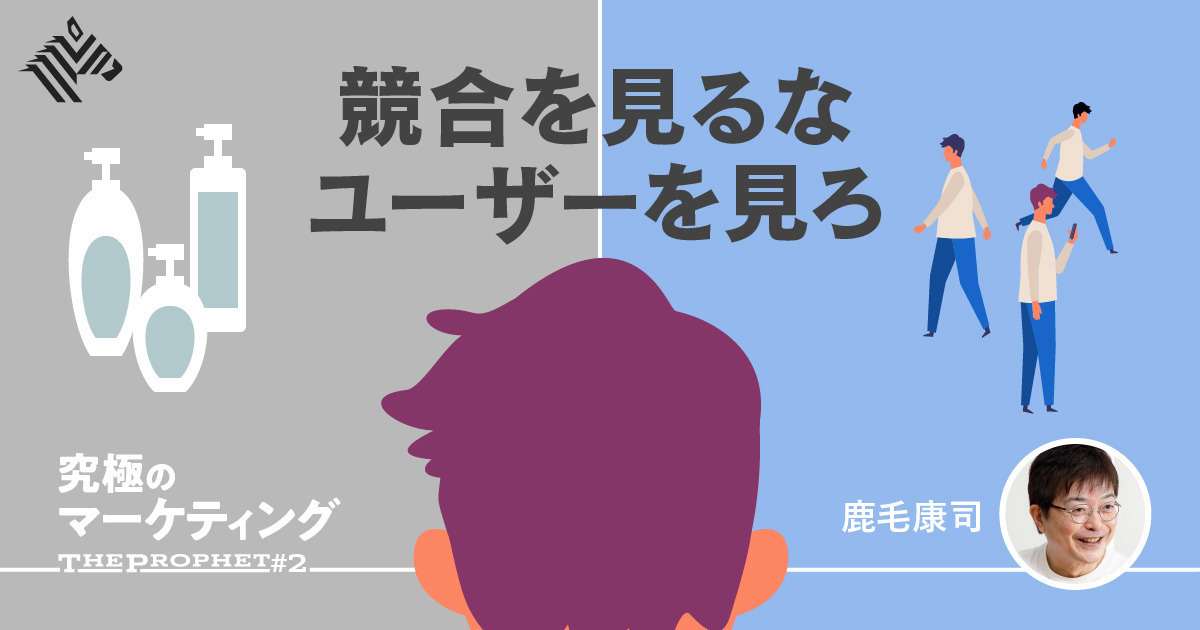
合わせて読む:【鹿毛康司】データ分析よりも大切な「マーケティングの本質」

文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳