夢物語を、夢物語で終わらせない
—— 林さんが考える、「事業開発」という職業の定義について教えてください。
一言で表現するなら、「事業の立ち上げからグロースまでを指揮する仕事」です。
事業開発の原点は、「世の中にこういうものがあったらいいな」と夢想することにあります。ただ、そのほとんどが、実現可能性を検討していない、いわば“夢物語”です。
事業開発の存在意義は、その夢物語を、夢物語で終わらせないことにあります。
「どうやったら実現できるのか」という戦略を立て、戦略に従ってプロジェクトをつくり、プロジェクトに人を巻き込んで形にしていく。
この一連の流れが、事業開発の職務です。

—— 学生からも人気が高く、企業からの需要の高い職業です。なぜ、それほど注目されているのでしょうか?
とにかく、希少価値が高い職業なのです。
インターネット時代が到来して以降、まずエンジニアの需要が急増して、次にUI、UXの文脈が広がってデザイナーの需要が増加しました。時代の要請によって需要が増えた職業はいくつか挙げられますが、そのほとんどが「作り手」です。
翻って、今度は事業づくり全体を設計できる、いうなれば「考える人」が求められるようになりました。この「考える人」こそが、事業開発です。
モノづくりの方法は、それなりに体系化されています。しかし、考えることは、全く体系化されていません。常に前提が違うので、情報共有がされにくく、相対的に生まれにくい。そうした背景もあって、需要が増しているのだと思います。
学生から人気が高いのも納得できますが、エンジニアやデザイナーといった専門職をマネジメントするスキルが求められますし、戦略構築から実装までを一貫して指揮する必要があるので、新卒から担当するのは非常に荷が重い仕事です。
デジタル化の波から逃げられない
—— 事業開発を目指すうえで、求められる素養やスキルにはどのようなものがありますか?
顧客理解と市場理解、そしてデジタルの理解です。
新規事業をつくるということは、つまるところ顧客の課題を解決するということです。顧客を理解する力がなければ、本当に求められているサービスをつくることができないので、結局のところ事業はうまくいきません。
また、顧客の課題を理解しても、市場理解がなければ、売上を持続的に生み出すことができません。競合がいないビジネスは存在しないので、この2つをセットで持っていることが大前提になります。

事業開発の歴史をたどると、かつては顧客理解と市場理解さえできれば、その責務を全うできていたと思います。
しかし、時代は変わりました。現在は、デジタルの知識がなければ、頭一つ抜けられない時代になっています。
新興企業だけではなく、日本を支えてきた大企業がこぞって「デジタル化が必要だ」「新しい事業をつくりたい」と言っているように、現代は何をするにもデジタルの知見が求められる時代です。
銀行口座もアプリになっているし、小売もオンラインショップやD2C(消費者直接取引)に移り変わっている。第一次産業である農業や漁業さえ、デジタルとくっついているはずです。
デジタルから逃れられない時代が到来している今、事業開発を志すのであれば、絶対的にデジタル人材としての素養が必要です。
—— デジタル人材としての素養を身につけるには、どのようなアプローチがありますか?
身の回りにあるデジタルプロダクトに興味を持ち、構造を理解するまで使ってみることだと思います。
デジタルと聞くと、プログラミングやデータサイエンスを想像されることがありますが、それらは必ずしも必要な知識ではありません。むしろ、「デジタル領域で、どのようにしてサービスがつくられるのか」を理解することのほうが重要です。

自分でデジタルプロダクトを開発したり、開発に携わることが、最も手っ取り早いかもしれません。いや応なしにデジタルプロダクトの構造を考えることになるし、発想力を鍛えることにつながるので。
自分の手でサービスをつくると、考え方がインストールされていきます。経験さえあれば、例えば会社から「ECの伸びが悪いから、ECに代わる何かをデジタルでつくって」と言われたときに、何かしらはつくれるはずです。
言葉や考え方がインストールされていれば、現実的な案が出てきますから。
考え方の引き出しを増やす
—— 事業開発として活躍するために、林さんが日頃から意識していることはありますか?
「マクロからミクロ」の順番で考えを巡らせていくことです。事業をつくるときはいつも、「3年後どうなっているのだろうか」とか、「5年後どうなっているのだろうか」とか、常に大きな流れに目を向けることを大切にしています。
事業立ち上げの最初の段階でもある「リサーチ」をするときは、例えば中国を参考にします。
中国って、一周早いんですよ。コロナ禍で日本企業が困っている場面をよく見かけますが、中国企業はその段階が終わっています。中国の最新動向を見て、それを応用するすべを考えると、自然とやるべきことが見えてきます。
リサーチを経て、そのサービスにおける一定のゴールを決めたら、今度は3つぐらいの大きなフェーズに区切って、「まずはここからスタートしましょう」というように、プロジェクトのスタートに向かいます。
サービスの設計がわかりやすいかもしれません。当たり前ですが、「付けたい機能」から考えるのではなく、顧客に届けたい価値から機能を逆算しますよね。
届けたい価値から体験を考えて、体験から機能を考える。この順番を守らないと、本質的な解決にならない場合が多いのです。
日本にはこの考え方が苦手な企業が少なくなく、機能ありきでサービス開発をしてしまうことがよくあります。でも、それではなかなか成功しないのです。
各論から考えることをせず、マクロから考える。これが、事業開発における全ての仕事の鉄則です。

—— 絶対に各論から考えない、というのは今日から意識できそうなフレーズですね。
もう一つ大切にしているのが「考え方の引き出しを増やすこと」です。情報収集をしているときは、考え方や面白い構造だけを抜き取って、頭の中の引き出しにストックしています。
「動画がはやっています」という情報を見たとき、それを眺めているだけだと「写真の次は動画なんだな」という記憶しか残りません。そうした知識はすぐに忘れてしまうし、深い理解がないので転用できないケースがほとんどです。
しかし、「なぜ動画が市場に今のタイミングで受け入れられ始めたのか」を考えていくと、事業開発の筋肉を鍛えるのに役立つ知識が増えていきます。
動画を扱う主な媒体は、これまでテレビしかなかった。テレビ局が制作会社にお金を投じて、マスメディアとして配信していたのが動画だった。そこから「コンテンツの制作」が民主化されたおかげで、一般人でも動画コンテンツを出せる、いわゆる1億総クリエイター社会になった......という構造だと思うんです。
より抽象化すると、「プロフェッショナルでしかできなかったものが民主化して、一般の人でもできるようになった」のだとわかる。

こういった思考を繰り返してストックしておくと、自分で事業をやろうと思ったときに、「あのとき考えたあの構造って、今回当てはまるな」と気付くことが山ほどあります。
—— 情報を整理して、引き出しに入れておく。
「何かが起きたときに、因果を理解できる能力」と言い換えられるかもしれません。
なぜコミュニケーションサービスの中でLINEが突き抜けたのか。なぜ人々はSNSで他者とかかわろうとするのか。一見しただけでは想像できなくても、多くの事例や思考をストックしている人であれば、ある程度分解して因果を理解できるはずです。
因果の因、つまり原因のほうを考えるのに長けている人は、事業開発に向いていると思います。中国の事例を調べて、最終的に参考にするのは結果ではなく原因のほうですから。
—— 日頃から引き出しを増やしておけば、自然とそういった思考ができるようになっていくと。
好奇心が強い人であれば、その好奇心をもう一段階深めるだけでいいと思います。
あなたが興味を持っている商品やサービスは、なぜ市場に受け入れられているのかを考えてみてください。きっと、何らかの仮説が立つはずです。
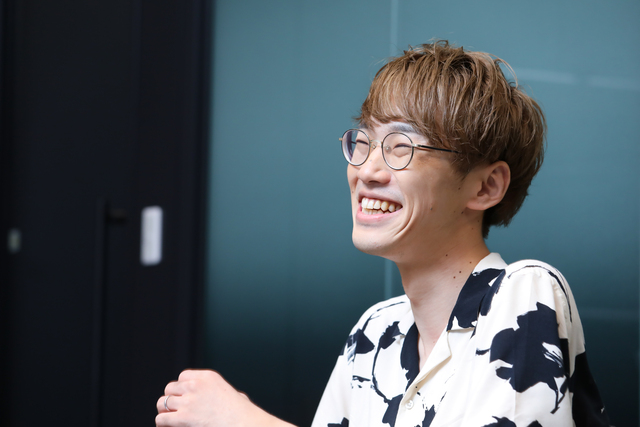
そこで見つけた仮説は、他の事柄にも当てはまる可能性があります。韓国コスメが人気になっている理由と、韓国料理が人気になっている理由は、もしかすると同じかもしれません。
そうやって仮説思考を鍛えていくと、商品やサービスが世に受け入れられるための構造がつかめるようになります。これをストックしていくことが、事業開発の第一歩です。
まずは自分の好きなことで、よく考えるところからスタートしてみる。そこにデジタルの色を当てはめられるようになると、市場に求められる事業開発になれると思います。
事業開発は、世界を変えられる仕事
—— 事業開発の仕事に、やりがいを感じるのはどんなときですか?
「世の中にあったらいいな」と思うものを、本当に生み出せることです。
5年前を思い出してください。多くの人が「現金はなくならない」と思っていました。それが今は、財布を持ち歩かないキャッシュレス社会になりつつありますよね。
想像すれば、世界は変わるんです。そして、実際に世界を変えるのが、事業開発です。
少し僕の話をすると、以前、子ども向け番組が見られるアプリ「NHKキッズ」をつくったことがあります。子どもを持つ親御さんたちが「あったらいいな」と思っていたサービスです。
リリースして以降、ユーザーである子どもたちの親御さんから「子育てが楽になりました」とか「子どもが食いついて離れません」とか、すごくうれしいメッセージをいただきました。
「あったらいいな」を実現し、誰かの世界を変えられる。これほどやりがいのある仕事はありません。
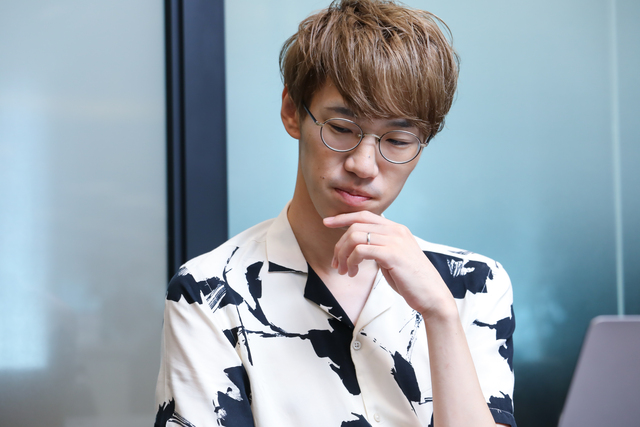
—— 一方で、事業開発ならではの苦労にはどんなことがありますか?
かかわった人が不幸になるリスクと背中合わせであることです。
僕はフラーで働く以前、自分で会社を経営していました。しかし、事業は思うように成長せず、目指していたゴールにたどり着くことができませんでした。
かかわる人の数年間を消費して事業をつくっていたので、「みんなの人生を変えてしまったな」と責任を感じて押しつぶされそうにもなりました。
事業開発は、事業をつくる責任者そのものですから、多くの人を巻き込むことになります。そうした意味で、仲間の時間を預かる責任と絶えず向き合わなければいけません。生半可な覚悟で務まる仕事ではないのです。
—— 他者を巻き込む分、重圧のかかる職種でもあると。
後悔はありませんが、当時のメンバーに対する申し訳ない気持ちは、今でも拭えていません。もしかすると、その悔しさがあるから、今も事業開発を続けているのかもしれませんね。
—— やりがいと責任、双方が大きな職業なのですね。そうした側面を踏まえても、林さんは事業開発としてのキャリアを若い世代に勧めますか?
もちろんです。改めて、事業開発って、世界を変えられる仕事だと思うんです。
日本って、もはやIT先進国ではないですよね。言い換えれば、まだ伸びしろがある国なんです。向こう10年ぐらいで、デジタルで社会が大きく変わります。これは間違いないことです。
その変化を見ている側になるのか、もしくは変える側になるのか——。どちらもすてきな選択ですが、若い世代の皆さんには、「事業開発には世界を変えられるチャンスがあるんだ」と伝えたいです。

合わせて読む:ロジックと直感。「いいとこ取り」するための作法
取材:オバラ ミツフミ、文:日野空斗、デザイン:黒田早希、撮影:遠藤素子