就職より起業が最も“安全策”な理由
私はUCLAを卒業後、投資銀行やファンドを経て、2015年にAIチャットボットサービス事業を展開する「ビースポーク」を創業しました。当初はインバウンド向けの観光案内を中心に始めましたが、現在では災害やテロへの対応など、危機管理方面にも活用範囲を広げています。
大企業での会社員生活も、起業も経験しましたが、私がいま22歳なら迷いなく就職はせずに起業します。
理由は2つ。まず、就職するよりも、起業のほうが自分のいる環境を安全にコントロールできるからです。
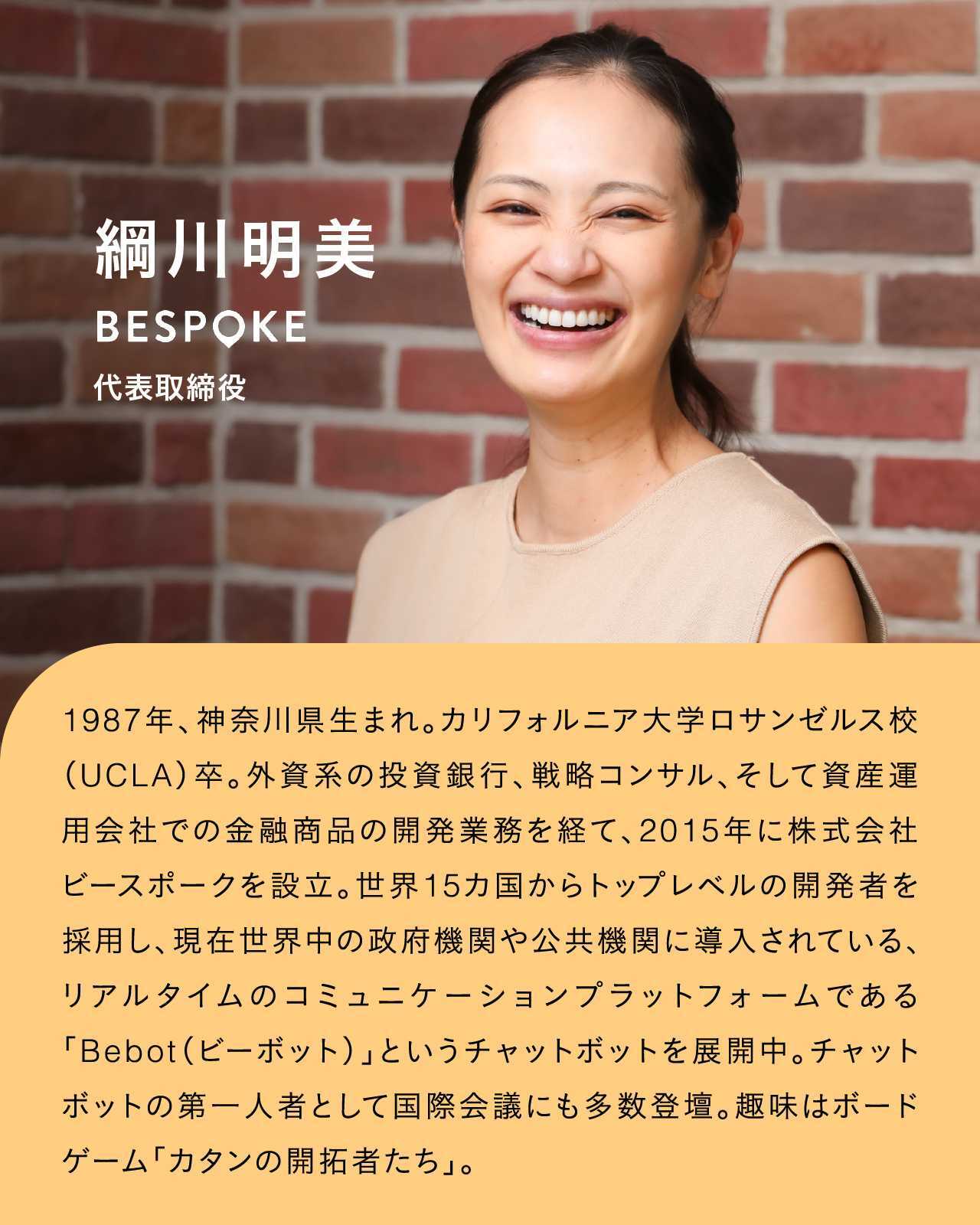
外資系の投資銀行やファンドで働いていた時は、昨日までいた隣の席の人が突然クビになっていたり、急な部署異動を命じられたり、会社の方針が変わったりと、周囲の事態に振り回されることが日常茶飯事でした。
もちろん、すべての企業が毎日シビアな競争に晒されているわけではないにしても、どんな企業でもポジションが限られているのは事実。本来、私たちは熾烈な椅子取りゲームで精神をすり減らすために努力をしているわけではないはずです。
しかも終身雇用の崩壊が叫ばれて久しい中、いつルールが変わるかも分からない場所に漫然と身を置くのはリスクが高い。
それならば、自分で判断を下せる範囲が広い起業のほうが、安全だと考えるのです。
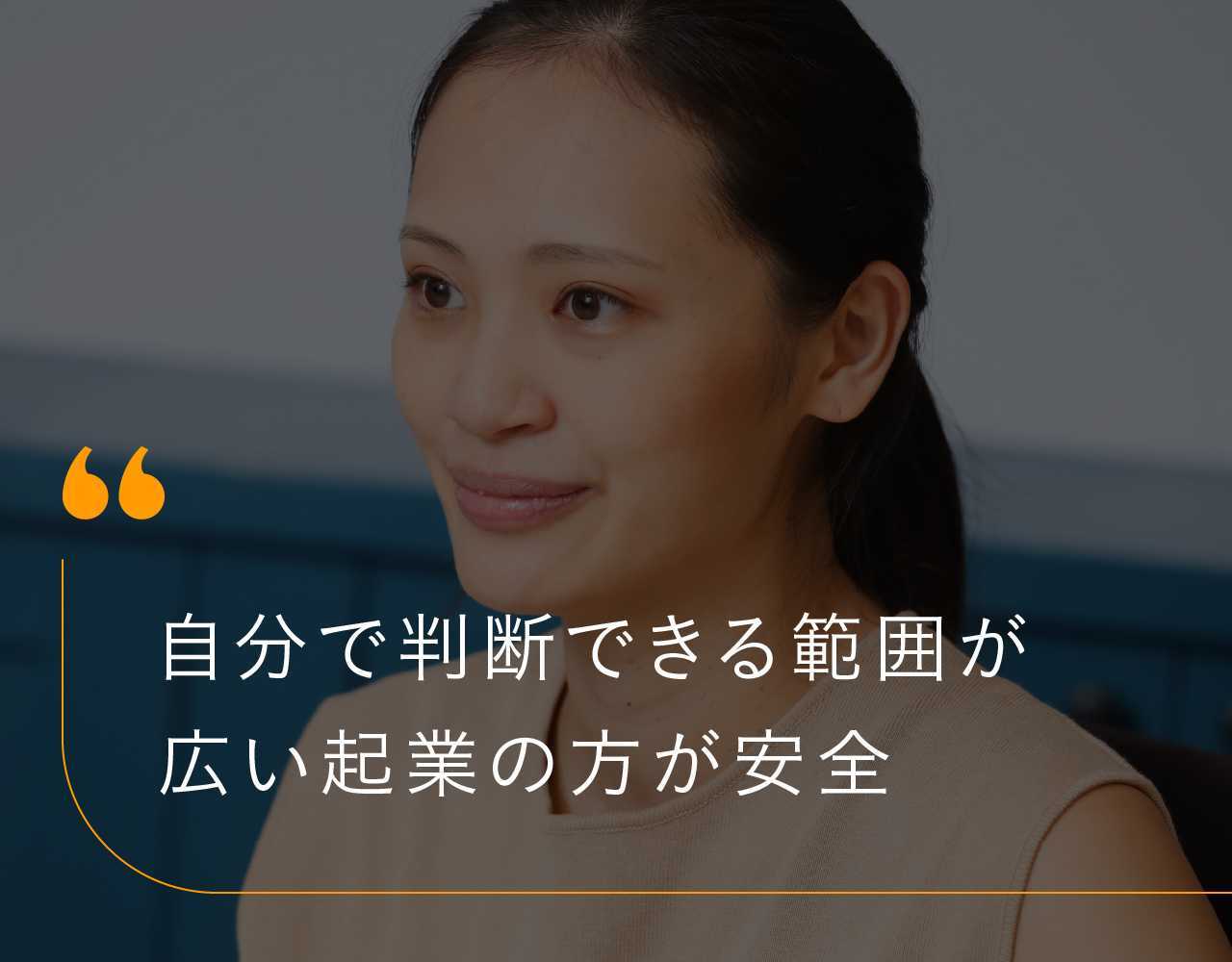
そしてもう一つの理由は、起業が最も満足感を得られ、自分が活躍できる仕事になる可能性が高いからです。
「まずは大手でいろいろ経験すべき」という意見をよく耳にしますが、個人的には賛成しません。実際、私も大手3社に勤め、日々慌ただしく仕事をしてきたものの、今となっては「役に立つスキルはほとんど学べなかった」と感じています。
結局は、すべてどこか他人事で、仕事に対して自分の気持ちが乗っていなかったのです。失敗してもどうにかなるだろう、誰かが後始末してくれるだろう。自分ができなくても埋め合わせする人はいるだろう、って。
だから、私は成長スピードも遅くて仕事が全然できない人間でした。いま、当時の自分を雇いたいかと聞かれたら、当然「ノー」と答えます。
会社員を経験したことで、「ビジネスマナーを守る」「対価をもらう以上は懸命に働く」など、ビジネスパーソンとしての基本は学べました。でも、これを習得するためにわざわざ大企業に入るのはもったいない。

やりたいことがあって大企業に入るならまだしも、「とりあえず社会人経験を積みたい」で大企業を選ぶのであれば遠回りになってしまいます。それならば、自分が起業する会社に大企業出身者をメンバーに入れ、その社員から直接ビジネスマナーを教えてもらうほうが効率的です。
本当に時間を割くべきなのは、自分が夢中になって取り組めることです。夢中でいれば、自然と貪欲になり、時間を惜しんで学ぼうとするはずだから。
だからこそ、いま22歳なら、自分がやりたいことに最短距離でチャレンジでき、自分が主役になれる選択肢を選ぶべきだと考えています。
成長の最短ルートは“自分事化”
起業という選択をするにしろしないにしろ、成長を求めるならば、どれだけ仕事を“自分事化”できるかどうかにかかっていると思います。
例えるなら「宿題に全く手を付けていない夏休み最後の日」状態に身を置くこと。つまり、仕事が“自分事化”すれば、怠けた分だけ自分にネガティブな結果が返ってくるので、必然的に手を動かさざるを得ないのです。

逆をいえば、必死になるほど、自分が追い求める理想に近づけ、楽しくなります。
何かに夢中になりたいならば、「欲しいけど今は手に入らないものを自分で作ってしまう」という思い切った手に出ることも有効です。
例えば、私が新卒で入社したマッコーリーは、実はリーマン・ショックの影響で中途採用しか行っていませんでした。
ただ、どうしても入社したかったので、リクルーティングやヘッドハンティングを行う企業20社ほどに「絶対損はさせないから紹介だけでもしてほしい」とテレアポをし続けていました。
ほとんどの会社が門前払いでしたが、最後の1社の担当者がたまたま同じUCLA出身で「同学のよしみでダメ元で聞いてやる」と言ってくれました。
その後面接に案内され「給料なしでもいいから入れてほしい」と訴えました。「数カ月の間に結果出せたら検討します」と月給10万円で1日約20時間働くという、相当ハードな条件ではあるもののチャンスを与えてもらい、最終的になんとか入社を果たせました。
ビースポークを起業をしたのも、自分が使いたいサービスがまだ世の中になかったからです。

趣味の旅行で、地元の人に教えてもらったお店をふらっと訪れるのが好きな私は、「この偶然の感動体験をスマホで再現できたら」と考え、AIチャットボット事業を始めました。
「起業」というと聞こえはいいですが、実際の社長業は取引先との調整や次々発生するトラブル対応など、雑用ばかり。
MeTooムーブメントの起こる前の起業で、VC(ベンチャーキャピタリスト)に「あなたも結婚して出産する予定あるでしょ? だから僕たち30前後の女性は相手しないんですよ」なんて言われて資金調達がままならないこともありました。
頭を抱えることも多い。それでも、自分が心から欲しいサービスを生み出せているから、仕事が楽しいんです。
“自分事化”には、大変なことさえも成長のエネルギーにし、ワクワクを生み出す力と私は信じています。
制約こそ、成長のチャンス
私は、仕事は「好きかどうか」より「活躍できるかどうか」が大切だと考えています。
「好きかどうか」を重視し過ぎると、ちょっとでも期待を裏切られた時にショックが大きいですし、逆に活躍できれば、自然と楽しさが付いてくるはずだからです。
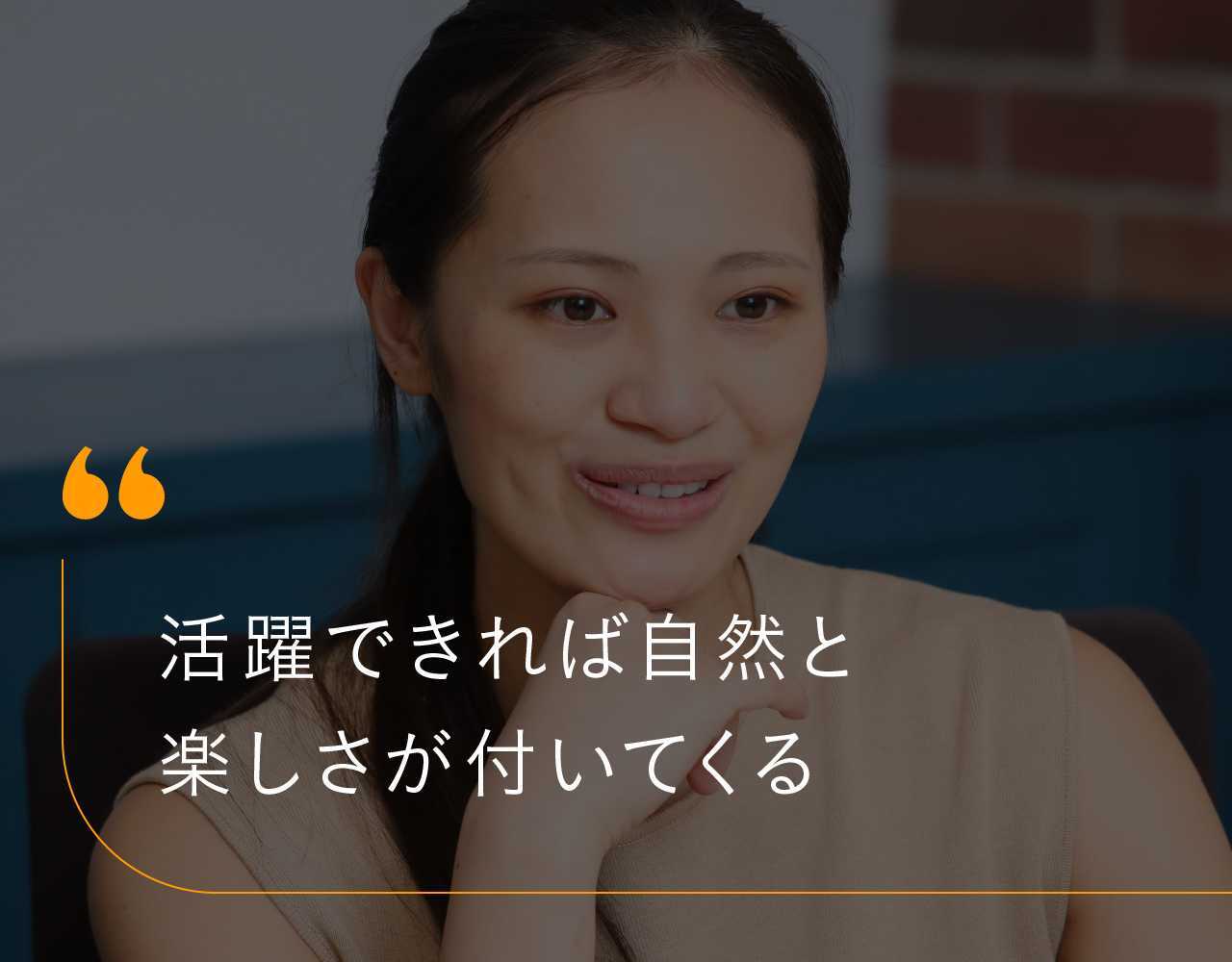
だから実際の仕事が「想像していたのとちょっと違う」と感じても、すぐに辞めるのではなく、一度本気で取り組んでみてほしい。
「目の前のことに真摯に向き合っていたら、いつの間にかブレイクスルーが起きていた」なんてことが起こり得るというのが、私の過去の経験から得た教訓です。
例えば、ビースポークは、当初は英語での案件に特化したAIチャットボットサービスとして展開しており、他言語の案件には原則対応していませんでした。
しかし2020年夏ごろに、コロナ禍の影響で英語での大きな案件が減少し、代わりに日本語の案件のオファーが増え始めていたのです。
経営方針を変えなければいけないため抵抗感がありましたが、他の打開策も出なかったので「仕方ないからやるか……」という感じで日本語の案件に着手し始めました。しかし、その後の売り上げが爆発的に伸びたのです。これが多言語展開に踏み切るきっかけになりました。
また、会社員時代には「朝5時半出社」を上司から求められていた時期もありました。

コンプライアンスに厳しい今だったらパワハラでほぼ確実にアウトですし、当時の私も「こんな時間に出社させるなんて、上司は頭おかしいんじゃないか!?」と思っていました。それでも朝から活動しているので他の人より有意義に使える時間は長かったですし、頭が冴えているので仕事で思わぬ発見をすることもありました。
周囲の環境や立場などの都合で、いろいろな制約から完全に逃れることは難しいかもしれません。組織の一員として働く場合はなおのことです。
ですので「今いる環境を最大限に楽しもう」というスタンスをとることは自分をポジティブにし、次のステップに進む力を蓄えることにも等しいと考えています。
物事を面白くするヒントは、意外と目の前にあるものなのです。
自分で選べば後悔しない
学生の皆さんの中には「やりたいことが見つからない」という人もいると思います。それ自体は決して悪いことではありません。実際、学生時代の私も「夢は会社員になること」と言っていたくらいで、近い将来起業することになるとはみじんも考えていませんでしたから。
それに、やりたいことのある人だけでは世界は回りませんし、やりたいことのない人には、「やりたいことがある人たちの応援団」としての活躍のポジションがあります。
しかし、「待ち」の姿勢では次に進むためのステップは掴めません。だから、いつでもチャンスを掴むための準備をする必要があります。
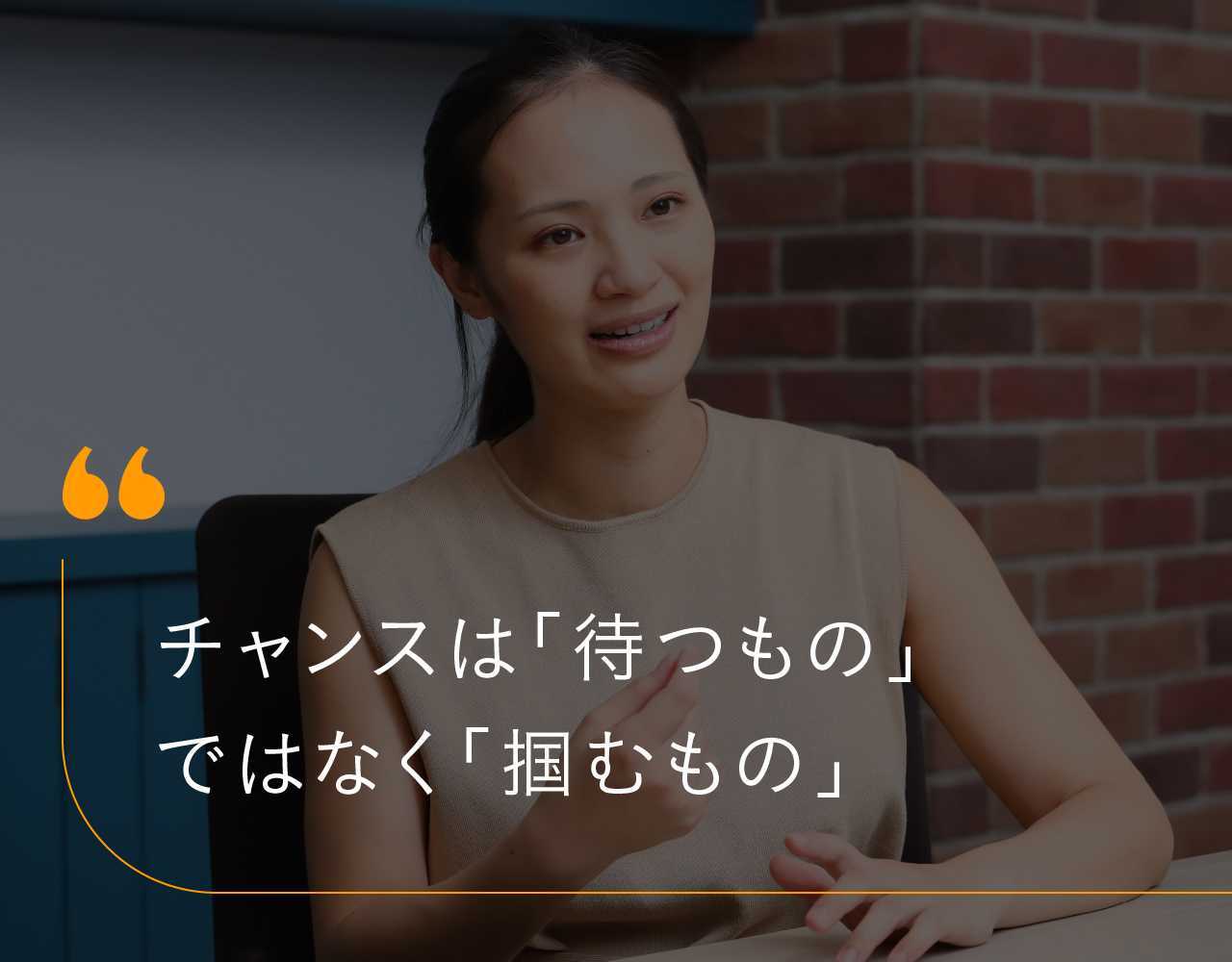
私が新卒で飛び込んだ投資銀行は、中途採用しか行っていなかったため、新人の教育制度は当然ありませんでした。
周囲の社員からは「仕事のやり方は勝手に盗んで。どんな仕事してるか知りたいなら、電話を横で聞いててもいいよ」と言ってもらえる程度でしたし、一つ上の先輩は34歳で、経験値に圧倒的な差がありロールモデルとするにはあまり参考になりませんでした。
ただ、イレギュラーな形での入社を望んだのは自分でしたし、「仕事が分からない、うまくできない」と泣き言を並べていても何も変わりません。
そこで、なんとかして活躍の場を作ろうと、とにかく行動量を増やすことにしました。顧客の雑用さえも引き受ける、といったほどにです。
例えば、私はブルームバーグ(経済、金融情報の配信、通信社、放送事業を手掛けるアメリカの大手総合情報サービス)のアカウントを持っていたので、アカウントを持っていない顧客を見つけると「何か欲しい情報があれば私に連絡してください! すぐに送ります!」と伝えました。
他にも、外国人の顧客が日本語の決算書を読むのに苦労している様子を見かけたら 「翻訳手伝います!」と手を差し伸べることもありました。
なりふり構わず自分にできそうなことは片っ端からやっていきました。すると、顧客からも顔を覚えられ、社内でも「君、ちゃんと勉強しているね」と評判になり、少しずつ仕事に慣れていくことができました。
与えられたものに従うだけでは、数多くの社員の中で存在が埋もれてしまう。だからこそ、水面から積極的に顔を出して自分をアピールしていく必要があるんです。
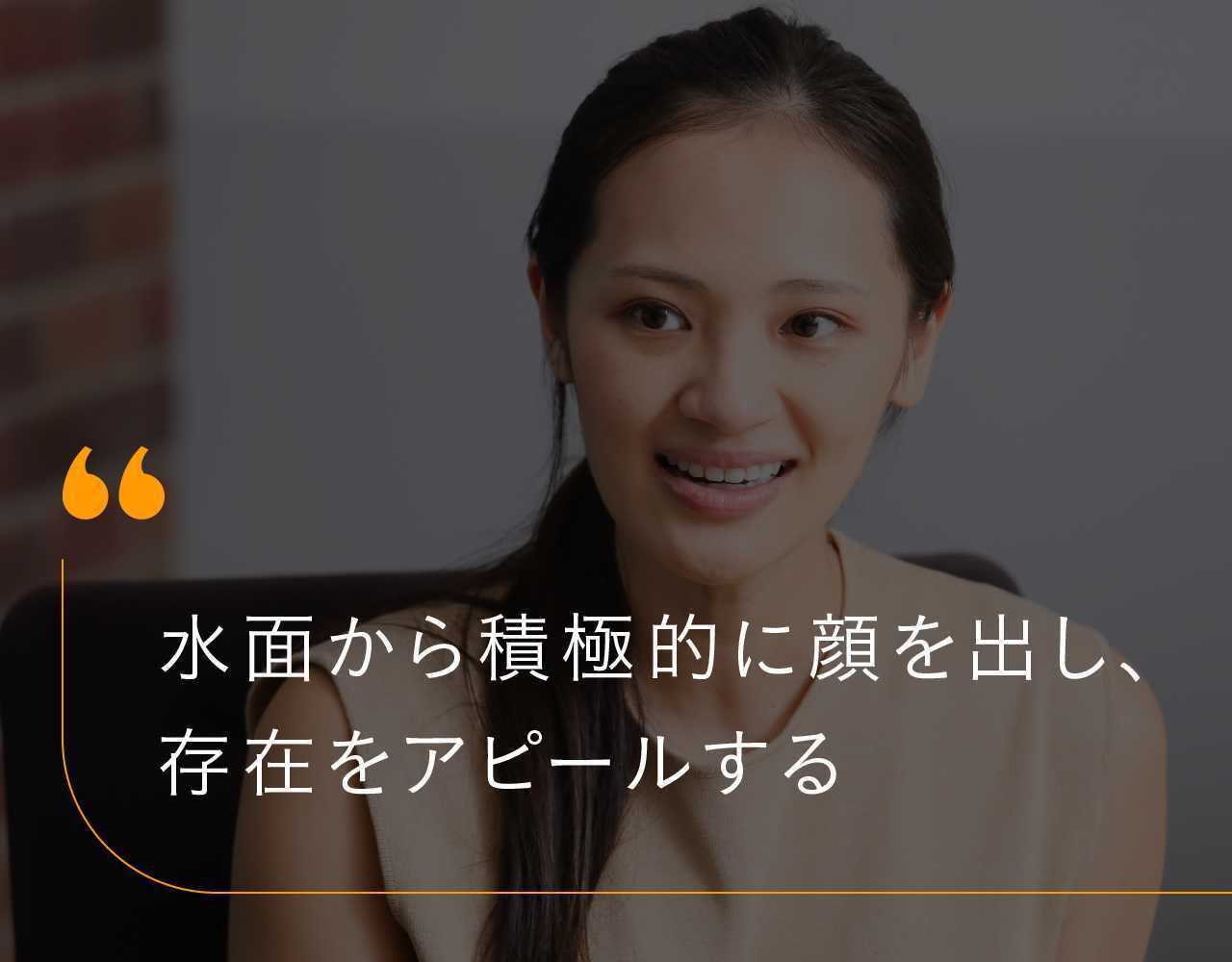
ここまで、自分自身の歩んできたキャリアの都合上、かなりタフなアドバイスを並べてきてしまいましたが、最後に一言。
安定を求め、穏やかに生きたいという人もいると思います。それはそれで一つの価値観として尊重されるべきものですし、結局は自分が何を求めているかが、進路選択の判断軸になるはずです。
ただ、どのような道を進むにしろ、人生を楽しむのであれば、折に触れて繰り返し己に問うてほしいことがあります。
今していることは、やらされていることなのか、それとも自らの意思で選択したことなのか。
キャリアの満足度は、どれだけ自分で自分の道を選べたかで決まります。人生の主人公は自分です。どうか周囲に惑わされず、自分が大切にしたいものをしっかりと見極めてください。

合わせて読む:【検証】ミレニアル女性とキャリア
取材・編集:佐藤留美、文:小原由子、デザイン:堤 香菜、撮影:遠藤素子