ファーストキャリアはコンサルに行く
いまでこそ、新規事業開発に熱を注いでいる僕ですが、22歳の時点では皆さんの多くと同様に、“何をやりたいか”は、はっきりしていませんでした。自分が考えたものを世に問うことさえできれば、業界や職種にはこだわりはなくて。
そんな中で、僕がいま22歳だったら、もう一度戦略コンサルに行くと思います。仕事の型が定まる20代の間に、モチベーションの高い同僚に囲まれて働くことが、大きな財産になるからです。
.png)
人間の脳みそは、短期的な合理性で判断するので、元来サボる方向に頭を使います。そのため、脳みそが柔らかい若いうちに、頑張ることが当たり前だと脳みそを勘違いさせたほうが、後々楽なんです。
新卒で入ったアーサー・D・リトルは、そうした意味では最高の環境でした。1年目から叩き込まれたのは、人の3倍働いて2倍の給料をもらうのが我々だという、とんでもないカルチャー。
クライアントは20歳も年上の、大企業の優秀な人ばかりです。そんな先達でも考えつかないような新しい発見を与え続ける仕事なので、限界まで思考を詰めなければいけません。
そんなことをしていると、毎日2~3時間ほどしか寝る時間がなく、寝過ごさないように浴槽に5センチだけお湯を張ってそこで寝ていました。
それくらいタフな環境でしたが、周りのモチベーションはとても高かった。
僕自身は、もともと意思があまり強くなく、周りの空気感に合わせるタイプです。ですから、新卒でコンサルに入り、モチベーションの高い人たちの中で働けたことは、大きな財産になっています。
働く姿勢だけでなく、汎用的なスキルを身につけるという意味でも、コンサルはファーストキャリアとして良い環境だったと思います。
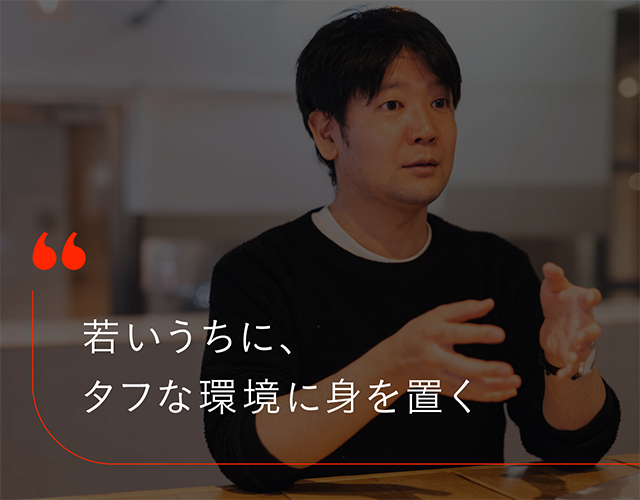
実際にコンサル卒業生は、業態・職種を問わず、大企業からベンチャーまでさまざまなフィールドで活躍しています。そのしたたかさの源泉はいくつかありますが、一番は彼・彼女らのキャッチアップ能力の高さにあると思います。
コンサルは、3カ月に1回程度、プロジェクトが変わるため、短期間で知識や情報をインストールして、いまの状況にアラインする能力が鍛えられます。
こうした習慣が、ユーティリティー・プレーヤー(1人でいくつものポジションを担当する選手)としての能力を高めてくれます。もっとも、40歳ぐらいになると器用貧乏になるので注意が必要ですが。
新卒で戦略コンサルに行った理由
ファーストキャリアで戦略コンサルに入社した理由は、自分なりの答えが評価される世界に魅力を感じたからです。
大学時代は、応用化学を専攻していました。
学生時代の僕は、自然科学とは、すでに神様が答えを決めている世界の中で、それを何とか理解しようとする学問だと思っていました(もっとも、いまはそんなことは思っていませんが)。
しかし、そうした唯一解を探すより、「井上の答え」が求められ、そこで勝負できる仕事がしたいと思い、コンサルに入社を決めました。
経営コンサルタントとは、新卒1年目から「井上はどう考えるか」を問われる仕事です。納品物がないので、アイデアや資料といった、自分の考えそのものがプリミティブにお金になります。
それがかっこいいなと、当時の僕は思ったんですね。
新規事業へのモチベーションは、コンサルタントとして多くの大企業の新規事業プロジェクトにかかわる中で、徐々に醸成されていきました。
例えば、あるメーカーの技術開発部門が、なんとなく思いつきでつくった面白そうな技術を、何とか価値に転換できないかを考えたり。
こうした案件に何回か携わる中で、新規事業は面白いなと思うようになりました。
一方で、このままコンサルに居続けることへの危機感も芽生えていきました。
新規事業の立ち上げはよく、「切れ味の良いナイフで切れ目を入れ、屈強なノコギリで切り開く」と表現されます。
素晴らしい戦略はもちろん価値があるものの、それを事業に落としこみ、しぶとく鍛え続けることの方が、より重要なのです。

特にいまの時代は、どんなに緻密に戦略を練ってモデルを考えても、市場に出してみるとうまくいかないことが多い。だからこそ、当初の戦略を練り直してピボットできるかどうかが、事業の成功を左右します。
例えば、Uberのアイデアなんて誰でも思いつきそうですよね。それなのにUberが成功したのは、ピボットを繰り返して、利用者側と配車側の両方のUXを本気で鍛え続け、マーケットや規制に柔軟に適応していったから。
アイデアが簡単に模倣できてしまう時代だからこそ、そうしたピボットのしぶとさが差別化を生むのです。
しかしながら、コンサルタントはあくまで戦略フェーズしか携わることができない。
200ページもの資料を作成してクライアントに説明しても、「この人たち本当にやってくれるのかな」「ぼくの方がこの事業本気でやりたいんじゃないかな」という感覚を持ち、歯痒さを感じていました。
この影響力の範囲を変えるには、コンサルから飛び出すしかないと思ったんです。
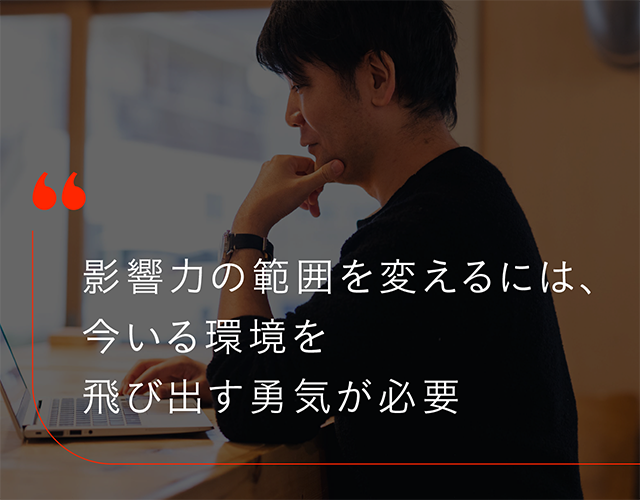
中東帰りの友人に刺激を受け転職
コンサルを辞めて外に出ようと決意した理由は、もう一つあります。
コンサルとして5年目に入った頃、同期で大手プラント会社(日揮)に就職した田部井君という友達が、久しぶりに中東から帰ってきたというので一緒に飲んだんです。
向こうで何やってんのって彼に聞いたら、もっぱらひげの伸ばし方を考えてると(笑)。確かに彼は、めちゃくちゃひげモジャになっていました。
ではなぜ、そこまでひげを伸ばしていたかというと、彼は当時、新卒5年目にして現地の外国人250人を管理していたのですが、彼らは目を離した瞬間サボるらしい。しかも言葉も通じないから、なめられたらおしまい。だからひげをはやし、怖い顔をすることだけ考えていたのだそう。

それを聞いた時に、僕はこのままコンサルにいたら、同質的な青白き秀才軍団しか動かせなくなるんじゃないかと、ものすごい危機感を感じました。
自分はコンサルティングファームにいるので、同期や後輩はとてもモチベーションが高く、仕事を振れば徹夜して上げてくるような人ばかりでした。
そういう人たちは、自分が苦労して引っ張らなくても、少し大きな相似形の背中を見せれば動いてくれます。実際に先輩方も、相似形で大きくなった人ばかりでした。
一方で、いずれ自分で事業を立ち上げたいと思った時に、それではまずいと思いました。
事業の立ち上げとは、いわば多様な能力を持つ仲間が協力して問題解決に挑む『ドラゴンクエスト』の世界です。資金調達からプロダクトの開発まで、全く違う脳みそを持った人たちを仲間にしないと、戦い抜くことができません。
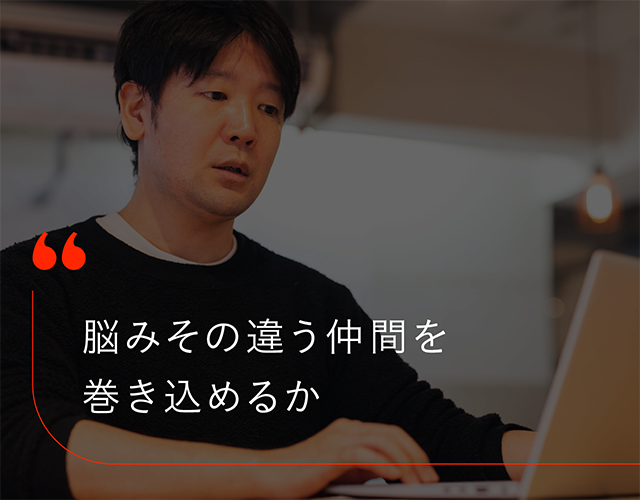
このままコンサルにいると、自分と似た脳みそ以外の人を動かせなくなる感覚があり、転職を決意しました。
事業会社とコンサルの違い
28歳の時に、5年間在籍したアーサー・D・リトルを退職し、メガネ屋のJINSに転職しました。約10年間在籍し、「JINS MEME」「Think Lab」という、2つの新規事業立ち上げを経験しました。
そんなキャリアなので、よくコンサルと事業会社の違いを聞かれるのですが、最も明確なのは思考法の違いです。
コンサルタントであれば、作成した事業計画に対し、「Why(なぜそうなのか)」を徹底的に聞かれます。
一方で事業会社の場合、経営者に事業計画を説明すると、特に社長から「So what(だから何?」と聞かれます。要は、「ごちゃごちゃ理屈を言っていないで、さっさとやろうよ」ということです。
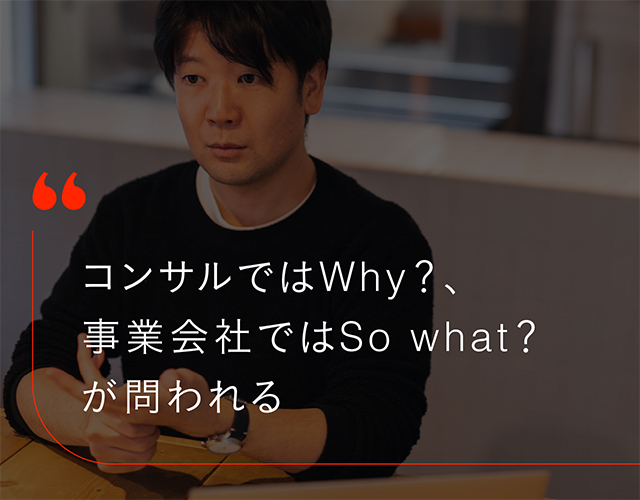
事業会社のオーナー社長は、僕の説明自体には信じられないくらい興味を持ちませんでした。途中からもう飽きてきて、iPadを見始めちゃうくらいです(笑)。
つまり、事前の説明よりも、実行して結果を出すことが求められる。
【ロールモデル】サイバー藤田、JINS田中社長。私を変えた名将の教え例えば、先にアプリのβ版を作成してフェイスブックに投稿してしまい、社長はそれを見て「ほう、そんなことをやっていたのか」と知る。新規事業開発にはそのぐらいのノリが必要です。
その違いは大きく、僕はコンサルの5年で鍛えた思考法を、次の5年である程度壊していきました。
もちろん、コンサルでWhyを考える能力を上げること自体は、間違ってはいないと思います。事業家の方々も、説明できないだけで、感性的な部分でしっかりWhyを考えていますから。
ただ、So Whatが問われる実際の事業では、思考する能力だけでなく、行動力や人を巻き込む力が求められます。
そのため、新規事業への強い関心がある学生の皆さんは、できるだけ早くそれができる環境に身を投じるのがいいのではないでしょうか。
新規事業に興味のある学生は多いと聞きますが、新卒が新規事業開発部門に配属されるのは、まれです。
そのため僕は、新規事業がやりたい学生には、正規ルート以外でアプローチすることをお勧めします。

例えばJINS時代、僕のいた新規事業の部門には、入社1年目の社員がいましたが、その人もいわゆる普通の配属ではなく、別ルートを駆使してやってきました。
知り合いの大学教授経由で、僕と社長にダイレクトメールしてきたんです。
面白い人だなと思ってオフィスに呼んだら、自作のプロダクトを持ってきて、見てくれと言うんです。そんなことされたら、我が社や業界を、相当勉強しているなと、こっちもうれしくなってしまいます。結局そんな彼に魅力を感じ、一緒に新規事業やろうよと、僕が引っ張りました。
このように、いまの時代は、やろうと思えばSNS経由で、会社のトップにもダイレクトにメッセージを送ることができてしまいます。面白そうな会社や職種があれば、思い切ってDMなどで話しかけてしまうのもありだと思います。
特に新規事業は、プロセスなんか関係なく、思い立ったら行動することが求められます。ですから、社長にDMしたJINSの彼は、その時点で適正があるともいえます。
異質な脳みそに触れ続ける
冒頭で、若いうちにタフな環境下に飛び込み、脳みそを勘違いさせたほうが良いという持論を述べました。
実はもう一つ、脳みその柔らかい若いうちに、心がけておくと良いことがあります。
それは、異なる“すごい脳みそ”に触れ続けることです。自分にはない思考を体得し、引き出しを多く持つことで、ビジネスパーソンとして著しく成長するからです。
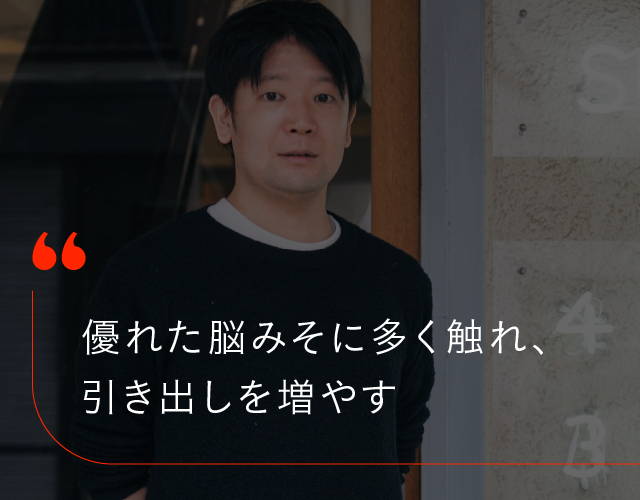
中でも僕のお勧めは、若いうちに複数のすごい上司と仕事することです。
例えば、カワグチさんという、すごく優秀な上司がいたとします。カワグチさんと仕事をすると、だんだん彼流の脳みその使い方を習得し、数カ月後には小さなカワグチさんを、あたかも“イタコ”のように降ろせるようになります。
複数の上司と仕事をして、こうした引き出しを増やしていくと、一流の思考を自在に使いこなせるようになります。
僕がファーストキャリアとしてコンサルに魅力を感じる理由も、プロジェクトごとに上司が変わるため、複数のすごい脳みそと絡みやすいからです。
中には入社早々、相性が良い上司に出会い、数年間ずっと一緒に仕事をする若手もいますが、注意が必要です。
同じことは、転職をはじめとした、長い目でのキャリア戦略にも通じます。
僕自身、最初の転職先にJINSを選んだ理由も、自分と全く異なる脳みそを持った社長に引かれたからです。
理屈っぽいタイプの僕と異なり、感覚的なセンスを持った、商売人そのものの人でした。
よく、「頭でっかちになるな」と叱ってもらいました。叱ってもらえる20代のうちに移動できたことも、良い決断だったと感じています。
今年の10月にSun Asteriskに転職しましたが、やはり決め手は、社長の小林(泰平)さんや取締役の梅田(琢也)さんをはじめ、「自分と全く違うタイプなのに、ビジョンは近い」という人々が多い環境に引かれたからです。
新しい価値を創ろうとしている人は全員そうだと思いますが、脳のタイプが違う人のほうが尊敬できるし、その人とビジョンレベルで共感できてしまうと、もうなんでもできるような気がしてくるんです。
そういう出会いの数々が、人生を豊かさにしてくれると思っています。
こうして種類の異なる“すごい脳みそ”に触れてきたおかげで、後輩の皆さんにキャリアのアドバイスをするなんていう偉そうなインタビューを受けている、いまの自分がいるのだと思います。

合わせて読む:ロジックと直感。「いいとこ取り」するための作法
取材・文:鈴木朋宏、取材・編集:佐藤留美、デザイン:國弘朋佳、撮影:井上一鷹(本人提供)