「きれい」と「美しい」の違い
今は、デザイナーとしてキャリアをつくっていくための選択肢がたくさんあります。
さまざまな会社がインハウスのデザイナーを抱えるようになり、フリーランスとして活躍する人も増えています。副業で同時にいくつものプロダクトデザインを手掛けることだってできる。
私がラジオ局傘下の制作会社に就職し、Webデザイナーを始めた2000年代に比べると、働き方は本当に多様になりました。デザイナーにとって良い時代になったと感じます。

そんな中で、私がいま22歳に戻るなら、ただ「きれいなデザイン」をするのではなく、できるだけ早く「美しいデザイン」ができる人になるのを目指すと思います。
「きれい」と「美しい」には、微妙な違いがあるんですね。
きれいなデザインとは、単にビジュアル面でかっこいいデザインを追求すること。
一方の美しいデザインとは、携わる事業の理想像やユーザー心理を考え抜き、何のためのデザインなのかをしっかりと定めてつくられたと感じるものです。
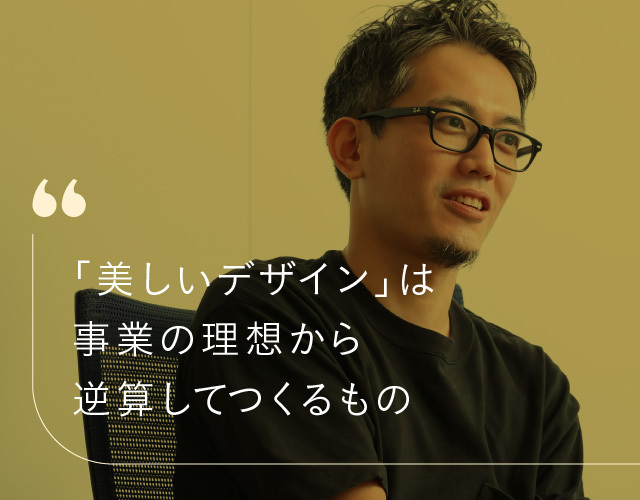
前者ができるデザイナーはたくさんいますが、後者ができる人はそう多くありません。私自身も、若い頃はきれいなデザインをつくるのが仕事だと考えていました。
その考えを根底から覆され、デザインには美しさが重要だと気づかされたのは、エムスリーでプロダクト開発の初期段階からコミットするようになってからです。
30代目前で言われた衝撃の一言
私は大阪芸術大学で映像を学んだ後、ラジオ局傘下の制作会社に就職し、その後USEN、エムスリー、ビズリーチと転職して2020年4月にエムスリーに戻ってきました。
これまでのキャリアを通じて、一つ確信を持っているのは、「デザインが何たるか」を語るには自分でつくれなければ話にならないということ。ラーメンをつくれないのにラーメン屋をプロデュースしても、説得力が生まれないのと同じです。
デザイナーは、いずれ他の仕事に就くとしても、まずデザインの基礎力を高めるのが不可欠です。
その意味では、自分の歩んできたキャリアに後悔はありません。よく、若いデザイナーに「制作会社と事業会社のどちらに入社するのがいいか?」と聞かれますが、個人的にはどちらも同じだと考えています。
追求すべきはステークホルダーが求めている本質的な価値の提供で、それは両者とも変わりありません。問題はどんな企業に入るかではなく、その企業で何をやるかです。

ただし、先ほど話した「きれいなデザイン」と「美しいデザイン」の違いに気づくには、働く環境や、そこで出会う人の影響が大きいのも事実です。
私がきれいなデザインをつくるだけのデザイナーでは先々行き詰まりそうだとはっきりと認識したのは、エムスリーに入ってからでした。
そもそも美大生だった頃を振り返ると、「次世代のタランティーノになるんだ!」と映画監督を真剣に目指していたんですね。
卒業後に入社した制作会社では、親会社のラジオ局で、番組ホームページのデザインや生放送の動画配信を行う毎日。当時はデザイナーとしての哲学などなく、文字通り、きれいにデザインすることしか考えていませんでした。
その後に転職する、「GyaO(現GYAO!)」という映像配信事業を手掛けるUSENでも、3年ほどの在籍期間でひたすら目の前のデザインワークをこなしていくような働き方をしていました。
連日終電で帰宅し、時にはオフィスの床で仮眠を取るような日々の中で、いつしか「このまま体力勝負で大丈夫か?」と疑問を持つようになったんです。
30歳を迎えるタイミングで再び転職活動を始めたのも、確固たる将来像や理想を抱いていたのではなく、単純に何かを変えたいという思いから。
そうして転職したエムスリーで、入社早々に「言われたことをやるだけだったら小学生でもできる」という一言を突き付けられます。
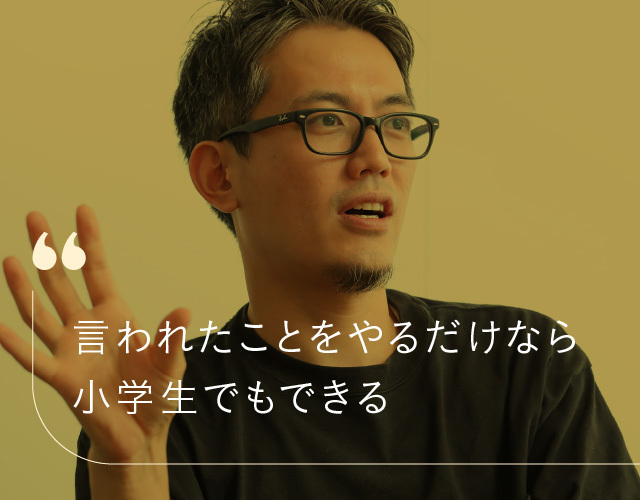
そのデザインにWhyはあるか
エムスリーは、医療業界向けにさまざまなプロダクトを提供している会社で、主力事業の一つである医療情報サイト「m3.com」は30万人以上の医師が利用するサービスになっています。
日本の医師の約9割が利用している計算になるのですが、このサービス以外にも製薬会社や医療従事者向けに国内外でさまざまなプロダクトを展開しています。
新規事業を立ち上げる機会も多く、デザイナーは、事業構想から普及フェーズまで幅広く携わります。プロダクトのUIデザインだけでなく、クリニックに貼らせてもらう告知ポスターのデザインなども含めて、とにかく守備範囲が広いんですね。
そんな環境に入り、最初の頃に言われたのが、当時の上司による先ほどの一言。とてもショックでした。
デザイナーはきれいなデザインをつくる人という思想に染まっていた私は、仕事が受け身というか、デザインは物事が決まった後にやるものという感覚があったのだと思います。
つまり当時の私には、何のためにデザインするのかというWhyがなかった。

それを上司に喝破され、「ユーザーのためにできることの集合体が事業なのであれば、事業を成功させることがユーザーのためになるのではないか」という考えに至るようになりました。
デザインで自分自身を表現していきたいのであれば、アーティストを目指したほうがいい。ビジネスの世界では、自分のためではなく事業のためだと理解できなければ、プロのデザイナーとして失格と言わざるを得ないでしょう。
当時の上司にその気づきを与えてもらい、きれいなデザインをつくる人から、「事業を変えられるデザイナー」になるべきではないのか、と考え始めたのをはっきり覚えています。
新規事業で学んだデザインの価値
その後も、事業を成長させるために考えて動くという、デザイナーにとっては慣れない仕事を任される機会がたくさんありました。
例えば、当時は10万人ほどの会員数だった医師向けのメールマガジンを拡大させるプロジェクトに、デザイナーの1人として参加した時は、いきなり「チームをよろしく」と言われました。
あまりに突然の出来事で、「え? 僕は肩書もないただのデザイナーなんですけど」と反応するしかありませんでしたが、今思えば気づきを与えるためのアサインだったのかもしれません。
このプロジェクトにリーダーとして携われたことが、「何がユーザーのためになるのか」と、本質的に考えるための分水嶺になりました。
その後、開発チームのメンバーとして立ち上げた「エムスリーデジカル」というクラウド型の電子カルテの成功体験も大きかったと言えます。
このサービスを立ち上げる際、デザインするコンセプトで掲げていたのが、「医師が1秒でも多く時間を短縮できるようなデザインを目指す」というものでした。
そのために、 AI搭載の自動学習機能によって診察や会計の手間を大幅に削減するとともに、ぱっと見た瞬間にユーザーが直感的に何をすればいいか分かるデザインを目指しました。

こうして、要素技術から搭載する機能まで全体を考えてデザインした結果、ユーザーから一定以上の評価をいただくことができた。美しいデザインを追求するとはどういうことなのか、各論で理解できた瞬間でしたね。
マネジメント修業を経て出戻り
手前みそですが、エムスリーのように事業開発そのものにコミットを求められる環境だと、デザイナーとして一皮むけるチャンスが数多く転がっています。
転職前は、エムスリーでインハウスのデザイナーが活躍していることすら知りませんでしたから、偶然がきっかけで良い選択ができたと思っています。
若いうちは、何となく「このままでいいのか」と不安を持つ瞬間が必ずあります。そんな時、今いる環境はデザイナーとして事業づくりにどれだけコミットできるのか?と自問してみるのもいいかもしれません。
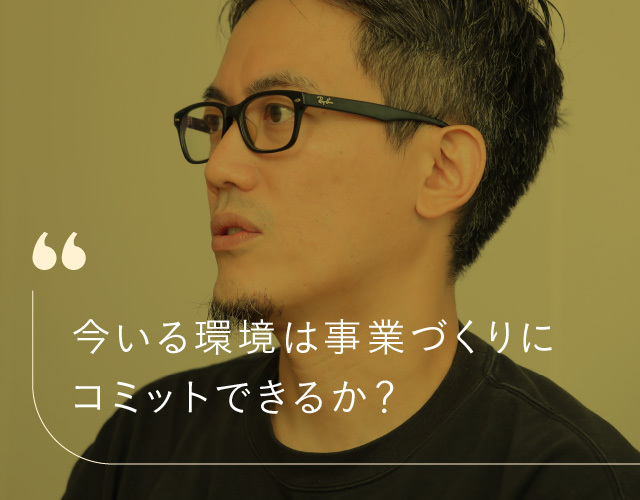
ちなみに、そんな私が一度エムスリーを辞めてビズリーチに転職したのは、さらにステップアップするために何かが必要だと感じていたからです。
当時の気持ちを言葉にするのは難しいのですが、一番近しい表現は「今と違う成長を求めていた」となります。
エムスリーは、職種を問わず事業づくりのプロフェッショナルが集まる会社で、今でも代表の谷村(格さん)が、自分で新規事業のアイデアを生み出しているほどです。
だからこそ、マネージャー職だけに集中できる環境ではなく、マネジメントを学ぶのが難しかったんですね。組織づくりやマネジメントを体得するために、一度エムスリーから出てみようと考えたのが、転職の経緯でした。
実際に、転職先のビズリーチでは、自分の望んでいたチームマネジメントやデザイナー向けの研修設計などを手掛けることができました。
そして昨年4月、エムスリーがデザイナーの組織をより大きくしたいと考えていると聞き、学んだことを生かそうと出戻りを決めます。
私のデザイナー人生で一番の成功体験は、プロダクト面でもチームマネジメント面でも「エムスリーデジカル」に間違いありません。再入社の相談を受けているうちに、「エムスリーデジカルのような開発チームをたくさん生み出したいけれどできていない」という話を聞き、エムスリーに復帰する運びとなりました。
空気を変えるのがデザインの本懐
復帰後は、主に2つの役割を担っています。
1つは、デザイナーチームの組織マネジメント。もう1つは、CDOとして、エムスリー自体や事業、組織などのデザイン戦略をつくることです。
ただ、マネジメントだけでなく、携わるプロダクトのデザイナーとして今でも手を動かしています。ユーザーの抱える課題を探りながら、プロダクトマネージャーである企画実行者の伴走もしています。
CDOという肩書が付いても、自分の手で事業をつくっていきたいという思いは消えていません。
そう考えると、今はある意味、「デザイナー出身の事業家」としての準備体操のような段階なのかもしれません。
これからの時代、デザイナー出身の事業家や起業家がもっと増えるべきだと思っていますし、私が目指しているのもそんな役割です。
デザイナーは、ビジネスパーソンとは別の角度から本質を問うことで、左脳で考えた理屈では説明できないようなアイデアを生み出すせると考えているからです。
時代やビジネスにくさびを打つ、あるいは空気を変える、流れを変えると表現できるかもしれません。
.jpg)
最近、デザイン思考という言葉を耳にする機会が増えているのも、既存のやり方ではビジネスをスケールさせづらくなったからだと思うんですね。
事業を成功させるには、今まで以上にデザインの力が求められるはずです。
ところが、今はUIやUXデザインの方法論が多く出回り過ぎたせいか、失敗を恐れているからなのか、要領よく仕事をこなすのがうまいデザイナーが増えているように感じます。
それで空気を読み過ぎた結果、きれいなデザインをすることに終始してしまうというか。
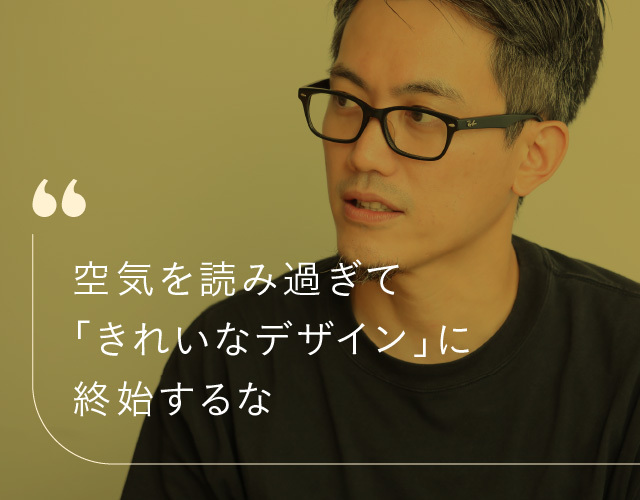
デザイナーの業務範囲が増えているからこそ、スキルを磨き、生産性を高めるのも大切ですが、そつがない形で仕事に取り組むだけでは面白さは生まれません。
もっと自由で無邪気に取り組めばいいのにと感じることも少なくありません。空気を読まずに「こいつ、バカか」と思われてもいいじゃないかと。
本来、それこそがデザイナーの生み出す強みだったのではないでしょうか。
私は幼少期から絵を描くのが好きだったのですが、描いた絵を見てもらって喜ぶことよりも、どうすれば絵を増産できるかと考えるような子どもでした。
描いた絵をコピーし、どのように製本して配本すればいいのか。いくらで販売すれば、いくら儲かるかとも考えていました。
その原体験からして、デザインはビジネスの手段だという考えが根底にあるのだと思います。
手段を学んだら、次はデザインの力を使って仕組みづくりや事業づくりがしたい。もし、同じような感覚を持っているデザイナーの方がいるなら、できるだけ早くそれができる環境に身を投じるのがいいのではないでしょうか。
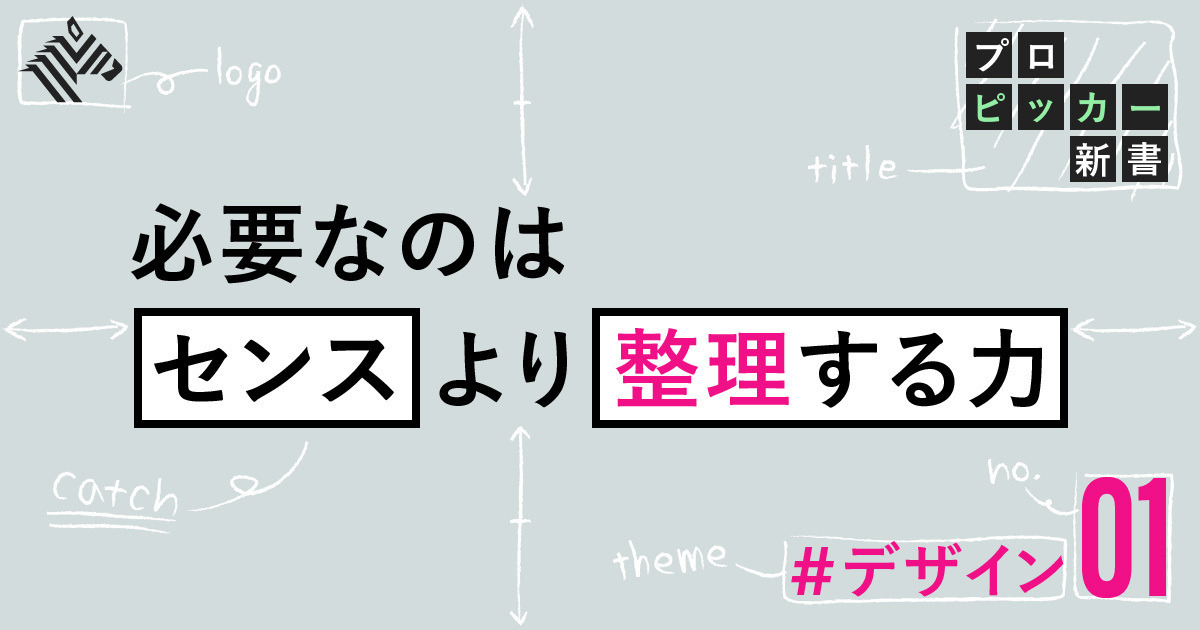
合わせて読む:【週末教養】ビジネスの必須スキル「デザイン」を基礎から学ぶ
取材:佐藤留美、原留千依、文:小谷紘友、編集:伊藤健吾、デザイン:岩城ユリエ、撮影:遠藤素子