話し方より大切なプレゼンの極意
営業や事業戦略のプレゼンテーションだけでなく、ちょっとした社内会議やウェビナー、就職・転職の面接でも。
多くのビジネスシーンがオンライン化した今、「プレゼン」のスキルは社会人のみならず学生にも必要不可欠なものになっている。
以前なら口頭で済んでいたようなコミュニケーションも、パワーポイントやGoogleスライドなどで資料を作成して説明しなければならない。そんな機会が増えたことで、プレゼンの方法論や資料の見た目を気にする人が多くなった。
実際、コロナ禍の昨年11月にNewsPicksで公開された以下の動画は、7000近いPicks数がつく人気コンテンツとなっている。
【実践仕事術】プレゼンの神、澤円の資料作りを全公開この動画では、IT業界でプレゼンの神様と称される澤円さんが自身の資料作成〜スピーチ術を解説しているが、重視しているポイントは次の11個だと述べている。
プレゼン環境に左右されない資料作り
骨子から始めよう
テキストは少なく
ビジュアルは統一せよ
アニメーションで情報を隠す
スライド枚数より「尺」で考える
資料管理のデータ命名規則
ノイズを排除せよ
共感を呼ぶ課題設定
資料作りは(プレゼンの)予行演習
起承転結に囚われるな
一貫して伝えているのは、スピーチのやり方以上に「相手の共感を呼ぶ課題設定」や「聞き手がハッピーになるプレゼントを明確にすること」が重要だという点。つまり、伝えたいメッセージの骨子作りや資料の見せ方を工夫することが、プレゼン成功の鍵を握る。
そこで今回は、提案や資料作成の仕事を行うことの多い職業に就くJobPicksロールモデルの投稿から、プレゼン資料作りに役立つ経験談とおすすめの参考書を紹介していこう(注:ロールモデルの所属・肩書は、全て本人が投稿した時点の情報)。
「良いプレゼン」の定義を知る
まず紹介するのは、「良いプレゼンとは何か?」を知ることのできる経験談だ。
GMOペパボの取締役CTO(最高技術責任者)で、一般社団法人日本CTO協会の理事も務めている栗林健太郎さんは、CTOになったばかりの頃、経営陣にある施策を提案する中で社長から本質的な指摘を受けたという。
「そのことについてのあなたのビジョンは何なのですか?」
統括するチームの意見や、他社の動向を並び立てて説明するより、自分が相手(この場合は自社の経営陣)に対してどんなビジョンを持って提案したいのかを説明せよ、というわけだ。
CTOはエンジニアの代表ではない
「CTOとは、エンジニアの代表ではなく自らのビジョンに基づいて意志決定する役割である」ということです(同業の先輩からの教えではありませんが)。 わたくしがCTOになってしばらくした後、経営メンバーに対して提案を行う機会がありました。エンジニアたちの声を集め意見を取りまとめた上で、ある施策の提案を行ったのです。その内容を聴いて社長がひとこといいました。「そのことについてのあなたのビジョンはなんなのですか?」と。 つまり、CTOというのは社員の意見を代表してものをいう立場ではなく、自らのビジョンをもって語るべきだと諭されたわけです。 CTOに限らず、CXOと称される人々の最も重要な役割は、ビジョンを描き意志決定をすることにあります。しかし一方では、それらの仕事には「こうやれば確実」という方法があるわけはありません。つまり、どうしても不確実性が残る中でことを行う必要があります。 そうすると、ついつい何か確実なことにすがりたい気持ちが出てきます。たとえば社員がこういっていたからとか、他社がこうしているからとか。もちろん、ひとの意見を聴くことは大事ですが、そのことに自分の意志決定の責任を転嫁することがあってはなりません。そんな教訓を得たエピソードでした。
栗林さんはこの時、意思決定に対する責任を痛感したという。これはまさに、上記で澤さんが挙げている「共感を呼ぶ課題設定」が重要という話にもつながる。
また、コンサルティングファームのA.T. カーニー(グローバル・ブランド名:カーニー)など、複数社の仕事を兼務する杉野幹人さんは、若手コンサル時代に先輩から「プレゼンに限らず、ビジネスコミュニケーションの極意を教わった」とコメントしている。
資料はゼロか1割がよい
これは、わたしが経営コンサルタントの先輩から教えてもらったプレゼンの
「資料はゼロか1割がよい」。この話には、相手に伝えたいメッセージを考え抜き、練り込むプロセスこそが重要という教訓が隠されている。
コンサル推奨「プレゼン内容を練り込む時の参考書」3選
では、プレゼンの前に行う「考え抜き、練り込むプロセス」は、どうやるのがベターなのか。メッセージ構成を練る上で参考になる書籍を紹介していこう。
■『イシューからはじめよ——知的生産の「シンプルな本質」』(出版社:英治出版)
プレゼン資料作成や提案が仕事の大きな割合を締める経営コンサルタントのロールモデルが、参考書として挙げる書籍で最も多かったのが、マッキンゼー出身の安宅和人さんが書いた『イシューからはじめよ』だ。
本書の何が役立つかは以下の記事に詳しいが、ここではPwCコンサルティングの大塚泰子さんの推薦理由を紹介しよう。
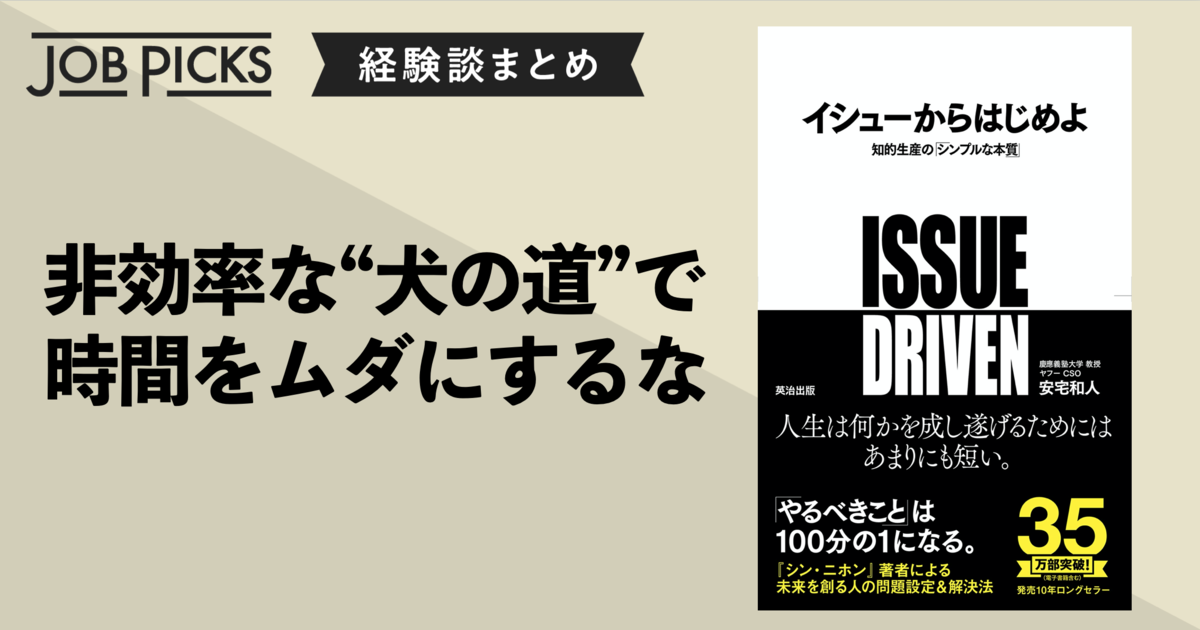
【証言6選】『イシューからはじめよ』で生産性が劇的に上がるワケ
イシューからはじめよ
コンサルタントの基本の基という感じです。 issue shaper
大塚さんの言葉を借りれば、この本を通じて「いきなり分析したり、手を動かす前に、課題の本質を考え抜き、その課題に対する論点と、それに対する自身の仮説を持つ」習慣を身に付けることができる。
これは、プレゼンの骨子を考える際の最重要スキルといえる。
■『考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則』(出版社:ダイヤモンド社)
『イシューからはじめよ』に次いで推薦者の多かった書籍は、米の作家兼コンサルタント、バーバラ・ミントさんが著者の『考える技術・書く技術』だ。
タイトルの通り、本書は「物事を考えて伝えるのは技術である」というテーマのもと、数々の方法論を紹介している。
経営コンサルタントの山本大輔さんは、本書が伝える「ピラミッドストラクチャーに基づくライティング技術は、身に付けておくとドキュメンテーション能力を高く評価される」と述べている。
考える技術・書く技術 入門&ワークブック
コンサルタントの推薦する本を見ると“難しい”本が並びます。(仕事柄当
他には、プレゼンにおけるメッセージを練り込む思考力を鍛える本として、
■『ロジカル・プレゼンテーション―自分の考えを効果的に伝える戦略コンサルタントの「提案の技術」』(出版社:英治出版)
を推薦するロールモデルも複数人いた。
ロジカルプレゼンテーション
考えること、伝えることの種類と脳の癖とその特性を知って、それをもとに
これらの本を参考にして、プレゼンにおける課題設定や骨子作りのやり方を学んでみよう。
デザイナー推奨「伝わる資料作りの参考書」3選
続いて、考え抜いたメッセージを「どう相手に伝えるか?」を工夫する際に役立ちそうな書籍を紹介しよう。
■『ウォールストリート・ジャーナル式図解表現のルール』(出版社:かんき出版)
この本は、米の大手新聞THE WALL STREET JOURNALで図表表現のディレクターとして活躍した著者が「図表作りのコツ」をまとめた一冊だ。
プレゼン資料は、写真や図版を用いて分かりやすく見せるのが大切だといわれるが、特に図表に関してはエクセルで作成したグラフをそのまま貼り付ける人も少なくない。
そこでひと工夫する上で、NewsPicksのグラフィックデザイナー斉藤我空さんは「データを可視化して相手に複雑な情報を分かりやすく伝える技術」が身に付くと本書を薦めている。
ウォールストリート・ジャーナル式図解表現のルール
データを可視化して相手に複雑な情報をわかり易く伝える技術が詰まっており、体系的に図解表現の技術を進化させてくれるのでおすすめ。似た系統の本が数多く存在するが、この1冊で初心者の方が学びたいことはほぼほぼ網羅することができる。グラフは作り手によって大きく印象を歪めてしまうことができてしまうので正しい情報を正確に伝えるために必要不可欠な本です。
■『Paul Rand: A Designer's Art / ポール・ランド デザイナーの芸術』(出版社:ビー・エヌ・エヌ新社)
また、ビジュアルの上手な使い方を学ぶ上で『Paul Rand: A Designer's Art』が役立つと薦めるのは、同じくNewsPicksのグラフィックデザイナー九喜洋介さん。
著者のポール・ランドさんは、IBMのロゴなど有名な作品を数多く持つ著名なグラフィックデザイナーだ。少々値が張るデザイナー向けの専門書だが(Amazonでは税込5060円)、九喜さんは「ポール・ランドの仕事のほとんどが、ワンメッセージとワンビジュアルだけで成立している」とすごさを語る。
これは、プレゼン資料作成で超が付くほど重要なポイントだ。一読する価値はあるだろう。
Paul Rand: A Designer's Art / ポール・ランド デザイナーの芸術
IBMのロゴを作ったことで知られる、20世紀を代表するグラフィックデザイナー、ポール・ランドの仕事がまとめられた一冊。 “ グラフィックデザインの本質は視覚的関係性である。 無関係なニーズやアイデア、言葉、絵のかたまりに意味を与えるのだ。 素材を選び、組み合わせるーーそして面白くするーーのが デザイナーの仕事だ ” (ジョン・カウウェンホーブン) ポール・ランドの仕事はどれもシンプル。ほとんどが、ワンメッセージとワンビジュアルだけで成立しています。 しかし、どれも独創的で、今まで見たことがない印象を受けます。 あるメッセージを伝えるために、何を選び、どう配置するか? たったそれだけのことで違いを生み出すこと。 同じ要素を自分が与えられたらどうするかを考えながら読むことで、いろんな発見がある一冊。
■『言葉ダイエット メール、企画書、就職活動が変わる最強の文章術』(出版社:宣伝会議)
さらに、「ワンメッセージ・ワンビジュアル」を追求する上で参考になりそうなのが、DMM.comのグラフィックデザイナー滝見壮平さんが推薦する『言葉ダイエット』。
電通のコピーライターでクリエイティブディレクターの著者、橋口幸生さんが本書で伝えているのは、“言葉の贅肉”を削ぎ落とすメッセージング術だ。
滝見さんは、「文章をブラッシュアップする時の思考が、グラフィックデザインの構成を練る時の思考に驚くほど近い」とも述べている。
言葉ダイエット
グラフィックデザイナーを目指す人にお勧めするのは不思議に思われるかも
プレゼン資料に使うフォントなど、見栄えを良くする技術を学ぶことも大切だが、それ以上に「伝えたいメッセージを短くまとめて構成する」技術があると資料全体の見せ方が変わる。
端的にメッセージを伝え、相手の心をつかむプレゼン資料作りに、必須の知識だといえるだろう。

合わせて読む:【鉄則】伝わる資料は、「余白」で決まる
文・デザイン:伊藤健吾、バナーフォーマット作成:國弘朋佳、バナー画像:iStock / TCmake_photo