「営業職はきつい仕事」は本当?
—— 営業職と聞くと、「ノルマに追われる泥臭い仕事」というイメージを持つ人が少なくないようです。実のところ、営業職とはどのような仕事内容なのですか?
そうした側面も少なからずありますが、新卒から法人営業職を担当してきた私からすると、やや誤解があると思います。
営業職の役割は、まず会社の売上をつくることです。
売上をつくるために必要なことは、自社の商品やサービスを購入・契約してもらうために、顧客のニーズを理解し、課題を解決することです。
また、どの顧客に、どのタイミングで提供するかによっても商品の価値は異なります。つまり、たとえ同じ商品でも、営業活動によって価値が変わると把握しなければなりません。
もし現状のサービスで契約に至らないのであれば、ヒアリングを通して「どのような機能があれば顧客の課題を解決できるのか」を詳細に突き止め、その情報を製品開発にフィードバックする役割も求められます。
顧客によって問題や悩みの種類はさまざまですから、それを特定するのは簡単なことではありません。
柔軟に課題を特定し、解決していくプロセスは泥臭いものですが、むしろクリエーティブと表現するのが正しいと思っています。
「顧客の前でペコペコする」「とにかくテレアポをして新規開拓営業の商談を獲得する」といったイメージを持たれているのであれば、きっと前時代的な営業方法や営業形態の印象が強く残っているのでしょう。
営業の現場も進化しており、クリエーティブで付加価値の高い営業手法をしている会社は多数存在します。
—— ひと口に営業職といっても、IS(インサイドセールス)、FS(フィールドセールス)、CS(カスタマーサクセス)と大きく3つの種類があります。そのどれもが、課題解決を目指す仕事なのですか?
その通りです。
私が定義している営業職とは、自社サービスを用いて顧客の課題解決をし、その結果として成約を通じた売上をつくっていく仕事であり、その意味合いではISもCSも営業職だと考えています。
ISは、マーケティングが獲得したリード(見込み客)のニーズを明らかにし、FSに引き継ぐ役割を担っています。顧客と長期的な関係性を築き、適切なタイミングでアプローチする、クリエーティブな仕事です。

FSは、商談を通して顧客に中長期的な利益創出をイメージさせ、自社の商品やサービスを購入・契約してもらう仕事です。顧客が抱える本質的な課題を掘り起こす、営業職の中でも非常に難度の高い役割を担うのが特徴です。
CSは、顧客に伴走しながら課題を解決し続け、顧客と自社の利益を上げ続けるのがミッションです。サポート対応のイメージを持たれがちですが、顧客のLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の最大化を実現する、営業職の中でもかなり大切なポジションです。
たしかに役割は異なりますが、「正しく課題を導き出し、それを解決する提案をしていく」という意味で、業務の目的は通底しています。
営業職は一般的に“根性論の仕事”と誤解されがちですが、気合いだけでなんとかなるようなものではなく、非常に難度の高い仕事なのです。
営業職で身につくスキルとは?
—— 営業職を経験すると、どのようなスキルが身につくのですか?
大きく2つの力が身につくと思っています。
1つは先ほども申し上げた「課題を特定する能力」、もう1つは「調整力(交渉力)」です。
営業職は、顧客だけでなく、社内のメンバーや外部パートナーなど、数多くのステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、仕事をする必要があります。
顧客の要望を開発スタッフにそのまま伝えたところで自社製品が良くなるとは限りませんし、決裁者と現場で働くスタッフ双方のニーズをかなえる必要があるなど、あらゆる方向への目配りが求められます。
これらの能力は、営業職以外にも強みとして生かされるものです。

ですから、ファーストキャリアで営業職を経験していると、先々のキャリアが広がりやすいと感じています。
—— 例えば、営業職で得たキャリアは、どのような職種に生かされますか?
営業職で得たスキルや知識、ノウハウが存分に生かされるのは、営業企画です。営業企画は営業戦略を立てる仕事ですから、現場経験があるのとないのとでは、成果や実績にも差が出るでしょう。
他にも、適切な課題を導き出す能力はマーケターやコンサルタントに、関係を構築していく能力は広報や人事の採用業務に生かされると思います。
売上をつくる能力はビジネスの根幹なので、経営者に転身される方も少なくありません。
私がファーストキャリアに営業職を選んだのは、「営業を極めることは、ビジネスをするうえで大きな武器になる」と考えたからです。
現在は営業組織コンサルティングを主な業務としていますが、ファーストキャリアに営業を選んだのは正しい選択だったと思います。
とはいえ、営業職を経験すれば、誰でも能力が身につくわけではありません。
当然スキルを得ようと努力する必要がありますし、正しくスキルを身につけさせてくれる会社を見極めなければ、キャリアを棒に振ってしまう可能性もあります。
それこそ、「とにかくテレアポをしなさい」「飛び込み営業で新規顧客を開拓しなさい」といった研修しかしてくれないような企業に入社してしまったら、正しい営業力は身につきません。
—— 正しい営業力を身につけるには、どのような企業に入社すればいいのですか?
個々人のパフォーマンスに高いレベルで差がつかない営業組織は、優れた営業ノウハウを持っていると思います。
毎月20万円しか売れない営業と毎月100万円を売る営業が混在する組織より、すべての営業が毎月60万円を売る営業組織の方が、体系的なノウハウを持っているはずです。
例えば、私が新卒で入社したキーエンスは、とにかく営業ノウハウを体系化している会社でした。
キーエンスでは、「気合い」や「根性」、「センス」や「偶然」といった具体的でない言葉を使いません。
売れた理由を明確に言語化し、それらをノウハウ化して、すべてのメンバーに浸透させていました。
そうした文化を持っている企業に入社すれば、少なからずノウハウが身につくはずです。

仮に、現時点で教育体制が充実していない企業だったとしても、組織の水準を高めようと教育体制やノウハウの蓄積に取り組もうとする姿勢や文化がある企業は、成長環境だと捉えていいと思います。
スキルが身につく会社を見抜くには?
—— 就職する前に、優れた営業組織とそうでない営業組織を見分ける方法はありますか?
説明会やOB・OG訪問で、直接話を聞いてみるのが一番です。
複数の企業に話を聞けば、営業スタイルの違いが見えてきます。
例えば営業のロープレ一つとっても、オープニング、ヒアリング、提案、クロージングのように、商談の場面によって分けているのであれば、それなりに育成の仕組みがあるはずです。
ちなみに、私であれば、営業組織のKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を聞きます。
KPIは、どれだけ営業組織をデータに基づいて科学的に分析できているかの一つの指標になります。
受注数のみをKPIに設定している組織よりは、営業プロセスを分解したKPI(架電数、商談数、案件数など)やアクションKPI(決裁者同席率、紹介数など)をデータに基づいて設定している組織の方が、営業組織として優れている可能性が高いです。
何をKPIに設定するかに正解はありませんが、少なからずスタイルは可視化できます。
また、どのような企業に入社するかを考えるうえでは、「これから単純な営業職の数は少なくなっていく」ことを覚えておくのも重要です。
オンラインで人の手を介さず商品が買える時代ですから、ただ商品を売るだけの営業職は不必要になっていきます。
翻って、これからの時代は、顧客のニーズに最適な提案ができる“コンサルタント視点”を持った営業職が求められます。
今後はデータ・ドリブンな営業スタイルがますます浸透していくので、「Salesforce」などの顧客管理システムを対象顧客に合わせてカスタマイズできたり、得られたデータから仮説を導いたりしなければ、発揮できる価値がなくなってしまいます。
そうした未来予測を踏まえながら話を聞けば、おのずと入社すべき企業が分かってくるはずです。
営業職に適性のある人は?

—— 野村さんの経験を振り返り、営業職に向いているのは、どのような素養を持った人材だと思いますか?
大前提として、お客様の事業や業界に対して、積極的に興味を持てる人だと思います。
営業をする際に、相手に興味を持ってヒアリングするのと、決められたトークスクリプトの流れをつらつらと読み上げるのでは、やはり結果に差が出ます。
信頼関係を構築できないことには、相手が抱えている課題に踏み込んでいくことが難しいからです。
これまでにたくさんの営業パーソンを見てきましたが、やはり相手と信頼関係を築けない人は活躍できていません。
逆に、相手に興味を持ってヒアリングができ、最適な提案ができれば、おのずと取引につながり、成果はついてきます。
また、営業職ほど成果やプロセスが分かりやすく、改善が目に見える職種はありません。PDCAを正しく回しやすく、成長を確認し、実感できる仕事だと考えています。
そうした意味で、徹底度の高い人も営業職に向いていると思います。
正しいアプローチを徹底すれば、やはり成果が出ます。営業成績が上がれば、仕事そのものが楽しくなりますから、個人と会社の双方が成長する良いサイクルをつくっていけるでしょう。
—— これから営業職に就こうと考えている若い世代に向け、伝えたいことはありますか?
「営業職の数は減っていく」と言いましたが、本質的に価値のある営業をしている人材の価値は、ますます高くなっていくと思います。
正しくスキルを積み上げていけば、商材が変わっても成果が出せるようになるので、自分次第で年収や給与、市場価値が高まっていくでしょう。
また、営業職には、会社の顔としてクライアントと接する仕事ならではの魅力があります。
販売した自社のサービスを活用して、お客様が課題を克服した瞬間は、大きなやりがいと喜びを感じられます。
私自身、未経験にもかかわらず、ファーストキャリアに営業を選んでよかったと感じているので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいです。
また、これから営業職に就こうと考えている方には、入社後にどのような営業職に就きたいかまでを考えてから求人に応募していただきたいです。
法人営業と個人営業は別職種といっていいほど毛色が違いますし、FSとCSの仕事は役割と業務に差分があります。
営業職といえばFSのイメージがあるかもしれませんが、SaaSプロダクトが主流になっている潮流に鑑みれば、今後はCSの重要度や求人数が上がっていくでしょう。
そのため、もしかすると、CSからキャリアを形成するのが、営業職のスタンダードになっていくかもしれません。
ともかく、「取引先の課題を発見して成功に導く」という営業職の本質は、あらゆる職業の基本的なベースになる能力です。
キャリアの“ロイター板”になる職種ですから、少しでも興味を感じられるのであれば、面接に臨む前に、身近な営業パーソンに直接話を聞いてみることをお勧めします。
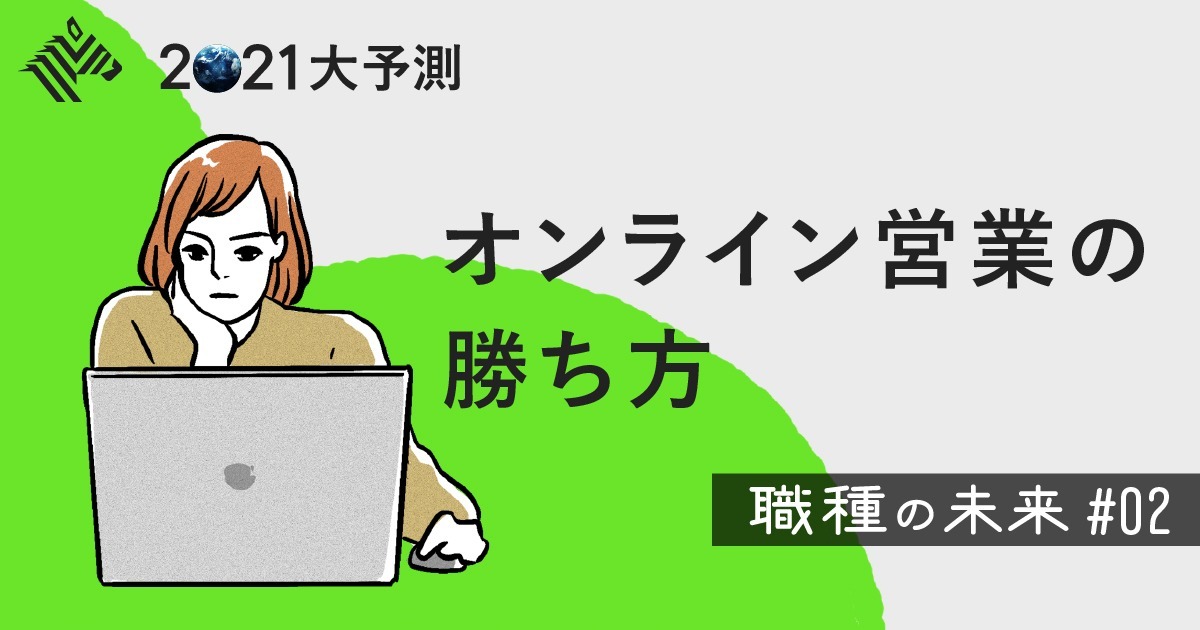
合わせて読む:【仕事の未来】2021年、営業に求められる「3つの力」
取材・文:オバラミツフミ、デザイン:國弘朋佳、撮影:遠藤素子