マーケティングは手段に過ぎない
—— これまでの経験を踏まえ、もし22歳に戻れるとしたら、どのようなキャリアを選びますか?
自分が得意とするマーケティングを主戦領域としてキャリアを形成すると思いますが、まずは「マーケターになる」というマインドセットを排除することから始めます。
ビジネスは、何かしらの課題を解決する人たちによって構成されています。
大きく分ければ、プロダクトをつくる人と、そのプロダクトの価値を伝達する人になります。
マーケターが該当するのは後者であり、向き合っている課題から結果的にマーケターとしてカテゴライズされているだけに過ぎません。
大前提として課題解決が役割ですから、特定の技能習得にこだわらず、「課題を特定して、適切な施策を導くこと」に注力すると思います。
たとえマーケターとしてアサインされたとしても、エンジニアリングなど、課題解決へのアプローチをマーケティングスキルに限らず高めた方がいいのではないかと考えています。
—— 「マーケティングができるようになる」という思考は持たないと?
できるようになることを「マーケティング」に絞り込んでしまうのは、もったいないという感覚ですね。
マーケティングにおいて、スキルやノウハウは手段でしかなく、スキルの習得機会も課題解決を行う過程で生まれると考えています。
スキルを得ることを目的にするのではなく、まず課題と解決策を考え抜いて、その結果としてスキルが育つというマインドセットであるべきです。
スキルを高めたいと思ったときこそ、課題解決に向き合うようにするべきだと考えています。スキルを得る必要性が高まるほど、スキルの習得度合いも高まる実感があるので。
インパクトの震源地を探せ

—— その考え方は、どのように築いてきたのですか?
ベースとなる思考は、新卒入社した企業でつくられたものです。
「しっかり顧客からヒアリングし、課題を見つけ、解決策を提示する。その過程に自分たちがいればいい」という上司の教えにも、深く納得しました。
業務自体は非常に泥臭いものの、「顧客が満足してくれたらいい。それこそがKPIだ」と。
例えば、誰かに誕生日プレゼントを贈ろうと思ったとき、自分の贈りたいものを贈るものでしょうか。
普通であれば、相手のSNSを見たり、友達に聞いてみたり、好みを確認するはずです。
ユーザーが欲しいものを見つけ、適切に届けるのがマーケターであって、スキルはそれを達成させる手段に過ぎません。
私が企業のマーケティング支援をする際も、特定のスキルで支援先に貢献することにこだわらず、事業課題を見つけてマーケティングチーム全体で解決しにいくよう心がけています。
—— 上流の課題をつかむために重要視していることはありますか?
まず重視しているのは、事業計画や勝ち筋を頭に入れることです。
どこを目指しているか、どう勝ちにいくかの前提を正しく把握することは、誤った課題設定を防ぐことにつながります。
次に重視していることは、何でも要素分解してみることです。
要素分解することは、課題を特定したり、仮説を持つことに役立ちます。
マーケターの森岡毅さんは、著書『確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力』(KADOKAWA)において、売上を7つの要素に分解し、中でも「認知度」「好意度」「配荷率」といった要素に焦点を当てました。
「認知度」を上げるためにテレビCMとデジタル広告をかけ合わせたり、「好意度」を上げるためにハリーポッターエリアをつくるなどして、USJの業績回復に貢献したそうです。
【森岡毅】USJを蘇らせた、数学マーケティングという「必勝法」視野を広げる、非合理の合理
——マーケターを目指す学生やスキルアップしたい人材は、データ分析ツールの技術は欠かせないといえそうです。
時間が余っているならば、学んだ方がいいとは思います。
ただ、手段と目的を混同するのではなく、学ぶのであれば学んで終わりではなく、何らかの課題解決につながっていればよいなと。
全ては課題から始まるといっても過言ではありません。
何かしらの課題があり、それを解決するためにデータ分析スキルやエンジニアリングスキル、もしくは広告運用スキルが必要となれば、学べるときに学んでおいた方がいいでしょうね。
—— 中川さんはかつてエンジニアを目指した時期もあったと聞きます。当時のスキルはマーケティング業務でも生きていますか?
それは非常に感じています。
例えば、SQLを学んで自発的にデータを見れるようになった結果、課題特定がスムーズになったり、仮説検証のサイクルを早く回せたりするようになりました。
きちんとデータを見れるようになると、定性的な理解をデータによって補強できるようになったり、直感的な思い込みが間違っていることに気づけたりもしたので、自分にとっては大きな進歩でした。

—— いま22歳だったら、改めてエンジニアリングのスキルを学びますか?
もちろん有用なスキルですが、それよりも「頼り力」や「巻き込み力」といった能力を手に入れると思います。
過去を振り返ると、仮説検証する際、リソースを自分自身のみに限定して、なんでも自前で解決しようとしていたのはもったいなかったと感じるからです。
肌感覚ですが、課題設定の質はインプットの質に大きく左右されます。
インプットの質を高めるには「自身の知見を広げること」と「他者の経験に学ぶこと」が大事だと感じるので、自分にない知見は、誰かに聞くことで補える可能性があります。
他人の脳みそを借りていれば、世界がより広がっていたはずです。
—— 知見を広げるために、実践していることを教えてください。
最近は、「合理的に生きていたらやらないようなこと」にあえて挑戦しています。
例えば、知人たちと共同出資し、シーシャ屋をつくりました。

勇気のいる試みでしたが、これまでWebプロダクトにしかかかわってこなかっただけに、リアル店舗を経営することで新しい学びや気づきが驚くほど得られました。
数字やデータだけを見ていても分からない部分があり、より上流の視点が得られましたね。
最近では、趣味の範疇ですが将棋も始めてみました。
将棋は自分が優勢かを判断する基準が4つほどあり、そのアナロジーで世の中を見てみると新たな発見も得られます。
そのうえ、仮説検証のプランを立てる際にも、詰め将棋のようなアプローチが効いたりするので驚きます。
将棋には序盤、中盤、終盤があり、序盤だけ強くても終盤で詰め切れなければ勝てないなど、ビジネスとも共通点があるんです。
自分自身がどんな攻め方なのか、どういう戦略が好きなのかという発見もあり、非常に興味深いですね。
こうして興味の幅を広げていかなければ、行き詰まる恐怖を覚える瞬間が多くなるため、自分が普段しないことに挑戦する機会を意識的に増やさなければと日々実感しています。
見えるものしか、見えない

——マーケターを目指す、20代前半の若者にアドバイスはありますか?
やはり、マーケターは目指すのではなく、あくまでも通過点だとみなしてほしいですね。
私自身そう考え、マーケターとしてのスキルにレバレッジをかけて、世の中により良いもの、人々が欲しがるものをつくる、「make something people want」を目指して事業を準備中です。
一流のマーケターであれば「人が欲しがるものをつくる」ことができると思いますし、私が本物のマーケターになったと自分自身で思える瞬間は、事業を立ち上げて世の中に価値を提供できたときではないかと考えています。
繰り返しになりますが、マーケティングは、世の中に価値を提供する手段でしかありません。
—— 最後に、マーケターになりたいと漠然と考えている若い世代に向け、アドバイスはありますか?
ロールモデルを見つけることに尽きます。
そもそも、私のようなWebプロダクトのマーケターと、P&Gのような消費財のマーケターでは、同じマーケターでも業務が全く異なります。
そのため、「あの人のようになりたい」という具体的なロールモデルを探すことで、取り入れるべきインプットを見定めるべきでしょう。
私もマーケターではなく課題解決者といえる存在に憧れ、自分も事業をつくってみたいという考えが芽生えたのも、ロールモデルとの出会いがきっかけです。
まずは、ロールモデルに近づくために、できることを小さく始めてみましょう。
マーケターになりたいのであれば、憧れの存在にどうすれば近づけるかという仮説を立て、検証してみるのが一番といえます。
—— その仮説検証のエピソードは、就職活動で話す内容としても生かせそうです。
たしかにそうですね。
「就活で勝つには」という課題を設定して、検証する。そのプロセスこそ、まさにマーケターの持つべき思考回路そのものです。
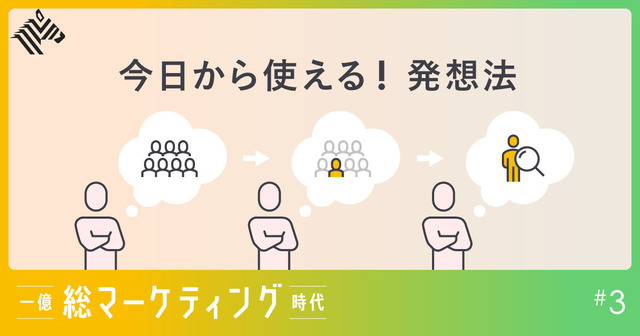
合わせて読む:【超実践】身近な事例で理解する、世界標準のマーケティング
取材・編集:オバラ ミツフミ、文:小谷紘友、デザイン:岩城ユリエ、撮影:遠藤素子