DeNA流、人を成長させる仕組み
—— ここ数年、秋元さんやSHOWROOMの前田裕二さん、スマホゲームのライブ配信で伸びているミラティブの赤川隼一さんなど、DeNAで働いた後に起業家として活躍している人が増えています。
秋元さんは2013年にDeNAに就職する前から、起業を考えていたのですか?
秋元 いえ、入る前も入った直後も、起業は全く考えていませんでした。
それどころか、就活を始めた頃は、DeNAにもIT業界にも興味がありませんでした。当時は金融業界にいこうと思っていたので。
ところが、偶然参加した就職説明会で南場さんのお話を聞いて、DeNAは「働き方が面白そう」と感じたんです。
南場 どんな話をしてました、私(笑)?
秋元 新入社員がいかに早く成長できるかを大事にしているというお話でした。
そのために、新人がやったら、成功確率が50%くらいになりそうな仕事を任せる。そうやって成長する機会を提供することを、意識してやっていると説明していました。
実際、私が参加した説明会でも、当時の入社1年目社員の方がプレゼンしていて。失敗談を含めて、どうやって仕事を回しているか、自分の言葉で話していたのが印象的でした。
それまではメガバンクをはじめ、大企業の説明会を中心に回っていて、何となく「仕事で大切なのはミスをしないこと」という雰囲気を感じていました。
それもあって、DeNAの説明会がとても新鮮ですぐに興味を持ったんです。
南場 確かに、DeNAのカルチャーは日本的な大手企業とは真逆です。新入社員に仕事を任せて、50%の確率で失敗したとしても、全然気にしません。
会社の成長は、人の成長と比例するからです。
組織とは人がすべて。人が成長して、組織が成長する。では、人はどうすれば成長するのかというと、それはもう、本物の“打席”に立つしかありません。
本物の打席とは、担当する事業にオーナーシップを持ちながら、「仕事の起承転結」を一通り経験することです。
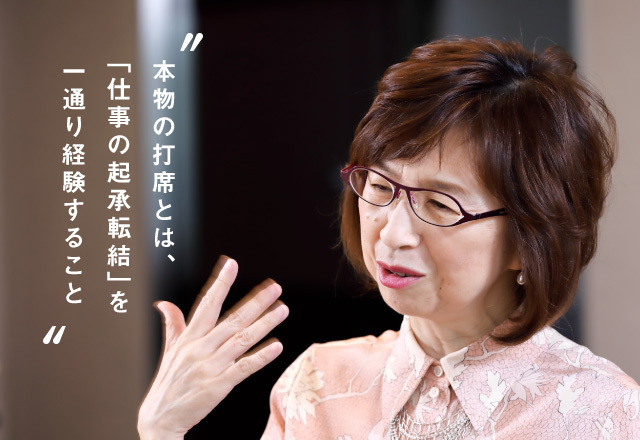
—— 具体的にどんな「起承転結」を経験するのですか?
秋元 私の場合は、入社してすぐ、あるサービスのユーザーの継続率を○○%上げるための施策を3カ月で一つ実施するというような、小さな目標から始めました。
その後、チラシ特売情報アプリの『チラシル』という新規事業を担当した時は、まず収益化させる(利益を出す)というミッションの下、新たな収益源となる機能を作り、電話をかけまくって広告を掲載してくれそうな企業を探しました。
何とか収益化の可能性も見え始め、ダウンロード数が100万を超えるまでは成長しましたが、2016年に撤退となって悔しい思いをしました。
すごくつらかったのもあって、一番記憶に残っています。
事業を継続させる分かれ道
—— 仕事の起承転結をやり切る過程で、成功と失敗の両方を経験するので、新人でも早く成長できるということですか?
南場 そうですね。50%の確率で仕事に穴が開きそうになるけれど、実際は、所属チームのみんなが寄ってたかって助けるわけです。チームワークなので。そうやって、事業全体の失敗確率を下げればいい。
みんな人間なので、『チラシル』のように事業が継続できなくなるようなこともあるし、失敗もします。
でも、ここが大事な点で、ウチは新しいことに全力でコミットした上での失敗には大らかなんです。
秋元 私の会社でも、社員の前向きな失敗に対しては、なるべく大らかに対応するようにしています。
DeNAが目指す組織文化を定義したDeNA Qualityには、「全力コミット(※2)」や「2ランクアップ(※3)」という言葉があって。個人的に、これが好きだったんです。
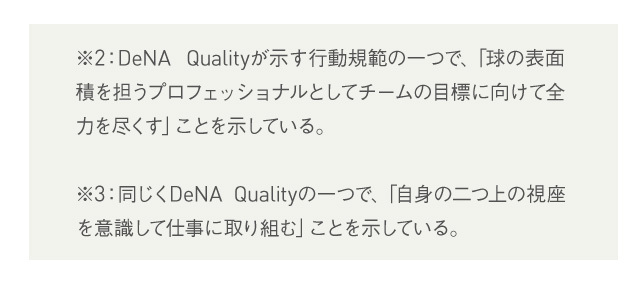
『食べチョク』のビジョンは「生産者のこだわりが正当に評価される世界へ」で、ビジョン実現に向けて5つの行動指針を定義しています。その中の一つに「本質思考」があるのですが、これを考える時も、DeNA Qualityを参考にしました。
自分がやりたい事業の見つけ方
—— 先ほど、秋元さんは「就職した頃は全く起業を考えていなかった」と話していました。そこから、どんな経緯で考えが変わったのですか?
秋元 DeNAにいた約3年半で、私はWebサービスのディレクター、営業のチームリーダー、新規事業の立ち上げ、スマホアプリのマーケティング責任者と4つの職種を経験しました。
その過程で、農業の事業を立ち上げたいという思いが芽生え、社内の新規事業でやるか、転職するか迷った末、独立することにしたんです。
私の実家は神奈川県で農家をやっていたのですが、中学時代に廃業しています。社会人になって久しぶりに帰った時、荒れ果てた畑を見ながら、「生産者のこだわりが正当に評価されるような世界にしたい」と考えたのがきっかけです。
南場 『食べチョク』は、コロナ禍の巣ごもり消費もあって、流通額がすごく伸びていますよね。立ち上げの思いと努力が報われて、本当によかった。
—— DeNAの新規事業としてやらなかった理由は?
秋元 農業というジャンルはDeNAの新規事業として合理性がないかもしれない、ならば起業して自分でやろうと考えました。
それと、知り合いの起業家に「やるか、やらないかで悩んでいるくらいなら、今すぐ起業してやれば?」と背中を押されたのも、起業した理由の一つです。
南場 今さら言うな!と怒られそうですが、秋元さんの突破力があったら、DeNAの新規事業としてやっても成功していたかもしれないと思っています。
DeNAで活躍していた頃の秋元さんの姿は、今でもよく覚えています。ウチの若手社員はみんな元気で優秀だけど、特に秋元さんはチャーミングで人間力が抜きん出ていましたから。
DeNAには、どちらかというと左脳型というか、ロジカルに戦略を考えたり、いろんな数字の計算が得意という人が多いんですね。
秋元さんもロジカルさは持ち合わせているけれど、それ以上に、どんな仕事にも夢中で取り組んでいる姿が印象的でした。
秋元 必死でした(笑)。とにかく担当する事業のユーザーに喜んでもらって、サービスを使い続けてほしいという気持ちが強かったです。
例えば建築業界向けのサービスを担当していた時は、「こんな住まいを提供できたら、幸せになる人がたくさんいるだろうな」などとイメージしながら、いろんな施策を考えていました。
南場 仕事に夢中になる度合いは、会社員だった頃も今も、あまり変わっていないんじゃない?
秋元 そうかもしれません。ほとんど同じ感覚で働いています。
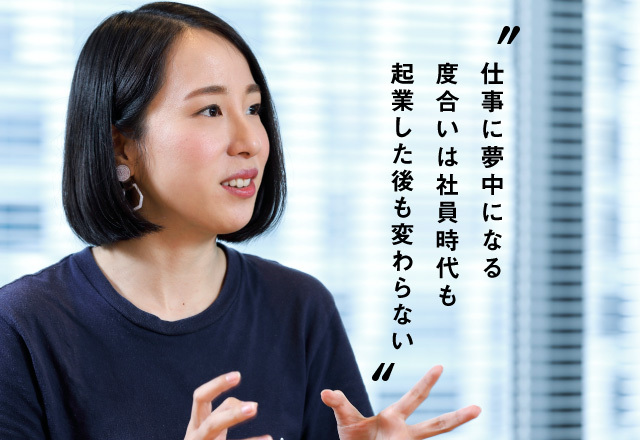
——自分で興した事業と、会社員として担当していた仕事の夢中度合いが同じというのは意外です。
南場 起業家になるうんぬんはさておき、人が幸せに働きながら成長していくには、「夢中になれる力」がとても大切だと思うんです。
DeNAが社員を採用する時も、この力を特に重視して見るようにしています。
私自身が仕事で幸せを感じるのは、夢中になっている時と、誰かの役に立っていると実感できた時なんですね。私の価値観を押し付ける気はありませんが、DeNAの社員にもこの2つを実感しながら働いてほしいと思っています。
ただし、この「夢中になれる力」は、もともと持っている人と、持っていない人の差が大きい。大人になってから開発するのは、私が見てきた限りでは、とても難しいものです。
これには教育の影響もあるかもしれません。従来型の教育では、子どもが夢中になっている対象を、一つ一つ取り上げていくのが日常茶飯事だったからです。
例えば、昆虫が大好きで虫取りに夢中なのに、算数のテスト結果が良くないと、親や先生は「算数ドリルをやってから虫取りに行きなさい」と言いがちです。
こうして弱点を人並み以上にするのを目的にしてしまうと、子どもが夢中になれるものを見つける能力は落ちていきます。だから、何かに夢中になれる大人が、それほど多くないのでしょう。
DeNAでは普通の優等生は採用せず、夢中になる力を持っている「レア人材」を採用するようにしてきました。
秋元さんは、まさにその典型です。傍から見ていても、目の前の仕事に常に夢中になっている。没入していましたね。
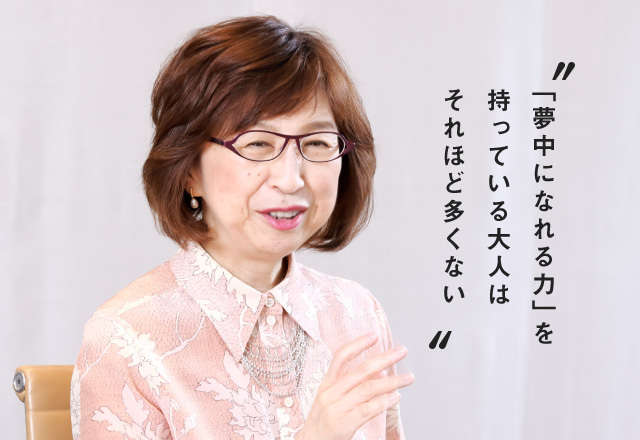
秋元 今日、南場さんにそう言ってもらって、自分が夢中になって働いてきたんだなと気付きました(笑)。
DeNAにいた頃、最後にゲームアプリ『キン肉マン マッスルショット』のマーケティング責任者を務めたのですが、配属前はキン肉マンの漫画を読んだこともなかったですし、思い入れもありませんでした。
けれど、配属が決まってすぐ、漫画喫茶に行って全巻読んでみました。そして、このゲームにかかわっている人たちとやりとりするうちに、皆さんキン肉マンに熱い思いを持っているんだと実感するわけです。
次第に、自分が頑張ることでキン肉マンの魅力を広め、チームメンバーや関係者の役に立ちたいと思うようになっていました。
あの頃を振り返ると、「この人たちに貢献したい」という気持ちが、目の前の仕事に夢中になるモチベーションだったのだと思います。
起業家の「タイプ」が変わった
—— 「誰かに貢献することに夢中になる」という文脈で言うと、最近は社会課題の解決と自己実現をイコールで考えて事業を興す起業家が増えているように感じます。お二人はどう思いますか?
秋元 確かに、私と同世代で20代〜30代前半くらいの起業家たちと話していると、「テクノロジーで世の中のこの問題を解決したい」「こういう人たちに喜んでほしい」という具体的なWillが先にあって、その解決手段として起業を選択した人が多い印象です。
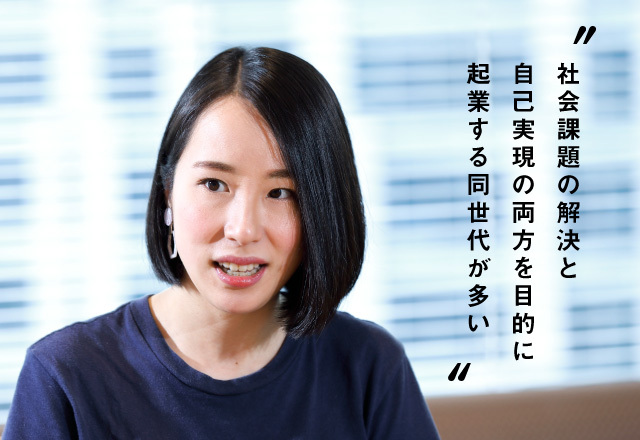
事業を継続していくため、利益を出すのは必要不可欠ですが、私益を増やすことにはそこまで執着心がないというか。自己実現欲のほうが強い気がします。
以前、ある先輩起業家に「お金持ちになりたくて起業したんでしょ」と言われた時は、ポカーンとしてしまいました(笑)。
やりたいことが明確になった時、ライトに一歩踏み出してみて、自己実現と事業のスケールアップを同時に進めていく。そういう起業家が増えているように思います。
もちろん、社会課題を解決するために起業する人は、昔からいたはずです。最近は起業のハードルが下がったため、そういう起業家の人数が増えて、注目されやすくなっただけかもしれませんが。
南場 でも、私が起業した頃(1999年)と比べても、確かに起業家たちの考え方が変わってきたように思います。より多様になったというのが正しい見方かもしれません。
2000年代くらいまでは、アメリカで成功したビジネスモデルを日本に持ち込むことで収益を上げるパターンがとても多かった。DeNAも、創業時の主力ビジネスはeコマースでした。当時はタイムマシン経営(※4)が勝つための定石だったのです。
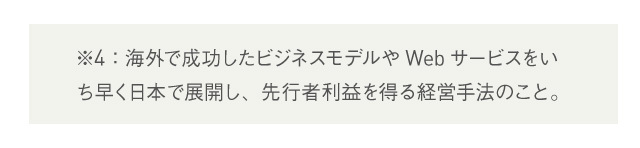
あの時代から考えると、今はテクノロジーが広まるスピードも速くなっていますし、ベンチャー投資も盛んになっているので、秋元さんが言うように社会課題を解決するのを目的に起業する人も増えているのでしょう。
—— DeNAは昨年、デライト・ベンチャーズというベンチャーキャピタルを立ち上げています。秋元さんの会社にも出資をしているそうですが、これも「多様なベンチャー」を育てる一環ですか?
南場 それもありますし、もう一つ、DeNAを卒業して起業した人たちを応援したいという思いもありました。
今までは、秋元さんのようなDeNA卒業生が起業したと聞いても、会社として公式に応援する形は取れていませんでした。
そこで、今DeNAで仕事をしている社員も含めて、優秀な人が起業して世の中を変えたいと思った時に、背中を押してサポートできる仕組みをつくりたいと思ったんです。
卒業生の会社とDeNAが会社同士のお付き合いをすれば、将来一緒に新しいビジネスを興すという素晴らしい関係にもなれます。
そして、出て行った人の会社に出資したら、その人が成功した時にリターンとして返ってくるので、その資金を糧に新規事業を増やすこともできます。
また、外に出て経験を積んだ人が、将来、一部でもDeNAの経営にかかわってくれたら、今よりも彩り豊かなボードになる。もういいことばかりですね。
—— 一方で、DeNAの社内から優秀な社員が抜けてしまうというリスクもありませんか?
南場 はい、いつも人手不足なので大変です。でも政府や官公庁が開く委員会などでいつも発言していることですが、日本経済の問題は、結局大手企業を中心に人材流動性が欠如している点と、スタートアップの層の薄さです。
もっと多様な人材を広く活用していくためにも、人は流動したほうがいいのです。
秋元 『食べチョク』でも、農家になるために退職した元社員が何人かいます。
その瞬間はもちろん悲しいですが、ビビッドガーデンは「生産者のこだわりが正当に評価される世界」を目指しているので、元社員が新たに農家になってくれるのは長期的に考えたらうれしいことです。
南場 秋元さんは、変化に対してしなやかに強いですね。雑にしなやかというか(笑)。これって悪い意味ではなくて、起業家にとって大事な資質だと思います。
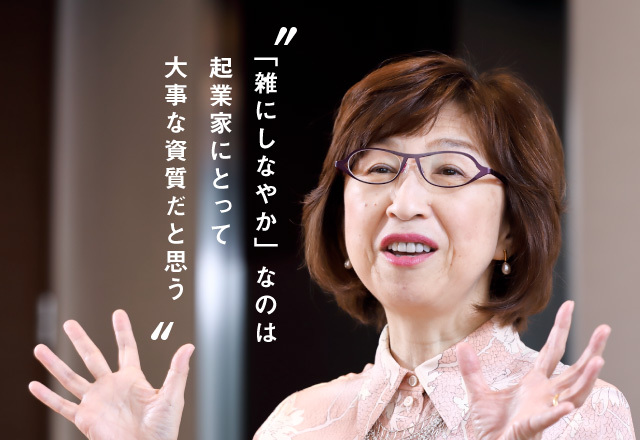
秋元 経験したことがない状況で失敗した時、落ち込むのではなく、どう状況を変えるかと思考を切り替えるのが大切なのだとDeNAで学びました。
これは、起業した今でもとても役に立っています。
自分が成長できる仕事を選ぶコツ
—— 最後に。今、お二人が学生だったら、企業に就職しますか、それとも就職せずに起業しますか?
南場 就職か起業かの二者択一を前提に考えるより、その時にやりたいことを実現するのに一番良い方法を選ぶと思います。
ただ、大学を卒業する時点では、ビジネスについての視野は広くないはず。やりたいこともハッキリとは分からないと思います。
なので、まずは自分の力が伸びそうな職場を探すでしょうね。やりたいことを発見した時に、すぐ立ち上げができますから。
私は新卒でマッキンゼーのコンサルタントになりましたが、今だったら絶対にコンサルにはならないでしょう(笑)。
—— 成長できそうな場所を選ぶコツは何でしょうか?
南場 大事なのは、仕事そのものの大きさではなく、企画から実施までを丸ごと任される環境です。目標を達成する方法を自ら考え、工夫できる職場かどうかも大切です。
組織が掲げる大きな目標に共感できたら、その目標を達成するのに必要な道のりを自分で描き、必要な資源を引っ張ってくる。
結局、成長するために問われるのは、「こと」を実現する経験をどれだけしてきたかです。
だからこそ、DeNAでは新卒1年目から、仕事の起承転結を回す役割を任せることにしています。

—— 秋元さんは、実際に1年目から起承転結を任されて、どうでしたか?
秋元 DeNAで一番身に付いた力は、やはり「何とかする力」だと思います。言い換えると、任されたことをやり切る力ですね。
先ほども話した『キン肉マン マッスルショット』ですが、マーケティング責任者になる2カ月前までマーケティングの経験はありませんでした。
何も分からない状態から勉強をし始めて、何とか目標を達成したのを覚えています。
DeNAでは、こうやって自分の経験より上の仕事を振られた時も、どうゴールにたどり着くかは自分で考え、いろいろな方法を試すことが求められました。
当然、失敗もしますが、必ず正解にたどり着くものです。だから、起業した後も「何とかする力」で今までやってこれたのだと思っています。
南場 “むちゃ振り”はDeNAのカルチャーですから(笑)。
秋元 そのむちゃ振りに、最初は「どう考えても無理だ」と思っても、頑張れば何とかなる。そういうマインドになれたことが、スムーズに起業の一歩を踏み出せた理由だったのかもしれません。


合わせて読む:【南場智子】私が22歳だったら、絶対マッキンゼーには行かない(NewsPicks)

合わせて読む:シゴテツ -仕事の哲人-秋元里奈の哲学(NewsPicks)
取材・文:栗原 昇、取材・編集:伊藤健吾、デザイン:九喜洋介、撮影:竹井俊晴