生きる意味を考えた高校時代
東京大学を卒業し、経済産業省へ。現在は、コロナ・ウイルスの煽りを受けた中小企業に向け、資金繰り対策の支援を行っている。
田口さんが現在のキャリアを歩むまでには、高校時代に「生きる意味を問い直した」経験がある。
「もともと、東大に進学するつもりはありませんでしたし、これといって目指している職業もなく、キャリアについては『大好きな弓道をずっと続けられればいい』くらいにしか考えていませんでした」
高校生当時は、一橋大学に進学して公認会計士になるキャリアパスを描いていた。本人いわく「飛び抜けた学力があったわけではなく、語学が堪能だったわけではない」そうで、「分かりやすく安定した職業を目指していた」のだという。
そんな田口さんに転機が訪れたのは、受験勉強の一環で倫理を学んでいた時のこと。
ユダヤ人心理学者のヴィクトール・フランクルがアウシュビッツ収容所に囚われ奇跡的に生還した経験を書いた『夜と霧』を読み、生きる意味を問い直したことが、キャリアのルーツになっている。
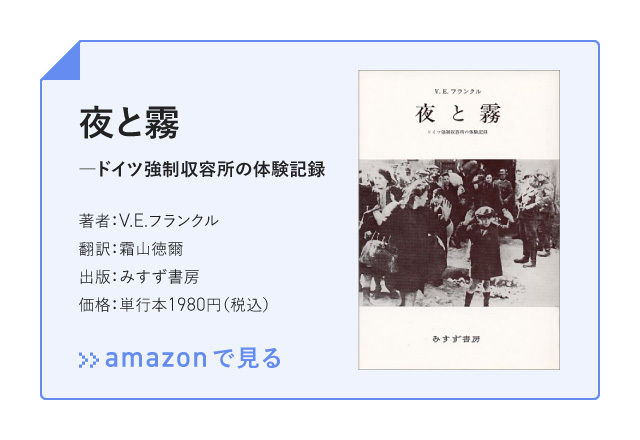
絶望的な環境の中でも希望を失わなかった人たちを観察し、人間の“生きる意味”を考察した名著
「私もフランクルと同様に、生きることの意味を問うても仕方がなくて、むしろ人生が自分自身に何を期待しているかを考えるべきだという結論に行き着きました。生きることの意味に答えはないかもしれないけど、別に死にたいわけでもない、と気が付いたのです。
では、どのように生きるのか。そこで私は、“飽きない人生”を送る決意をしました。私が考える“飽きない人生”とは、自分の強みやバックグラウンドを活かし続けられる人生です。
私が持っている経験の中で、強く人生観を揺さぶられたのが、父が経営する会社の倒産でした。住んでいたマンションは売却しましたし、車もなくなるなど、生活環境が一変しました。そのタイミングで初めて、自分には関係のないことだと思っていた『政府の経済政策』が、実は生活に身近なものであることを知ったのです」
生きる意味を問い直し、当事者意識を持ち続けられる仕事を思案した結果が、父親が経営していたような中小企業を支援する役目も持つ経産省に入省することだ。
生きる意味など元から問うても意味はないのだから、生かされている自分を活かそう——。
そんな思いで、1年間の浪人を経て東京大学に進学した。
原発、災害、スタートアップ
2015年に入省し、最初に配属されたのは資源エネルギー庁原子力政策課だった。2011年の東日本大震災で稼働を停止していた原子力発電所が、再稼働に向けて動き出すタイミングだ。
電力の安定供給やCO2対策の観点に立てば、原子力発電所の再稼働は妥当な判断だとは思った。しかし世論は、それを認めない。1年目から“激動の瞬間”に直面し、官僚としてのキャリアをスタートした。

「政府が下す決断は全て、国民全員の満足を得られるものではありません。しかし、それでも決断しなければならない。ステークホルダーの意見が複雑に絡み合う中で政策を推進する難しさを、ありありと感じた1年目でした」
関連する象徴や事業者との窓口になり、「政策をつくる側」としての業務を学んでいく。いわゆる“ロジ(関係部署間の調整)”を学ぶのも、官僚1年目の仕事なのだという。
「『経済政策をつくる』というと難しく聞こえますが、予算なのか、あるいは法律なのか、政策を実現するツールはせいぜい20程度です。最も大切なことは、どんなツールを使うかではなく、課題をピンポイントで特定すること。そうした仕事の本質も、先輩たちから学びました」
3年目になると、資源エネルギー庁を離れ、政府のシステムのクラウド化を推進する商務情報制作局へ異動。翌年は、経産省の意思決定を行う大臣官房総務課に異動した。
省庁間の調整を行う内部的な業務から、災害現場へ駆け付け復興を支援する仕事まで、4年の間に毛色の異なる経験を積み重ねた。
新人社員から若手社員への階段を登り、迎えた5年目。志していた中小企業にかかわる仕事に就く前に、経産省を離れ、表参道駅にオフィスを構えるスタートアップへと期限付きの“レンタル移籍”をする決断をした。
スタートアップの現場で働くことで、「鳥の目」ではなく「虫の目」(編集部注:経済を見るには、鳥の目、虫の目、魚の目の3つの目が必要と言われる。鳥の目とは俯瞰して物事を見ること、虫の目とは現場でミクロを見ること、魚の目とは流れを知ることだ)で、企業のリアルを知るための選択だった。
「経産省の研修に『経営現場研修』というものがあります。経産省に籍を置いたまま職員がベンチャー企業にレンタル移籍し、リスクが高い環境下で現場感覚を学び、のちの政策立案に活かすことを目的としたものです。
社会課題の解決に官民の連携が必要不可欠であることは自明ですが、それぞれの文化や行動原理にまだまだ差がありますし、相互理解も十分ではありません。
もちろん私も、例外ではありません。そうであるならば、自分自身も一度は民間の世界から社会課題に取り組むべきだと考えました」
移籍先に選んだのは、信用経済の仕組みづくりに挑戦していたスタートアップのVALUだ。
「価値の物差しが複雑化する中で、社会のシステムをどうアップデートしていくべきか」という田口さんの課題意識にフィットする企業であり、また「評価の基準を変え、お金の流れを変え、フェアな世界をつくる。」という同社のミッションに強く共感したことも、移籍を決める要因の一つとなった。
キラキラなしのスタートアップ

田口さんがVALUに移籍したは、2019年9月。同年の初頭にシリーズA(サービスや商品などのプロダクトがおおよそ完成し、初期ユーザーへの販売実績などが評価されるフェーズ)の資金調達を行っており、次の調達に向けて売上を拡大しなければいけない段階にあった。
しかし、目標に対して順調な成長を遂げているとは言えず、田口さんが入社した時点で、タイムリミットが始まっていた。
暗号資産の利用者保護などの観点から施行された改正資金決済法により、莫大な費用と工数をかけて暗号資産交換業者としての登録を受ける必要があったのだ。
VALUの価値を拡大し、資金調達を実施できなければ、サービスが終了してしまう。まさに、瀬戸際での入社だった。
「VALUの新規ユーザーを増やすことが私に任された大きな役割でしたが、サービスの存続がかかっていましたから、売上を上げるための施策は何でもやっていたというのが実際のところです。
しかし、SNSというビジネスモデルの特性上、短期間で大きな売上をつくるのは困難でした。短期間で万単位のユーザーを獲得する起死回生の一手を探しつつも、事業譲渡をするのか、もしくは新たなビジネスモデルにピボットするのか、あらゆる選択肢を考えていましたね」
20人以上いた社員が5人までに減るというスタートアップのリアルを目にし、「多少なりとも想像していた“スタートアップキラキラ感”は一切ありませんでした」と当時を振り返る。
代表の小川晃平氏とあらゆる選択肢を検討するも、最終的にはサービスをクローズする意思決定を下した。
「与えられたミッションに貢献できなかったのは心残りです。正直、もっとできるだろうと思っていたところもありました。とはいえ、生きるか死ぬかの世界で戦うスタートアップというものを肌身で体感できたことは、私の人生に活かされる貴重な経験だったと思います」
官民の架け橋として、経済を司る
サービスは終了してしまったが、激動の7カ月間で得られた経験は、田口さんにとって大きな資産となった。
次の産業を生み出すスタートアップの一員として、手探りで集めた知見は、経済・産業の発展を使命とする経産省に活かされ始めている。
「移籍を通じ、スタートアップと役所にある距離をまざまざと感じました。官民の壁が溶け始めているとはいえ、まだまだお互いが“異なる言語”で会話をしているきらいがあります。
スタートアップの人からすると、規制やルールに対して不満もあると思います。ただ、それら全てに背景や経緯があります。こうした事情を理解しないまま不満だけを伝えても、議論は進捗しません。
また役所も、スタートアップの人たちが『生きるか死ぬかの世界で戦っている』ということを理解しないといけない。連絡や決済の遅さが命取りになる可能性もあるので、距離を取らず、日頃からコミュニケーションを取っていく必要があると思います。
立場の違いはあれど、突き詰めればどちらも、公共の課題解決に向かっているんです。手段は異なっても目的は同じなのであれば、お互いの距離はもっと埋められるのではないかと思います」
官民双方の視点を持つ身として、公共の課題解決に向けた取り組みを加速していく。その伝道師として、今後どのようなキャリアを歩んでいくのだろうか。
編集部の問いかけに、田口さんは「具体的な絵を描いているわけではない」と話す。
「繰り返しになりますが、自分が今、生きていることの意味を問うても答えはないと思っています。ただ、自分のバックグラウンドを何に活かすか、興味関心があることは何かという問いは常に持っています。僕の場合、経済を取り巻くマクロな課題を解決し、社会に対するインパクトを残すことです。
霞が関の役所は、無駄な仕事が多いとか、残業が長いともよく言われますが、今この瞬間は、経産省以上に自分の思いを実現できる場所はないと思っていますし、誇りをもって楽しく仕事しています」
田口さんは、自分のキャリアを“パーパス型”だと言う。
つまり、大上段には目的がある、そのために何をするかを考える生き方だ。めまぐるしい速度で変化する社会の中で、目的に対して柔軟に役割を変えていく“プロティアン・キャリア(変幻自在のキャリア)”とも言い換えられるだろう。

【図解講義】あなたの“不満”こそ、次なるキャリアの道しるべだ(NewsPicks)
「中長期視点でキャリアを考えるのは、当然大切なことです。しかし、5年後に社会がどう変化しているかを正確に見通すことは不可能です。そうであれば、『面白そう』という直感に従い、目の前の選択肢を選び取ってもいいのではないかと思います」
数年前から「好きなことで、生きていく」というセンセーショナルなメッセージが聞かれるようになり、それによって自由になった若者がいる一方、「好きなことが分からない」と、キャリアの迷子になってしまう人が増えているように思う。
働くということへの固定概念が、良くも悪くも壊れてしまったからだ。
もしあなたがキャリアに迷っている一人なら、田口さんのように、何をするかに固執しないキャリアを歩んでみてはどうだろうか。
その時代の“ホットなアジェンダ(課題)”に飛び込んだり、その瞬間に興味を持てることを仕事に選んだり。そうやって、自分の役割を探していくこともできるはずだ。
取材・文:オバラ ミツフミ、編集:佐藤留美、デザイン:黒田早希、撮影:遠藤素子