言いたいことはひとつ、嫌なことすな!
野上:こんにちは。JobPicks編集長の野上英文です。今回のテーマは、「嫌な仕事を断っていい3つのとき」です。 ゲストは、日経BP社から『嫌な仕事のうまい断り方』の書籍を出された山本大平さんをお迎えしております。最初にこの本を一言でご紹介いただけますでしょうか。 山本:これは簡単で……「嫌なことすな!」ですね。 野上:関西のオカンが言ってるみたいになってますけども(笑)。 山本:バリバリ関西弁でね(笑)。もうこの一言に尽きます。 野上:「嫌なことすな」ということですが、この本の中で、断っていい仕事として「能力がない、時間がない、意義がない」という3つが紹介されています。まず最初の2つを説明していただけますでしょうか。
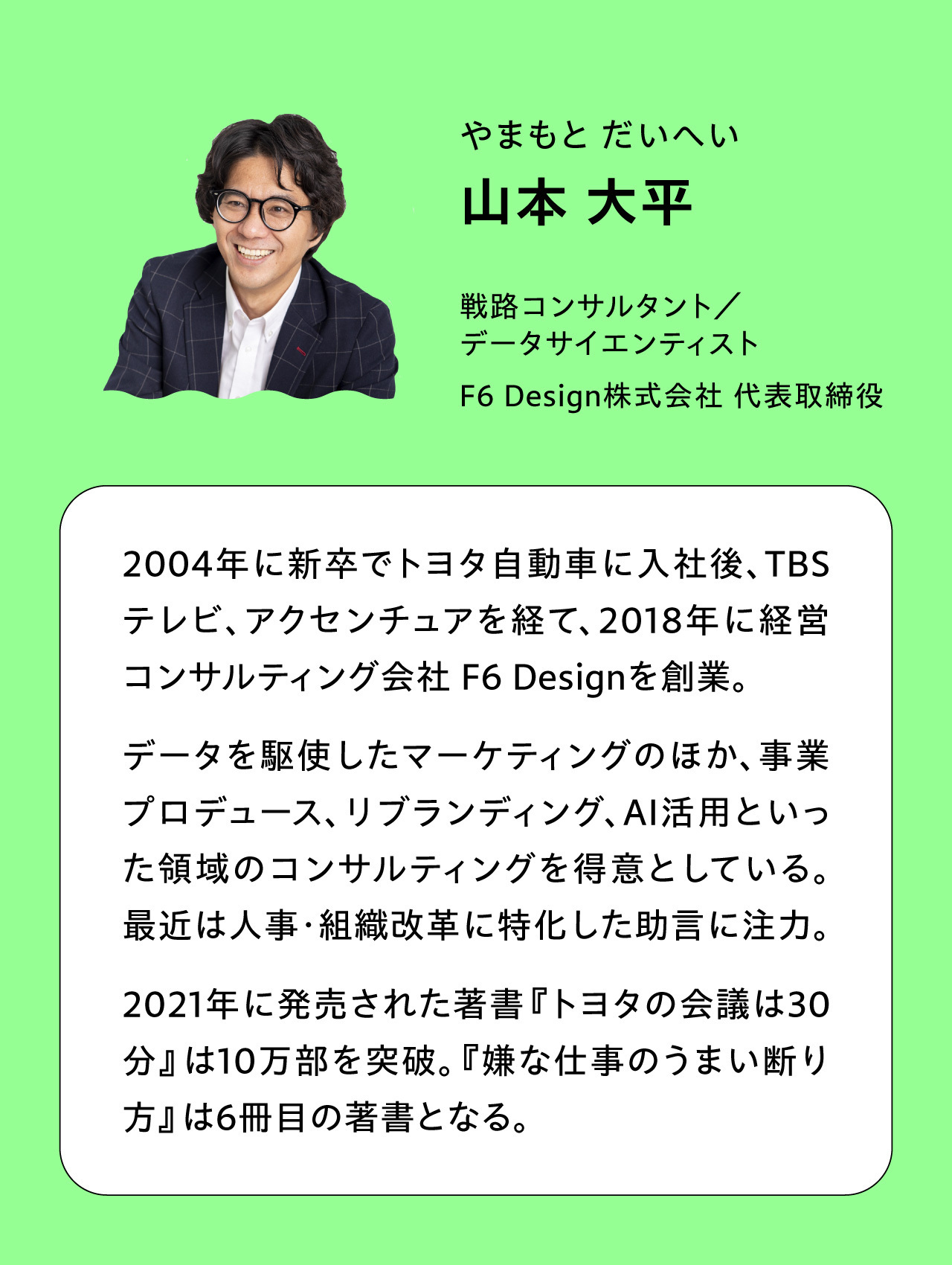
断っていい仕事は「能力がない、時間がない、意義がない」
山本:「能力がない」っていう方は、シンプルに自分の能力がないから無理ということで、例えば「100メートル8秒台で走って」みたいなことですね。「無理」と「無茶」は僕は違うと思ってまして、ここで言っているのは「無理」の方です。
一方で、「時間がない」は、ダブルブッキングという言葉が当てはまりやすいです。例えば生放送の「ミュージックステーション」に出るとして、同じ時間に別の局で別の番組に出てくださいと言われても、時間的にも行けないじゃないすか。これも物理的、時間的な側面で無理ですよね。そういったことが、ビジネスシーンでも実はある、ということです。
野上:Aという仕事で今日1日取られてるときに、Bというのを振られてもそれは難しい、ということがダブルブッキングということですね。
では、3つ目の「意義がない」。これは結構、日頃感じることは多いと思うんですけれども、どうやってアウトライン化するかはなかなか難しい感じがしますね。
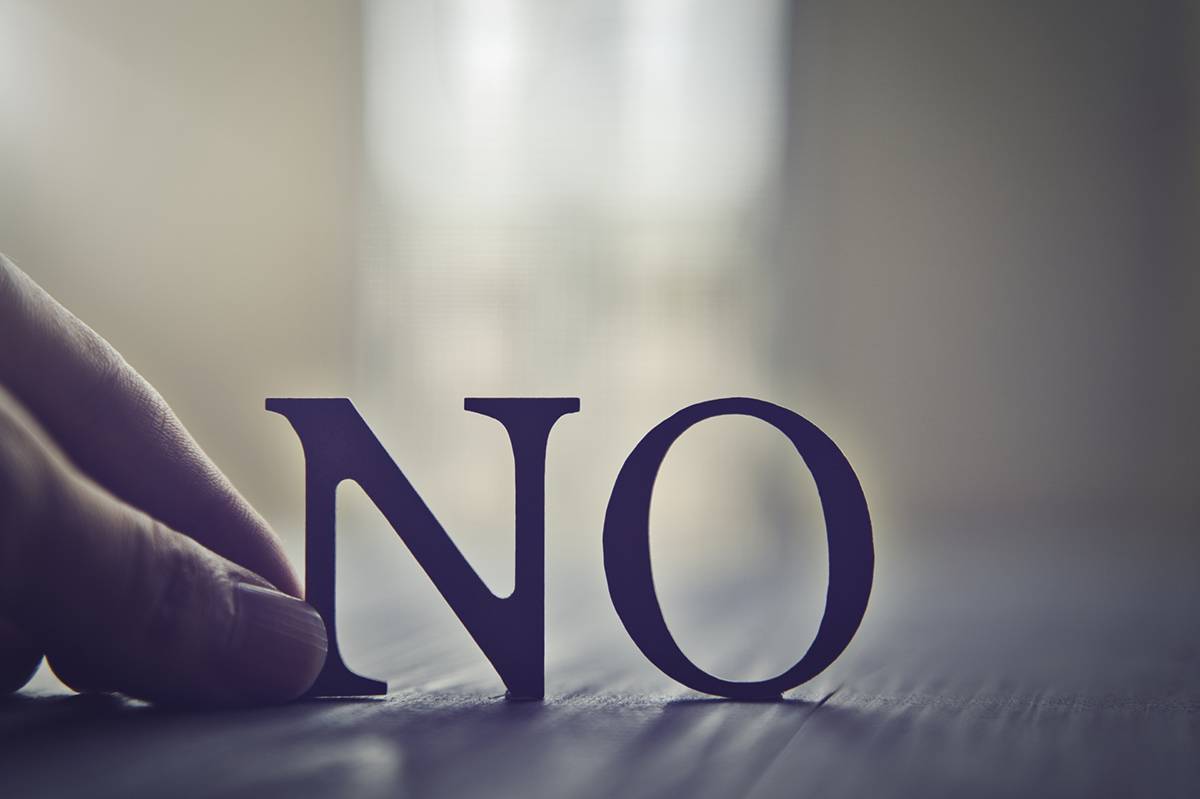
山本:そうなんですよ。よく言われるんですけど、「意義がない」は2つに分解できると思っていて。1つは「ほんまに意味がない」、もう1つは「その意味を感じ取れていない」。この2つしかなくないですか?
野上:ファクトとしてほんまに意味がないということと、その意義が本人に伝わっていない。
山本:そうです、そうです。まず前者の「ほんまに意味がない」ということは、確かにありますよね。最初「意義」という言葉を、パーパスみたいな言葉で定義してもいいんじゃないかな、と思っています。
何のために仕事して、何のためにこの会社があって、何のために社会と交わっているのか。それを理解しないまま、特に組織の末端になればなるほど、話がずれて違うことをしてしまったり、違う認識をしてしまったりして、意味がないってなる場合もあると思うんですよね。
例えば、野上さんに逆に聞きたいんですけど、今日のこの収録は意義ありますよね?
野上:(笑)。一応これは意味があると思ってですね、会議も重ねて今日お呼びしてるんで、意義あるかなと思ってますよ!僕としては。
山本:よかったです(笑)。僕このオファーをもらった時、とても嬉しくて。意義あるものとして来てますから。
野上:めちゃくちゃ意義ありますよ、当たり前じゃないですか!(笑)ただこれが、他のメンバーや、お相手の山本さんに伝わるかどうかってまた別問題ですよね。
山本:そこでお聞きしたいのは、他のメンバーに対して、自分は「意義がある」と思っていることが伝わらないときってやっぱりありますか。
同僚に「これって意味あります?」と言われた時どうするか?
野上:たまに「これ、何のためにあるんでしたっけ?」と聞かれることはありますよね。
山本:そうですよね。うちの会社は経営コンサルティングをしているので、いろんな企業からそういう悩み相談は増えてきてるんですよ。
野上:「これって何の意味があるんですか」と言われるとか、振った仕事をうまく振ってくれないとか、そういうことですか。
山本:そうです。その時に、あんまり熱く強く上から説明すると、パワハラだと言われちゃう、という感じですね。小さい会社だとあまりない悩みです。意識がやっぱり浸透しやすい。一方で、1万人とかの規模になってくると、まぁそういった現象が起きやすいです。
野上:人数が多いことで、コミュニケーションが不足しているからですかね。上の決めたことと、日々の業務までがちょっと乖離してるっていう状況なんですね。

山本:さっきの「意義がない」の2つの分類の話に繋がりますが、実は意義があるのに「意義がない」と人が感じるのはなぜか、ちょっと分析してみました。
要するに説明不足って言葉に尽きるんですけど、もうひとつ大事なポイントがあって「振られた仕事しかやらないよ」ってマインドセットがあるのも大きいと思うんです。
例えば野上さん、部下の方に「やっぱり意味ないと思うんですよね~」と言われたら、どう思いますか。
野上:顔真っ赤にしてキレるかもしれない!?(笑)ただ、こちらからはそうも言いづらいですよね。
山本:そうですよね。その後、その子に同じ仕事をこれからも振ろうと思いますか。
野上:それは無理ですね。他を探します。
山本:ですよね。「意味なくないですか?」と言い出す部下の視点からしても「『意味がない』と思っていても、それを言うと、仕事はもらえない」とわかっています。なので、お見合い、探り合いが本質的に起きてしまっているんですよね。
野上:なるほど。一方で最近は、ゆるすぎる、ホワイトすぎる会社が、野心ある若い人には「成長機会がない」と敬遠されることもあって難しいですよね。パワハラはダメ、ブラック企業もダメだけどホワイトすぎてもダメ、みたいな。どうすればいいの?と悩みそうです。
今こそ考えたい“昭和”なやりとりの効能
山本:まさにその「どうすればいいの?」というところで、コンサルさせていただく機会も多いです。振られた仕事に対して「意味ないです」と言ったらケンカになりますし、言われた方も嫌ですよね?だったら、その土台を作りませんか?という話をします。
僕らはAIじゃなくて人間なんだから感情抜きで語れない、どうやって土台を作るんですか?と聞かれます。なかなか難しいですが、そんなときに推奨しているのは能動的なコミュニケーションです。
例えば、廊下とかですれ違ったときに「お疲れ様です」と挨拶できているかって大事だと思うんです。挨拶って「あなたの敵じゃないですよ」っていう意思表示にもなるんです。
野上:憮然としてるよりはやっぱり話しやすいですよね。
山本:大阪だと、電車で座った隣のおばちゃんがアメちゃんやみかんくれたりするじゃないですか(笑)。そういったノリってまぁ“昭和”なんですけれども、社内では結構必要じゃないかなと。
トイレに行ったときも結構チャンスで、誰かとすれ違うことが多いですよね。例えば明日同じ会議に出る予定の他部署の人と出会ったら、「お疲れ様です、明日よろしくお願いします」とお互いに声をかけたら、何もないよりも安心して会議に臨めます。
そういう何気ないコミュニケーションで培われる「土台」は、ちょっとした安心感や空気感を作るために必要です。
野上:本音を言われても、ある程度カチンとこずに議論ができる雰囲気があるのが大切、ということですよね。
山本:そうです。人間関係のふわっとした空気を作っておくだけでもいいと思っていて。「意義がないですよね?」って言い方は絶対駄目ですけれども。「ちょっと教えてもらえませんか?」って言えば、大体教えてくれますよ。
上司がそれでもし説明できへんっていう状態であれば、まずその人も理解してないか、ほんまに意義がないか、の2択。
野上:さっきの「ほんまに意味がない」か「意味を感じ取れていないか」ですよね。
山本:だから、「仕事の断り方」というタイトルにしていますけど、まずは、お互いの関係を確認しましょう、というのを推奨しますね。
(続く)
フルバージョンは音声版で!
このあとは、こんな話をしています。
自分に合った仕事を呼び寄せる簡単な方法
転職先で自分のキャラを出すには?
相性のいい会社にどう出会う?就活や転職の面接で心がけるべきこと
(文:鍬崎拓海 デザイン:高木菜々子 編集:山崎春奈)