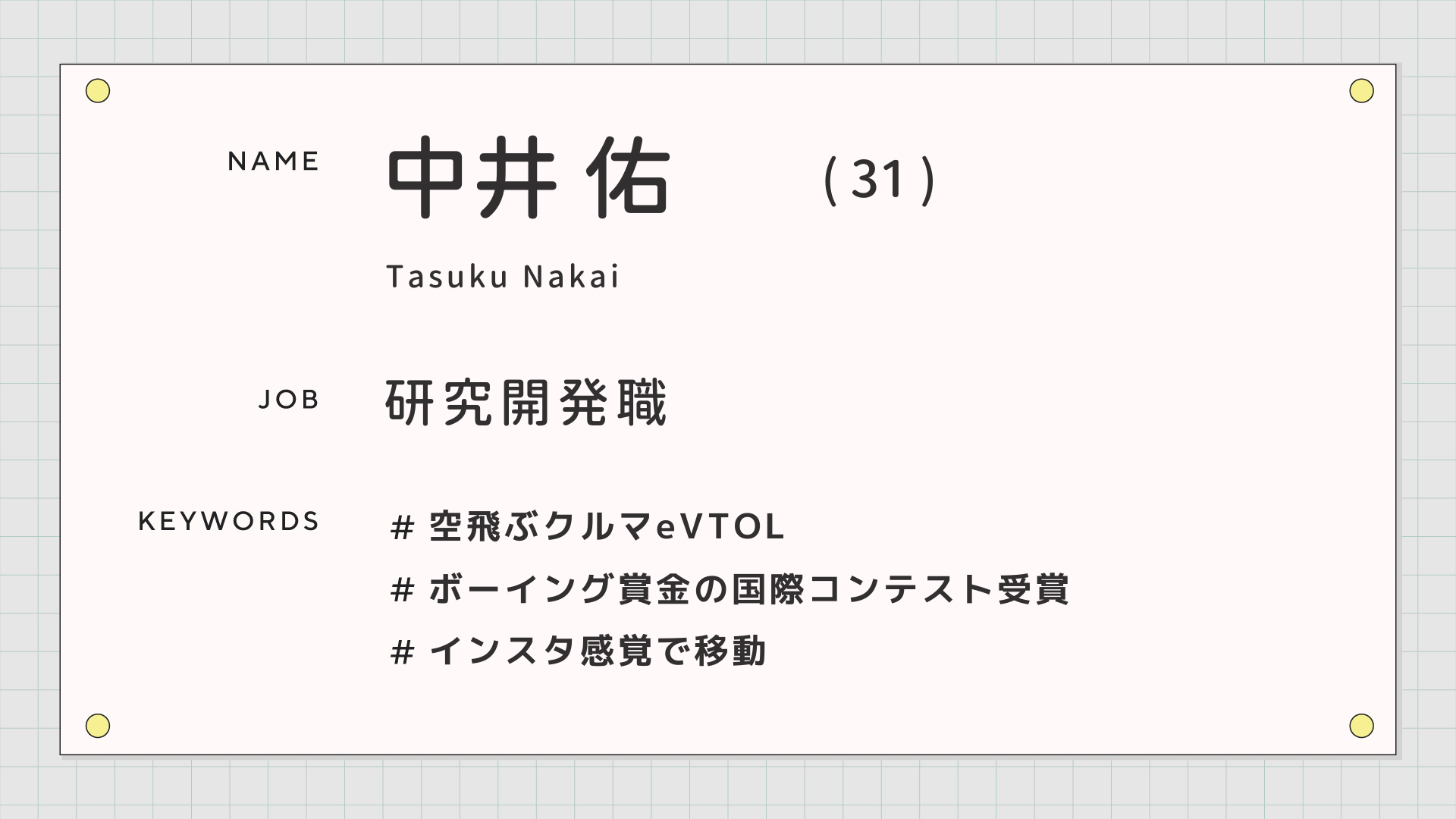
インスタのような気軽な飛行体験
ユニークな働き方をする次世代の担い手たちに、15分間のインタビューをする動画番組『働くっていいかも!』。いまどんな仕事をしているのか、なぜそのキャリアに至ったのか、これから何をしたいのか……。友人の紹介もしてもらって、“ビジネスの輪”をつないでいきます。 今回注目したジョブ(職)は「研究開発職」。次世代型全自動歯ブラシを開発する栄田さん(#08出演)のご紹介で、中井さんに話を聞きました。中井さんは、2018年に空飛ぶクルマ「eVTOL」を開発するテトラ・アビエーションを立ち上げました。
──どんな開発をしているのでしょう? 中井:いわゆる空飛ぶクルマと呼ばれる、垂直に離着陸する機体「eVTOL」を開発しています。 eVTOL(イーブイトール、electric Vertical Take-Off and Landing aircraft):電動垂直離着陸機 「VTOL」というカテゴリがあるのですが、これはヘリコプターをはじめ、戦闘機のハリアー、米軍輸送機のオスプレイを含む大きなくくりで、垂直に離着陸するのが特徴です。その中でも「eVTOL」は、電動ということです。 2018年に会社を設立してから試作機の開発を繰り返し、現在は新機種「Mk-5(マークファイブ)」の開発を進めています。 2023年内にテスト機として一部のお客様に提供を開始し、2025年に実施される大阪・関西万博をターゲットに実用化を目指しています。

──Mk-5をはじめeVTOLは、一般利用が当たり前になっていくのでしょうか? 中井:この新しい移動体験の「快適さ」は、なんとしても広げたいです。 イメージしているのは、リラックスしながらInstagram(インスタグラム)で旅行先の画像を見て楽しむかのうように、行きたい場所に気軽に行ける世界観です。 より多くの人が使いやすいように、Mk-5の操作にはハンドル式ではなく、ゲーム機のリモコンに使われるようなジョイスティック式を採用しています。 Mk-5の航続距離は50kmで、例えば瀬戸内海を渡るとか、東京都内でもどこでも行けます。将来は、個人のお客様が近所の立体駐車場の屋上から離陸し、地方の観光地まで遊びに行けるようような社会を作りたいです。
LAの事業化が最初の顧客。いずれ日本に還元したい
──実用化が近いとのことですが、反響はすでにありますか? 中井:実は機体の予約は開始しており、お問い合わせもいただいおります。 いまお世話になっている方の一人に、アメリカの事業家がいます。ロサンゼルスを中心に不動産やオフィスをいくつか持っているのですが、交通量の多い大都市で、移動に苦労されていました。 ただ移動を楽にしたいというニーズだけでなく、「環境に負荷をかけず、どこでも充電できる乗り物を使いたい」と、私たちにお声がけいただきました。 その方は、お客様でありながらも、機体に何度か乗っていただき、いろいろとフィードバックをいただいております。その声を開発に反映することで、少しずつスペックを高めることができています。 機体価格は約5,000万円なので、より安く販売できるには、どう技術を高めるべきか難しい課題にも向き合っています。

──第一顧客はアメリカですが、日本ではどう展開しますか?
中井:日本は、移動手段として使う場合の法律や制度がまだ整っていません。このため、レクリエーションや趣味を目的とした活用から始めていく予定です。
一方、アメリカでは米国連邦航空局が審査したeVTOLであれば飛行試験ができ、2021年にMk-5も認証を取得しています。日本でも移動手段として認められるために、まずはアメリカで成果を残す必要があるのです。
より多くの人に、制度さえ整えれば、日本でも飛行実験ができることを知ってもらいたいですね。そして、日本全体が抱えている渋滞や環境への負荷を解決する手段としてeVTOLの可能性を伝えていきたいです。

イノベーション・スキルセット~世界が求めるBTC型人材とその手引き
技術職として働くうえで、自らの技術的知見のみならずそれをどう他の分野に伝えていくのか、何をイノベーションと考えるのかについて気付きを与えてくれる1冊。 空飛ぶクルマの開発はまだ市場もなく、どのようなものが求められているのか明確になっていません。そのため、未来へのあらゆる想定を開発段階でも頭の片隅に巡らせる必要があります。 一方で、航空機開発はとても夢がある分野です。 未来のお客様がどのような要望で空飛ぶクルマに乗りたいと思うのかをデザイン的思考を持ちながら技術革新に一人一人が意識するための考え方の気づきとなる1冊です。 テトラ・アビエーションでは従業員が自由に技術関連書籍を購入できる制度があり、従業員は自らの判断で書籍を購入しています。
航空機業界「30年に1度」の転換期
──航空機業界全体のトレンドを教えてください。
中井:面白いことに、航空機業界では、新機体が受け入れられる周期として「30年」が1つの目安になっています。
まず、1970年代に一度でたくさんの人を遠くに素早く運ぶ「ジャンボジェット機」が登場しました。ヨーロッパのの航空宇宙企業エアバスをはじめ、新しいメーカーが続々と設立されたのもこのタイミングです。
30年後の2000年代から、今度は小回りの利く輸送目的の「ビジネスジェット機」が注目され、本田技研工業の「HondaJet」をはじめ多くの企業が参入し始めました。
そして、次の2030年に向けて、eVTOLマーケットが期待されています。
実際はジャンボジェット機が一番もうかりますし、ビジネスジェット機のニーズも伸び続けています。それらと同様に、eVTOL市場も伸びていくポテンシャルを感じています。

偶然知ったボーイング賞金の国際コンテスト
──空飛ぶクルマの開発を志した背景を教えてください。
中井:大きく分けると3つあります。
まず、私は基本的になるべく早く物事を終わらせることが好きなんです。昔から時間を効率化できるような道具を作りたいと考えていました。特にこの領域は、IT技術の進歩も後押しとなり、これから一気に成長していくと感じています。
2つ目に、高校時代まであまり「移動しなかった」反動があります。
千葉県の西部出身なのですが、同じ千葉でも東部や南部で遊ぶ機会はほとんどありませんでした。だからこそ、もし私自身の学生時代に毎日ヘリコプターに乗れるような生活だったら、一体どんなところに出かけていたのだろうかと想像します。
これからの子どもたちには、そういう機会を提供したいです。
最後は、国際大会に参加するチャンスが舞い込んできたことです。
X(旧Twitter)を見ていて、偶然、世界最大の航空宇宙機器開発製造会社のボーイングがメインスポンサーを務めるコンテスト「GoFly」の存在を知りました。
新しいモビリティで世界を変えたい、変わった先の未来を見てみたい。当時、東京大学大学院博士課程に在籍していた私は、大学院の友人や社会人の方とチームを結成し、この大会に参加しました。
応募から3年後の2020年までコンテストは続き、最も⾰新的な機体を開発した“ディスラプター”に送られる賞と、賞金10万ドル(当時の約1080万円)を獲得しました。偶然見つけた大会でしたが、チームの仲間にも恵まれて、参加してよかったと心から思います。

Slack・Notion・miro・Zoom・GSuite
どれもベーシックな業務用SaaSです。 前職までで使ったことがない人もみなさん使いこなせています。 Slack 社員のみならず、業務委託の方にも使っていただいています。 私たちが研究開発を行っている福島ロボットテストフィールド近隣の他のスタートアップの方ともSlackコネクトを活用して事務職から研究職まで、いろいろな情報交換を行っています。 Notion 情報集約はNotionにまとめています。外国人スタッフもいるため、インターフェイスを個々人で選んでいます。 miro 事務業務フローの作成や開発におけるアイディアだしにおいてmiroを使っています。 GSuite 社員のみならず、業務委託の方にもアカウントを発行し、一元的にデータ管理をしています。
中高の学びは基礎。80歳になった時に後悔したくない
──中学・高校時代での学びは、研究開発に結びついていますか?
中井:文系、理系にかかわらず、すべて結びついている感覚があります。飛行機の設計には数学や物理は必須ですし、バッテリーは化学の知見を用いています。さらに、飛行機を売るために、地理や経済に関する理解が必要です。
中学・高校で学ぶ内容は、大学・大学院に比べると専門性は高くないものの、製品全体をデザインするための基礎学力だと思っています。
──学生時代、いまのような姿は想像されていましたか?
中井:全く想像していなかったです。
チームを立ち上げてからのこの5年間、当時ではイメージできないような経験ばかり。新しい学びを楽しみつつも、がむしゃらに駆け抜け、ようやくテスト機の販売までたどり着いた感覚があります。
実は、「GoFly」を知る前まではコンサルティング職に関心がありました。でも、もしコンテストに挑戦しなかったら、自分が80歳になった時に後悔すると思い、研究開発職の道を選びました。
正直、不安もあります。ただ、大抵は考え抜いた先に「考えてもしょうがない」といきつき、腹をくくるんです。この選択で後悔しないように、これからも挑戦し続けます。

未来の移動をアップデート
未来の移動をアップデート
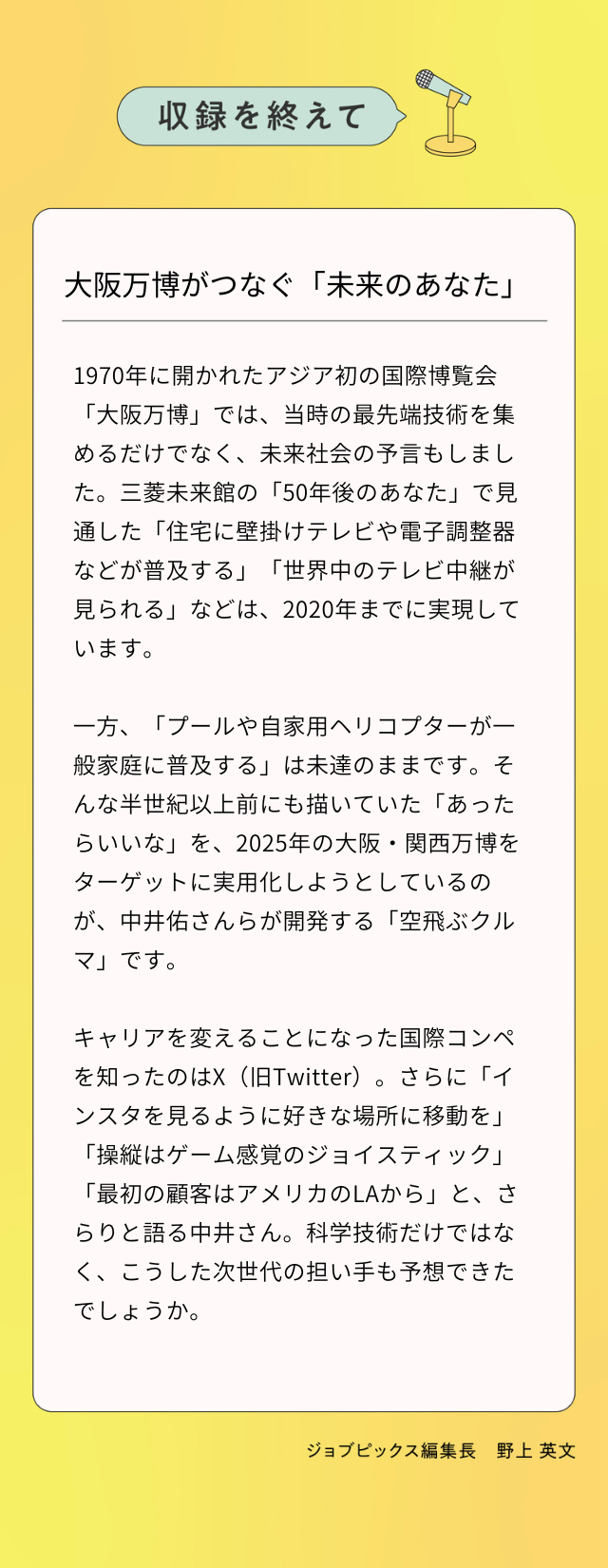
次回は、楽さん(#02出演)のご紹介で、腸内細菌の研究をされているbacterico代表の菅沼名津季さんへのインタビューを公開予定です。 番組や記事への感想はハッシュタグ「 #いいかも」とつけて、X(旧Twitter)に投稿してください。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけるとうれしいです。 (文:鍬崎拓海、池田怜央、映像編集:長田千弘、デザイン:高木菜々子、編集:野上英文)