採用担当者も試行錯誤している
これまで「就活生への手紙」という連載を11回続けてきましたが、私が過去に出会ってきた就活生たちと同じ、もしくはもっと多いくらいでしょうか、たくさんの採用担当者にも会ってきました。
就活生から見れば「品定めされる」という印象から、おびえられることも多いかもしれません。ですが、採用担当者のみなさんは「内定を出した人に受諾してもらえるか」を、就活生と同じくらい気にして、配慮に配慮を重ねています。
そもそも採用は、企業の今後の方針に大きく関わる業務。どんな人に働いてもらえたら、会社がもっとよくなるのか。そのためにはどんな採用をしていけばよいのか。さらにはどういった形で会社を認知してもらう必要があるのか......。いわば経営に直結するといっても過言ではありません。

実はやることが膨大な採用担当
採用担当には、社内組織のつくり方に精通した人もいれば、広報として認知度を上げるプロフェッショナルもいるでしょう。
中小企業で一人で採用を担当、なおかつ他の業務と兼任という方も少なくありません。採用広報で周知してから、多数の応募を一人でさばいて、一人一人と選考の日程調整をして、面接にも同席して、内定を出して……。やることが、とっても多いのです。
大企業で人事部にある程度の人数がいたとしても、決して楽だというわけではありません。
各部署の現場の社員に面接官をしてもらうために、内部調整もすごく多い。だから、きっと就活生が想像するよりも、はるかに、企業が「一つの面接」にかける労力は大きいものです。

理想を求めすぎて、存在しない高度な「ペルソナ」に
これまでに採用支援をしてきて感じるのは、「目の前の業務に追われて、ターゲットとなる人物像が見えなくなってしまう」ことが頻繁に起きているということです。
どんな人に入社してほしいかを考え、現場のヒアリングを重ねれば重ねるほど、理想像がとても高くなってしまうことがよくあります。
たまに募集要項の添削などもするのですが、「ここまでのハイスペックで、この給与で働ける人は、ほぼ存在しないのでは?」と思うこともしばしば。社内の人とのコミュニケーションが多いほど、ついつい視点が社内だけに向いたものになってしまうのです。
社内へのアンテナばかりが発達してしまうのは、大企業の新卒採用でもよく起きることです。たとえば、経営層の方針に合わせて採用戦略を立てる場合です。福利厚生もアピールしたい、イノベーティブな発想のある若者に入ってほしい、世の中の変化に合わせてこう変わろうとしていることも伝えたい、など要点がいつの間にか盛りだくさんになっています。
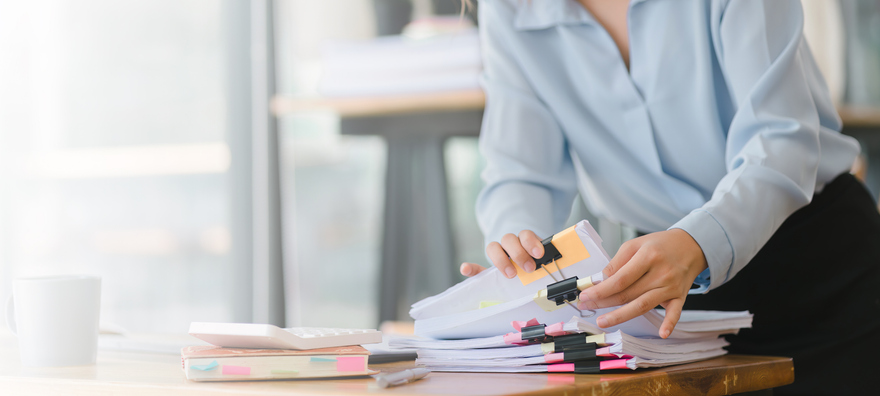
採用サイトあるある「伝えたいことが伝わらない」
全部をてんこ盛りにした採用サイトは、客観的に見ると、次のような疑問だらけになることも。
「なんか社名でイメージしていた会社と違うかも?」
「採用サイトで見た内容と、面接の雰囲気が全く違ったなぁ」
「同業他社との違いって、結局なんだったんだ?」
採用担当者がやりたくてやっているわけではなく、社内のいろいろな要望の板挟みになった結果、陥ってしまうことも多々あります。どうにか頑張った結果、なぜかサイトの色使いまで同業他社の数社とそっくりに……。そんなケースも見てきました。

ターゲットをどれだけ深く理解できているか
採用情報を狙ったターゲットに届けるためには、就活生がどんな環境に置かれているのか、どんなサイトを使って、どんな比較をして考えているのか、という点に重きを置いて考えることも大切です。
もっといえば、ずっと新卒採用を担当していると、毎年「新卒の就活生」を相手にし続けることになりますが、彼らは1年前、下手したら半年前までは就職やキャリアについてまだ何も考えていなかった可能性もあります。急いで情報収集をしていて、限られた情報にしか接していない、ということも忘れてしまいがちなのです。
大学生や就活のトレンドを追って、TikTokやInstagramなどを活用した採用広報も素晴らしいと思います。ただ、もっと根底にある「リアルな大学生の生活」を想定することが、ないがしろにされているケースが、本当に多いと感じています。

採用担当に必要なのは「就活者目線」
編集やライターの仕事をしていると、よく話題に出るのが「読者目線を持っているか」ということです。書き手が伝えたいことを一方的に押し付けるのではなく、どういう人が読むのか、読んでどう感じてほしいのか。そして、読んだ後にどんな行動をしてほしいのか、などを考えることがよくあります。
この「読者目線」を採用に置き換えれば、「就活者目線」が大切ということになります。
採用広報のサイトや動画を通した伝え方だけではありません。メールの書き方や、電話のかけ方で、どういう印象を与えるかにも自覚的である方がよいはずです。

さらに、採用担当の人事部だけでなく、面接官を担当するすべての人にとっても、「あなたの対応が会社のイメージになる」といっても過言ではありません。
コンプライアンスを守るという以前に、就活生の立場に立って考えてみたらどうだろう?と目線を変えると、振る舞い方がシンプルにわかるかもしれません。
一人でも多くの「一緒に働きたい」と思った就活生の心をつかむには? 最先端のトレンドを追ったり、目新しい取り組みを試みたりするのではなく、人と人のコミュニケーションとして「どうしたら内定を受諾してもらえるか」と考えてみるのが、案外一番の近道なのかもしれません。
(文: 山本梨央、デザイン:高木菜々子、編集:野上英文)