就活中の不安をあおる「うわさ」たち
就活生と話していると、こんな声を聞くことがあります。
「〇〇業界に憧れているけど、私にできるわけがない」
「〇〇の仕事に就いてみたいけど、きっと僕より優秀な人しかなれないと思う」
こういう悩みに遭遇するたび、なんてもったいない!と私は思ってしまいます。
なぜなら、私自身は就活当時、「やりたいこと」なんて見つかっていなかったから。憧れがうっすらと見えているだけでも、当時の私より、よっぽど前に進んでいるように感じます。
ただ、挑戦する前から、あきらめたくなってしまう気持ちもわかります。
理由の一つが、就活を進めていくと、「うわさ」がたくさん耳に入ってくるからです。
あの会社は〇〇大学が有利らしい
ここの会社は、体育会出身だけで大半が決まるらしい
この会社は去年内定辞退した先輩がいるから、うちの大学は不利らしい
就職活動を前に、ただでさえ不安な気持ちになっているときに、こんなうわさ話があれこれ耳に入ったら、さらに不安な気持ちになって、自信を無くしがちなのも当然です。

うわさは本当なのかデマなのか。一学生の立場から確かめるのも至難の業です。個々の内定情報や会社の採用情報といったセンシティブな内容の真偽を調べることは、実際は難しいです。
裏返せば、それくらい取り扱いの難しい情報がうわさとして流れてきたら、「信憑性は薄いな」と疑う。斜に構えるくらいでいいと思います。
東京には......見えないライバルと比べてしまう
全国各地の大学や専門学校などでキャリア支援講座を行ってきましたが、学歴だけでなく、住んでいる地域の違いで自信をなくしている学生さんにも、たくさん会ってきました。
どの学校に通っているのか、どのエリアに住んでいるのかにかかわらず、優秀だと感じる学生さんを多く見かけます。ただ、心の中で自分を卑下してしまう人たちもいます。
「東京にはもっと優秀な人が多いだろうから」と。
よくよく聞いてみると、東京には「学生時代から参加できるコンテストなどが多い」「インターンで経験できる職種が豊富」といった理由から、引け目を感じているようです。
今はリモート参加できるインターンやアルバイトもあれば、全国から参加できるコンテストも昔からたくさんあります。ただ、そうした経験を積極的に積んでいるケースでも、「東京の学生の方が……」と、思わず弱音が漏れるものなのです。

そうした相談に乗れば乗るほど、私はこう感じるようになりました。
就職活動で同じ土俵に立つ前から、「自分の方が劣っている」と可視化されるのを恐れて、土俵に上がること自体を自らあきらめてしまうケースがあまりに多い、と。これは本当にもったいないことだと思います。
ライバルが見えないところにいるからこそ、手ごわいように感じてしまうかもしれません。
でも、業種を問わず、その会社とマッチさえしていれば、入社のチャンスは必ず巡ってくるはずです。
一歩社会に出れば、学生時代にこうした弱音を吐いていたのがうそのように、社会人として大活躍している人をたくさん目にしてきました。
まずは、うわさ話や姿の見えないライバルに惑わされないようにすること、から始めましょう。

自己分析とガクチカで埋もれる“苦手”
「自信がない」という声に、違った切り口から耳を傾けてみます。
実際は「憧れてはいるけれど、こういう仕事を今までにやったことがないから、自分にできる気がしない」という理由で応募をためらうパターンも多いようです。
自己分析でたどり着く「自分の強み・弱み」。または、学生時代に力を入れた「ガクチカ」。これらについてはなんだかんだ、自分なりにポジティブにも捉えられるポイントを探しがちで、得意なことをアピールしたくなります。
そうやって就活の準備を進めていくと、書いたり話したりする機会が少ない「自分の苦手なこと」に向き合うことを避けがちです。
その結果、「まだやったことがないだけで、挑戦したらできるようになるかもしれないこと」と「そもそも適性がなくて本当に苦手なこと」を混同して、すべて「苦手なこと」とひとくくりにしてしまう人が大勢います。
でも、考えてみてください。
学生さんで、社会人経験がないのであれば「できない」と自分で決めつけてしまうのは、まだ早いのではないでしょうか?
仕事をしたことがない目線で「できない」とジャッジする基準は、本当に正しいでしょうか?
もしかしたら、自分の気づいていないポテンシャルを憧れの会社が、見抜いてくれるチャンスがあるかもしれません。

自覚していない伸びしろ、見つけるのは企業
採用活動で企業のお手伝いをする経験もありますが、採用に至るのは、次の2つがかけ合わさったケースが多いと思います。
学生側が「挑戦すればできるかもしれない」と熱意をしっかりとアピールできる。
企業側が「こういうタイプの人はこういう仕事に向いている」という基準に当てはまる。
自分の「強み・弱み」や「ガクチカ」のPRだけで、入社や配属が判断されることはありません。
企業はたくさんの人を採用選考で見ています。さらに就活生から実際に入社した人、さらにどんなタイプの人が、どういう変遷を経てキャリアを伸ばしていったか。そうした知見をデータのように蓄積しています。
本人は自覚していなくても、「こんな伸びしろがある」と見抜く力を企業側が大なり小なり持っているということです。
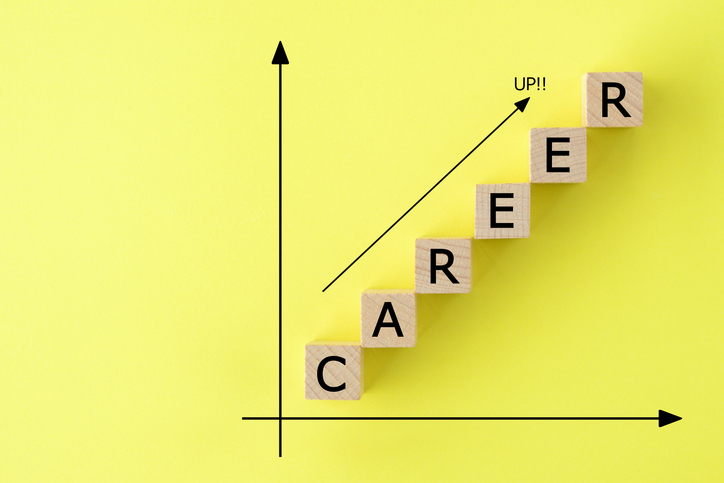
時には、希望と違う部署を提案されることもあるでしょう。会社側の事情もあります。
これを「融通の利かない会社だ」と捉えることもできますが、「自分が気づいていない、自分の伸びしろがそこにあるのでは?」と捉えることもできます。
私も、新卒のときは企画職などに憧れていたのですが、配属は法人営業でした。今で言う「配属ガチャ」です。
希望は全然通らなかったし、「営業って、なんだか泥くさい印象があるしイヤだなぁ」なんて思っていたのが本音です。
しかし、やってみたら、意外とこれが楽しい。もちろん、慣れるまでは苦労もしました。でも、日常生活では出会わないような人たちと会話をすることができるし、商談だけでなく雑談などのスキルも求められて、高まる。自分の交渉力次第で案件を大きくすることもできました。
今はフリーランスとして、ライターや編集の仕事もしていますが、実は営業の仕事も積極的にやっています。自ら選んで営業の仕事をするくらい気に入った仕事の一つになりました。
もちろん、フィットしない仕事を延々とやることに意味はありません。ただ、自分では気づくことのなかった伸びしろを、新卒の就職活動で企業に見抜いてもらったことには、今でも感謝しています。
自分の目線以外でも、「強み・弱み」「得意・不得意」を見つけられることがある、とぜひ知ってほしいのです。
OB・OG訪問で、こう聞いてみよう
こうした経験は、きっと私だけではないはずです。
OB・OG訪問をする機会があれば、先輩たちのなるべく個人的なキャリアの変遷を聞いてみることをおすすめします。
社風や企業の業務全般のことを聞きがちですが、チャンスがあれば、こんな質問を投げてみてはいかがでしょうか?
(1)「就活時の第一志望はどんな会社だったのか。悩みはあったのか」
(2)「内定が出た当初の希望部署はどこだったのか」
(3)「キャリアの希望はかなったのか。どうやって仕事を覚えていったのか」
バリバリと仕事をこなしてカッコよく輝いて見えるOB・OGかもしれませんが、就活時点では悩んでいた人も多いはずです。そうした人が、どのように今に至ったのかを聞いてみたら、「自分と大きく変わらないんだ」と、きっと励みになるでしょう。
もしかすると、苦手を取り違えていたり、意外なプロセスから自信を得ていくケースにも出合えるかもしれません。
今の仕事のやりがいや仕事についてダイレクトに聞くというよりは、質問のボールを少し先に出して、少し面倒かもしれませんが、OBやOGに取りに行ってもらうイメージです。
さらにこんな深掘りの質問もできるといいですね。
(4)「もともと得意だったことは何ですか?」
(5)「会社に入ってから、できるようになったことはありますか?」
その会社の教育体制がどれくらい整っているのかを垣間見るチャンスにもなります。

「就活生への手紙」を書き始めてから、ある同級生から連絡がありました。
彼女は、就活中にキラキラと輝いて希望する業界への内定をバシッと決めているように見えていたけれど、実は就活中に悩んでいたとのことでした。
「社会人歴」を積み重ねた今だからこそ、実は当時、同じ悩みを抱えていたことがわかりました。今さらながら、悩んでいたのは一人きりではなかったと、なんだか救われた気持ちになりました。
自信のなさというのは、客観的なものだけではなく、自分で自分のことを「私なんて、こうだ」と決めつけてしまうことで、生まれる部分も大いにあるように思います。
だからこそ、自分一人で判断せずに違った視点で見直してみたり、先輩に振り返りの質問を投げてみたりしましょう。自信のなさの解像度が上がり、払拭できるかもしれません。
(文: 山本梨央、デザイン:高木菜々子、編集:野上英文)